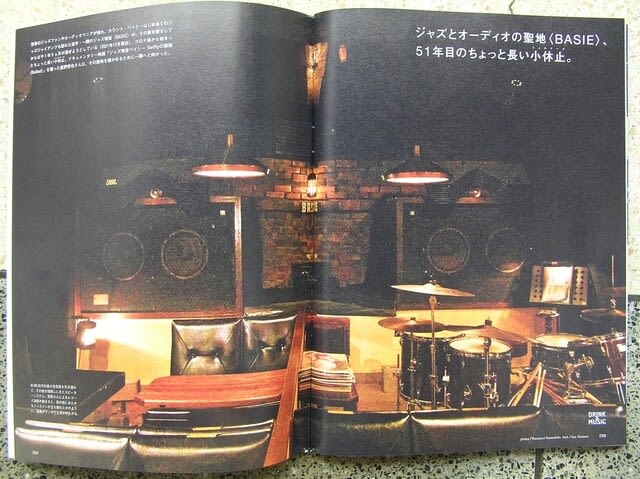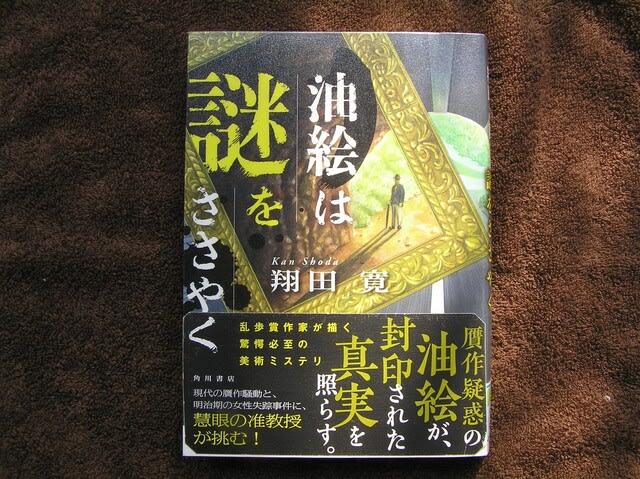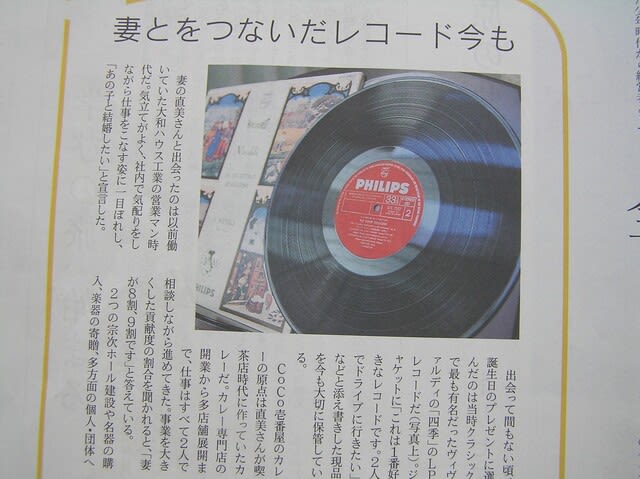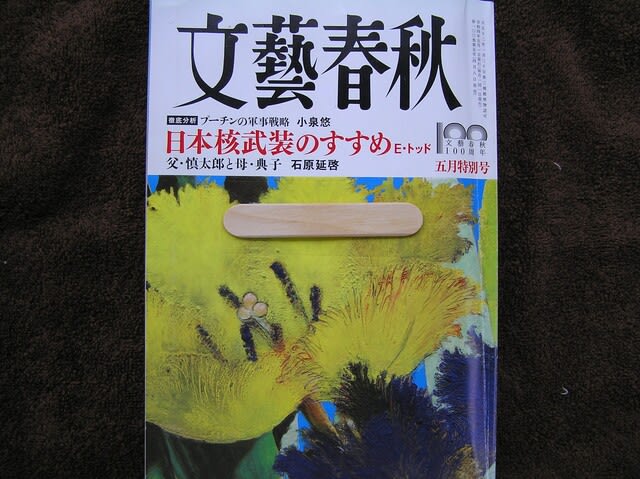前々回の「二番手が好きな理由~6~」からの続きです。
ちなみに、大好評だったこのシリ~ズも非常に惜しまれつつ今回で終了します。なぜかはブログを終わりまで読んでいただければわかります(笑)。
さて、「二番手」として最後に登場した6台目の「371Aプッシュプル」アンプ。
我が家での立ち位置は可もなく不可もなく、平均的な存在だったが前段の「27」真空管を「G27」(マゼスティック)からこのほど落札した「227」(レイセオン)へ変更して一歩抜け出したいところ。
右側の球のトップの部分のマイカが初期製造の特徴である「矢印」の形になっているのがお分かりだろうか。
さあ、ワクワクしながらスイッチオン・・。
ところが、出てきたのは「ブ~ン」という盛大なハム音だった。
これはアカン・・。まるで地獄に落ちたような心境だった(笑)。
さっそく「北国の真空管博士」にご注進。
「ハム音が大きくて困ってるんですが・・」
すると「初期製造の球はどうしてもそういう症状が時折あります。で、二段目の球と差し替えていただきませんか。ノイズが1/7になるはずです」
というわけで、初段は従来通り「マゼスティック」にして、二段目の球の「ARCTURAS」(ブルー管)の代わりに差し込んでから恐る恐る音出しへ~。
どうかハム音が出ませんように・・。
すると、微塵ほども濁りのない想像以上の見事な極上のサウンドが飛び込んできた!
エ~ッ、これはまあ・・、と思わず絶句した。
音の躍動感がまったく違うのである。元気溌剌、まるでモーツァルトの「天馬空を駆ける」ような音楽みたい。
それに両方のSP(AXIOM80)の間の楽器の位置がさらに奥深~く位置するようになってクラシックにはたいへん好ましい鳴り方。
しかもサブウーファー(ウェストミンスター:100ヘルツ以下)が要らないくらい、ローエンドが伸びているのにも驚いた。
ちなみに、このウェストミンスター(内蔵ユニットはワーフェデールの赤帯マグネットのスーパー12)は市販のサブウーファーとは明らかに一線を画すもので、圧倒的な重量感に加えて優れた分解能といい世界で一番贅沢なサブウーファーだろう。
この箱は100ヘルツ以下で鳴らすに限りますな(笑)。
それからは手持ちのあらゆる音楽ソースを鳴らしてみたが、まったく破綻を見せず、さらにはそれほどお気に入りでもなかった曲目がそ~っと琴線に触れてくるのには参った。
あえて採点するとすれば軽く95点以上で、我が家の中では最高点。
たかが二段目の真空管を入れ替えたぐらいで「天国と地獄」を味わうことになったのだからやっぱり真空管オーディオは怖いですね。
このアンプがあればもうほかのアンプはピンチヒッター程度の存在で、これで「二番手」シリ~ズは終了といこう。
となると、いつものように急にスペア球「27」が心配になって倉庫の中を確認した。
銘柄は「デフォレ」「カニンガム」「マゼスティック」「ARCTURAS」「マラソン」「スパートン」と多士済々・・。
1930年代のアメリカの真空管業界はメチャ元気が良かったんですねえ。しかも第二次世界大戦の戦場にならずに済んだため、当時の真空管が比較的よく残っている。
いずれにしても、これだけあれば命尽きるまで大丈夫だろう(笑)。