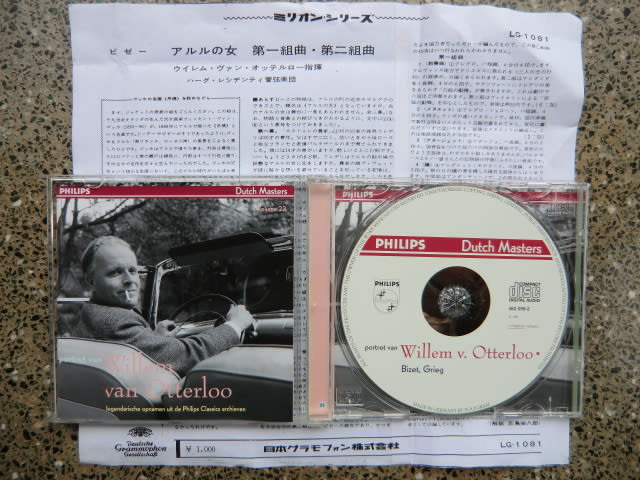ご存知の方も多いと思いますが「イグノーベル賞」というのがあります。
人々を笑わせ、そして考えさせた研究に与えられる賞で、1991年創設。「ノーベル賞のパロディー版」とも言われており、授賞部門は開催年によって異なるが、なぜか日本人は授賞の常連になっています。
この本には、これまで受賞した40本の内容が紹介してありましたが、音楽関係を拾ってみると「ネズミはオペラを聞くと寿命が伸びる」があったので紹介してみましょう。
帝京大学チームによると心臓移植を受けたネズミにオペラ「椿姫」を聞かせたところ通常術後1週間の寿命が1か月まで延びたという。
「何も処置をしないと拒絶反応が起こり8日で心臓は止まります。ある時、10匹のネズミが入った箱2つを並べて置いておくことが出来ず、別々の場所で保管しました。
すると片方の箱では8日前後で止まるはずの移植後の心臓が止まりませんでした。そこで環境の変化があるのではないかと直感したのです。
そこでまずはヴェルディ作曲の「椿姫」を聞かせてみることにした。音楽がとても好きだというリーダーの新見院長、イギリスに留学していたころはよくオペラや楽団の演奏を聴きに行ったそうだ。
研究員によると「椿姫」を選んだ理由はボス(新見院長)が好きだからというのが理由。研究者たちは他にもモーツァルトやエンヤなどの音楽を聞かせたが結局一番効果があったのが椿姫であり、寿命が平均26日生き延びた。
次にモーツァルトで20日、エンヤは11日程度で微増。また石川さゆりの「津軽海峡冬景色」も試したが残念ながら効果はなかったそう。
さらに寿命が延びた理由がほんとうに音楽によるものなのかを検証するためにネズミに音が聞こえないようにして同様の実験を繰り返した。その結果、ネズミの寿命が伸びることはなく、術後の長生きが音楽の効果であったことが証明された。
新見院長は「この研究結果から言えることは音楽が脳を介して免疫系に良い影響を与えているということです。
病気には医学的対処はもちろん大切ですが脳に影響を及ぼすような環境、希望や気合、家族のサポートなどが大切であることに通じる結果です。”病は気から”とよく言いますが、あながちウソではないです」。
昨今、とりわけ欧米諸国で音楽は様々な病気の治療の一環としてじわじわと定着し始めている。音楽療法は精神病や中毒症の両方の一つであることに加え、身体的な病気の治療を手助けするものと認識されつつある。
効果の度合いや再現性については諸説あるが様々な症状において、音楽が痛みや吐き気そして不安感を和らげると報告されている。音楽を通常の治療と合わせることで安らぎを与え、症状をポジティブな方向に向かう手助けをしているようだ。
新型コロナ関連のウィルス肺炎が続く中、感染予防にも大脳の働きが大切です。ストレスを溜めないことが、がん予防、感染予防、そして長寿につながります」
以上のとおりですが、「音楽&オーディオ」に限らず趣味と名のつくものの効用は免疫系にとても良い作用を及ぼすのでけっして無駄な投資ではないことがわかります。
そして、ずっと以前にも「乳牛にモーツァルトを聞かせるとお乳の出が良くなる」という話を読んだことがありますが、これらのことを踏まえると、美しい芸術を人間が独り占めしてはいけないということでしょうかね(笑)。
最後に「チャットGPT」さんに「ネズミはオペラを聴くと寿命が延びますか?」と訊ねてみました。
「面白い質問ですね!ネズミがオペラを聴くと寿命が延びるという科学的な証拠はありませんが、音楽が動物に与える影響についてはいくつかの研究があります。
例えば、クラシック音楽を聴かせるとストレスが軽減されるという研究があり、ストレスが減ることで健康状態が改善され、間接的に寿命が延びる可能性は考えられます。また、特定の音楽(モーツァルトなど)が学習能力や神経の働きに良い影響を与えるという「モーツァルト効果」も研究されています。
ただし、音楽の効果は動物の種類や個体差によるので、ネズミにとってオペラが本当に寿命を延ばすかどうかは、さらなる研究が必要ですね!」