


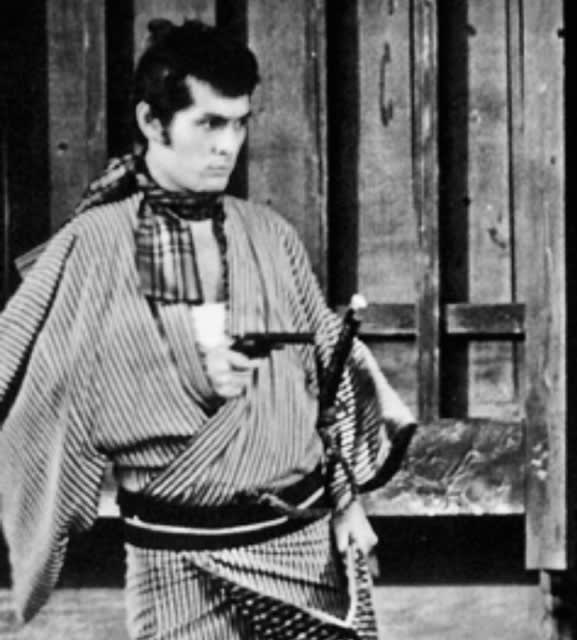

このクロサワ映画無くば、今の
それにつけても、映画『幕末』
での24才の吉永小百合さん
演じるお龍の綺麗な事よ。
綺麗というより美しい。
美し過ぎる。
これはタモリさんも言ってるが、
吉永さんはトイレにも行かない。
小百合ちゃんは、そうなのだ。





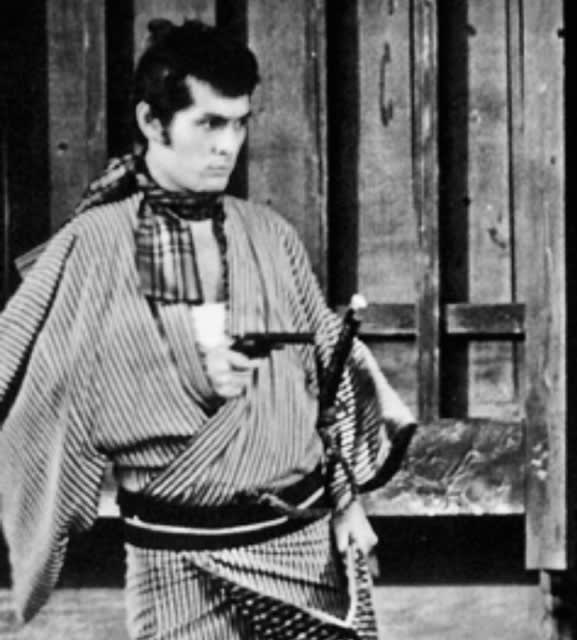







1872年、カンザスの銃砲店
時代考証というものは、多くの
文献精査に始まり、多角的に
かつ包括的に時代性を捉えない
と全体像と詳細が見えてこない。
ミクロ的視点だけを有すると
単にオタク的な偏頗な偏執と
なるし、また概略だけを押さえ
ても、それは日本の学校の社会科
でのつまらぬ意味ない授業の延長
にあるマクロ史眼の域を超えない。
しっかりとした視点を持つ研究
者によるアメリカ西部開拓時代
の解説サイトを下に紹介する。
良サイト。

西部開拓時代資料集|西川秀和|note
※写真や絵図を中心に西部開拓時代についてまとめています。 ※一般的に西部開拓時代とは広くは19世紀全般、狭くは1840年代から1890年に...
note(ノート)

イラストレーターの小林弘隆さん、
通称イラストのコバさん=イラコバ
さんのこの画集は最高だ!
まだご覧になっていないガンフリ
ークは、是非ともこの集大成の画集
をお買い求めください。
小林さんが亡くなって久しいが、
多くの人に愛されたそのタッチは
各方面に影響を与えた。
だが、イラコバさんが表だって活躍
したのは1985年から1994年と、極
めて短い期間だったのだ。
駆け抜けた。まさにそんな人生
だった。
銃や映画について非常に造形の深い
イラコバさんで、私も大好きな作家
なのだが、コアで詳しい知識をお持
ちなのに、ちょっと独断で決めつけ
たりするところもあったりする(苦
笑)。
表現が複雑で細かい映画を「面白く
ない映画」と決め付けたり、俳優
が非常に良い演技をしている映画
をやはり「つまらない」と一蹴し
たりとか。おれみたい(笑)。
画集の中にこういうのがあった。
『ヤングガン』(1988)の劇中
ファッションをベタ褒めしてい
る。
そして、こう記す。
「『レイン・スリッカー』を着て
いるのが良い。ウォルター・ヒル
の『ロング・ライダー』も着てい
たが、その昔のウエスターンでは
見る事も出来なかった。」
「ロング・ライダー」とは邦題
『ロング・ライダーズ』(1980)
のことだろう。
だけど・・・イラコバさん、誤認
してるような気が・・・。
もしかしたら、密かな名作(興行
成績は良くなかった)である『11
人のカウボーイ』(1971)を観て
はいないのかもしれない。
『11人の・・・』では、ジョン・
ウェインも出てくる少年カウボー
イたちも皆がレイン・スリッカー
=ダスター・コートを着ているの
である。
これはカウボーイの定番雨具兼
埃避けコートで、春先などに乗馬
したまま着用したりする。
乗馬用であるので、ロングコート
ながら、裾がまくれないように足
に結び付けるストラップが中に
あったりする。日本では乗馬文化
が無いため、この本式ダスター・
コートはほぼ無い。すべてアメリ
カからの輸入物だ。
文化そのものが日本に無いのは、
ビリヤード観戦専門の椅子のスペ
クテイターチェアーのようなもの
だ。
米国ではどこでもあるイスなのだが、
日本には存在しないし販売もされて
いない。
本物のダスター・コートも、その
「日本には無いアメリカの物」の
一つだ。
『11人のカウボーイ』(1971)から。
主演のジョン・ウェインのアンダー
センも少年カウボーイもダスター・
コートを着ている。簡易雨具であり
砂埃避けのアウトドア・コートだ。
別な少年も着用。つまり11人の
全員が着ている。
この少年はたぶん私と同じ年あたり
だろう。撮影された1970年時では
10歳齢程だろう。
また別な少年も着ている。これは
珍しくコートを脱ぎ畳むシーンが
収録されてい入る。ここからある
ことが看破できるのだ。観て行こう。
馬上で走りながらコートを脱いで
いる。これは小雨がやんだか、ある
いは埃立つ地域を抜けたかしたから
だろう。
脱いで脇に抱えたのに、コートが
立っている。つまり、このオイル
が表面に塗り込められたコットン
コートは、熨斗をかけたように
パリパリに硬いコートであるとい
うことだ。ダスター・コートはし
なやかで軽く軟らかいという印象
があるが、本物はどういうコート
であるかがよく判断できるシーンだ。
この状態になってもコートはピン
と立っている。
牛追いのキャトルドライブには
欠かせないカウボーイアイテム、
荒野の旅人が欠かせないアイテム
が帽子とこのダスター・コート
なのである。
日本国内で販売している物は
すべて輸入品だ。
この画像のは・・・ちょっと
本格本式とは仕様が違うよう
に感じる。ファッション用だ
ろうか。
本物本式は前の合わせが右から
左になっている物が多い。
あえて一般合わせと逆様式に
してあるのだろう。


映画『バッドガールズ』(1994)
でもダーモット・マローニーが
ダスター・コートを着ていた。


この西部劇に出てくる本格ダスター
・コートがなかなか売っていない。
ショルダーカバーの着いたタイプ
のハーフ・ダスター・コートを
私は持っていて、17年程前に山で
着ようと思ったのだが、家族から
不評だったので着ていない(笑
さて、本格的ダスターコートは、
西部開拓時代の春先の砂埃避け
のために北米で生まれたコート
なのだが、その後の第一次世界
大戦での塹壕戦の中で生まれた
トレンチコートは日本でも大い
に普及している。一般的な紳士服、
レディ服としても普及している。
これはまた不思議な現象だ。
軍服が一般化したのは、セーラー
服とトレンチコートくらいのもの
であろうか。
とはいっても、1990年代にダスター
・コートとよく似た超ロング・コー
トを私は通勤で着ていた。それと
M-51モッズコートを交互に冬場は
着ていた(踊る大走査線の青島より
も私のほうがずっと先だったと思う)
のだが、やはり本物のダスター・
コートではないので、乗馬などには
とても使えそうにないものだった。
今では内側に脚紐がある本物のダス
ター・コートが結構あるようだ。
ビシッと全体が締まっていて、コー
トの裾だけがひらめいて走る姿は、
結構カッコいいのではと思ったり
もする。
あれっぽいよね。オープンカーで
真冬にコート来て走らせるような
感じ?
そんな「理不尽な男気」というの
は、それ自体がハードボイルドだ
と思う。
「男の料理」とか「男のなんとか」
という言い回しや発想は大嫌いだが。
ということで、『ロング・ライダ
ーズ』以前には古いアメリカ映画
では見たことがないとイラコバさん
が言うダスター・コートなのだが、
1971年公開の『11人のカウボーイ』
の中では、わざわざ脱ぎ畳むシーン
まで挿入してこのコートが西部開拓
時代の牛追いには欠かせない物で
あることをさりげなく表現している。
ただ、実際のところ、『ヤングガン』
がリアルな描写であることは確かだ。
それにしても、時代考証をきちん
としている西部劇は少ない。
みんなウエスタン・ショーのよう
な恰好をした登場人物ばかりだ。
それって、まるで歌舞伎衣装で
昔の侍が全員日常的に過ごして
いたというような認識に近いもの
で、間違いなんだよね。
パンツ=ズボンのベルトにしても、
パンツのベルトなんてのは無かった。
ズボンにはボタンが付いていて、
それに引っかけてサスペンダーで
吊ったのだし、ベルトがあっても
外側から巻く帯のようなものだった。
ベルトループが考案されたのは西部
開拓時代よりもずっと後代だし、
そもそも帽子からしてハリウッド
ウエスタンと実際の開拓時代の写真
では異なる。要するに舞台劇みたい
な恰好ばかりなのが西部劇の定番
だったりするのだ。
ブーツにしても、靴先はハリウッド
ウエスタンのように尖がった靴先
ばかりではない。本物の西部開拓
時代は。
今の日本のサラリーマンの革靴
の靴先と同じほど種類があった。
西部ならばウエスタンブーツ、と
いうのはワイルドウエスト・ショー
とハリウッド映画によって作られた
作り事だ。
そして、西部劇遊びをするにしても
衣装やガンベルトがやたら新品で
綺麗すぎて、まるで七五三のよう
な見た目が多すぎる。
これは現代人たちのカウボーイ
シューティング大会などでも
そうであって、まあ単なるコスプレ
かと思う。
本場アメリカでもそうであるので、
日本を見渡すと、なんというかもう
コミケみたいな感じ。
とにかく新品ピカピカランドセル
のようなリグやブーツやハットや
シャツやパンツはカッコ悪いん
だってば・・・。
なんだかなぁ・・・。
そんなのは無いのだから。
いくらごっこでも。
何だかアイロンプレスした野戦
服で長期行軍してきたんです、
みたいで、変。
もっと「時代着け」を研究したら
どうでしょうか。映画製作する
ような気合で。
パティーナ無き西部開拓時代の
アイテムというのは真実、珍妙
でしかない。
西部劇において、時代考証など
のリアルさが追求され始めたのは
1980年代後半からだった。
まさに『ヤングガン』などはそれ
で、劇中では考証無視の場面も
あるが、大まかにおいてはよく
「時代の空気」を描いていた。
時代考証にこだわって主張し続け
て来た映画人はクリント・イース
トウッドが代表格だ。
彼はステージガンによるブランク
(空砲)での射撃においても、反動
を初めて表現した俳優だったといえ
る。特に『ダーティハリー』に
おいては、.44マグ独特の反動を
よく表現していた。
日本で反動を初めて表現した俳優は
誰だろう。
意外と反動を表現している俳優は
21世紀の情報社会の現代でも少ない。
皆さん調べない。俳優という演技の
プロなのに無頓着。手抜き。テケトン。
銃の反動は、銃口を平手でドンと
上に押し上げるような反動だ。
これは銃の形から真上に逃げる構造
になっているためで、撃つたびに
真下に反動が逃げる銃は存在しない。
危ない、それ(笑
意外なところでは、草刈正雄さん
が若い時からガバメントにこだわり、
かなりマニアックな演技をしていた
ことはあまり知られていないかも
知れない。
石原軍団の俳優陣は皆さんよく
研究されていると思える。
やはりトップクラスであまりにひど
かったのが、映画『ホワイトアウト』
での松嶋菜々子だ。
AK47をフルオートで連射して全くの
無反動。
電動ガンでもそれは無い。
役を真面目に身近に引き寄せて演技
をしている俳優というものは以外と
少ないのだ。
時代劇にしろ現代劇アクション物
にしろ、ほとんどが手抜きだ。
特に時代劇に出る俳優がひどい。
ひどすぎる。
何もリアルに本式武術剣術として
やる必要はない。必要不可欠な
ところ=キモを外さずに「立ち
まわり」として殺陣ができる役者
が少なすぎるのだ。
それは「プロの俳優が激減した」
ということなのだろうと思う。
殺陣のみでいえば、若山富三郎先生
の殺陣が史上最強だろうか。
かといって、芸術的な殺陣もありか
と思う。
田村正和さんの殺陣はリアルでは
ないが華がある、というような。
いずれにしろ、映像業界では役者
の「プロ」が減った。

迷彩の柄物服は実に多くの種類が
あるが、私はこのセージ系のタイ
ガー迷彩柄の個体の色とパターン
がかなり好きだ。
あまり見ない柄。
正規軍で採用している国は無い。
デザートタイガーとも違うし、
もちろんベトナムタイプのタイガー
カモフラージュ柄とも異なる。
タイガー迷彩は個人的にはパターン
としてはかなり好きだ。
それのベースとなったフランス軍
のリザードも好きだし、さらに
タイガーやリザードの先祖である
英軍のブラッシュパターンは一番
好きだったりする。


映画『サボテン・ブラザース』(1986/米)
これは1989年にビデオで初めて観た。
とにかく笑えた。
ドタバタ喜劇なのだが、1916年に
当時の無声映画を本物のドキュメン
タリー映像だと勘違いした盗賊たち
に苦しむメキシコの人が村を助けて
もらおうと彼ら映画俳優三人を呼び
寄せることから話がはじまる。
彼ら三人は映画撮影だと思ってメキ
シコに行くのだが、本物の盗賊団
たちと対決するハメになってしまう
という物語だ。
そして彼らはコメディ路線で窮地を
乗り切る。
やがて彼らは、善良な町の人々に
感謝されて町を去るのだった。
これ、作品の根っこに意地悪さが
ひとつもない作品で、観ていて
気持ちが良いです。
なにより、素直に笑える。
心に健康を取り戻す映画作品で、
心が疲れた現代人にこそおすすめ。
SAAにハマり氏A氏から連絡あり。
われらの刀剣探究会にはSAA
好きが4人いる。
各人とも常に新規購入したSAA
がどんどんチューンナップされ
て行ってるのだが、バックスト
ラップのブルーイングを完全
に剥がしてポリッシュしたと
のことだ。
お~、ツルツル!これはいい
仕事!まさに「そこはつるんと
していた」(by 峰隆一郎)
すげ~。ピカピカだよ!
でもね、亜鉛合金がこのように
クロムメッキのような輝きを保っ
ているのは1週間ほどの命なんだ
よね。
表面が酸化して化学変化が起きて、
すぐにネズミ色にくすんできちゃうん
ですよ。これは仕方ないことなの。
外気から遮断したらもう少しもつ
のだけど。
私のSAAのポリッシュから一週間後
の状態。白銀のピカピカメッキ風が
このようにすぐにネズミ色に変色
してしまう。
このSAAはボブチャウスペシャル
のガバメントのように角をすべて
落としてあるところがファースト
ドロウ・カスタムとしてのミソ。
手前味噌だけどさ。
シリンダーさえ、フルートのエッヂ
まで落としてる。
ただ、白銀化ポリッシュした部分
は亜鉛合金素肌むき出しなので
磨きから時間が経つと色が変色し
てくすむ。
だったらニッケルメッキのトリガー
ガードとバックストラップに交換
すればいいのでは、とか思うでしょ?
その通りなのよね(笑
でもポリッシュしたい、磨きたい
というのが本音にあったりするの
だから、もうすでにビョーキなわけ。
磨き方は、サンドペーパー →
スチールウール+ジフ → ピカール
です。
一度ポリッシュした後は、くすん
だらピカールのみでピッカピカに
復活します。
以上、日本刀探求苑コルトSAA
分科会ハマりーズからの報告でした。

日本語吹替版がどうして観たくて
ブルーレイを購入した。
東北新社から出されたDVDのボー
ナス解説トラックが史上最低の
クソトークだったので、DVDは
歴史上の最低編集の最低円盤と
なっていたが、このブルーレイ
はそういうことはない正統派
メディアだろう。
この初ブルーレイは、なかなか
凄い内容だ。
・オリジナルネガより製作した
HDニューマスター版
・デジタルリミックスによる
5.1ch音声を世界初収録
・TV版日本語吹替音声(テレビ
朝日「日曜洋画劇場版」)を収録
・ユアン・ロイド、ロジャー・
ムーア等による音声解説を
初収録
・ファン筋然の貴重な映像を満載
した特典ディスク付き(メイキング
/各種インタビュー/製作者ドキュ
メンタリー/予告編 他)
映画作品の洋画は原音で観る
のが基本だと思う。
ただ、私は日本の声優は俳優で
あると思っているので、声の俳優
さんの演技もぜひ堪能したいのだ。
特に『荒野の決闘 ~愛しのクレ
メンタイン~』などは、日本語
吹き替えの声優陣の演技が秀逸
で恐れ入った。
また、どうしてもクリント・イー
ストウッドなどは山田康雄さんの
あのトボけた人を喰ったしゃべり
方が合っているように思えるのだ。
原音のイーストウッドはスティー
ブン・セガールのようにボソボソッ
と話すのだが、あれは演技だ。
作品によっては軽快に早口で明瞭
にクリントはしゃべる。
吹き替えの山田マジックでは山田
キャラが活きて来て別キャラの
ようになる。
この『ワイルド・ギース』は実際
にコンゴに実戦投入された傭兵
部隊の第五コマンド=ワイルド・
ギースから名称を取っている。
各地を転々とする並んで飛ぶ渡り
鳥の姿が野性の雁の飛ぶ姿に
ソックリだからだ。降下作戦で
落下傘降下する姿はまさに野生
の雁たちが飛ぶ姿そのものだ。
ギースとはグース(野性雁)の
複数形のことである。
そのため、航空機から管制塔に
着陸許可を申請する時には
「こちらはワイルド・グースだ」
と言っている。そういう細かい
ところも映画の見所だ。
さらにこの作品の軍事アドバイ
ザーは本物のワイルド・ギースの
指揮官だったマイク・ホアー
中佐本人が担当した。
そして・・・イアン・ユーリ
はじめ、本物の当時の傭兵たち
が実に多くこの作品の撮影で
傭兵役のエキストラをやって
いるのだ。
ユーリのみ俳優として名前が
出てくるが、他のメンバーたち
はテロップにさえ名前を出さ
ないようにしている。
使用銃は、映画版『戦争の犬
たち』がイングラムをUZIの
ように見せかけたUZIグラム
と呼ばれるナンチャッテガン
を使っているのに対し、こちらは
すべて実物を使用している。
将校はUZIを使い、下士官と兵は
FALとL1A1(英軍FAL)を使用し
ている。
また将校は護身用短銃として、
1970年代当時はまだメジャー
だったワルサーP38を使用して
いる。日本軍でも個人的に装備
していた将校たちもいたりした。
(日本軍は将校・下士官の軍刀
と拳銃は自弁で揃える必要が
あった。私の伯父は少尉だったが
ブローニングM1910を携帯して
いた。この銃は峰不二子の愛銃
として有名だが、戦後1980年代
まで日本の私服刑事の多くに
配備されていた。38口径と
.32口径の二種があり、日本
警察の場合は.32口径が多かっ
た。この流れで、現行標準配備
の私服刑事やSPなどに配備され
たシグ・ザウエル社のP220-JP
採用の際には.32口径が円滑に
採用されたのではなかろうか)
映画『ワイルド・ギース』は
各シーンの表現描写において
かなりリアルだが、これは作品
のスーパー・バイザーの役目を
担ったマイク・ホアー中佐の
アドバイスによるものだろう。
指揮官役のリチャード・バートン
はマイク・ホアー本人の役どころ
だが、非常に容姿骨格もホアー
中佐本人に似ている。ホアー氏も
あまり長身ではなかったが、
リチャード・バートンもそうで
あるし、何よりも顔の雰囲気が
似ている。
リチャード・バートン。映画
『ワイルド・ギース』から
マイク・ホアー中佐。某国政権転覆
の傭兵作戦失敗で民間機をハイジャ
ックして脱出したため逮捕収監され、
公認会計士の国家資格は剥奪された。
民間旅客機は強奪ではなく、機長ら
の協力による脱出行為だったが、
国際法上はハイジャックとされた。
傭兵は国際法上はテロリストなの
である。現行国際法では傭兵の
存在自体が禁止されたため、現行
傭兵は警備会社のガードマンと
いう名目になり、内実としても
組織も気質も旧来の傭兵は一切
消滅した。
今の傭兵たちは大国の利益の為だけ
に戦闘行為を行なうが、かつての
傭兵たちは西も東も関係なく義勇
軍的な戦闘にも参加した。参加条件
は報酬の多寡ではなく、戦闘行為
がもたらす先の中身如何だった。
そこが現代戦争屋と大きくきっぱ
りと違う点だ。
そういう意味でも現代PMCは従来
の概念での「傭兵」とは呼べない。
本物の傭兵ワイルド・ギースたち。
これはコスプレではない。
これはあくまでコスプレ。
だってこれはあくまで俺だから(笑
具体的には明らかにしないが、
以前友人と話をしている中
で、銘鑑漏れの刀工の作に
ついて、私は「この刀工が
怪しい」と目星をつけて多
角度から二人で検証した。
友人曰く「この刀工の作で
間違いないですね」とのこと。
一発で的中だった。
完全銘鑑漏れ。
だが私のサイティングで特定
できた。しかも一発だった。
この友人とは二人しての解析
で、現代刀工の代銘を数名
特定したことがある。
本当は誰が銘を切っていたの
かを。物故者まで含めて。
そういうのというのは、見て
いれば判るのだ。ず~っと
見ているのである。
何から何まで隅々までずっと
見るのだ。狙撃兵の訓練
「キムのゲーム」のように
観ながらも見るのである。
すると自ずと見えるべき
ものが見えてくる。
刀という物は、よ~~~く
見るに限る。それは観るの
ではなく、診るように視る
のであり、眺めるのでも
ただ目をやるのでもない。
見て見て見抜くのである。
see でも look でもなく
watch であり gaze なの
である。
よくあるイラストの間違い
探しが不得意な人は日本刀
を見る事はまずできない。
注意力の問題でもあるが、
「見えるものが見えない」
という人は日本刀の状態が
何がどうなっているのかが
見えない。現実的に目の前
に存在する事象を認知でき
ないからだ。
ぐねぐねに曲がっている刀
にも気づかず、ひどいのに
なると、多数の刃こぼれが
あることさえも感知できな
かったりする人もいる。
私が知っているので強烈だっ
たのは、古刀と新刀の鋼の
色の違いついて話をしていて、
古刀が青いということが
どうしても判らないらしいの
で、「これとこれどう見える?」
と尋ねたら「どちらもピカピカ」
というのがあった。
色以前の捉え方の問題なの
だが、研ぎ師が白くこすった
部分を焼き刃=刃文だと思い
込んでいる人たちが世の中は
大多数であるので、もうそういう
ことはどうしようもないこと
なのかも知れない。
日本刀に関しては、私は一つ
の傾向性を知っている。
それは、刀が見えない人は、
10年経とうが20年経とうが、
同じようにいつまでも刀が
見えない、ということだ。
これは不動の定理としてある。
そしてそれは、刀を用具として
使うスポーツ武道をやっている
人たちに異様に多い。
理由は分かる。彼らは日本刀や
日本の文化には興味が無いから
だ。試合での旗上がりにしか
興味が無い。
だから日本刀などは箒と同じ
用具としてしか扱わない。
これは現実にそうだ。
刀が見えないということは、
その刀が持つ特徴も感知で
きないということであるから、
当然にして、物の善し悪しや
何がどうであるのかも感知
できない。
感知できないということは、
まったくもって皆目不明の
ままであるということなので、
いつまで経っても目が開か
ないままなのだ。
また、そういう人は努力も
しない。
努力もせずに最初から完成
されているようなことは、
こと人間に関してはまず
存在しない。
ただ、努力すると「より
一層良くなる」というので
あって、努力しても駄目な
ことはあるので難しい問題
だ。
たとえばセンスや性根は努力
では変りようがない。
だが、しっかりと見ないと
刀は見えない。こればかり
はどうしようもない。
日本刀に多く接する機会が
ある職業に日本刀研磨師=
研ぎ師がいる。
ところが・・・
研ぎ師でもまったく刀が
見えないのがいるので、
あれは一体どうなっている
のかとは思うが、現実は現実
として刀が見えない人なの
だから致し方ない。
たぶん・・・ずっと一生刀は
見えないことだろう。
よせばいいのに、そういうの
に限って、人に対して偉そう
にしたがる。これ実際に。
誰かガツンと言ってやれよ、
とか思うのだが、まあセンセ
センセと言われて来て勘違い
しているのだろう。
これは私。




