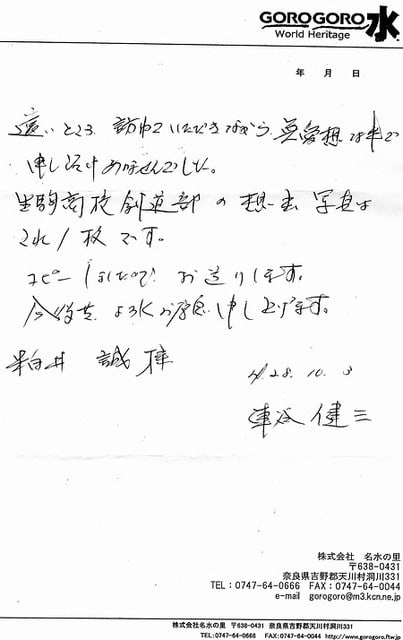〇高上極意五点
この五点は伊藤一刀斎景久が鐘巻自斉から許された高上極意の技と、その玄理の教えです。
1)妙剣は木に象(かた)どる。
この形は極めてすぐれた巧みなものであり、全く夢想であって、万事空なる所で木の芯がのびるように、のびのびとした調子で勝を完了する執行である。
2)絶妙剣は火に象る。
絶妙剣は妙剣のはたらきをも絶したところである。すべてを焼きつくし、全く無我無心の境地に出入した絶想の場である。しかも一点の火が大火と燃え上がり、一切を無にする執行である。
3)真剣は土に象る。
真剣の仕方の構えは常に真中を指す。土は中であり、すべて物があたって帰るところである。どこへどう高く物を投げても皆土に落ちて来て土に帰ってくる。己が剣は必ず打方に当ってはずれることはない。それは打方の中心を刺し、技の中心を刺しているからである。
4)金翅鳥王剣は金に象る。
金は貴い光をもって、銀、銅、鉄、鉛などの上に臨む。その重さは他にまさる。技に於いては上段の高い位の輝やかしい尊い気分をもって、上から圧するものである。即ち尊い位の威光を備える執行である。
5)独妙剣は水に象どる。
水は最も柔らかで、最も強いものである。水は自らどんな形をも持たず、方円の器に従う応適自在なものであり、然も低きにつく主心があり、どんな隙間へでも侵入浸透する。又、万物を生かし育てる主心がある。これは独妙剣の本音である。水は金の上に、いつしか目に見えぬ間に、露の玉となって、どこからともなく、ひとりで生ずる。それは蒸気が空中に充満しているからである。独妙剣の能動は、いつでもどこへでも充満していて、要に応じて働くものである、と述べられています。
〇ちなみに木より火が強く、火はまた燃えつきて皆灰と化して土にかえる。その土の中に燃然と輝いて姿を表すのは金であり、その最高の金でさえも、いつの間にかその金の上に水滴が乗るのであり、水が一番上であることを順序よく切組の形を作られたのが五点であります。
〇以上は笹森順造先生が「一刀流極意」259頁のところをよく見て頂きたいと思います。尚、蛇足ですが、五点の夫々の形の紹介は中途半端ですが、この項は各々技の解説が本意ではありませんし、又、私自身、形をやりますものの、まだまだ真の理合を体得するまでは道が遠く、従って机上の空論に終ってしまいますので、申訳ありませんが省略させて頂きます。「一刀流極意」247頁→259頁参照。われわれの日常生活に水なくしては考えられないことは前述の通りで、日常の会話でも水を使った言葉が多いことに気がつきます・
水にする。水に流す。水をさす。水になる。水いらず。水入り。水かけ論。水くさい。水ごころ。水の泡。水もしたたる・・・。水も漏らさぬ・・・。水を打ったように・・・・等々、水=無色透明(無)=無心(心)=万物。かくありたいものと思います。今年は辰どし、龍吟じて雲を呼ぶ。勢いにあやかって頑張りましょう。終り