2001年9月11日にニューヨーク滞在中に9/11の同時多発テロが発生したことは、僕の人生においても、ニューパルツと新見市との姉妹都市交流においても、重要な出来事です。
2024年5月14日にニューパルツの消防署を訪問した際、消防署前の同時多発テロの追悼碑を訪問しました。









同時多発テロに遭遇したことについては、このブログでも何度も記事にしています。
よろしければこちらからどうぞ。
2001年9月11日にニューヨーク滞在中に9/11の同時多発テロが発生したことは、僕の人生においても、ニューパルツと新見市との姉妹都市交流においても、重要な出来事です。
2024年5月14日にニューパルツの消防署を訪問した際、消防署前の同時多発テロの追悼碑を訪問しました。









同時多発テロに遭遇したことについては、このブログでも何度も記事にしています。
よろしければこちらからどうぞ。
今日、第172回直木賞と芥川賞の受賞作が発表されました。
直木賞の予測を先日書きましたが、受賞はあるかもと思いましたが最終的には僕の受賞作予測から外した伊与原 新さんの『藍を継ぐ海』が選ばれました。
おめでとうございます。
とても描写がうまい作品です。
皆さん、是非お読みください。
僕の直木賞予測記事はこちらです。
第172回直木賞受賞作予測 - 山内 圭のブログ(Kiyoshi Yamauchi's Blog)
今さらながら、昨年5月の姉妹都市ニューパルツ公式訪問団によるニューパルツ訪問の記録の続きを書きます。
2024年5月14日(火)、まずはニューパルツの新設の消防署を見学させていただきました。
この消防署訪問は、次のような経緯で実現しました。
コロナ禍において直接の訪問交流ができない間、姉妹都市間でZoomを使ったオンライン交流の機会を3度持ったのですが、その中でNew PaltzのRogers市長と新見市の戎市長(当時)の間で、それぞれの自治体で消防署の新設が話題となりました。
そして、New PaltzのRogers市長が2023年10月に新見市を訪問された際、新見市の消防署の視察をされました。
その流れの中で、今回新見市長をはじめとする公式訪問団がNew Paltzを訪問した際、New Paltzの新築の消防署を訪問する機会を設けてくださいました。










次にはNew Paltz Rotary Clubの訪問を行いました。
これは2018年の豪雨災害の時に、New Paltz Rotary Clubから新見ロータリークラブを通じて新見市への義援金をいただいたことに対するお礼訪問でした。
次期会長の豪邸にお招きいただき楽しいひと時を過ごしました。

以前からの交流で旧知のアイリーンさんとも再会することができました。

その後、Mohonk Mountain Houseに行きました。




ここでは、Gullickson社長のご厚意で、ランチをごちそうになりました。

午後は、まず、New Paltz High Schoolを訪問させていただきました。

この日は、どなたかが亡くなられたか何かで、半旗でした。


美術室で生徒たちの作品を見たときの様子です。

ここは、ニューパルツ国際交流協会のSue Sherburneさんがお務めだった学校であり、Sueさんが在勤中に新見市との交流を記念して植えられたFriendship Treeと名づけられた桜の木の前で記念撮影をしました。
高校では両自治体内の高校同士の交流についての協議も行われました。
その後は、ニューパルツのダウンタウンを散策しました。

そして、夕方はエルティング図書館において私たちのための送別会を開催してくださいました。
とても短い滞在だったため、歓迎会の翌日の送別会となりました。



ソフトボールの交換を行いました。





今回の交流でもお世話になり、またこれまでの交流でも本当にお世話になっている方々と再会を喜び、再会を誓い合い、通訳業務は大変ながら楽しいひと時を過ごしました。
前日の交流についてはこちらをどうぞ。
2024年5月12日~17日にかけて新見市の姉妹都市ニューパルツへの公式訪問団員としての派遣からの帰国翌日から、鳴滝祭が開催されました。
写真部員の学生たちの写真に交ぜてもらい、顧問として今回も僕の作品も出展してもらいました。

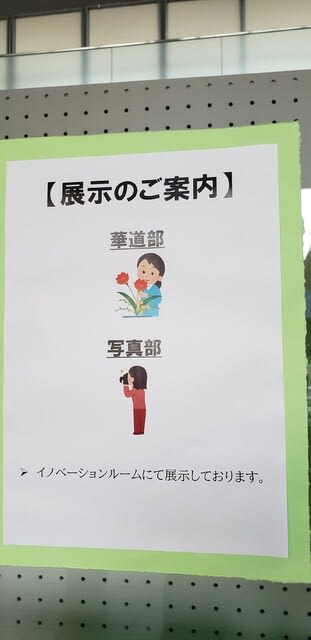
今回のテーマは「好きな食べもの」と「懐かしい思い出」でした。



僕の作品は、「好きな食べもの」は

「懐かしい思い出」は

でした。
ちなみにこのフォークとスプーン、僕が大学入学時に一人暮らしをする際に買った食器セットの生き残りで、今でも自宅で新しいものに交じって使っています。
前回の写真部出展については、こちらをどうぞ。
2024年4月1日付で、修学・キャリア支援センター長を拝命しました。
2019年4月1日から2021年3月31日まで2年間、キャリア支援センター長(当時)を務めましたので、返り咲きということです。

修学・キャリア支援センター長の挨拶は大学のウェブサイトで紹介していただいております。
2024年3月16日(日)、2023年度の卒業式が行われました。

今回は会場係を務めました。
卒業式に続いて、卒業生から謝恩会を開いていただきました。
山内ゼミ生たちも無事卒業となりました。


学生たちが手に持っている紙は、山内ゼミの「卒業証書」です。
前年度の卒業式についてはこちらをどうぞ。

2024年3月10日(日)、新見市国際交流協会では国際交流ふれあいデイを開催しました。
コロナのため中止の年もありましたが、国際交流ふれあいデイは、毎年この時期に新見市グラウンド・ゴルフ協会のご協力のもと、市内在住の外国出身の方々とグラウンド・ゴルフを楽しみながら、交流を図っています。
開会式では砂田会長の挨拶

国際交流協会の顧問である小林県議からのご挨拶

をいただき、グラウンド・ゴルフ協会の方によるルール説明の後、グラウンドに出て競技を行いました。

競技後は新見婦人会の方々が作ってくださったおこわを昼食としていただきながら楽しいひと時を過ごしました。

一緒に回ったチームのメンバーと
以前の国際交流ふれあいデイについての記事はこちらをどうぞ。
近年、趣味として直木賞と芥川賞の候補作が発表されると受賞作の予測を行ってきましたが、今回は時間的制約から直木賞に絞って予測を行うこととします。以下のコメントはあくまでも個人の感想です。
朝倉かすみ『よむよむかたる』(文藝春秋)
作品中に用いられる比喩がうまいので、比喩表現に関心がある作者と見受けられました。
受賞にはやや弱いかと思いました。登場人物の把握が難しかったです。
伊与原 新『藍を継ぐ海』(新潮社)
5つの作品を収めた短編集です。それぞれの作品の舞台になっている土地のことをよく調べ作品に取り入れていることがわかりました。また描
写も上手いと感じました。受賞はありうると思いました。
荻堂 顕『飽くなき地景』(KADOKAWA)
東京の歴史を踏まえた物語です。描写がうまい文章、しっかりした小説であると思いました。
実在の人物(作家を含む)も出てきてフィクション中のノンフィクションが面白かったです。
直木賞の有力候補と思いました。
木下昌輝『秘色の契り 阿波宝暦明和の変 顛末譚」(徳間書店)
五章「蠅取り」では、箸で蠅を取る芸が出てきて、有名な宮本武蔵のエピソードを思い出しました。また一章「末期養子」では「阿波の藍か、
藍の阿波か」という言葉があります、などと歴史的描写はうまいと思いましたが、個人的問題ではあると思いますが、物語に入っていけない感
じがしました。
月村了衛『虚の伽藍』(新潮社)
候補作『飽くなき地景』が東京の歴史を踏まえた作品であるのに対し、こちらの作品は京都の仏教界(架空のものですが)を舞台にした作品で、
読んでいて面白かったです。架空の仏教宗派名、寺院名が用いられてはいますが、実在の世界にもこのような人間ドラマがあるだろうと思わせ
る描写力でした。
受賞の有力候補と思いました。
ということで、今回の僕の受賞作予測は、日本史の中で日本の重要な両都、京都と東京の歴史を踏まえた二作品、つまり、月村了衛『虚の伽藍』(新潮社)と荻堂 顕『飽くなき地景』(KADOKAWA)を挙げさせていただきたいと思います。
伊与原 新『藍を継ぐ海』(新潮社)も受賞可能性はあるかもしれませんが、次点とさせていただきます。
受賞作を2作にしているのは、最近の傾向を踏まえています。受賞作は(候補作も)、それだけ本の売り上げが増えるので、本の売り上げを伸ばすことを考える文学界の思惑が反映しているものと思っています。
受賞作の発表は2025年1月15日です。どうぞお楽しみに!
僕のこれまでの直木賞(および芥川賞)受賞予測についてはこちらをどうぞ。
第171回直木賞受賞作予測的中 - 山内 圭のブログ(Kiyoshi Yamauchi's Blog)
年明けの1月2日、昨年を振り返る記事を投稿しようとしましたが、新規投稿欄がいつもと違い、うまく投稿ができませんでした。
メールからの投稿で
この投稿をしましたが、これもこの写真をアップして国際交流ふれあいデイについての記事を書こうとしたのですがうまくいかず、こうなってしまったものでした。
1月2日からgoo blogで不具合があったようで、だから投稿ができなかったことがわかりました。
1月10日現在、僕のアカウントからは以前同様の方法で投稿できそうです。
遅れていますが、昨年の記事を少しずつアップしていこうと思います。
2024年3月3日(日)、ピュアリティまきびにおいて第17回岡山県知事杯児童英語表現発表大会が開催され、審査員を務めさせていただきました。
小学生の皆さんによる見事な英語発表でした。
最後に各審査員からのコメントを述べ、この日覚えたことを今後の国際交流や自分が外国に行った際などに必ず活かすことができる場面があるでしょうということを述べました。
また、暗誦の部で今回から『トム・ソーヤーの冒険』が加わったため、アメリカ文学を研究している僕がマーク・トウェインのこと、『トム・ソーヤーの冒険』について話をするよう要請され、急遽お話をさせていただきました。
第15回岡山県知事杯児童英語表現発表大会で審査員を務めさせていただいた時のことはこちらをどうぞ。
第15回岡山県知事杯児童英語表現発表大会(2021年3月21日) - 山内 圭のブログ(Kiyoshi Yamauchi's Blog)
また、『トム・ソーヤーの冒険』については、こちらをどうぞ。
2024年3月2日(土)、日本ジョン・スタインベック協会「オンライン研究学会」が開催されました。
僕は今回は国士舘大学非常勤講師の加藤麗未先生の「スタインベックとメキシコ革命」の司会を務めました。
実は、外出中だったのですが、駐車場にとめた車の中からスマホでの参加でした。
外出中でも学会に「参加」し「司会を務める」ことができる、とても便利な時代になりました。
ただ、スマホの画面での参加でしたので、小さな画面でやや苦労しましたが…。
The John Steinbeck Society of Japan
前回の日本ジョン・スタインベック協会の学会についてはこちらをどうぞ。
日本ジョン・スタインベック協会2023年度研究学会に参加( 2023年9月3日) - 山内 圭のブログ(Kiyoshi Yamauchi's Blog)
2024年1月28日、DV被害者と子どもの支援実践研究会のDavid Mandel氏によるオンラインセミナーがありました。
セミナー後の交流会の通訳担当をしました。
前回のセミナーに続き二度目の通訳でした。
前回の記事はこちらです。