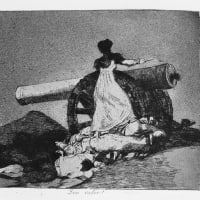篠田桃紅さんがお亡くなりになった。107歳、老衰による逝去。見事である。女性が長生きだとしても、その仕事というか芸術的営為のエネルギーの放出は半端ない。健康のことなんか考えたことはなかった人だ。自由に、個性的に生きるのは、実は二の次で、筆による至高の美しさを表現することだけに心血を注いだ。モノクロの世界から色彩を採りいれたバリエーションは、表現のさらなる高みへの志向か・・。
とにかく、作品を作り続けた結果、彼女がたまさか長く生きた。そう言ったら、篠田さんは「そうもいえるかもね」と興味なさそうに仰ったかもしれない。
篠田作品を純粋に比較した場合、たとえば70歳のときと、100歳のときの作品では、進化とか、表現の差異はあったのだろうか。ニューヨークに行ったときには、篠田の芸術はほとんど完成の域に達していたのではないか。作品制作をつねに求められる、まるでピカソのような芸術家になったのかもしれない。抽象画をしらない愚生は、勝手なことを言っている。
愚生の心の奥底に、末永く生きることの欲望が無意識にあるのか、そんな疑問がもたげている。いつ死んでも悔いはない覚悟はあるのに・・。
篠田桃紅という人の存在を知ったのは、世間ではあたりまえのTV番組を見たこと。彼女が百歳になられて、芸術家としての営為を顕彰するドキュメンタリーだった。老いてなお作品を仕上げるときの集中力を垣間見て、ただただ感嘆した。細身の老いた体躯から、なにかのエネルギーが迸るように見えた。ゆったりした動きのなかに、シュッと切り裂くような筆つかい。
書家として単身ニューヨークに出て、水墨画の前衛美術の大家になったのは、やはり凄まじい美への集中があったからであろう。それが我が儘と批判されようと、独創と称賛されようと、彼女にはどうでもいいことだったはずだ。
百歳を超えたときのエッセイ集(語り下ろし)を読んだことがあるが、いま新しいエッセイ集の刊行を目前にしてあの世に逝かれたそうだ。新聞にはこんな談話が紹介されていた。
「(本が)話題になるのは、私が珍獣だからでしょ。この年の人が何を考えているのか、みんな知りたいのね」と、自分の存在を絶妙に言い表す達観もしていたのだ。
人は自分というものの生きる場をある程度占めているだけで、野放図に広い場で生きているんじゃないみたいね。杭に縛られている紐の範囲しか動けないでしょう。人には何か目に見えない紐があると思うの。その一つが、生まれ育った環境でしょうね。生まれ育った環境の紐の長い人は、行動範囲が自由に近くなっていく。紐が短い人は、範囲が決まってしまう。(中略)字を書いている、ということは紐つきなんですよ。範囲が決まっている。自由がない。自由がないのがいやだったのね。だから墨で抽象画を描くようになった。(『百歳の力』より)
人は何かしらの紐で縛られている。杭につながれて生きている。篠田桃紅さんはそういうくび木から自己を解放し、創造の原野を自由に飛びまわった女性だ。そうした気持ち、魂を自分なりに会得できたらと願う。そう願うだけでも、ある種の生きがいとして励みになる。それでいいのだと思う、今日この頃である。