2018年5月5日に発行された日本経済新聞紙の朝刊2面に掲載された見出し「肩車型社会 回避なるか 就業率上昇で支え手増」を拝読しました。
少子高齢化が進む日本では、高齢者の生活を支える現役世代の人数が年々減り、いずれは現役世代1人で高齢者1人を支える「肩車型社会」の社会が来ると予想されています。
この「肩車型社会」の到来を避けるために、働く人を増やす就業率上昇によって、社会保証費の“支え手”を増やす考え方が始まりそうだそうです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「『肩車型社会』回避なるか 就業者増え支え手増える」と報じています。
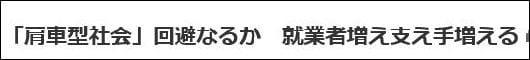
要は、60歳での定年制度から65歳定年制に変え、さらに65歳以上の高齢者でも働きたい希望者は働く世界を目指しています。これによって社会保証費の“支え手”を増やす考えです。
総務省が行った「労働力調査」「人口推計」を基にした試算では、2017年には現役世代(15歳から64歳)2,2人が非就労者0.69人を支えていますが、2030年になると現役世代1.9人が非就労者を支えます。
この試算では、22歳以下の方が働いているという仮定ですが、この想定がよくわかりません。日本の大学への進学率を考えると、不思議な仮定です。
また、日本ではフルタイムの正規社員と、パートタイムの非正規従業員の給料格差などが議論されていません。実際にはパートタイムの非正規従業員が増えているからです。何を前提にした試算なのかよく分かりません。
この記事でも、労働時間や年齢によって給料が決まる仕組みを改め、働いた成果によって給料水準が決まる仕組みが必要と指摘します。しかし、そのためには多くの方の議論が必要になりますが、その仕掛けづくりはかなり難しいようです。
現在は、65歳以上の高齢者でも男性が就業率は30パーセント、女性は15パーセントになっているそうです。
この記事とは別に、総務省は5月4日に14歳以下の子供(日本に住む外国人の方も含みます)は1553万人と前年度に比べて17万人減り、過去最小になったと発表しています。子供の人口減は止まりそうにありません・・。
また、さらに別の解説記事では、見出し「年金繰り下げ 選択柔軟」と、公的年金を受け取る年齢を遅らせて、その後の公的年金の受取額(絶対額)を増やす年金額の試算を示しています。なかなか微妙な試算提示です。60歳ぐらいの年齢の方はいろいろと試算した方がよさそうです。
少子高齢化が進む日本では、高齢者の生活を支える現役世代の人数が年々減り、いずれは現役世代1人で高齢者1人を支える「肩車型社会」の社会が来ると予想されています。
この「肩車型社会」の到来を避けるために、働く人を増やす就業率上昇によって、社会保証費の“支え手”を増やす考え方が始まりそうだそうです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「『肩車型社会』回避なるか 就業者増え支え手増える」と報じています。
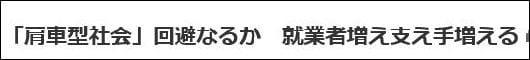
要は、60歳での定年制度から65歳定年制に変え、さらに65歳以上の高齢者でも働きたい希望者は働く世界を目指しています。これによって社会保証費の“支え手”を増やす考えです。
総務省が行った「労働力調査」「人口推計」を基にした試算では、2017年には現役世代(15歳から64歳)2,2人が非就労者0.69人を支えていますが、2030年になると現役世代1.9人が非就労者を支えます。
この試算では、22歳以下の方が働いているという仮定ですが、この想定がよくわかりません。日本の大学への進学率を考えると、不思議な仮定です。
また、日本ではフルタイムの正規社員と、パートタイムの非正規従業員の給料格差などが議論されていません。実際にはパートタイムの非正規従業員が増えているからです。何を前提にした試算なのかよく分かりません。
この記事でも、労働時間や年齢によって給料が決まる仕組みを改め、働いた成果によって給料水準が決まる仕組みが必要と指摘します。しかし、そのためには多くの方の議論が必要になりますが、その仕掛けづくりはかなり難しいようです。
現在は、65歳以上の高齢者でも男性が就業率は30パーセント、女性は15パーセントになっているそうです。
この記事とは別に、総務省は5月4日に14歳以下の子供(日本に住む外国人の方も含みます)は1553万人と前年度に比べて17万人減り、過去最小になったと発表しています。子供の人口減は止まりそうにありません・・。
また、さらに別の解説記事では、見出し「年金繰り下げ 選択柔軟」と、公的年金を受け取る年齢を遅らせて、その後の公的年金の受取額(絶対額)を増やす年金額の試算を示しています。なかなか微妙な試算提示です。60歳ぐらいの年齢の方はいろいろと試算した方がよさそうです。



















