☆仕事の前に更新しておきましょうかね^^
◇ ◇ ◇
[私の1991年のメモ日記・2(好評なので^^;)] (2007/07/21 20:49)
▼好評のようなので、また転載する^^
今日は、姪っ子のバレエの発表会に行ったのだが、
姪っ子のダンスが非常にうまくなり、マジで感動してしまった^^
また、発表会には、3歳くらいの女の子も出ていたのだが、寸足らずの手足を棒のように動かす様がメチャ可愛かった^^
# # # # #
☆1991年11月27日(水)
昨夜は徹夜でゼミ発表の草稿の清書。とりあえず書き終わると、AM5時、さすがにまたもバイトを休んでしまう。丸井に11・12・1月分のローンを払い、家賃を下ろすと、第一勧銀の自分の定期預金からの借金もあり、今月稼いだ14万円、プラマイ0と消える。昨日と今日、仕事休んでしまったのは、後々、大きな悪影響を生むだろう・・・。さあ、ゼミ発表だっ! 僕が2時に学校に着くと、広瀬君は来ていたが、星名さんがまだだった。どうした星名!? で、星名さんが遅れてきたと思ったら、今度は広瀬君の作業が進まない。どうした広瀬!? ともあれ、原稿をプリントし、三人でホッと一安心し、コーヒーを飲む。さて、発表! そして先生との問答、緊張しながらも言いたいことは言えた。終わった後に、半澤さんが、僕の発表に対し、「力作じゃん」と肩を叩いてくれて、それがメチャ嬉しかった。
☆1991年6月25日(火)
「日分特研(近代)」のレポートを、今日の三次限目までに書かなくてはならないなあ。昨日は、「女の一生」を読んだわけだが、一つの作品をじっくりと読み込むのはいいことだと思う。読み飛ばしていったら、頭に残らないものなあ。でも、あと5時間でレポートを一本あげなくちゃならないのは辛いもので。・・・だが、思ったよりスムーズに書けた。もちろん、内容が問題となるのだが。バイトを終え、サンプラ(中野サンプラザ)の横を通っていると、北島三郎が裏口から出てきた。日に焼けていて、服装がヤクザのようだった。空には、少し欠けた月が雲の隙間から見え、美しかった。ビールを飲み、すみやかに寝る。
☆1991年6月26日(水)
暑い。メチャ暑い。扇風機からの生温い風が熱い。アパートの下では、大家の子のチーちゃんがさっきから泣いていて、更に暑い。おっと、咳き込みつつ、泣きやんだぞ。面倒臭いので、学校には行かなかった。5時半から再放送の「ドラゴンボール」を見て、7時から「ドラゴンボールZ」を見た。面白いけど、「Z」の方は、絵がかなり雑だ。特に背景が。アニメーターの賃金の低さから、人が集まらないと言うニュースを見たけど、その影響なのかなあ。昨日から暑くて、読んでて充分に楽しめないのだが、雑誌を買いすぎた。「キネ旬」「SPA」「シティロード」「ミスターマガジン」「少年マガジン」・・・。
☆1991年6月27日(木)
暑い日だった。後日分かった事だが、観測至上6月では最高だそうだ。38℃、温室効果! ジムでも、今までになく汗をかいた。授業中の大ホールの中は、一種異様な熱気で、汗がしたたった。机と、置いている腕の間に水滴が溜まった。山本梨香子というAVギャルのビデオを借りてくる。すっごく美人なのだが、すっごくいやらしいので、思わず超興奮する。なんで、こんなに美人なのに、こんなことをしているのだろうと、しみじみと考えてしまう夏のはじまりだった。今日のとんねるずはメチャ笑った。二人とも頑張ってるなあ、暑いのに。「巨人の星」のパロディー、「博士と助手」のコント。
☆1991年6月28日(金)
今日も負けずに暑かった。夏のアルバイトはどうしようかと思っている。学校もないことだし、電話加入権のローンや沖縄旅行のために、金を稼がにゃあならん。まあ、いろいろ考えよう。昨日、菅君が、新橋駅のパナソニックの電光掲示温度計を見たら、35℃だったそうだ。今日は31℃、まあボチボチか。ジムでも汗をかき、帰宅。
◇
▼金がないない、と言いつつ、妙に楽しげに暮らしてやがる。
まあ、保険とも年金とも税金とも無縁だからなあ、学生は・・・。
(2007/07/21)
◇ ◇ ◇
こちらが山本梨香子ですな。
今で言う、柴崎コウのようなキツネ顔の美人でした。
でも、エロかった^^;
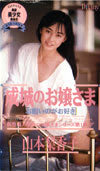
ネットで検索すると、多くの人の思い出のAVギャルのようですね^^
(2009/04/14)
◇ ◇ ◇
[私の1991年のメモ日記・2(好評なので^^;)] (2007/07/21 20:49)
▼好評のようなので、また転載する^^
今日は、姪っ子のバレエの発表会に行ったのだが、
姪っ子のダンスが非常にうまくなり、マジで感動してしまった^^
また、発表会には、3歳くらいの女の子も出ていたのだが、寸足らずの手足を棒のように動かす様がメチャ可愛かった^^
# # # # #
☆1991年11月27日(水)
昨夜は徹夜でゼミ発表の草稿の清書。とりあえず書き終わると、AM5時、さすがにまたもバイトを休んでしまう。丸井に11・12・1月分のローンを払い、家賃を下ろすと、第一勧銀の自分の定期預金からの借金もあり、今月稼いだ14万円、プラマイ0と消える。昨日と今日、仕事休んでしまったのは、後々、大きな悪影響を生むだろう・・・。さあ、ゼミ発表だっ! 僕が2時に学校に着くと、広瀬君は来ていたが、星名さんがまだだった。どうした星名!? で、星名さんが遅れてきたと思ったら、今度は広瀬君の作業が進まない。どうした広瀬!? ともあれ、原稿をプリントし、三人でホッと一安心し、コーヒーを飲む。さて、発表! そして先生との問答、緊張しながらも言いたいことは言えた。終わった後に、半澤さんが、僕の発表に対し、「力作じゃん」と肩を叩いてくれて、それがメチャ嬉しかった。
☆1991年6月25日(火)
「日分特研(近代)」のレポートを、今日の三次限目までに書かなくてはならないなあ。昨日は、「女の一生」を読んだわけだが、一つの作品をじっくりと読み込むのはいいことだと思う。読み飛ばしていったら、頭に残らないものなあ。でも、あと5時間でレポートを一本あげなくちゃならないのは辛いもので。・・・だが、思ったよりスムーズに書けた。もちろん、内容が問題となるのだが。バイトを終え、サンプラ(中野サンプラザ)の横を通っていると、北島三郎が裏口から出てきた。日に焼けていて、服装がヤクザのようだった。空には、少し欠けた月が雲の隙間から見え、美しかった。ビールを飲み、すみやかに寝る。
☆1991年6月26日(水)
暑い。メチャ暑い。扇風機からの生温い風が熱い。アパートの下では、大家の子のチーちゃんがさっきから泣いていて、更に暑い。おっと、咳き込みつつ、泣きやんだぞ。面倒臭いので、学校には行かなかった。5時半から再放送の「ドラゴンボール」を見て、7時から「ドラゴンボールZ」を見た。面白いけど、「Z」の方は、絵がかなり雑だ。特に背景が。アニメーターの賃金の低さから、人が集まらないと言うニュースを見たけど、その影響なのかなあ。昨日から暑くて、読んでて充分に楽しめないのだが、雑誌を買いすぎた。「キネ旬」「SPA」「シティロード」「ミスターマガジン」「少年マガジン」・・・。
☆1991年6月27日(木)
暑い日だった。後日分かった事だが、観測至上6月では最高だそうだ。38℃、温室効果! ジムでも、今までになく汗をかいた。授業中の大ホールの中は、一種異様な熱気で、汗がしたたった。机と、置いている腕の間に水滴が溜まった。山本梨香子というAVギャルのビデオを借りてくる。すっごく美人なのだが、すっごくいやらしいので、思わず超興奮する。なんで、こんなに美人なのに、こんなことをしているのだろうと、しみじみと考えてしまう夏のはじまりだった。今日のとんねるずはメチャ笑った。二人とも頑張ってるなあ、暑いのに。「巨人の星」のパロディー、「博士と助手」のコント。
☆1991年6月28日(金)
今日も負けずに暑かった。夏のアルバイトはどうしようかと思っている。学校もないことだし、電話加入権のローンや沖縄旅行のために、金を稼がにゃあならん。まあ、いろいろ考えよう。昨日、菅君が、新橋駅のパナソニックの電光掲示温度計を見たら、35℃だったそうだ。今日は31℃、まあボチボチか。ジムでも汗をかき、帰宅。
◇
▼金がないない、と言いつつ、妙に楽しげに暮らしてやがる。
まあ、保険とも年金とも税金とも無縁だからなあ、学生は・・・。
(2007/07/21)
◇ ◇ ◇
こちらが山本梨香子ですな。
今で言う、柴崎コウのようなキツネ顔の美人でした。
でも、エロかった^^;
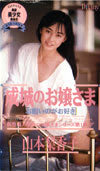
ネットで検索すると、多くの人の思い出のAVギャルのようですね^^
(2009/04/14)

















