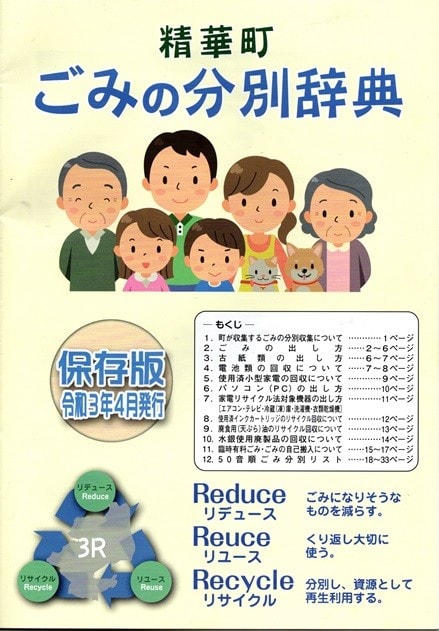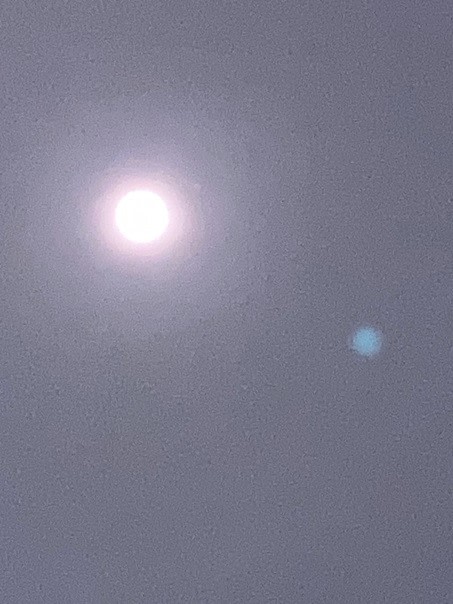朝日歌壇の入選歌(選者は馬場あき子さん、佐佐木幸綱さん、高野公彦さん、永田和宏さん)より、戦争を詠んだ歌を、わんちゃんが独断で選り抜きを。
☆⇒共選作
2024年9月掲載分より
馬場あき子選
養蜂家への支援にもなるウクライナのひまわりの蜜のあまさせつなし(盛岡市)山内 仁子
帰国して笑顔弾ける選手団こんな世代を戦地に送りし(塩尻市)原 田鶴子
【評】若々しいオリンピック選手団の帰国。眺めつつ思う学徒出陣の光景など。かの日の悲痛な群像とのちがいを嚙(か)み締める。
被爆者なき時代近づく令和の世語り部となる被爆四世(石川県)瀧上 裕幸
【評】被爆四世の自覚と責任の思いは実に切実だ。
カメラレンズひたと見据えし片足のガザの少女に問われる我ら(大阪市)田中 秋子
【評】ガザの映像。片足を爆撃などで失った少女の眼(め)は、戦争の惨(さん)をレンズを通して世界の人々に問うている。
立って生きる夢中で生きるプラスチックなどガレキで義足を産むガザの人(木更津市)小田きく江
夏祭浴衣に照れるクルドの子右手に金魚左手ケバブ(朝霞市)青垣 進
『ケバブとは?』こちら
佐佐木幸綱選
戦争を忘れ飢餓さえ忘れおり「お米育ちの豚」など食べて(水戸市)中原千絵子
満州を知らずに育ちし我なれど日本を知らぬ兄を忘れず(横浜市)白川 修
【評】「兄」は満州で他界してしまったのだ。
高野公彦選
ミサイルも砲弾も飛ばぬセーヌ川トリコロールの花火が上がる(観音寺市)篠原 俊則
聖火灯り旗や望みや妨害を愛の讃歌が包み込みゆく(京都市)中谷 康範
【評】一首目と二首目、戦争やテロに心を痛めつつも、パリ五輪の開催を喜び、開会式を見て楽しんでいる歌。
八月六日は被爆二世として祈り九日になれば曽祖母を悼む(町田市)北沢 洋子
【評】6日は親が広島で被爆し、9日は長崎で曽祖母が被爆死した、の意と解釈した。
九条のおかげというが現実は自衛隊もあり米軍もいる(東京都)茶木登茂一
遺骨なき七十九年の空白よ戦死せし義父の墓じまいする(松戸市)遠山 絢子
銃弾で下肢奪はれしガザの男子パリの大地に砲丸を投ぐ(朝霞市)岩部 博道
永田和宏選
B29を「にじゅうきゅう」と読むアナウンサーありて遥かに遠のく戦後(五所川原市)戸沢大二郎
【評】戸沢さん、間違いではないだけに、一層時代の隔たりを感じざるを得ない。文字としての記録を如何(いか)にリアルな記憶として継承していくかが問われる。
広島に百年草は生えないと噂を信じた小二の夏に(取手市)緑川 智
二年経しウクライナでの倍以上一年満たぬガザの犠牲者(五所川原市)戸沢大二郎
五輪へは行けなかったウクライナ選手たち「だって私は死んだのだから」(生駒市)辻岡 瑛雄
【評】ガザ、ウクライナの歌も途絶えることはないが、辻岡さんの一首は、AIによって再現された死者の声。本紙8月13日の記事から。
『番外編』朝日川柳 山丘春朗選
ポリオさえ仏に見える地獄ガザ(静岡県 増田謙一郎)
【評】接種のため一時休戦。
殺すなよワクチン打ったその子らを(神奈川県 奈良握)
【評】もう攻撃やめよ。
『赤旗日曜版:9/15号』
すし詰めの引揚げ列車に九九を誦(す)す級友(とも)に倣(なら)ひし八歳の夏(静岡県 遠山長春)
終戦の八月巡りてページ繰る吾の戦後史黒塗り教科書(長野県 古藤良枝)
☆⇒共選作
2024年9月掲載分より
馬場あき子選
養蜂家への支援にもなるウクライナのひまわりの蜜のあまさせつなし(盛岡市)山内 仁子
帰国して笑顔弾ける選手団こんな世代を戦地に送りし(塩尻市)原 田鶴子
【評】若々しいオリンピック選手団の帰国。眺めつつ思う学徒出陣の光景など。かの日の悲痛な群像とのちがいを嚙(か)み締める。
被爆者なき時代近づく令和の世語り部となる被爆四世(石川県)瀧上 裕幸
【評】被爆四世の自覚と責任の思いは実に切実だ。
カメラレンズひたと見据えし片足のガザの少女に問われる我ら(大阪市)田中 秋子
【評】ガザの映像。片足を爆撃などで失った少女の眼(め)は、戦争の惨(さん)をレンズを通して世界の人々に問うている。
立って生きる夢中で生きるプラスチックなどガレキで義足を産むガザの人(木更津市)小田きく江
夏祭浴衣に照れるクルドの子右手に金魚左手ケバブ(朝霞市)青垣 進
『ケバブとは?』こちら
佐佐木幸綱選
戦争を忘れ飢餓さえ忘れおり「お米育ちの豚」など食べて(水戸市)中原千絵子
満州を知らずに育ちし我なれど日本を知らぬ兄を忘れず(横浜市)白川 修
【評】「兄」は満州で他界してしまったのだ。
高野公彦選
ミサイルも砲弾も飛ばぬセーヌ川トリコロールの花火が上がる(観音寺市)篠原 俊則
聖火灯り旗や望みや妨害を愛の讃歌が包み込みゆく(京都市)中谷 康範
【評】一首目と二首目、戦争やテロに心を痛めつつも、パリ五輪の開催を喜び、開会式を見て楽しんでいる歌。
八月六日は被爆二世として祈り九日になれば曽祖母を悼む(町田市)北沢 洋子
【評】6日は親が広島で被爆し、9日は長崎で曽祖母が被爆死した、の意と解釈した。
九条のおかげというが現実は自衛隊もあり米軍もいる(東京都)茶木登茂一
遺骨なき七十九年の空白よ戦死せし義父の墓じまいする(松戸市)遠山 絢子
銃弾で下肢奪はれしガザの男子パリの大地に砲丸を投ぐ(朝霞市)岩部 博道
永田和宏選
B29を「にじゅうきゅう」と読むアナウンサーありて遥かに遠のく戦後(五所川原市)戸沢大二郎
【評】戸沢さん、間違いではないだけに、一層時代の隔たりを感じざるを得ない。文字としての記録を如何(いか)にリアルな記憶として継承していくかが問われる。
広島に百年草は生えないと噂を信じた小二の夏に(取手市)緑川 智
二年経しウクライナでの倍以上一年満たぬガザの犠牲者(五所川原市)戸沢大二郎
五輪へは行けなかったウクライナ選手たち「だって私は死んだのだから」(生駒市)辻岡 瑛雄
【評】ガザ、ウクライナの歌も途絶えることはないが、辻岡さんの一首は、AIによって再現された死者の声。本紙8月13日の記事から。
『番外編』朝日川柳 山丘春朗選
ポリオさえ仏に見える地獄ガザ(静岡県 増田謙一郎)
【評】接種のため一時休戦。
殺すなよワクチン打ったその子らを(神奈川県 奈良握)
【評】もう攻撃やめよ。
『赤旗日曜版:9/15号』
すし詰めの引揚げ列車に九九を誦(す)す級友(とも)に倣(なら)ひし八歳の夏(静岡県 遠山長春)
終戦の八月巡りてページ繰る吾の戦後史黒塗り教科書(長野県 古藤良枝)