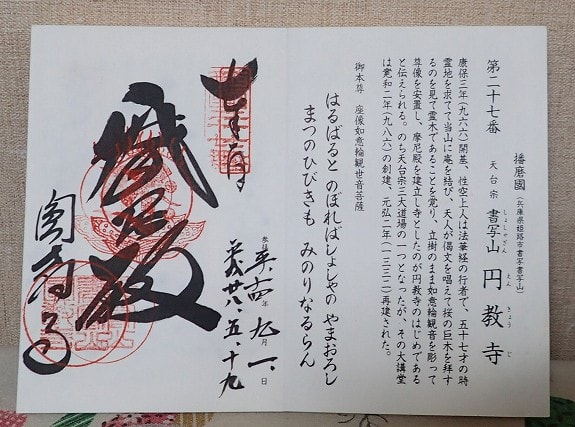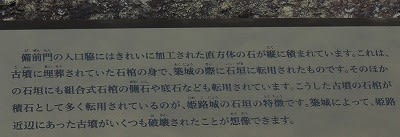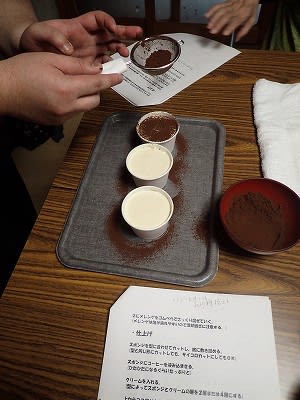シチダンカ(七段花)ユキノシタ科


シチダンカはヤマアジサイの八重化したものと言われています。
六甲山の「幻の花」とも言われています。
この花はシーボルトが「日本植物誌」で紹介して以来、日本人のだれもがその実物を見た人がなく、”幻のアジサイ”とよばれて長い間さがしつづけられていました。ところが、たまたま六甲ケーブル西側で昭和34年(1959)に見つかりました。それはシーボルトが紹介して以来約130年ぶりになります。その間、この花は誰の目にもとまらず、まぼろしの花であったわけで、これが「幻の花」といわれる由来です。
森林植物園ではこれを約3000株に増殖栽培し、6月中旬から下旬にかけて園内アジサイ園では見ごろとなります。(‘95六甲高山植物園森林植物園ニュース)
そんなシチダンカがウチの庭で咲いているのは? こちら
アマリリス(Amaryllis)ヒガンバナ科


中南米原産と南アフリカ原産のものがあります。5月~6月に直径7~10cmのユリに似た花を咲かせます。
1本の茎に2~3輪の花(ウチでは3~4輪)をつけ花の色も赤、白、ピンク、オレンジと咲きます。
わが国には江戸の天保から安政の時代に渡ってきました、アマリリスといいますとベートーベンの「第九第4楽章の歓びの歌」の作詞者である岩佐東一郎が作詞・ギース作曲のアマリリスを思い出します。ルイ13世が作曲したとか、フランス民謡だともいわれています、いずれにしてもフランスがルーツのようですね・・・
花言葉:誇り
ウチのアマリリスは一株は舅からのプレゼントと一株はご近所つながりのKさんからいただいたもの、
どちらも鉢植えでいただいたのを土におろしました、するとね、今や8株に増えてるんですよ、まんべんなく花をつけるので数えるのが大変なくらい咲いてくれました。今年の花が終わると一株はOさんちのお庭にお嫁入り・・・
ウチの庭の草ぬきですが、いつもは春のお彼岸の頃、冬の間にジミ~~に生えていた庭の草たちをイッキに草抜きやるんですが、今年はなんとなくしそびれて、草に埋もれてしまってシャクヤクの豪華なお花が一輪も咲いてくれませんでした、わんちゃんとしては猛反省です。
一大決心をして、さぁ~草抜するぞぉ~~ いつものようにウォークマンしながら・・・
1時間もとっくに過ぎると腰に来ますね、するとちょっとはマシな庭になったかな?(もう少し残ってるけど、また今度ね)
ゴミ袋ギュウギュウに2袋ありました。
草ぬきしながら、写真も撮りながら・・・
クレマチス


ユキノシタ ホタルブクロ


トケイソウ

チェリーセージ ドクダミ


こんな蛾が居ました

マドガ 学名 Thyris usitata マドガ科
択捉島から九州まで分布する日本の固有種。
属名 Thyris はギリシア語のθύρα (窓、ドア、入り口)から
翅の中室にある半透明の白色斑を窓に見立てたもの。
和名の窓蛾も同様。
そしてこんなクモも 大きさ5mmほど

図鑑で見ると「チビアカ・・・」によく似てるんだけど
「オニグモの仲間の幼体のようにも見えます。」っと、詳しい名前はワカリマセン
「なつぐさ」 釈 迢空
沙地には、 すべり莧(ヒユ) 力芝
頑(カタクナ)に 根深めて、
わづらはしき夏 いよいよ長く――、
地しばり 熊桜
せんもなき装ひに
人を怒らしむ。
山ごばう 藪がらしの花過ぎて、
その実の げに 我は貌(ガホ)なるが、
目に立ちて侮(アナヅラ)はし――。
もの思はしげに 蕺草(ドクダミ)の青白み――
情(ナサケ)濃く 萱草(クワンザウ)の婉(ナヨ)めく――、
見かけだふしは、矮叢(ボサヤブ)にもあれど、
叢(クサムラ)の古代日本の よろしさ――。
鴨頭草(ツキグサ)の 縹(ハナダ)深き瞳(マミ)――
たびらこの空色の――小き紋章――。
甘んじて 雑草(アラクサ)に対ふおのれの
ゆゑ知らぬ気おくれを叱りて、
一挙に薙ぎ仆して 火をかけぬ
↑道草さんから。
《おまけ》