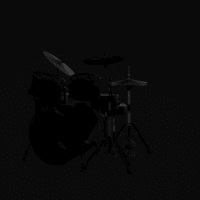今回は、音楽記事です。
最近は日本のフォークについて書いていますが……この流れを受けて、今回はいよいよ高石友也さんについて書こうと思います。
高石友也――
本邦フォーク界における巨人の一人といえるでしょう。
いろんな意味で、日本のフォークを体現する人だともいえると思います。
その‟いろんな意味”のうちの一つは、海外の曲を日本語訳で歌う作品が多いということが挙げられるかもしれません。
新しいジャンルは基本的に海外の文物を移入するところから始まる――これは、日本文化の特質といえるでしょう。
フォークの場合も、アメリカでフォークリバイバルという動きがあったのが日本に伝わってきてフォークブームを起こしたという側面があります。
アメリカのフォークソングを日本語にして歌うという高石さんのやり方は、それを象徴するものといえるでしょう。
そのカバー元は、ピート・シーガーであったり、トム・パクストンであったりします。
バリー・マクガイア「明日なき世界」なんかもあって、後にRCサクセションがカバーしたバージョンも、高石さんの訳をもとにしています。
代表曲「受験生ブルース」も、おおもとをたどるとボブ・ディランに行きつきます。
中川五郎さんがディランの歌を替え歌にした詞があって、その詞に新たに曲をつけたもの。
「サイン、コサインなんになる」というそのユーモラスな歌が、大ヒットしました。
しかし、高石友也というミュージシャンを受験生ブルースの人だというのはあまりにも大雑把な評価ということになるでしょう。
この方は、硬派な反戦歌といったような歌も多く歌っているのです。
そのなかから、ここでは「冷たい雨」という歌を紹介したいと思います。
これは、マルビナ・レイノルズのBitter Rain という歌を日本語でカバーしたものです。
高石さんのフォークアルバム第一集に収録されています。
このアルバムには、マルビナ・レイノルズの代表曲である
Little Boxes を訳した「小さな箱」も収録されています。
「冷たい雨」の詞は、次のようなものです。
静かに暮らしたい けれど目まぐるしい僕らの毎日
でもどこかで着るものもない子が 冷たい雨に打たれてる
私一人なら 飢えや寒さから身は守れる
でもどこかでおなかをすかせた子が 冷たい雨に歩いてる
誰のためにか若者たちが殺されてゆく
そしてどこかで血を流した子が 冷たい雨に死んでゆく
いかにも60年代の社会派フォークソングという歌です。
こういう歌が出てきたのも、あの時代だったからこそと思えます。ここで歌われている内容は、ベトナム戦争のみにとどまらず、飢餓や貧困などさまざまな問題です。「プロテストソング」というところも超えた内容といえるでしょう。
海外の曲の日本語訳をやるということは、その目のつけどころみたいな部分が重要になってくるわけですが……マルビナ・レイノルズの曲の中でもさほど有名とはいえないこういう歌をチョイスしてくるのは、さすがの高石友也というところです。
さて……
高石友也の名前が出てきたところで、ついでにURCレコードというものについて書いておきましょう。
日本のフォークを考えるとき、URCレコードに触れておかないわけにはいきません。
多くの伝説的フォークシンガーを輩出したレコード会社であり、また、単にフォークというジャンルにとどまらない、大きな可能性を秘めた実験でもありました。
URCは、会員制組織として出発しました。
会員たちで会費を出し合い、大手のレコード会社からはリリースされないような音楽を聴こう――という組織。もともとは「アングラ・レコード・クラブ」と名乗っていて、これが発展してURCレコードとなったのです。
その設立において、中心的な役割を果たしたのが、高石事務所でした。
最初は会員数の上限を千人に設定して細々とやっていましたが、入会希望者があとを絶たず、制作本数も増加していったために、URCレコードという新会社を創設し、レコードを市販するようになったのです。このURCこそが、日本最初のインディーズレーベルといわれています。
ここから、たとえばフォーク・クルセダーズがリリースしようとしてできなかった「イムジン河」(と、その原語バージョン)や、高田渡の問題作「自衛隊に入ろう」(奇しくも、この曲もマルビナ・レイノルズの作詞した歌がもとになっています)などが出てきたわけです。URCレコードとなってからの最初のアルバムは‟フォークの神さま”と呼ばれた岡林信康さんの作品集であり、そこでジャックスの面々が伴奏したりもしていました。
こう書いただけでも、その実験性、前衛性はじゅうぶんに伝わってくるでしょう。
URCレコードの出発点にあったのは、このブログで何度か触れてきた、アーティストがみずからレコード会社を作るというDIY精神です。
パンクスたちのお家芸であり、エルヴィス・プレスリーの映画『監獄ロック』にその原型が見られるということを、このブログでは書いてきました。
音楽業界のお偉い方にむかって、「俺たちの音楽の良さを認めないなら、勝手に自分たちで作って自分たちで売るよ」という、既成の価値観に対するある種の宣戦布告。
そしてそれが若いリスナーにバカ受けして、お偉い方のほうが価値観の修正を迫られる……それと同じことが、日本でも一定程度起きていたのです。
URCの場合そこまで挑戦的なものではなかったとも思いますが、URCのレコードがヒットを連発したことで、大手レコード会社側もフォークに注目するようになり、それが70年代のフォークブームにつながったということはいえるでしょう。
若者のDIY的行動が大人の価値観を覆す――そのスピリッツが日本にもあった。
それが、あったがゆえに、草創期のフォークは、自由であり、実験的であり、またメッセージ性も持っていたと思われるのです。
URCはその最前衛であり、やはりDIY的な活動から生まれたエレックレコードと並んで、この国のフォークを育みました。
では、そのスピリッツは、その後どうなっていったのか……?
この点に関しては、一口ではいえないものがあります。
経過をすっ飛ばして結末だけをいえば、URCレコードは1977年にその活動を終えました。
1977年――エルヴィスがこの世を去った年であり、パンクが勃興し、クラッシュは「エルヴィスも、ビートルズもローリング・ストーンズもいらない」と歌いました。
それは偶然ですが……しかしなにかが失われてしまったというか、一つの分岐点を超えたというふうに、私には感じられます。
そのあたりのことは、これからフォークソングについて書いていくうちに、また言及することがあるでしょう。
今回は、ちょっと長くなったので、このあたりで。