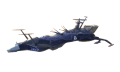George Harrison - All Things Must Pass
今回は音楽記事です。このカテゴリーでは以前ポール・マッカートニーについて書きました。そこからのビートルズつながりで、今回はジョージ・ハリスンについて書きましょう。ジョージ・ハリスン......
過去記事です。
ジョージ・ハリスンについて書いています。
今回も、プラスアルファとして関連動画をいくつか紹介しましょう。
まず、元記事で言及した曲を。
I Want to Tell You。
ソロ活動期の、日本でのライブ音源です。ポールがつけた「へんてこなピアノ」もちゃんと再現しているのが律儀というか……
I Want To Tell You (Live In Japan, 1991 / 2004 Mix)
ジョージ追悼コンサートにおける Somethingのパフォーマンス。
ポール・マッカートニーがウクレレ弾き語りで歌い始めるという演出です。
Paul McCartney, Eric Clapton - Something (Live)
While My Guitar Gently weeps。
以前、ジョージ追悼コンサートの動画を紹介しましたが、こちらはそれとは別のロックンロール栄誉の殿堂におけるトリビュート。
プリンス、トム・ペティ、ジェフ・リン、スティーヴ・ウィンウッドという豪華な面子です。
2021 Remaster "While My Guitar Gently Weeps" with Prince, Tom Petty, Jeff Lynne and Steve Winwood
この手の動画でジョージ・ハリスン自身が出ているものはそう多くはないようです。
そのレアななかの一つ、ロックンロール栄誉の殿堂における、I Saw Her Standing Thereの動画を。
以前ポールの記事でも紹介したように、これはジョージの曲ではありませんが……
George Harrison, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Bob Dylan and others -- "I Saw Her Standing There"
同じステージにボブ・ディラン、ミック・ジャガー、ブルース・スプリングスティーンとすさまじすぎる面子がそろっており、これはさすがにジョージが埋もれてしまっているといわざるをえません。ディランは後方でギターを弾いているだけであまり目立った動きを見せませんが、これは友人であるジョージへの配慮でしょうか。
せっかくなので、ジョージ自身のソロ曲のMVも一つ。
George Harrison - When We Was Fab
Fabとは、Fab4、すなわちビートルズのことを指しているととるべきでしょう。「俺たちがファブだったころ」というこのタイトルは、過去の栄光にすがっているようにもみえ……まあ、そういうところもあったのかもしれません。
ここからは、カバー曲を。
まずはじめに、オリビア・ニュートンージョンによる What Is Life。
Olivia Newton-John - What Is Life
ニーナ・シモンによる Here Comes the Sun。
ビートルズのジョージ曲といえば、Something と並んでこれが有名でしょう。
Nina Simone - Here Comes the Sun (Audio)
ジョー・ボナマッサによる「タックスマン」。
ロック方面でいうなら、これが私個人としては一番かもしれません。
スティーヴィー・レイ・ヴォーンのカバーも有名で、このバージョンはそっちに近いでしょうか。
Joe Bonamassa - "Taxman" - Live at The Cavern Club
エリック・クラプトンによる「愛はすべての人に」。
この曲は、クラプトンの記事でも紹介しました。彼がこの曲をカバーしたのは、ジョージへの追悼という意味合いでしょう。
Love Comes to Everyone
ビリー・プレストンによる My Sweet Lord。
最近公式MVが公開されて話題となりましたが、ここでは敢えてそっちじゃないほうを。
Billy Preston - My Sweet Lord (Live)