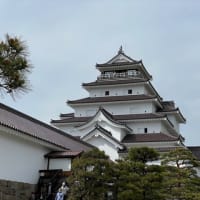いつものように母屋の中央の間で会った。
徐粛は、甥にでも接するように親し気な笑顔を浮かべる。嫌味のないその笑顔を見れば誰でも徐粛を信じるだろうと、西門豹はふと思った。
「大変なことが起きました」
「どうしました」
西門豹は、ことを起こしたのはあなただろうと腹の中で冷ややかに思いながら、射抜くような目で老人を見据えた。
「溜池のほとりで龍の化石が見つかったのです」
「珍しいものではないでしょう。龍の骨なら煎じて飲んだことがあります。子供の頃、病気をした時に母が購《あがな》ってくれました。もっとも、正真正銘の龍の骨なのかどうか、私は存じませんが」
「龍骨《りゅうこつ》」と称する薬は、値段は張るものの比較的簡単に手に入った。市へ行けば行商人が売っている。熱病や中風などの特効薬として用いられた。
「それは龍骨のかけらですな。私も時々飲みます。見つかったのは、龍の全体がそっくりそのまま残っている化石なのですよ」
徐粛は「本当に大きいのですよ」と両手をいっぱいに広げながら、孫を遊びに連れ出そうとする爺やのように目尻に笑い皺を作る。西門豹はどこを見るわけでもなく、黒曜石のような瞳を小刻みに動かした。徐粛がなにを企んでいるのかはわからないが、相手の手に乗ってみなければ事態は動かない。掌で太股を叩き、
「見てみましょう」
と、言って案内を頼んだ。徐粛は、願ったりかなったりだと頷く。
二人は、城市からさほど遠くない現場へ行った。
なんの変哲もない、ひなびた池だった。広さは半里(約二百メートル)四方といったところだろうか。若草が静かに周囲を覆い、藤色のこまかい花が咲き乱れていた。のびやかな春風が水面にさざなみをたて、こぶ牛の水浴びする姿が遠く見える。向こうの池の縁沿いに崩れた低い土塁が続いていた。その昔、ここには小さな邑《ゆう》(城壁で囲った集落や町)があり農民が住んでいたのだが、ずいぶん前に打ち捨てられ、廃墟になっていた。池はかつての邑の貯水池だった。
「あそこです」
徐粛が指差す。
池の一角に純白の幕が張ってある。幕は風を孕《はら》んでは鳩の胸のようにふくらみ、息を吐き出すようにそっとしぼむ。傍には角材が積み上げられ、大工が鉋《かんな》をかけていた。風に煽られた削り屑が浪の花のように舞い上がる。もっこを担いだ人夫がその下を無造作にくぐり抜ける。
二人は幕の内へ入った。
「どうです。素晴らしいではありませんか」
徐粛は感に堪えない声を上げ、豊かなあごひげを自慢気にしごく。
龍の形をした大きな骨格が黄土の上に横たわっている。
西門豹はわずかに右の眉を吊り上げただけで、なにも言わない。化石の頭で立ち止まって両足を揃え、ぶんまわしのように正確な歩幅で足を進めて尻尾の先までの長さを測った。六歩(約六メートル半)あった。西門豹は振り返り、再び全体を見渡した。化石は、磨き上げた大理石のようにまぶしい光沢を放っている。長年土の中に埋まっていたものとはとても思えない。不自然にぎくしゃくと曲がった背骨は、童が描いた絵にも似てまるで玩具のようだ。
「立派なお姿でしょう。昇龍のようですな」
徐粛は、満面に笑みを浮かべた。
「お言葉ですが、そんな風には見えません。私には空の真ん中でまごついて失速した龍のように見えます。さしずめ空を昇りきれない昇り龍、もしくは墜落中といったところでしょう。徐粛殿、どうやって埋めたのですか」
険しいまなざしのまま西門豹は言った。徐粛は、からからと愉し気な声を上げる。冗談だと受け取ったようだ。
「そんな畏れ多いことはいたしませんよ」
「龍ではなく、ただの大蛇かもしれませんね」
「そんなことはございません。そこを見てください」
徐粛は溌剌《はつらつ》とした風情で小走りになり、化石の胸のあたりに近づいた。
「ほら、足があるでしょう。蛇には足がありませんよ」
確かに、足の骨があった。太い足指が三本伸び、指先にはざっくりとした鉤爪《かぎづめ》までついている。
「爪まで念入りにこしえらたのですね。顔はどう見ても牛のようですが」
「龍も顔が長いから似たような形になるのでしょう」
徐粛は、しゃあしゃあと言ってのける。
――証拠と証言さえ揃えられれば、龍の化石を偽造して民をたぶらかした罪で逮捕することもできるな。手荒な真似はあまり気が進まないが。
西門豹は、化石の一点を睨みながら心の内で考えをめぐらした。最善の策は逮捕によって徐粛の権力をそぐことではなく、彼が自分に協力せざるを得ないよう仕向けることだった。
――だが、とりあえず張敏に命じて極秘裏に捜査させるか。逮捕に踏み切る必要が出てこないとも限らない。いずれにせよ、選択肢は多いほうがいい。
西門豹は腹を決めた。
「まだ私が埋めたとお疑いですかな」
「ええ」
西門豹は、張り出した頬に薄笑いを浮かべた。徐粛は、我々は同志だろとでも言いた気になれなれしく西門豹の肩を抱き、
「この池で釣りをしていた者が偶然見つけたのです。が、まったくの偶然だとも思えません。河伯様が私たちになにかを伝えたくて、このお骨をお見せになったのではないでしょうか」
と、耳元へささやきかける。
「と言いますと」
「私は、河伯様が自分たちをもっと大事にしてくれと言っておられるような気がする。私財を投じてここに立派な祠を建て、この龍神様を祀るつもりです。鄴(ぎょう)の民のためにそうするのです。故郷に貢献したいのですよ」
徐粛は、自分の言葉に酔っていた。
――だいたい詐欺師はまず自分を騙して己の妄想に酔いしれるものだ。自分に嘘を信じこませれば、他人を騙しやすい。端《はた》から見れば、嘘をついているようには見えないからな。
西門豹は徐粛を一瞥し、
「贋物《にせもの》を祀ったところでご利益などないでしょう」
と、素っ気なく言った。
「本物ですよ。そう決めつけずに、我々の河伯様に対する熱い想いを理解していただきたいものですな」
徐粛の配下が彩の到来を告げた。
「西門様、彩様の意見を聞こうではありませんか。彩様が本物と言えば、納得なさるでしょう」
徐粛は自信たっぷりだ。
「いいでしょう。彩殿の霊力の高さは私も認めます」
西門豹は、もっともだと頷いた。
彩が現れた。
大きな鷺羽を一枚、髪に挿している。よく似合っていた。
彩は、近所の人に挨拶するようにごく自然な親しみのこもった顔で微笑んだ。西門豹は照れくさくもあり、嬉しくもあった。西門豹も近所の子供の様子を聞くようにこの間の男の子の様子を尋ねた。順調に恢復《かいふく》して、今ではすっかり元気だと言う。龍骨の正体を調べて欲しいと頼むと彩は快諾した。
彩は細長い棒の先を器に入れた清水にひたし、呪文を唱えながら弾くようにして棒を振る。きれいな弧を描いた水滴が化石に振りかかる。軽く目をつむった彩は頭を垂れ、じっと精神を集中させて交霊した。
ふっくらと丸みを帯びた体の周りで、ふっと気流が揺れる。目に見えない微細な波が広がる。清楚な花の香りが西門豹の鼻を撲《う》った。彩の心の香りだと感じた。
――どこか似ている。
西門豹は、遠い記憶をまさぐった。そして、少年時代にあこがれた理知の世界の清明さに似通っていると思い当たった。神々を見つめる心と澄んだ論理の二つがどう結びつくのか、そこまではわからない。ただ似ていると感じた。
十代の頃の西門豹は、理知の世界にこそ真善美がある、そう信じて万巻の書物を読み、師と問答を交わしたものだった。その時に学んだことが、血となり肉となり、心の芯になった。しかし、官吏として生きる日々は、当然のことながら青年期に形成した信念をたやすく実践できるほど容易ではない。もし今ここで彼女を抱きしめれば、現実世界にまみれるなかで失ったすべてを取り戻せるような、そんな想いにも囚われた。
やがて、彩は大きく息をつき、
「龍神さまの姿は感じませんでした。この化石に牛と亀の霊が憑いているのはわかるのですが」
と、汗ばんだ額を手の甲で拭った。
「なにかの間違いでしょう」
徐粛は、とぼけた甲高い声を出す。
「いいえ、龍神さまではありません」
「彩様、どう見ても龍の形をしているではありませんか」
「それはそうですが」
彩は杏子《あんず》のような目をかげらせ、困った風に首を傾げる。誰かが故意に埋めたとは、疑いもしないようだ。巫女として純粋培養された年若の彩には俗世の狡知《こうち》が見えないのだろう。
「彩様、民は龍神様のお骨が出てきたと言って喜んでいるのです。そのようなことをおっしゃられては皆悲しみます」
「恐れおののいている者もいるでしょうね。彩殿が違うと言うのですから、やはり贋物でしょう」
西門豹は割って入り、冷静に諭した。
「なんですと」
常におおらかに振舞っていた徐粛が初めていらついた顔を見せた。彩に本物でないと言われ、かなり動揺している。
「贋物の龍を祀るのはいかがなものでしょうか。徐粛殿の沽券《こけん》に関わると思いますが」
西門豹はあくまでも穏やかに言ったが、徐粛は顔を真っ赤にしてなにも言わない。
「民を正しく導くのが三老殿の役目のはずです。無理が通れば道理が引っこむと申します。よく考えていただきたい。それに、彩殿が困っているではありませんか」
「彩様も彩様だ」
徐粛は、怒ったようにつぶやく。
――世の中の人間は、皆自分に都合のよいことしか言わないものだと思いこんでいるのだな。猿と同じだ。なにが正しいかなどと考えようともしない。他人は自分が利用するためだけにいるとしか思っていないのだろう。
西門豹は唇を噛み、腰に下げた韋を揉んだ。韋の表面に波紋のような皺が寄り、きゅっと軋んだ音が鳴る。
「彩殿は本当のことを言ったまでのこと。咎《とが》めるのは筋違いと言うものでしょう。彩殿は神々に仕える身ですから、嘘をつけるはずがないではありませんか。そんなことをすれば、神罰が下ります」
「口出ししないでいただきたい」
徐粛は老人の癇癪を起こし、きっと唇を歪めて西門豹を睨み据える。
「彩殿は気兼ねして言えないから、私が代わりに申し上げたのです」
「これは鄴(ぎょう)のことであって、あなたには関わりのないことですぞ」
徐粛は、西門豹に背を向け、
「彩様、明日鎮魂祭を行ないます。よろしいですか。民のために祈ってください。彩様が祝詞を上げれば、皆心安らかになるのです」
と、拝み倒さんばかりに繰り返した。西門豹がいくら止めようとしても聞く耳を持たない。
結局、彩は祈祷を上げることになった。皆のためと言われれば断りきれなかった。西門豹はまだ打ち合わせが残っている二人を置き、先に帰路へついた。
彩が名付け親になった蒼風を走らせる道すがら、
――徐粛はやっと挑発に乗ってくれたな。本気で怒らせたから成果は十分だろう。
と、今日のやりとりを思い返しながら総括した。しかし、ふと、彩と徐粛は今頃どんな話をしているのだろうかと考え、なんとも言えないざらつきを心に覚えた。
――鎮魂祭を止めらなかったのは心残りだった。彩殿は道化師もいいところだな。気の毒なことをした。
ああして、彩は大人たちの喰い物にされてしまうのだろう。考え方や立場は違っても、神々へ捧げる彩の純粋な想いを大切に守ってあげたかった。人類の理想から程遠いこの不完全な世界にあって、それはかけがえのない想いなのだと西門豹は識《し》っていた。もちろん、そのからくりは重々承知のうえでだ。彩の純粋な想いは、いわば嘘だ。嘘と言うのがきつければ、作り話だ。彩の想いは、現実を蒸留に蒸留を重ねた後でしたたる極上の美しい作り話の滴だ。虚構の結晶だ。いくらきれいに思えても、神々や理想などはしょせん御伽噺にすぎない。だが、人は皆汚辱にまみれているからこそ、そのようなものが不可欠なのだとわかっていた。人の心の良質な部分を永遠に支えるのは、この世にはあり得ない純度一〇〇%の作り話にしかできない。それがあるからこそ、人間は人間であり続けられ、他人を幸せにすることもまた可能なのだ。このままでは、その清らかな一滴を徐粛らによって薄汚い錬金術の道具にされてしまう。
光が目に射しこむ。はっと心を打たれたような気がして、西門豹は蒼風を停めた。
溶鉱《ようこう》のように煮える落陽が黄色い大地の向こうへ落ちてゆく。
西門豹は、喰らいつきそうなまなざしを夕陽へ投げかけた。
――理性を鍛えろ。焼けた鋼《はがね》を鍛えるように、思考を鍛えろ。考え抜け。大切なものを守るためにどうすればよいのか、考えるのは己しかいない。立ち上がるのも己しかいない。
心の底に得体の知れない力が湧く。それはたぎる闘志のようでもあり、破壊的な暗い衝動のようでもあった。
明日の朝、太陽が東の地平線から生き返れば激しい戦いが始まる。そんな予感に駆られ、西門豹は巨躯を震わせて雄叫びを上げた。
(続く)