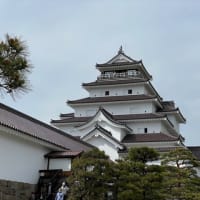雪解けがもう始まっていた。
薄ぼんやりとした夕陽が低い山並みの向こうへ落ちる。紅く染まっていた田畑の雪は、灰を撒き散らしたように色を変える。レールを踏みしめる車輪の音がリズミカルに響き、踏み切りの警報機が乾いた音を立てながら車窓を流れた。
僕は新庄発秋田行きの普通列車に乗っていた。赤い電気機関車が牽引する四両編成の客車列車だ。乗客たちはほとんど眠っているかのようで、青いボックスシートが並んだ車内は静かだった。
僕は曇った窓ガラスを手で拭い、ぼんやり外を眺めた。あてのある旅でも、誰かを訪ねるための旅でもなかった。東京で暮らしているうちにどうしようもなく窮屈な気分になってしまったから、列車に乗ってどこか遠くへ行きたくなった。ただそれだけのことだ。今朝、上野発の始発列車に乗り、鈍行を乗り継いでここまでやってきた。
僕の真向かいには三十過ぎくらいの男が坐っていた。男はずっと目を瞑っていたが、時々鼻を鳴らしたりするので眠っているわけではなさそうだった。丸い顔にがっちりとした体つきをしている。屋外で体を使う仕事をしているのだろう。顔は日焼けして、節くれ立った手は荒れていた。僕の隣には老眼鏡をかけた五十がらみの女性が坐り、手を休めることなく編み物をしていた。翡翠色のマフラーが彼女の膝元ですこしずつ伸びた。
このあたりの雪がすっかり解ける頃、僕は卒業する。だが、まだ就職は決まっていない。さしあたって今のアルバイトを続けることになりそうだ。無名の業界雑誌を発行している小さな出版社で雑用係りをしていた。資料収集のために図書館へ出かけたり、新聞社のライブラリイへ行って写真を借りたり、図表のデータをそろえたり、文字校正をしたりと簡単な仕事だ。たまに編集長の気が向いた時には、小さな原稿を書かせてもらえた。一か月間フルで働いてもたいした稼ぎにはならない。身分もアルバイトだから不安定だ。会社の経営もうまくいっていないようで雑誌の発行部数も伸び悩んでいるから、いつ首を切られてもおかしくない。経済的にもきついし、精神的にもなかなか落ち着かないのだけど、とはいえ、仕事自体は気に入っていた。いつか責任を与えてもらって、取材へ出かけたり、自分自身の手でひとつの記事を編集できるようになりたかった。
親は卒業したら里へ帰ってこいと言う。だが、帰りたくはなかった。帰ったところで目ぼしい就職先があるわけでも、親が就職の斡旋をしてくれるわけでもない。子供がそばにいなければさびしいから、というだけの話だ。延々と続く母親の愚痴を聞かされるのは、ごめんだ。気分が滅入って、気力が吸い取られてしまう。母親がよく通っている占い師の御宣託をもとに「あなたはこれだからだめだ」と断罪されるのも、もううんざりだ。母親は、僕の幼い頃に父親と義母――つまり僕の祖母――から手ひどくいびられ、心を圧(お)し潰されてしまった。それ以来、常になにかに苛立ち、終わることのない怒りを発散させている。占いによってすべてを解釈しようとするだけで、自分の頭を使って目の前の現実を考えようとはしない。浅く狂っていると思うが、今更、どうすることもできない。家にいると針のむしろに坐っているようなやり場のない気分にさせられる。どうにも折り合いのつけようがなかった。
僕になにかができるとはとても思えない。自分のことは、あまり信用していない。それでも、ささやかでかまわないから、自分の人生は自分の手作りで生きたかった。
通路のドアがゆっくり開く。
初老の車掌が現れ、帽子を取って深くお辞儀する。
「毎度ご乗車ありがとうございます」
と礼を述べた後、
「ただいまより、車内検札を始めます」
とまた頭を下げた。車掌のアクセントはこの地方の訛りがかすかに香った。人の心を落ち着けるのんびやかさがあった。
車掌は順番に検札し、切符を発券やら乗り越しの精算をすませる。
僕は手慣れた仕草で仕事をこなす車掌にいささかの羨望を覚えずにはいられなかった。落ち着いた仕事を手に入れれば、落ち着いた暮らしが手に入り、落ち着いた倖せを得ることができるのだろうか。
二年ほど一緒に暮した恋人は、先月、彼女の故郷へ帰った。僕に内緒で見合いをしたようだ。突然、別れを切り出した彼女は「チャンスだから」と何度も繰り返し言った。地元の名士の家との縁談がまとまったようだった。いい暮らしができるのなら、それも悪くない。ただ、二度と彼女とかかわりになろうとは思わない。忘れ物があるのから宅配便で送ってほしいと手紙が届いたが、そのままくずかごへ捨てた。それは僕のエゴイズムだとわかっているけど。
車掌がそばにきた。
向かいの男が小さな切符を渡す。車掌の顔が険しくなり、
「上野……」
と、くぐもった声でつぶやいた。
車掌が彼へ話しかける。カーブに差しかかった客車は軋み、車掌の声をかき消す。男が黙って頷くと、車掌は困惑にした深い皺を眦(まなじり)に刻みながら今度は彼の耳元へ口をあて何事かをささやいた。男はやはり表情を変えず、無言のまま頷いた。
「帰りたかったのけ――」
車掌はやるせなく首を振った。僕の隣の女性が放心したように編み物の手をとめる。だが、彼女はずり落ち気味になった老眼鏡を手の甲で押し上げるとすぐに続きを編み始めた。
「あんただけが悪いわけじゃないんだけどな」
そう言った車掌の顔には怒りも憎しみもなかった。ただ悔しさだけを謹厳な顔に浮かべている。なにが悔しいのだろう? キセルを見つけてしまった自分だろうか。それとも、男にキセルをさせてしまったこの世の理不尽に対してだろうか。たしかに、男は不幸に違いない。そんな男をキセル犯として告発しなければならない車掌も不運には違いなかった。帽子の庇に手をあてて哀しげにじっと視線を落とした車掌は、さっと踵を返した。
おそらく、男は上野でいちばん安い切符を買い、ここまで列車を乗り継いできたのだろう。トイレにこもってやり過ごすこともできただろうに、素直に切符を見せた男が不思議だった。もうどうにでもなれとやけになったのだろうか。もしかしたら見逃してもらえるかもしれないと、心の片隅で期待していたのだろうか。それとも、なにがなんでもふるさとへ帰り着き、幼い頃の思い出たちと膝を交えて話をしてみたかったのだろうか? 置き去りにしていったわだかまりと和解したかったのだろうか?
列車は、一つまたひとつと無人駅に停まっては出発する。男はじっと眼を閉じたままみじろぎもしない。運命というものがもしあるとすれば、それに身を任せるよりほかないと観念しているようだ。周囲の乗客はなにもなかったように静かだった。誰一人として、彼を見つめたりするものはいない。あるいは、同情のこもったやさしい沈黙だったのかもしれない。夜の帳が車窓に幕をおろした。
やがて車掌が引き返してきた。列車は煌々と灯りのともった大曲駅へ滑りこむ。このあたりでは比較的大きな駅だった。鉄道警察の腕章を巻いた男が二人、プラットホームの真ん中あたりで直立不動の姿勢をとって列車を迎えた。
車掌が男の肩を叩く。
男は疲れたように立ち上がり、車掌に付き添われながら汽車をおりた。僕はさきほどまで男が坐っていた席に場所を移した。初老の女性はうつむいたまま編み物を続けている。
ひゅっと鋭く笛が鳴った。
客車が揺れ、定刻通りに出発する。
薄緑色に塗ったホームの柱が窓の外でゆっくり動く。鉄道警察に両脇を抱えられた男の後ろ姿が瞬く間に後ろへ流れ去る。
「帰りたかったのけ――」
車掌の言葉がやさしくむなしく耳の底で甦った。
(了)
小説家になろうサイト投稿作品
2013年2月23日投稿
http://ncode.syosetu.com/n7388bn/