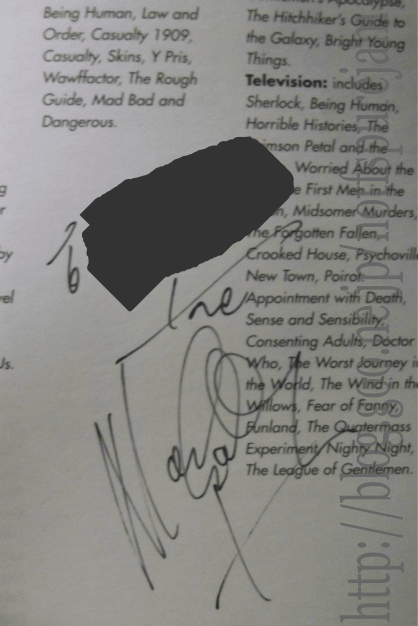話は長くなりますが…。
そもそも私が英国行きを決意した一番のきっかけとなったのは、
"リーグ・オブ・ジェントルマン 奇人同盟(The League of Gentlemen)"(以下TLoG)でした。
TLoGとは主に1999年から2002年に放送されたコメディ番組、及びそのクリエイターである4人組のことを指します。
 (左上から時計回りにMark Gatiss, Jeremy Dyson, Reece Shearsmith, Steve Pemberton)
(左上から時計回りにMark Gatiss, Jeremy Dyson, Reece Shearsmith, Steve Pemberton)
「SHERLOCK」好きの方なら共同製作者であり出演者のマーク・ゲイティスがその一員であることは知っているかもしれません。
元々英国のコメディが好きだった私ですが、TLoGはそれまでスルーしていたので、
「SHERLOCK」を見始めたのを期にきちんと見てみたところ、
そのキワドさ加減と登場する個性的なキャラクターにすっかり魅了されてしまい、熱烈なファンになってしまいました。
そして、いつものように彼らのライヴDVDを見ている最中に、唐突に思いついてしまったのです。
「そうだ、英国に行こう!」w
それというのも、TLoGの出演者3人(作家のJeremy以外)がちょうどこの4月まで、
各々別の舞台に立つということを知っていたからなのです。
Reece Shearsmithは、Alan Ayckbourn作の"Absent Friends"、
Steve Pembertonは、Oliver Goldsmith作の"She Stoops To Conquer"、
Mark Gatissは、George Farquhar作の"The Recruiting Officer"。
BBCのヒット番組の出演者である彼らが、
West Endである程度の評価を得て今のように活躍出来るまでには、意外にも時間が掛かったようで、
その内容が記事にもなっていました。
ともかく、こんな渡英のための絶好なタイミングがあるだろうか!?と思ったわけです。
さっそく"Absent Friends"をWebで予約し、
"She Stoops To Conquer"は他の2つよりも楽日が遅いので、滞在が落ち着いてから予約することにして、
"The Recruiting Officer"のチケットを調べると、売り切れ…。
ところが、こまめに劇場のサイトをチェックしていたところ、
一週間分の公演に若干数のチケットが出ていて、その中から予約することが出来ました。
無事に予約出来た時は、手の震えが止まりませんでした。
「本当に3人の芝居を生で一気に見られるかも…夢じゃなくて現実なんだっ」
特にMark Gatissは、ユニークな性格俳優というだけでなく"SHERLOCK"や"DOCTOR WHO"の脚本家としても心底憧れているので、
「お目にかかれたらもうお土産は一切要らない! 一生それを支えに生きて行く!」
とまで考えていました。
そんなわけで、前置きが長くなりましたが、滞在3日目にこの"The Recruiting Officer"を見に行ったのです。
------------------------------------------------------------
DONMAR WAREHOUSEは、大好きなサム・メンデス版「キャバレー」の初演が上演された憧れの場所。
かわいい劇場のお兄さんにチケットを見せて階段を上がると、
一階(Stall)と二階席(Circle)の外にそれぞれバーカウンターがあり、開場まで飲み物を飲みながら待つことが出来ます。
私はどうもソワソワしてしまい、早く開場してもらいたかったので、
入口の女性に開場時間を訊くと、
「もうすぐ開場しますよ」
「"もうすぐ"ですか?」
「ええと…あと、5分くらいで」
何時って、決まってないんですね。
パンフレット(たしか3ポンド)を買ってから、実際に中に入って見ると、
客席は250席程で、思った以上にこじんまりした(でも雰囲気のいい)芝居小屋!
椅子は長椅子で番号が振られており、舞台を囲むようにコの字型に並んでいます。
私の席はStallの下手側。一番端の席でした。
開場後から、ミュージシャン(Woodwind,Guitar,Violin,Double Bass Mandolin, Baritone Ukelele)が、
舞台上だけでなく、客席もウロウロしながら演奏を始めています。
無駄なセットはなく、天井に古風なシャンデリアと、空の模様が描かれた背景にロウソク台が並んでいるだけ。
出演者が下がってきたシャンデリアのロウソクに火をともし始めると、開演が近づきます。
'The Recruiting Officer' at the Donmar - rehearsal preview
徴兵のためにシュルーズベリーにやってきたPlumeと、彼の友人であるWorthy。
彼らはそれぞれの意中の女性―
PlumeはSilvia、Worthyは彼女のいとこのMelindaと結婚せずによろしくつき合いたいと思っています。
しかし、彼女たちは財産の相続人となっていて、愛人として彼らに囲われる必要はない立場にありました。
男性たちを惑わせようと、いとこのMelindaは別の徴兵役の将校Brazenに気のある振りをし、
Silviaは男装をしてPlumeに近づき、彼の部下として徴兵されます。
(本当いうと、彼女たち2人とも殿方たちに気があるのです。)
Plumeが遊び心で手を出した地元の女中を、彼から引き離し"一夜を共にした"Silviaでしたが、
それが原因で逮捕され、父親である判事の前に突き出されてしまいます…。
この作品は1708年に生まれた、王政復古時代の「風習喜劇」と呼ばれるもので、
ただでさえ英語が聞き取れない私にとってはかなり難しかったです。
プロットと、途中まで戯曲を読んでいたものの、
やはり細部を理解するまでは程遠く…追えない台詞に笑い声が起こると悔しい気分に。
それでも、演劇の生の楽しさは十分に味わうことが出来ました。
ミュージシャンが定番の携帯電話の着信音を演奏し始めたり、
WorthyとMelindaが最前列のカップルに「いちゃいちゃするな」ってちょっかい出したりw
(ミュージシャンも2人にやたら近づいて演奏したりしてたな。)

お目当てだったMark GatissはCaptain Brazen役だったのですが、
彼も下手からキャップ(帽子)をパーン!と客席に投げ捨てて登場!
(はけるときに「どうも」と言ってまた受け取っていたけども。)
その後で、杖も最前列の男性に預けてたし。
(男性が戸惑うでもなく、厳かに受け取ってるのがなんだか面白かったな。)
実際に見た彼の印象は、直視するのを躊躇う程の、"圧倒的なオーラのある役者"w
出てきた途端に、客席からも「待ってました!」「笑わせてくれ!」という熱気と期待がビシビシ感じ取れ、
ゴージャスな出で立ちと軽妙な演技でその期待に応えていました。
また、"The Office"のギャレス役で知られるMackenzie Crookも、
手を変え品を変えて街の人間を徴兵しようとする、Plumeの相棒:Sergeant Kiteとして熱演。
舞台と客席が近いだけあって、普段見ることの出来ない英国の役者の演技をつぶさに見ることが出来て、
興奮すると同時に、もっと理解したい!という気持ちも高まりました。
最後は、ミュージシャンたちがひとりひとり戦場へ赴いて行く描写で幕に。
喜劇だけれど、静かな余韻を残す終わり方でした。
------------------------------------------------------------
興奮を押さえきれないまま、劇場を出て階段を降りると、
階段下に、パンフレットとサインペンを持って待っている女の子たちが。
(もしかして、出演者も同じ階段で降りて来る?)
すると、Worthy役のNicholas Burnsが劇場から降りて来たのです。
早い! 客がまだハケきってないのにもう出て来るなんて!
ともかく、出演者もここから出て来ることは確かみたい。
(Mark Gatissとお話するチャンスがあるかもしれない…。)
出待ちなんて無作法なのかもしれないけれど、日本から10時間以上かけて来て、
こんなチャンスがあるなら、逃すわけにはいきません…。
私も、入口傍で待つことにしました。
(でも、待っていても気付かれずに通り過ぎてしまうかもしれない、
ヘタしたら気付いていてもスルーされちゃうかも…)
はち切れんばかりの期待を胸に抱きながらも、頭は失敗した時のショックに備えようとします。
劇場から出て来る人たちを見つめながら、
寒い中で立たされているかのように、ソワソワと足踏みをしてその時を待ちました。
しばらくすると、長身の男性が、スタッフらしき人たちと話しながら階段を降りて来ます。
(彼だ、Markが降りて来た!)
私は思い切って階段の下まで駆け寄りましたが、
Markは知り合いの女性と待ち合わせをしていたらしく、
手前で楽しげにハグと挨拶を交わしています。
(どうしよう、完全に話しかけるタイミングを失ってしまった…)
硬直して呆然と立ち尽くす私。
すると、それに気付いたMarkが、こちらの言葉に注意深く耳を澄ませるようにして近づき、
満面の笑顔で向こうから声をかけてくれたのです。
「ハァイ!」
「こんにちは…。ミスター・ゲイティス、あなたに会うために日本から来ました。よろしければ写真を…」
「写真? もちろん撮ろうよ!」
ああぁっ! ありがとうございますっ!
あたふたとカメラを取り出そうとする私。
緊張で手がガタガタ言ってしまい、電源を入れるのにも一苦労。
そんな私を彼は「じゃあ、ここは人が通るから、あっちに行こうか」
とBOX OFFICE近くにエスコートしてくださいました。
そして、私の様子を近くで面白そうに見ていた紳士にシャッターをお願いし、
私はMark Gatissと一緒に写真に写ることが出来たのです! ああっ…奇跡!
紳士にお礼を言った後、私はMarkに旅の計画を話しました。
「再来週Hadfieldに行くつもりなんです。」
Hadfieldとは、TLoGの番組が撮影された英国北部の街。
ロンドンからコーチ(長距離バス)で約5時間、
そこからさらに列車に乗って1時間かかります。
そう、Hadfieldが私のもう一つの旅のメインイベントでした。
TLoGのメンバーの芝居を見て、TLoGの撮影地を巡礼する…
バカな発想ですが、その皆が呆れそうな計画自体が、
一人旅で縮み上がりそうな私の心を強く支えてくれていました。
この私の旅の予定を話せば、本気で彼や彼の仕事のファンであることが、伝わるのではないかと思ったのです。
するとMarkは「えー! 本当に!?」
ガハハハハハー!と豪快に笑ってくれましたw
その笑い方もインタビュー等で見ていた笑い方そのもの。
服装もいつも見るお気に入りらしいチェック柄のシャツだし。
本物のMark Gatissが私の話で爆笑している…(涙)。
彼は私のHadfield行きを喜んでくれたらしく、
嬉しいよぉー!と、向こうから私の右手を両手でがっしり握ってブンブン握手してくれました。
(その後、早口で何か言ってくれたのですが、うまく聞き取れず聞き返せず。
「行ったら戻って来れないよ!」だったかもw)
相変わらず満面の笑みをたたえた彼から、こちらが驚く程のリアクションを貰えて、
ひとりで考えた無茶な計画が、特別な使命になったような気がしました。
そしてここぞとばかりにサインもお願いし、
(「名前教えて?」「xxxxxxです」「…スペルも教えてw」
分かりやすい名前ですが、意外と難しいらしい。)
何度もお礼を言い、頑張ってください!と声を掛けて見送りました。
…ほんの数分の、それだけの話なのです。
でも、私にとっては一生分の価値のある出来事になりました。
(たぶん今夜は人生で一番幸せな夜なんだわ…)
大人になると、幸せな気分を素直に味わうのに抵抗を感じるものですが、
Piccadilly Circus駅までの道をパンフレットを抱きかかえて歩きながら、
この日ばかりはその喜びにどっぷりと浸かりました。
今まで好きな人にサインを貰った経験はありましたが、
こんなにも優しく受け入れてもらえた事はありません。
日本から来た、上手く英語の話せない、どう見ても冴えない女子(という年齢でもないし)に
気さくに接してくれたMarkに感謝のしようがないです。
今でも思い出す度に涙が出てきます。
彼のようなSWEETな大人になりたいっ!
なんだかんだ言ってお土産はいろいろ買ってしまいましたが、
(でもそのうちのほとんどは彼が関わってるDVDや書籍ですからね!)
始めから心に決めていた通り、
この日のことを支えに、死ぬまで生きて行こうと思います。
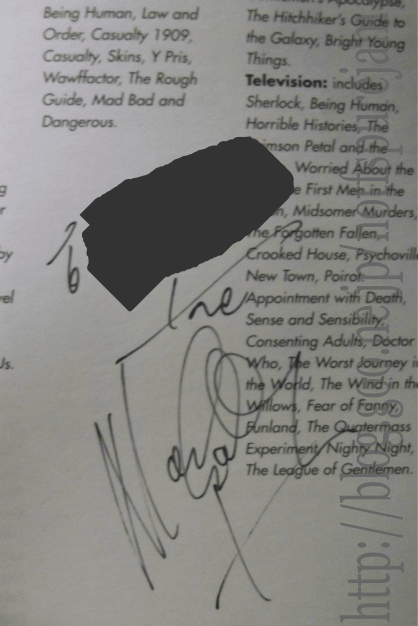
そもそも私が英国行きを決意した一番のきっかけとなったのは、
"リーグ・オブ・ジェントルマン 奇人同盟(The League of Gentlemen)"(以下TLoG)でした。
TLoGとは主に1999年から2002年に放送されたコメディ番組、及びそのクリエイターである4人組のことを指します。
 (左上から時計回りにMark Gatiss, Jeremy Dyson, Reece Shearsmith, Steve Pemberton)
(左上から時計回りにMark Gatiss, Jeremy Dyson, Reece Shearsmith, Steve Pemberton)「SHERLOCK」好きの方なら共同製作者であり出演者のマーク・ゲイティスがその一員であることは知っているかもしれません。
元々英国のコメディが好きだった私ですが、TLoGはそれまでスルーしていたので、
「SHERLOCK」を見始めたのを期にきちんと見てみたところ、
そのキワドさ加減と登場する個性的なキャラクターにすっかり魅了されてしまい、熱烈なファンになってしまいました。
そして、いつものように彼らのライヴDVDを見ている最中に、唐突に思いついてしまったのです。
「そうだ、英国に行こう!」w
それというのも、TLoGの出演者3人(作家のJeremy以外)がちょうどこの4月まで、
各々別の舞台に立つということを知っていたからなのです。
Reece Shearsmithは、Alan Ayckbourn作の"Absent Friends"、
Steve Pembertonは、Oliver Goldsmith作の"She Stoops To Conquer"、
Mark Gatissは、George Farquhar作の"The Recruiting Officer"。
BBCのヒット番組の出演者である彼らが、
West Endである程度の評価を得て今のように活躍出来るまでには、意外にも時間が掛かったようで、
その内容が記事にもなっていました。
ともかく、こんな渡英のための絶好なタイミングがあるだろうか!?と思ったわけです。
さっそく"Absent Friends"をWebで予約し、
"She Stoops To Conquer"は他の2つよりも楽日が遅いので、滞在が落ち着いてから予約することにして、
"The Recruiting Officer"のチケットを調べると、売り切れ…。
ところが、こまめに劇場のサイトをチェックしていたところ、
一週間分の公演に若干数のチケットが出ていて、その中から予約することが出来ました。
無事に予約出来た時は、手の震えが止まりませんでした。
「本当に3人の芝居を生で一気に見られるかも…夢じゃなくて現実なんだっ」
特にMark Gatissは、ユニークな性格俳優というだけでなく"SHERLOCK"や"DOCTOR WHO"の脚本家としても心底憧れているので、
「お目にかかれたらもうお土産は一切要らない! 一生それを支えに生きて行く!」
とまで考えていました。
そんなわけで、前置きが長くなりましたが、滞在3日目にこの"The Recruiting Officer"を見に行ったのです。
------------------------------------------------------------
DONMAR WAREHOUSEは、大好きなサム・メンデス版「キャバレー」の初演が上演された憧れの場所。
かわいい劇場のお兄さんにチケットを見せて階段を上がると、
一階(Stall)と二階席(Circle)の外にそれぞれバーカウンターがあり、開場まで飲み物を飲みながら待つことが出来ます。
私はどうもソワソワしてしまい、早く開場してもらいたかったので、
入口の女性に開場時間を訊くと、
「もうすぐ開場しますよ」
「"もうすぐ"ですか?」
「ええと…あと、5分くらいで」
何時って、決まってないんですね。
パンフレット(たしか3ポンド)を買ってから、実際に中に入って見ると、
客席は250席程で、思った以上にこじんまりした(でも雰囲気のいい)芝居小屋!
椅子は長椅子で番号が振られており、舞台を囲むようにコの字型に並んでいます。
私の席はStallの下手側。一番端の席でした。
開場後から、ミュージシャン(Woodwind,Guitar,Violin,Double Bass Mandolin, Baritone Ukelele)が、
舞台上だけでなく、客席もウロウロしながら演奏を始めています。
無駄なセットはなく、天井に古風なシャンデリアと、空の模様が描かれた背景にロウソク台が並んでいるだけ。
出演者が下がってきたシャンデリアのロウソクに火をともし始めると、開演が近づきます。
'The Recruiting Officer' at the Donmar - rehearsal preview
徴兵のためにシュルーズベリーにやってきたPlumeと、彼の友人であるWorthy。
彼らはそれぞれの意中の女性―
PlumeはSilvia、Worthyは彼女のいとこのMelindaと結婚せずによろしくつき合いたいと思っています。
しかし、彼女たちは財産の相続人となっていて、愛人として彼らに囲われる必要はない立場にありました。
男性たちを惑わせようと、いとこのMelindaは別の徴兵役の将校Brazenに気のある振りをし、
Silviaは男装をしてPlumeに近づき、彼の部下として徴兵されます。
(本当いうと、彼女たち2人とも殿方たちに気があるのです。)
Plumeが遊び心で手を出した地元の女中を、彼から引き離し"一夜を共にした"Silviaでしたが、
それが原因で逮捕され、父親である判事の前に突き出されてしまいます…。
この作品は1708年に生まれた、王政復古時代の「風習喜劇」と呼ばれるもので、
ただでさえ英語が聞き取れない私にとってはかなり難しかったです。
プロットと、途中まで戯曲を読んでいたものの、
やはり細部を理解するまでは程遠く…追えない台詞に笑い声が起こると悔しい気分に。
それでも、演劇の生の楽しさは十分に味わうことが出来ました。
ミュージシャンが定番の携帯電話の着信音を演奏し始めたり、
WorthyとMelindaが最前列のカップルに「いちゃいちゃするな」ってちょっかい出したりw
(ミュージシャンも2人にやたら近づいて演奏したりしてたな。)

お目当てだったMark GatissはCaptain Brazen役だったのですが、
彼も下手からキャップ(帽子)をパーン!と客席に投げ捨てて登場!
(はけるときに「どうも」と言ってまた受け取っていたけども。)
その後で、杖も最前列の男性に預けてたし。
(男性が戸惑うでもなく、厳かに受け取ってるのがなんだか面白かったな。)
実際に見た彼の印象は、直視するのを躊躇う程の、"圧倒的なオーラのある役者"w
出てきた途端に、客席からも「待ってました!」「笑わせてくれ!」という熱気と期待がビシビシ感じ取れ、
ゴージャスな出で立ちと軽妙な演技でその期待に応えていました。
また、"The Office"のギャレス役で知られるMackenzie Crookも、
手を変え品を変えて街の人間を徴兵しようとする、Plumeの相棒:Sergeant Kiteとして熱演。
舞台と客席が近いだけあって、普段見ることの出来ない英国の役者の演技をつぶさに見ることが出来て、
興奮すると同時に、もっと理解したい!という気持ちも高まりました。
最後は、ミュージシャンたちがひとりひとり戦場へ赴いて行く描写で幕に。
喜劇だけれど、静かな余韻を残す終わり方でした。
------------------------------------------------------------
興奮を押さえきれないまま、劇場を出て階段を降りると、
階段下に、パンフレットとサインペンを持って待っている女の子たちが。
(もしかして、出演者も同じ階段で降りて来る?)
すると、Worthy役のNicholas Burnsが劇場から降りて来たのです。
早い! 客がまだハケきってないのにもう出て来るなんて!
ともかく、出演者もここから出て来ることは確かみたい。
(Mark Gatissとお話するチャンスがあるかもしれない…。)
出待ちなんて無作法なのかもしれないけれど、日本から10時間以上かけて来て、
こんなチャンスがあるなら、逃すわけにはいきません…。
私も、入口傍で待つことにしました。
(でも、待っていても気付かれずに通り過ぎてしまうかもしれない、
ヘタしたら気付いていてもスルーされちゃうかも…)
はち切れんばかりの期待を胸に抱きながらも、頭は失敗した時のショックに備えようとします。
劇場から出て来る人たちを見つめながら、
寒い中で立たされているかのように、ソワソワと足踏みをしてその時を待ちました。
しばらくすると、長身の男性が、スタッフらしき人たちと話しながら階段を降りて来ます。
(彼だ、Markが降りて来た!)
私は思い切って階段の下まで駆け寄りましたが、
Markは知り合いの女性と待ち合わせをしていたらしく、
手前で楽しげにハグと挨拶を交わしています。
(どうしよう、完全に話しかけるタイミングを失ってしまった…)
硬直して呆然と立ち尽くす私。
すると、それに気付いたMarkが、こちらの言葉に注意深く耳を澄ませるようにして近づき、
満面の笑顔で向こうから声をかけてくれたのです。
「ハァイ!」
「こんにちは…。ミスター・ゲイティス、あなたに会うために日本から来ました。よろしければ写真を…」
「写真? もちろん撮ろうよ!」
ああぁっ! ありがとうございますっ!
あたふたとカメラを取り出そうとする私。
緊張で手がガタガタ言ってしまい、電源を入れるのにも一苦労。
そんな私を彼は「じゃあ、ここは人が通るから、あっちに行こうか」
とBOX OFFICE近くにエスコートしてくださいました。
そして、私の様子を近くで面白そうに見ていた紳士にシャッターをお願いし、
私はMark Gatissと一緒に写真に写ることが出来たのです! ああっ…奇跡!
紳士にお礼を言った後、私はMarkに旅の計画を話しました。
「再来週Hadfieldに行くつもりなんです。」
Hadfieldとは、TLoGの番組が撮影された英国北部の街。
ロンドンからコーチ(長距離バス)で約5時間、
そこからさらに列車に乗って1時間かかります。
そう、Hadfieldが私のもう一つの旅のメインイベントでした。
TLoGのメンバーの芝居を見て、TLoGの撮影地を巡礼する…
バカな発想ですが、その皆が呆れそうな計画自体が、
一人旅で縮み上がりそうな私の心を強く支えてくれていました。
この私の旅の予定を話せば、本気で彼や彼の仕事のファンであることが、伝わるのではないかと思ったのです。
するとMarkは「えー! 本当に!?」
ガハハハハハー!と豪快に笑ってくれましたw
その笑い方もインタビュー等で見ていた笑い方そのもの。
服装もいつも見るお気に入りらしいチェック柄のシャツだし。
本物のMark Gatissが私の話で爆笑している…(涙)。
彼は私のHadfield行きを喜んでくれたらしく、
嬉しいよぉー!と、向こうから私の右手を両手でがっしり握ってブンブン握手してくれました。
(その後、早口で何か言ってくれたのですが、うまく聞き取れず聞き返せず。
「行ったら戻って来れないよ!」だったかもw)
相変わらず満面の笑みをたたえた彼から、こちらが驚く程のリアクションを貰えて、
ひとりで考えた無茶な計画が、特別な使命になったような気がしました。
そしてここぞとばかりにサインもお願いし、
(「名前教えて?」「xxxxxxです」「…スペルも教えてw」
分かりやすい名前ですが、意外と難しいらしい。)
何度もお礼を言い、頑張ってください!と声を掛けて見送りました。
…ほんの数分の、それだけの話なのです。
でも、私にとっては一生分の価値のある出来事になりました。
(たぶん今夜は人生で一番幸せな夜なんだわ…)
大人になると、幸せな気分を素直に味わうのに抵抗を感じるものですが、
Piccadilly Circus駅までの道をパンフレットを抱きかかえて歩きながら、
この日ばかりはその喜びにどっぷりと浸かりました。
今まで好きな人にサインを貰った経験はありましたが、
こんなにも優しく受け入れてもらえた事はありません。
日本から来た、上手く英語の話せない、どう見ても冴えない女子(という年齢でもないし)に
気さくに接してくれたMarkに感謝のしようがないです。
今でも思い出す度に涙が出てきます。
彼のようなSWEETな大人になりたいっ!
なんだかんだ言ってお土産はいろいろ買ってしまいましたが、
(でもそのうちのほとんどは彼が関わってるDVDや書籍ですからね!)
始めから心に決めていた通り、
この日のことを支えに、死ぬまで生きて行こうと思います。