角苦(かどく:圓楽の逆の意味)がニタニタして何を世論でいるのかと思いきや?億値段の家を作ったとか。
賤しい弥(林家じゃないよ)のクソ馬鹿は、200万円の食費で豪勢に食っているぐらいしか「取り柄」は無く、まぁ母親は、何か良い人を捏造したんだろうけど、育てた男は柔弱、女は狂気と来ては、育て方は当に「亜承の嫁取り真似するまいぞ」である。
長女のみどりは、どうやら峰隆太を実際に刺したらしい。また、泰葉も、その狂気を記者会見で暴露した。
これは船越英一の嫁を2つ持っているようなもので、多分、母親も、その気があるのだろう。
全くもって賤しい弥(林家じゃないよ)の姦しさ、狂気が止まらず出ています。人の目に晒す姿なら、どうぞ角を隠してくれおおせ、それなら般若の面付けずとも、怖い本心顔に出て、その目を見たら石になる。もって怖気は、人情の通じる世にない醜女の有り様よ、元気なだけなら良いけれど、心醜き意味なれば、怖い怖いの賤しい弥(林家じゃないよ)。
さて、一方で、どっちも糖尿確実の不能確実のち○このあるやつだが、まぁ笑点をお笑いの番組からせせら笑いの番組になって、そして、おいぼれと一緒に消えればいいのさ。
もう、落語は、下らなくなってしまった。
思えば、昔の談志のドキュメンタリーのような、そんなスパルタな…と言うか、芸能に恋し焦がれた、談志のような存在はもう居ない。木久蔵ラーメンのような笑われる下らない存在である。
私は、江戸の息吹を伝えてこそ、芸能と思っている。何故なら、今の芸能では、お能や狂言、絵画を除くと、芸能は江戸時代のそれであり、談志は、その息吹を大事にしていた。だから講談とか、謡とか、そんなものを叩きこめと言っていたのである。
らく朝なんかを見ていると、あの頃の昇格試験で、下手な民謡をやっている姿を思い出す。
私は、談志とは違うスタンスで江戸時代を見ている。
大体、落語も歌舞伎も文楽もクソみたいなもので、時代劇の嘘をちっとも文句を言わない。
私は、色々な研究資料を元にして、江戸時代の事実を探している。それからすると、落語や歌舞伎などの、コミットメントがないのが腹が立つ。
多分歴史研究者も同じだろう。
さて、私は談志を高く評価するのは、評価ってのは上から目線で良くないな。
談志師匠は、食い物は食えりゃァいい、無駄にしないと、賤しい弥(林家じゃないよ)の豚の糖尿の勃起不能とは違う、倹しい生活で、それだからこそ、江戸時代の庶民の生活を生き生きと描けるのである。
ただ、ちょっと私の研究と言うか、物見では、江戸時代の庶民は、言う程悲惨ではなく、捨てる神あれば拾う神ありって感じで、金も仕事もなくても江戸なら生きられると言うほどのもののようである。
ただ、庶民の生活は記録が残らない。紙が高価だったので、日記を残す習慣がないので、書面の記録が殆ど無い。だから、商人の記録や、武家の記録が主に残っており、これが笑うのだが、「めぞん一刻」の中で響子さんの亭主、惣一郎さんが日記に「献立」ばかりを記入するのだが、実はこれは、日記の基本であり、宮廷日記も、往々にして食ったものを記録するのが基本である。
武家の記録も往々にしてそうで、だから江戸時代の研究として、食生活を基礎として、武家の上中下の相場を見せる研究が多いのである。
私は、談志にニヤケテ諂る狭漠闇(太田光の逆の意味ね)とは違って、談志に問うね。
先ず、江戸時代の運輸はどうだったか?例えば大八車は、赤坂などの坂の道の前後でしか運行されていなかった。輸送の多くは船であるとか、川舟と海船の違いがある。
内海佳江師匠とかにも、お聞きしたい。「粋な黒塀見越しの松」よく師匠がおっしゃっていたことだ。粋な黒塀は、塀の仕上げに、商家は黒く薄い塀を塗るのである。これが黒塀と言って、当時一流の左官しか塗れなかった。見越しの松は、お棚の庭に植えてある松が建物の端っこに見えるのだが、それが見越しの松だ。
私は、もし談志師匠と縁があれば、例えば、植木屋はどんな威勢だったのか?とか、江戸時代の出勤ラッシュがあっただろう?と聞くね。
また、落語の演目で取り上げないものがあるだろう。例えば、一人相撲とかは、小説では面白いが、落語にはならない。私は、この一人相撲で話を書きたい。
だが、今の落伍者には、一人相撲が面白そうだとは思うまい。新作だが、江戸時代の風物をひとつ取り上げたものだ。
また、話をするにも色々な風俗が必要だ。例えば、庶民は歩くか、船で移動する。一方で、武家は歩くか、偉い人は籠で移動する。
この籠だが、庶民の籠と大名の籠はえらく違い、どんな商人でも、高級な籠には乗れない、それは決まりが明文化されている。
また武家でも大名とか旗本とかでも格に依って乗れる籠が違う。もっと言うと、江戸お留守居役と江戸家老の籠も違う。
籠自身は同じでも、赤坂の「豊田屋」は若くて力のある人足ばかりで、商家の大手は、豊田屋に声をかけていた。
この様な知識は、落語に限らず江戸話に色を添え華を添えるのである。
ただ、困った事に、この様な方向での意識は、私の知る限り立川談志以外に、そう思っている奴はいない。
談志はさほど高いものを喰わず、また、家も棲家と資料室をソコソコのやつを作っているだけだった。
それは角苦の様に家なんぞが目的ではなく、自分の中の芸、その中に生き生きとした、表現を増やすことに興味があって、それだから、余計なものに興味はない。
だから、余計な今朝の自慢ばかりするクソ坊主と落伍者が似ているのである。
そして、落伍者を無能者に変える賤しい弥(林家じゃないよ)の勢力は、それこそ、独裁恐怖政治をしかねないっていうか、林家三平夫婦の怯え方は、何処の嫌な奴の影響なのか?だいたい分かるだろう。
売文業と違って、芸人は芸人カルテルの中の存在だ、だから、昔をさかのぼって新しいものを見ない奴は、今の時代をとり込もうとするが、それは軽薄と、技の下支えがない。つまり軽佻浮薄の最たるものである。だが、それが今の笑えない笑点の限界だろう。
談志の一門しか期待はしていねぇが、師匠に全部が及ばないにも、これはオレは勝てると思うものを、やっぱり追い求めるべきだ。
また下らない、飲み会ではなく、互いの芸を見せて、こう言う方向性で、私は芸を深めていますと言う方向性を見せ合うのはいいんじゃないだろうか?
逆に、誰々がこうだからと派閥を作るんじゃなくて、談志の意思のもとに集まった立川流は、そんなクソみたいな政治を無くして、本道の落語を求めているんでしょう?
今の古典落語は、古典の描いてある文字の意味や行間を読めない人間がオウム返しでやっている。だけど、経験や見方で、話の強弱を付けるのが噺家の個性ではないだろうか?
談志がお前ら、芸にのめりこめ!と言ったのは、江戸時代の息吹、それも別の世界の息吹を呼び込めと言いたかったのではないだろうか?
私はそう思う。だが、それを一番材料として提示するのは、多分、歴史学者となりそうである。だが、そういった人々を下に見るのが賤しい弥(林家じゃないよ)の豚だろう、あるいは姦か?











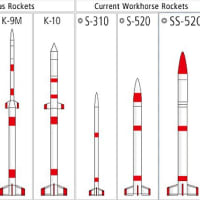
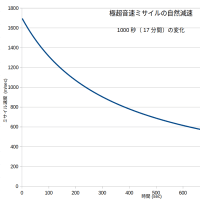


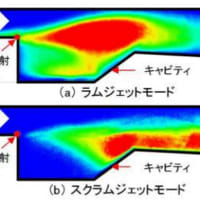


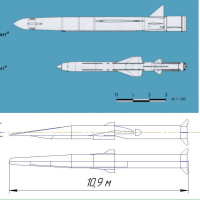

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます