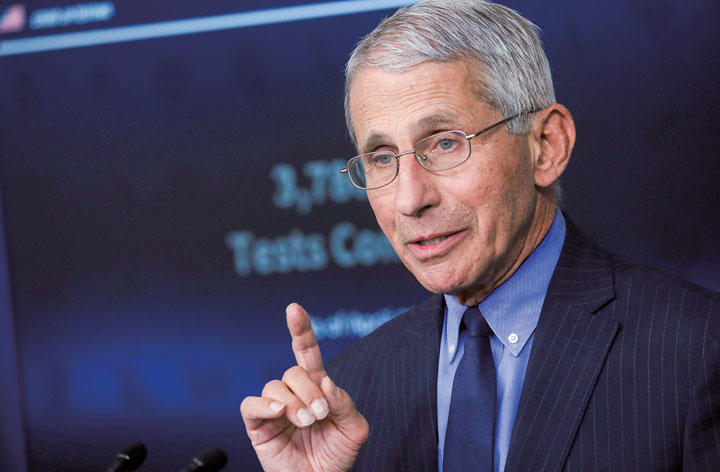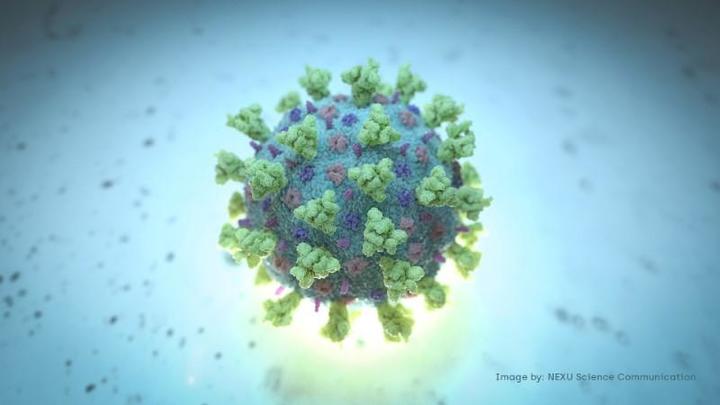日経の技術サイトXtechが、『“テレワークをせざるを得ない”緊急事態。中小企業、働き方をどう変える?』という記事が出ていたが、第一の壁がセキュリティー、第三の壁が、IT管理者の負担が大きすぎると指摘している。しかし、従業員300人以上の大手企業は、テレワークを60%が導入しているというが、大手企業は新型コロナの脅威でテレワークが叫ばれる以前から、全国の支店や工場などとのコミュニケーションを図るためにリモートワークを実施していた。しかるに授業イン300名以下の中堅企業は、新型コロナ脅威になって始めて、在宅勤務を導入せざるを得ず、何が何だかわからない状況が続いている。しかもリモートワークのシステムはアメリカ製ばかりで日本製は完全に”ゼロ”。日経ともあろうものが、テレワーク導入の企業状況をつかみ切れていないし、日本製テレワークがないと言う事も改善警告をすべきであろう。
新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、4月7日に7都府県に対して発出された「緊急事態宣言」も、10日たった4月17日には全国に拡大。街の様子がガラリと変わったように、ビジネスワーカーの働き方も変化の時を迎えている。テレワーク、リモートワーク、在宅勤務―――。これらの言葉とともに、もはや働き方を強制的に変えざるをえない状況が訪れたのだ。さて、この状況下でどのように働き方をアップデートする必要があるのか。
加速させたいテレワーク、立ちはだかる第1の壁とは?
新型コロナウイルスの影響で在宅勤務、テレワークが急激に増えている。
以前からBCP対策としてテレワークを推進してきた事例もあるが、もはや“テレワークをせざるをえない”緊急事態が企業を襲っている。
しかしながら、東京商工会議所が会員企業約1万3000社に行った「新型コロナウイルス感染症への対応について」の結果によると、都内でテレワークを実施している企業は26%、実施検討中は19.5%と日本企業、特に中小企業にとってはテレワークの実施はやはり高い壁であるようだ。

新型コロナウイルス感染症対策、テレワークの取り組み状況
(出所:東京商工会議所 新型コロナウイルス感染症への対応について)
では、どうして中小企業のテレワーク実施がスムーズに進まないのか。
第1に企業が頭を悩ませるのは“セキュリティ”の問題だ。
基本的にテレワークでは自宅で作業をすることになるが、「家族がいる」「集中できない」などの理由からカフェやコワーキングスペースでテレワークする人も増えている。社外アクセスのセキュリティ対策がなされていない場合は、自社の社員が外部からPCやタブレット、スマホなどの端末を使い直接インターネットへ接続することが多くなるため、逆にインターネット側から端末へアクセスされるリスクが高まる。
実際、テレワークの増加とともに、爆速的に普及したビデオ会議システムでも攻撃者がグループチャットのリンク共有機能を悪用したり、ニセの会議招集メールに誤ってアクセスしてしまい情報漏洩が引き起こされる例も挙がっている。情報漏洩を防ぐためにも、1台1台のデバイスのセキュリティを確保することが非常に重要になってくるのである。

テレワークにおける脅威と脆弱性について
(出所:総務省「テレワークガイドライン 第4版」)
このようなセキュリティの問題を解決する選択肢の1つに、Intel vPro® プラットフォームを活用したシステムの保護をおすすめしたい。Corei5以上の高性能CPU、チップセット、ネットワーク・インターフェースで構成されるIntel vPro® プラットフォームは、ビジネスニーズに応える為に設計されており「セキュリティ」だけでなく、「パフォーマンス」「安定性」「運用管理性」の4つの領域において、強力な機能を提供するインフラを構築することができる。
たとえば、「インテル® ハードウェア・シールド」は、OSより下層のファームウェア・レベルでの攻撃に対する保護を強化しているため、BIOSを攻撃対象としたマルウエアなどに感染し、システム管理権限が乗っ取られるケースやBIOSの書き換えなどからPCを守ることを可能にしている。
また、OS稼働中は、「Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT)」により、ウイルススキャンの処理をCPUからGPUにオフロードすることが可能となるため、ウイルススキャン実行中でも、ユーザーへの影響を抑え、生産性を維持することが可能だ。
立ちはだかる第2の壁、IT管理者の負担はどう削減するか?
さらに、テレワークの実施で浮かび上がる問題はセキュリティだけではない。
1台1台のデバイスのセキュリティを確保することは非常に重要なポイントだが、実際に管理するIT管理者が同じくテレワークを実施している場合は問題が起きたときにすぐに対応できるか不安なところだ。
しかも今後、有事だけでなく平時でもテレワークする動きになった場合、たとえば出張先などで一時的に会社のPCを使って仕事をするリモートワークならば、PC自体に多少のトラブルがあってもそれほど業務に大きな影響を与えることもないだろう。会社に戻り、IT管理者のところにPCを持っていけばすぐに対処してもらうことができる。加えてメンテナンスを行っている間は代用のPCを用意してもらえるし、その場で正常に動いているPCに交換してもらえることもあるので、業務への影響は最小限に留めることができる。
しかし、長期間会社に行かずにテレワークする場合、またIT管理者も同じくテレワークをしている場合は、PCのトラブルにすぐに対応してもらえず業務に与える影響が大きくなる可能性もある。
そこで活躍するのがテレワーク中のPCをリモートで管理可能にする「インテル® EMA」だ。インテル® EMAは、ファイアウォールの外側にあるPCに対して、インテル® AMTによるリモート管理機能を有効にするクラウド・ベースの管理コンソールで、自宅で作業しているユーザーのPCを管理できるだけでなく、IT管理者も自宅からテレワーク環境でさまざまなPCの管理や修復作業を行うことができるようになるという。
インテル® AMTではOSレベルではなく、Intel vPro® プラットフォームが持つハードウエアレベルのネットワーク接続機能でインターネットに接続するため、システムに障害が発生してブルー画面が表示されてしまっても、ITシステム管理者がその内容を確認した上でPCの再起動などの電源操作をリモートで実行できる。再起動後には、BIOS画面からのメンテナンスも実行できるため、IT管理者の負担を軽減することができる。
有事だけではなく、平時でも有効にテレワークを行うために
テレワークを継続的に実施するにはOSやアプリケーションの更新作業という課題もクリアしておかなければならない。例えば年2回実施される Windows10 のフィーチャーアップデートはダウンロードするプログラムのサイズが大きく、適用範囲も広いために業務時間中に実施してしまうと長時間に渡ってユーザーの業務を妨げる可能性がある。またIT管理者のサポートが難しいテレワーク環境において、これらの作業をユーザー任せにしてしまうと、結果的にソフトウエアの脆弱性が放置されたままになり、重要な情報の漏洩など大きな問題が発生する可能性もある。
しかしIntel vPro® プラットフォームが搭載されたPCならば、IT管理者が必要なときに遠隔でアップデートが実行できるのでその心配も不要だ。たとえPCがシャットダウンされた状態にあってもインテル® AMTを利用して遠隔で電源をオンにすることもできるため、業務時間外で、社員がPCを使用しない時間帯にアップデート行うことができる。
さて、この緊急事態にテレワークの実施を急ピッチで進めるにあたり、コストの問題もある。そんな時は以下のような制度もあるので活用を考えてみてはいかがだろうか。
2020年3月5日に東京都は「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」という名称で、東京都内の従業員999人以下の中堅・中小企業を対象に、機器やソフトウエアの費用、またクラウドサービスの利用料を最大250万円まで全額助成するという制度を打ち出している。

助成事業の流れ
(参考:公益財団法人東京しごと財団 事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 募集要項 )
目まぐるしく状況が変化する激動の社会であるが、ある意味でこれが企業の変革の第一歩となるかもしれない。