ミハイル・ブルガーコフ『犬の心臓・運命の卵』
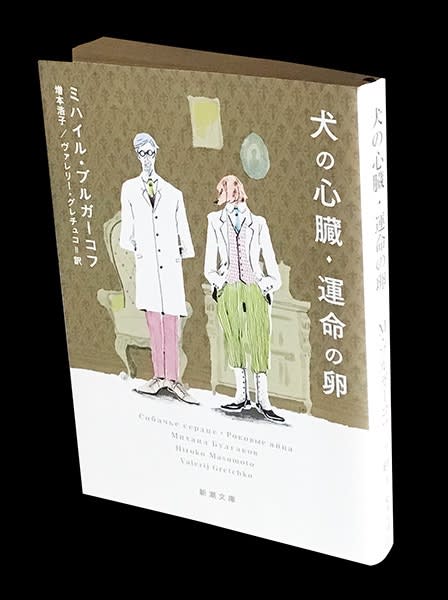
白衣を着た男性と、彼を睨む犬。
犬の首から下は普通の人間で、二人羽織のような違和感がある。
そんな二人が描かれたカバーのイラストは、とてもお洒落。
スマートな小説を想像するのだが。
『犬の心臓』は、野良犬のモノローグから始まる。
空腹な犬は、いじめられて怪我をし、死を覚悟している。
1920年代のソ連。
その犬の目を通して、いかに人々の食が貧しいのか、生活が苦しいのかが示される。
そこへ、裕福な身なりの、ソーセージを持った男が通りかかり、犬は必死に這って近づく。
こうして、医者と犬は出会う。
犬が思うことを、まるで漫画の吹き出しのようにはさみながら進行していく物語は、馬鹿馬鹿しくも滑稽な味わい醸し出す。
体制を小馬鹿にしたような箇所もあって、当時の状況を考えると、おかしいけれど、これ大丈夫? と思ったりする。
手術を施された犬が、徐々に変わっていく様子は、グロテスクでもあるが、どこか物哀しい。
ドタバタの喜劇なのに、ちょっとホロリとさせられるときの、気持ちの揺さぶられ方にも似ている。
装画は坂本奈緒氏。(2019)



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます