ヘンリー・ミラー『北回帰線』
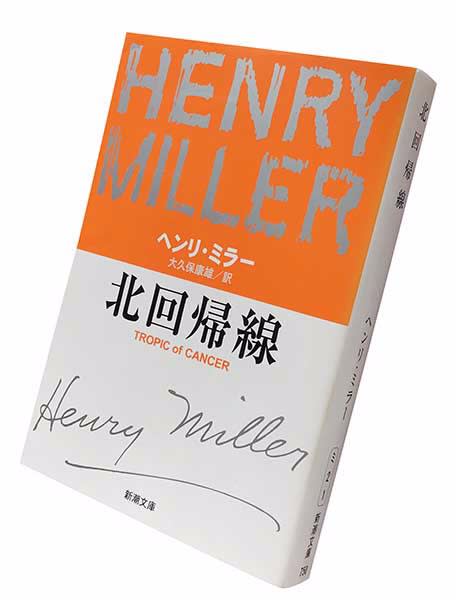
どうやら読みにくいらしいと聞いていたため、なかなか手に取れない本だった。
長い休みを利用して一気にある程度まで読んでしまえれば、残りはなんとかなるかもしれない。そう考えていたところ都合よくまとまった休みが手に入り本を開いた。
読んでみると、懸念したほどわかりにくくはないが、話があちこち飛ぶし、次から次へ新しい名前が出てくるため混乱する。
彼らとの関係ははっきりしなくて、突如話の中心に躍り出た人物が改行とともに消えてしまい、存在を忘れた頃にひょっこり再び登場するようなことがある。なかには二度と登場しない人もいるかもしれない。
モナという女性が、アメリカに残してきた妻だと知るのは、最初に彼女が現れてからだいぶあとのことで、謎の愛人としてぼくはしばらく記憶に留めておいた。
1930年代、ヘンリー・ミラーはパリにしがみついていた。囚われていたと言えるのかもしれない。パリについてミラーは「チャンスが万人にないからこそ、ほとんど希望がないからこそ、ここパリでは人生が楽しいのだ」と書いている。
常に金がなく、希望もなく、絶えず誰かから食事を恵んでもらえないかを考えている生活なのに、自分は幸福な人間だと言う。
「パリのような都会は、癌のようにわれわれの内部で生長し、徐々に大きくなっていって、われわれは、ついにはそれに食いつくされるのである」とも書いていて、底辺から抜けられないことを嘆くのではなく、当たり前のことのように受け止めている。
異国にいて発揮されるこの逞しさは、故郷アメリカを完全に見限ったからこそ得られたものなのか。アメリカでは万人にチャンスと希望があり、成功を夢見られる国だろうとぼくは思っているが、それはミラーの望む人生ではないのだ。
ところで、思いつくまま断片的に書かれたこの文章は何なのか。
「小説ではない」、「ぼくは歌っているのだ」と言う。読む人を意識しない書き散らした印象はあるのだが、ところどころ面白くて捕らわれてしまうこの「歌」は、また時間ができたらさらにじっくり読んでみたい作品だ。
装丁は新潮社装幀室。(2020)















