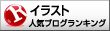ほんの手すさび、手慰み。
不定期イラスト連載・第五十九弾は、アンデルセン童話「赤い靴」。

昔々、「カーレン」という女の子がいました。
母子家庭の貧しい暮らし向きのため、靴を買う余裕がなくいつも裸足。
見かねた靴屋が、赤い端切れで靴を拵えてくれました。
やがて、体の弱かった母が他界。
告別式当日、棺の後ろに並ぶ彼女の足元は「赤い靴」。
何とも不釣り合いですが、他に履物がないのだから仕方がありません。
しかし、これが怪我の功名につながります。
通りすがりの裕福な老女が、葬列の中の紅一点に注目。
憐憫の情にかられ「カーレン」を引き取ることにしました。
天涯孤独の自分を救ってくれた「赤い靴」を脱ぎ捨てた「カーレン」の境遇は一変。
寝食足り、教育を受け、何不自由ない生活のお陰で、町一番の美少女に成長します。
そんなある日、彼女は靴屋の店先で動けなくなりました。
視線の先には、光を反射し艶々と輝くエナメル革の「赤い靴」。
数年前、王族行幸の折に王女がお召しになっていたのとよく似た逸品でした。
色物が禁じられた大切な宗教儀式へも、お構いなしに履いて出かけ、
保護者の老女が死の床に就いていても「赤い靴」と連れ立って舞踏会へ。
最初は楽しく踊っていましたが、疲れ果て、休みたくなっても、
そのステップは止まりませんでした。
踊りながら会場を飛び出し、往来に出て、森の奥深くへと分け入り、
来る日も来る日も、雨の日も風の日も、昼も夜も踊り続ける「カーレン」。
勿論「赤い靴」を脱ごうとしましたが、ピッタリと張り付いて離れません。
…そして、ついに決心します。
死のダンスから逃れるため、首斬り役人の元へ。
『私は「赤い靴」の虜になり、神様をないがしろにしたうえ、
恩人を見捨ててしまいました。
どうかお願いです。 私の足を切り落としてください。
罪を悔い改めたく存じます。』
懇願は聞き届けられ、か細い足首に斧が振り下ろされます。
「赤い靴」を履いた両足は、去っていってしまいました。
首切り役人に作ってもらった木の義足を付けた「カーレン」は、
松葉杖を突き、街の教会へと向かいました。
そこで、犯した大罪と悪行の報いを人目に晒し、神に救いを求めようと考えたのです。
高熱に耐え、下肢を引きずりながら辿り着いた扉の前には、
あの「赤い靴」が、踊りながら主の到着を待っていました。
<後略>(※原作:ハンス・クリスチャン・アンデルセン / 粗筋要約:りくすけ)
「赤い靴」のお話しはもう少し続く。
「カーレン」は神父の家の下働きとして、祈りと労働に明け暮れる献身的な生活を送り、
その魂は天へと召されてゆくのである。
…美しいエンディング。
だが、取って付けたような、座りの悪さを感じるのは僕だけだろうか。
残酷かつ中途半端に終えた方が、読後の感慨は深まり、想像は広がり、思考する。
物語としては完成度が高いと思えるのだが、
何故、作者は、最後に「救済」を用意したのか?
著された19世紀の常識。
キリスト教の宗教観。
子供向けの読み物。
良くも悪くも、そうした諸々の柵(しがらみ)が反映されたからではないだろうか。
同じ傾向は「人魚姫」にも見て取れるのである。
次回へ続く。
不定期イラスト連載・第五十九弾は、アンデルセン童話「赤い靴」。

昔々、「カーレン」という女の子がいました。
母子家庭の貧しい暮らし向きのため、靴を買う余裕がなくいつも裸足。
見かねた靴屋が、赤い端切れで靴を拵えてくれました。
やがて、体の弱かった母が他界。
告別式当日、棺の後ろに並ぶ彼女の足元は「赤い靴」。
何とも不釣り合いですが、他に履物がないのだから仕方がありません。
しかし、これが怪我の功名につながります。
通りすがりの裕福な老女が、葬列の中の紅一点に注目。
憐憫の情にかられ「カーレン」を引き取ることにしました。
天涯孤独の自分を救ってくれた「赤い靴」を脱ぎ捨てた「カーレン」の境遇は一変。
寝食足り、教育を受け、何不自由ない生活のお陰で、町一番の美少女に成長します。
そんなある日、彼女は靴屋の店先で動けなくなりました。
視線の先には、光を反射し艶々と輝くエナメル革の「赤い靴」。
数年前、王族行幸の折に王女がお召しになっていたのとよく似た逸品でした。
色物が禁じられた大切な宗教儀式へも、お構いなしに履いて出かけ、
保護者の老女が死の床に就いていても「赤い靴」と連れ立って舞踏会へ。
最初は楽しく踊っていましたが、疲れ果て、休みたくなっても、
そのステップは止まりませんでした。
踊りながら会場を飛び出し、往来に出て、森の奥深くへと分け入り、
来る日も来る日も、雨の日も風の日も、昼も夜も踊り続ける「カーレン」。
勿論「赤い靴」を脱ごうとしましたが、ピッタリと張り付いて離れません。
…そして、ついに決心します。
死のダンスから逃れるため、首斬り役人の元へ。
『私は「赤い靴」の虜になり、神様をないがしろにしたうえ、
恩人を見捨ててしまいました。
どうかお願いです。 私の足を切り落としてください。
罪を悔い改めたく存じます。』
懇願は聞き届けられ、か細い足首に斧が振り下ろされます。
「赤い靴」を履いた両足は、去っていってしまいました。
首切り役人に作ってもらった木の義足を付けた「カーレン」は、
松葉杖を突き、街の教会へと向かいました。
そこで、犯した大罪と悪行の報いを人目に晒し、神に救いを求めようと考えたのです。
高熱に耐え、下肢を引きずりながら辿り着いた扉の前には、
あの「赤い靴」が、踊りながら主の到着を待っていました。
<後略>(※原作:ハンス・クリスチャン・アンデルセン / 粗筋要約:りくすけ)
「赤い靴」のお話しはもう少し続く。
「カーレン」は神父の家の下働きとして、祈りと労働に明け暮れる献身的な生活を送り、
その魂は天へと召されてゆくのである。
…美しいエンディング。
だが、取って付けたような、座りの悪さを感じるのは僕だけだろうか。
残酷かつ中途半端に終えた方が、読後の感慨は深まり、想像は広がり、思考する。
物語としては完成度が高いと思えるのだが、
何故、作者は、最後に「救済」を用意したのか?
著された19世紀の常識。
キリスト教の宗教観。
子供向けの読み物。
良くも悪くも、そうした諸々の柵(しがらみ)が反映されたからではないだろうか。
同じ傾向は「人魚姫」にも見て取れるのである。
次回へ続く。