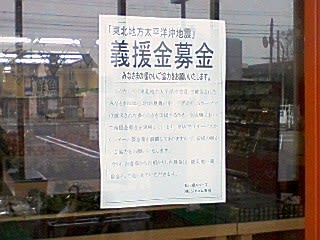「今日の一枚」は、津幡川に架かる「住ノ江橋」付近で撮影。
ちょうど「津幡郵便局」に隣接した辺り、
緩やかな下り坂の欄干には、点々とパンジーの鉢植えが飾られている。
散歩中、その風に揺れる花びらに目をやると、
奥にある倉庫の壁に書かれた文字が目に付いた。
『水防備蓄資材置場』。
写真ではピントが花に合っていてよく読めないが、そう書いてある。
倉庫の前に回ってみると…

堰を造るための木の杭や石、木材が置いてあった。
去年、11月13日にも投稿ように、かつての津幡川は「暴れ川」。
現在は護岸工事と水門などによる治水で、なだらかな流れになっているが、
度々氾濫し、近隣に甚大な被害を与えてきた。
資材は、その教訓を活かした備品なのではないかと推測する。
…正直、大事が起った時、ここにある量では賄いきれないだろう。
しかし、小規模ならば抵抗はできるかもしれない。
そして、災害への心構えを忘れない意味でも、存在価値はあるのだ。
また「アルプラザ津幡」近くの新興住宅街とバイパスの間には、
プールのような広いスペースが確保してある。

コンクリートで固めたそこは「2号調整池」。
近くに立て看板があって、次のような説明文が書かれていた。
『この調整池は、津幡町北中条地区土地区画整理事業に伴う
防災上の調整池であり、下記の施設については責任をもって
維持管理します。(※中略/調整池の概要) 管理者 津幡町』
「調整池」とは…一言で言うなら「人工の受け皿」だ。
宅地や工場など、人の手によって山林が開発され、
治水能力が低下した土地に作られるケースが多い。
集中豪雨など、短時間の局地的な出水が河川に流れ込む前に、
一旦、ここに溜めてから少しづつ放流する。
未だ、水を讃えた様子は見たことがない。
見ずに済めば越したことはない。
これも「備え」だ。
ちょうど「津幡郵便局」に隣接した辺り、
緩やかな下り坂の欄干には、点々とパンジーの鉢植えが飾られている。
散歩中、その風に揺れる花びらに目をやると、
奥にある倉庫の壁に書かれた文字が目に付いた。
『水防備蓄資材置場』。
写真ではピントが花に合っていてよく読めないが、そう書いてある。
倉庫の前に回ってみると…

堰を造るための木の杭や石、木材が置いてあった。
去年、11月13日にも投稿ように、かつての津幡川は「暴れ川」。
現在は護岸工事と水門などによる治水で、なだらかな流れになっているが、
度々氾濫し、近隣に甚大な被害を与えてきた。
資材は、その教訓を活かした備品なのではないかと推測する。
…正直、大事が起った時、ここにある量では賄いきれないだろう。
しかし、小規模ならば抵抗はできるかもしれない。
そして、災害への心構えを忘れない意味でも、存在価値はあるのだ。
また「アルプラザ津幡」近くの新興住宅街とバイパスの間には、
プールのような広いスペースが確保してある。

コンクリートで固めたそこは「2号調整池」。
近くに立て看板があって、次のような説明文が書かれていた。
『この調整池は、津幡町北中条地区土地区画整理事業に伴う
防災上の調整池であり、下記の施設については責任をもって
維持管理します。(※中略/調整池の概要) 管理者 津幡町』
「調整池」とは…一言で言うなら「人工の受け皿」だ。
宅地や工場など、人の手によって山林が開発され、
治水能力が低下した土地に作られるケースが多い。
集中豪雨など、短時間の局地的な出水が河川に流れ込む前に、
一旦、ここに溜めてから少しづつ放流する。
未だ、水を讃えた様子は見たことがない。
見ずに済めば越したことはない。
これも「備え」だ。