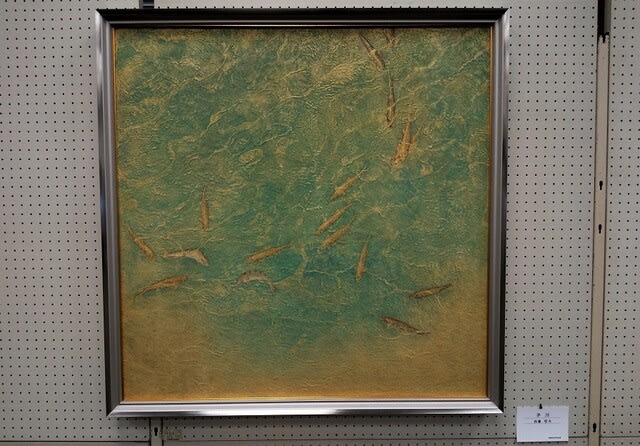先日の散歩中「勝﨑館(かつざきかん)」に立ち寄った。

創業120年を超える料理旅館。
銭湯も併営していて、僕も折に触れお邪魔している。
現在『勝﨑の湯』と称するお風呂は、かつて「津幡温泉」を名乗っていた。

時を遡ること200余年。
江戸時代、文化・文政期に発見されたと伝えられる津幡鉱泉。
その地下からの恵みを薪の炎で温め、浴場として創業したのは、明治22年(1889年)。
以来、近隣諸人の身体を癒し続けている。
そんな憩いの施設の正面玄関軒先に、見慣れないモノを発見した。

紅白の水引で結んだ奉書に包まれているのは、どうやら「トウモロコシ」。
紙の文字は「長谷山観音院」とある。
帰宅後に調べてみたところ、金沢市観音町のお寺が出処。
四万六千日分のご利益があるとされる功徳日に祈願した「とうきび」は、
「魔除け」兼、商売繁盛や子孫繁栄の「縁起物」なんだとか。
--- 拙ブログをご覧の皆さまは「縁起を担ぐ」だろうか?
思えば、僕が子供だった頃、亡母に縁起が悪いと諭されたことがある。
【夜に爪を切ると親の死に目に会えないからやめろ】
理由を尋ねたが、とにかく「ならぬ」の一点張り。
腑に落ちない僕は考えた末に、一つの結論に至った。
照明が発達していない昔の夜は暗く、手元がおぼつかない。
また爪切りの道具も、いわゆる和鋏(わばさみ)。
指を切る危険が高いから、明るい時間帯にするものだ。
そんな意味合いが込められているのだろうと、納得した。
縁起が悪いとされることは他にもある。
【霊柩車を見たら親指を隠さなければいけない】
【雛人形の片付けが遅れると婚期が遅れる】
【夜に口笛を吹くと蛇が出る】等々。
どれも眉唾である。
さて、オッサンになった僕が、縁起を担ぐ機会はあるだろうか?
--- あった!

競艇の投票をする際に使う「ペグシル」の中から、
1着になって欲しい「色」を選んでマークするのだ。
1号艇・白、2号艇・黒、3号艇・赤、4号艇・青、5号艇・黄、6号艇・緑。
レーサーは乗艇する枠番によって、6つの色に振り分けられている。
不確かな未来に銭を張る時「その色」を手に取るのに、理由も根拠もない。
ただ、祈りがあるだけだ。