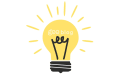【令和6年1月18日】林芳正官房長官 記者会見(午前の部:岸田派の会計責任者立件、日本共産党の公安取扱いの件)
【令和6年1月18日】日本共産党 第29回大会④新体制で記者会見

共産党の志位和夫委員長(KYODONEWS)
共産、志位委員長交代へ 後任に田村氏有力、女性初
共産党は18日、静岡県熱海市で開会中の第29回党大会で志位和夫委員長を交代させる方向で最終調整に入った。午後に正式決定する。交代すれば2000年11月以来、約23年ぶりとなる。党関係者が明らかにした。後任には田村智子政策委員長の就任が有力視される。女性初の委員長となる。 志位氏は1990年に35歳で書記局長となり00年に委員長就任。党運営の中枢を担ってきた。党内では、国政選挙で野党共闘路線を推進した手腕を評価する一方、歴代最長の在任期間に対し世代交代への期待も高まっていた。 田村氏は10年参院選で初当選。19年に「桜を見る会」問題に火を付け、20年の前回党大会で女性初の政策委員長に就任した。今回の党大会では大会決議案の起草責任者と報告者を務めた。 共産大会は18日が最終日で、次期衆院選に向け、野党共闘の再構築を目指す方針を盛り込んだ大会決議を採択した。午後に幹部人事を決める。17日の議事では、不破哲三前議長は党の方針や運営に決定権を持つ中央委員に就かず、名誉役員となる人事案が示された。
大島九州男 公式チャンネル 参議院議員 れいわ新選組 がライブ配信中!上関原発視察の感想
【音喜多、聞け!】これを見てもまだ「迷惑系国会議員」と呼ぶのか!? 山本太郎の“ど正論“に拍手!(れいわ新選組 会見)
日本共産党 第29回 党大会 生中継 【最終日:中央委員会の選出・委員長など新三役の記者会見】
【声明】石川県能登半島地震の復興にかかるれいわビジョン(れいわ新選組 2024年1月17日)
(主旨)
2024年元旦(1月1日)に石川県 能登半島地震が起きてから、
政府は一度も大きな復興の見通し・ビジョンを示していない。
それにより、被災された方々のみならず、支援する人々の間にも、
どこまで走り続ければいいのか、いつになれば終わるのか、
という疲弊が拡がり、希望が持てないとの声を現場で多く聞いた。
以下、私たちとしてのビジョンをこの国に生きる全ての皆様に呼びかけると共に、
現行政府に必要な施策を徹底的に求める。
(れいわビジョン)
れいわビジョンとは、 甚大な被害をもたらした「能登半島を完全復興」させ、
どの地域にどんな災害がおきても、必ず国の責任で元の生活水準を取り戻すことを
国民に示す約束である。
誰もが住み慣れた地域で、なじみのコミュニティとともに幸福な生活を希求できるよう、
憲法上の国の責務を履行する政策を能登から実現する。
復興、と言葉だけ踊り、実際は将来的に過疎地域として放棄する様な取り組みは許されない。
この災害復興は、日本全国あらゆる地域での国民の生活を守る国の姿勢が問われている。
【本物の国土強靭化のモデル・能登半島】
建物の倒壊が多数。自宅の再建も難しい。
インフラも壊滅状態、復旧の見通しはない。
その間にも生活の安定を求めて人口の流出は続く。
「次に大きな地震があったときにはもう立ち上がれない」など
様々な不安の声を被災された人々から聞いた。
これまで言葉だけの国土強靭化は何度も耳にしたが、
実際、実行に移された大胆な強靭化を私たちは知らない。
だからこそ、能登半島から本物の国土強靭化を始めたい。
例えば「半年」という期間で徹底的に持てる国力を集中させ、
次の災害にも耐えられる能登半島にする。
インフラの再整備、津波浸水地域の嵩上げ、十分な耐震性も担保しながら、
輪島朝市など焼失した地域の雰囲気も再現する試み。
日本の原風景とも、独特ともいえる 息をのむ能登の美しさを保ちながらも、
災害に強い街造りを1から始めよう。
復旧を半年で急速に進めつつ、
息の長い生活再建・事業環境の再生にもコミットし続ける。
能登半島で移住や移転を選ぶ人や企業には、長期に及ぶ減税措置など
様々なインセンティブを作り出そう。
災害があるたびに街が終わっていく、
人の流失が止まらない。
災害大国日本における問題に、本気で取り組む最初のモデルケースとなるのが能登半島である。
集中的にあらゆる資源を投じて、半年の期間で基本的な住環境、ライフラインを復旧させる。
その間は基本、広域避難。
被災した方々に「今年の夏祭りまでに地域生活のライフライン・基盤を再生する」
そして 「次の元旦こそは避難先でなく、地元で家族・親族と正月を祝う」
という希望をもって生きていただけるよう国をあげて取り組む。
1、2年では難しい、ではなく
国の持てる力を全て注ぐ気概と決意で住民に目標を示す誠意が必要である。
以下、そのために必要な国からの支援を要求する。
1.復興までの広域避難について。
地域の復興を確約の上、 命を守るため、
一切の被災者負担なく、所得補償も含め 政府主導で速やかに行う。
地区単位で避難先を設け、 コミュニティを壊さない形で広域避難を進める。
その移動手段の1つとして、フェリーなど大勢を運べる方法を一刻も早く実行すること。現在、七尾港に停泊しているフェリーは防衛省がたった一隻のみPFI契約する民間船舶であり、食事と入浴、一泊だけできるという休憩船として使われている。全国には2104隻の旅客船があり(一般社団法人日本旅客船協会)、「はくおう」と同クラスのフェリーも1隻や2隻ではない。現地のニーズに合った船を数多く手配し派遣することは十分可能だ。至急調整を行い、国交省が停泊可能とする港湾の岸壁を使い広域避難に対する人々の移動手段及び一時避難所としての使用を開始させる。
2.地域に残る人等のために仮設住宅を爆速で作る。
仮設待ちを出さないためにも、全国に登録のある20万台近いキャンピングカーの一部を国が有償で借り上げ、
または買い上げ、仮設住宅とみなす動きを加速する。
それらの一部は感染症の有症状者、その疑いがある人の一時保護や、自治体職員、応援職員、NPO、福祉専門職や看護師などの仮宿舎としても先述のフェリーと合わせて活用する。
高齢者や障害者の方々などが望めば、早期に地域に戻れるように、福祉施設の復旧、応援職員の増員のための予算を迅速につける。
3.ノウハウのある国・自治体の職員の長期派遣、支援組織への公費投入も行う。
土木の専門職とあわせ、公的な医療・介護等福祉専門職の確保を行う。
4.「自治体マターだ」と通常の役割範囲を理由に復旧を放棄せず、
道路、電気、上下水道などインフラ復旧の全てを国が責任をもって行い、ボトルネックを解消する。
「非常災害」指定により既に道路 (のと里山海道) など国が代行復旧することとなっている。
これらを急ぐのは当然のことである一方、三井から輪島を結ぶ輪島道路の第2期は、
2012(平成24)年度に事業化したが、当初目的の災害用途に間に合わなかった。
今回の災害復興の流れで完成を目指す。
5. 不要不急な事業(大阪万博、辺野古埋立工事)は中止し、
被災地に社会的リソースを回すとともに、復興を理由とした増税をおこなわない。
6.地域の経済・なりわい再生のため、
コロナ禍以上の事業継続・債務免除・社会保障負担免除、雇用維持支援策を追加導入する。
「平時に戻している」場合ではない。
「平時以上に戻す」ことを目標として取り組む。
7.被災された方々や地域と関わり、
復興やコミュニティー再生への伴走が物理的に長期間、可能になるよう、
復旧・復興に取り組むNPO、ボランティアなどへの経費精算、有償化を進める。
8.農林水産業や伝統文化への支援も国からの100%補助とする。
例えば、地震津波被害により新規造船が必要な方に対しても同等とする。
9.本復旧・復興が軌道にのるまでの間、
衆参における災害対策特別委員会を週一回の定例とし、
総理大臣が必ず出席するものとする。
2024年1月17日
れいわ新選組
豊田真由子氏「誤魔化されちゃいけない」岸田首相の派閥パーティー、人事の推薦禁止“検討”に
元衆議院議員の豊田真由子氏(49)が17日、MBSテレビの情報番組「よんチャンTV」(月~金曜午後3時40分、関西ローカル)に生出演。岸田文雄首相の“検討”に疑問を呈した。
自民党は16日、岸田首相を本部長とする政治刷新本部の第2回会合を開催。岸田首相は派閥パーティーや、人事に関する派閥の推薦を禁止する方向で検討に入ったとみられる。
豊田氏は「私はごまかされちゃいけないと思っている」とピシャリ。「厳しいことを言えば、国民目線で1番大事なのって政治資金の流れの透明化。派閥が解消するかしないか以前に、ちゃんと政治資金収支報告書に載せるとか、デジタル化して1円まで入りと出をきちんとするということを制度化してほしい」。
さらに、議院内閣制を採用する日本では、人事は与党内で決まることから「必ずグループができて勢力争いが起こる」とし、「派閥的なものは残る」と主張。「国民が納得できるかというと、そこじゃないと思う」と首をかしげた。
コメンテーターのタレント、REINAが「キックバックの使い道が何だったのかっていうのが明確になっていない。そこの説明が一切ない」と指摘すると、豊田氏は「入りと出をちゃんと国民に見せるようにしないと、『何が刷新なの?』ってなっちゃうと思う」と同調。「誰か言った方がいいと思いますけど」と苦笑していた。

人手不足なのに──。昨年「早期・希望退職者」を募集した上場企業が増加していたことがわかった。
東京商工リサーチの調査によると、2023年に「早期・希望退職者」を募った上場企業は41社だった。2022年を3社上回った。社数が前年を上回るのは3年ぶりのことだ。対象人数は3161人(前年比45%減)と半減したが、これは前年1社あった1000人以上の大型募集がなく、小規模の募集が多かったためである。
41社のうち黒字企業は21社、赤字企業は20社だった。IT企業などの情報通信が11社(前年比266.6%増)と、前年の3社から増えて最多。情報通信が最多になるのは、初めてだ。電気機器、アパレル、医薬品が、それぞれ5社だった。
それにしても、これだけ深刻な人手不足が加速しているのに、なぜ“人減らし”に踏み切る企業が増えているのか。2023年は「人手不足」倒産が、過去最多になったと発表されたばかりだ。
東京商工リサーチ情報本部の本間浩介氏はこう言う。
「市場ニーズの変化が原因のひとつです。一例をあげるとIT企業です。コロナ禍ではDX化が叫ばれて需要が増え、人を確保しましたが、コロナ禍が収束して需要が落ち、社員が過剰になっているのでしょう。さらに、黒字企業にも、円安やコスト高など、激しい変化に対応するために人材を入れ替えたい、という意向があるようです。もちろん、赤字企業は固定費の削減が目的です。赤字企業の場合、会社が予定していた早期退職者の人数に達しないと、整理解雇に移る例もあります」
これまでは、たとえばメインの営業先を国内から海外に移す場合、国内部門の人材を海外部門に異動させることもあったが、最近は、国内部門はそっくりリストラし、海外部門に必要な人材は外から補うケースも増えているという。
「不採算部門にいる社員のスキルでは、好業績の部門では通用しない、ということも起きているようです。人手不足のため、新規採用には時間もコストもかかりますが、それでも不採算部門の社員を活用するより、外部から優秀な人材を採用した方がいい、と考える企業が増えています」(本間浩介氏)
人手不足でも、常に新しいスキルが求められるのは変わらないということだ。