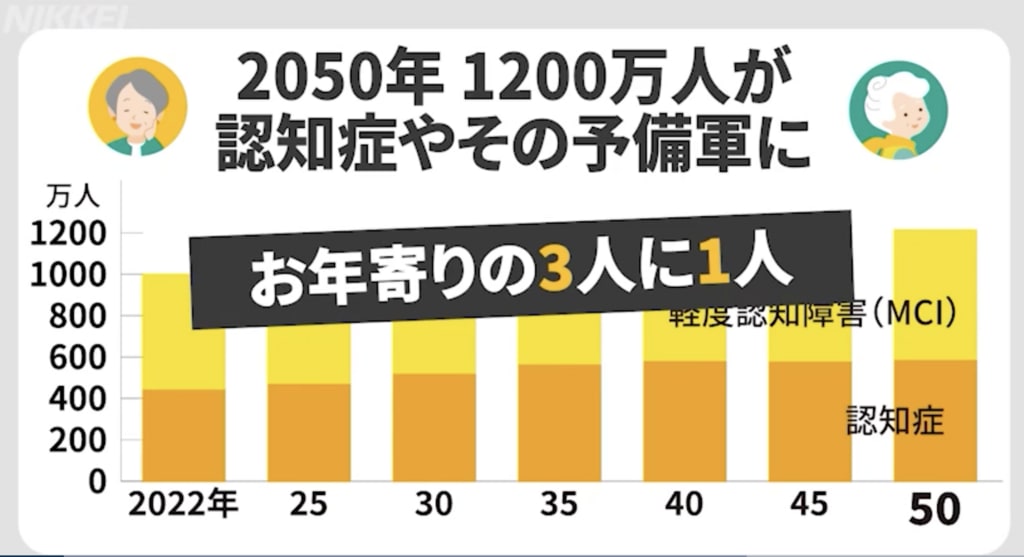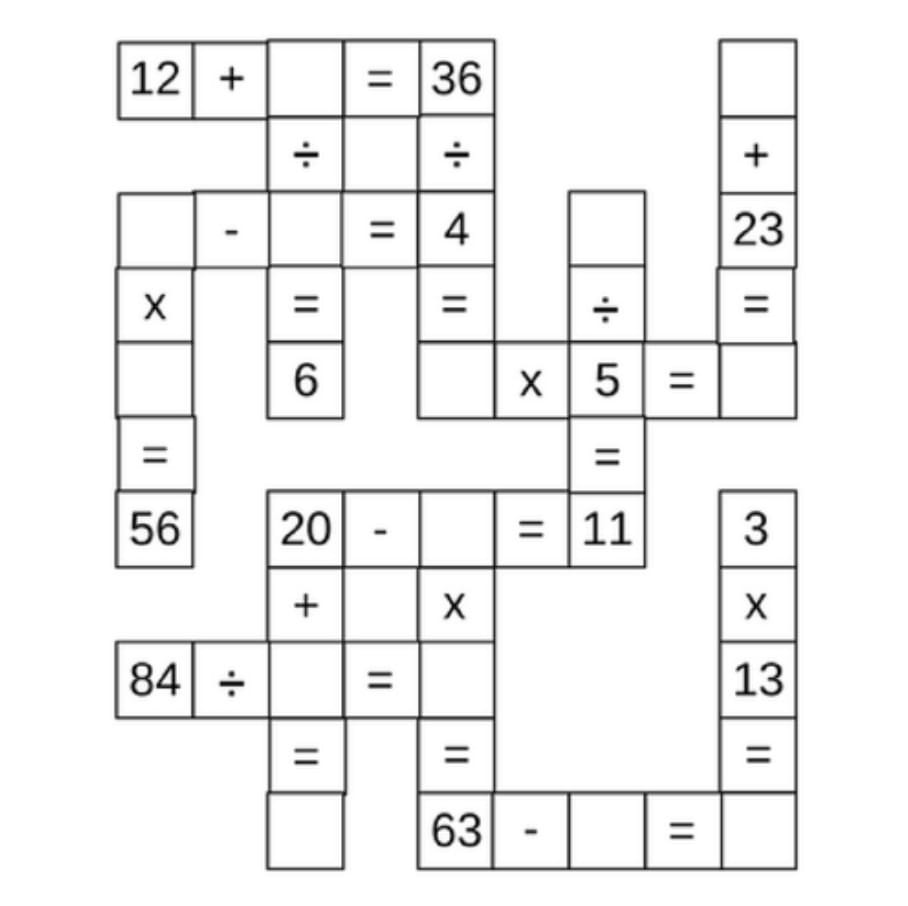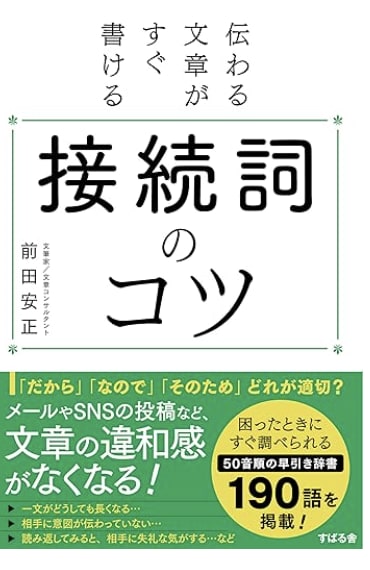@「ミニマル・ライフ」とは生活・仕事の人間関係などに対して「More」よりも「Less」、「Big」よりも「Small」、「Fast」よりも「Slow」であること、さらに「足るを知る」技術を習得することで「軽量化」を極限まで削ぎ落とせ健康体を保ち、人間関係、お金の管理まででき幸福度が増すに繋がるのだ。人間は「欲」の塊、死ぬ時は何も無い。だから歳をとれば1つづでも「捨てる」覚悟が必要だ、と思う。最後まで残せる欲は、人間本来の「欲」である睡眠欲、食欲、性欲であり、モノに対する物欲、金に対する財欲、自慢などの名誉欲は一才放棄すべきものだと言うことになる。
『超ミニマル・ライフ』四角大輔
「概要」思い込み」「脳疲労とストレス」「体」「食事」「人間関係とコミュニケーション」「お金と働き方」のすべてを軽量化するための【全技法】公開!その【全技法】は〈7つのSTEPと61のMethod〉に体系化されていて、それらすべては「3つの原則」に集約される。
①「自由時間」最大化のために、仕事と家事を超効率化する
②「パフォーマンス」最大化のために、体・脳・心の負担を最小化する
③「幸福度」最大化のために、お金・仕事・人間関係の不安をなくす
著者は、「減らす」「手放す」「軽くする」「削ぎ落とす」といった引き算をしていった。不安定な経済に振り回されず、不確かな世間の価値観ではなく、自分の意思に従って生きる――それが目指すべき「ミニマル・ライフ」である。
ー日本の現状
幸福度は極度に低い、ただならぬ不安と焦りに駆られ渇望症なる病を患っている
どうでもいいことに注ぐ労力、お金、時間を最小限にして、可能性を最大にする
ケミカル農薬大国世界ワースト3位(インドの30倍、スエーデンの20倍、米国の5倍)
長寿国ランキングではすでに日本は香港、スイスに次いで3位
過食傾向で食べ物残す(食べ過ぎで残すフードロス現象)
慢性ストレスで自殺やうつ病、精神疾患患者が増え経済的損失(年間15兆円)
ー軽量化できること(ミニマル化vsシンプル化:極限まで削ぎ落とすvs簡素化する)
・思い込みの軽量化
「忙しい」で人生を破綻させているのをロングスローディスタンスにする
「選ぶことは手放すこと」=減らす・軽くする・削ぎ落とすこと
「足るを知る・身の丈を忘れず」心地よいペースを続ける
・体の軽量化
健康な心身「ちゃんと食べ、体を動かし、休み、寝る」
「TO DO」から『WANT TO DO』やらされているから挑戦するへ
毎日20分のヨガと週3回45分のスロージョグ(自然の中)
・食事の軽量化
気になる食品添加物を摂らない
亜硫酸ナトリウム・甘味料・カラメル色素・加工澱粉・酵素・防カビ剤
健康リスクの高い食材
赤肉(大腸癌)、乳製品(虚血心性疾患)、小麦粉(アレルギ)、砂糖(糖尿病)
季節外れの野菜(栄養加減)を止め、旬な作物と地元国産品を選ぶ、ミニマル料理
サプリメントは非常食とし健康発酵物(味噌、納豆、キムチなどが良い)を摂取
食べ過ぎ・夜の大食などには断続的ファスティング(間欠的断食)
断食がもたらす効能:肥満症・糖尿病・心血管疾患・癌・神経疾患
・脳疲労とストレイの軽量化
「遊び」で精神的・脳・体へのストレス軽減(心も軽くする)
「睡眠」(長さと深さ)ノンレムとレムの90分サイクル(長すぎてもだめ)
10代で8時間以上、25歳で7時間、45歳で6.5時間、65歳で6時間
成長ホルモンの7割が睡眠時に分泌される(筋肉・骨・皮膚など全身へ)
「朝日を浴びて」体内のセロトニンを分泌させる:幸福感・集中力ホルモン
「カフェイン摂取は15時までに」体内に残り上質な睡眠ができない
「お風呂は寝る2時間前」深部体温温存(脳と内臓の保温で寝つき熟睡効果)
デバイス・オフライン化(セルフケアタイム)脳疲労を防ぐ
・人間関係とコミュニケーションの軽量化
人間関係こそメリハリが大切(心を許せる優先順位をつけて付き合う)
苦手な人とは少しポジティブな言葉を使う(プライミング効果)
失礼のない完璧な礼儀で接する(距離感を保ち、いい所を見つけるゲーム感覚で)
「誰もが口にする一見正しそうなアドバイスは絶対ではない」と言う哲学
無駄な時間を交わすことを避ける(余計な接待と効率の悪い仕事への不満)
信念に従って行動する勇気を持つ(誠実さ、情熱、前向き)
・お金と働き方の軽量化
大きな挑戦には逃げ道を用意しておく(ポジティブエスケープ・精神的セーフティネット)
ライフコストを予算化(投資・消費・浪費分)ミニマム化を計画
大胆なメリハリ経営を計画(ハイライト思考・一点突破的起業)
定年無し・年金なしで副業(パラレルキャリア)と継続的な多面的社会貢献など
「私は決して頭が良いわけではない。ただ、誰よりも好奇心があるだけだ」アインシュタイン
「そこに山があるからだ。Because it’s there」登山家ジョージ・マロリー