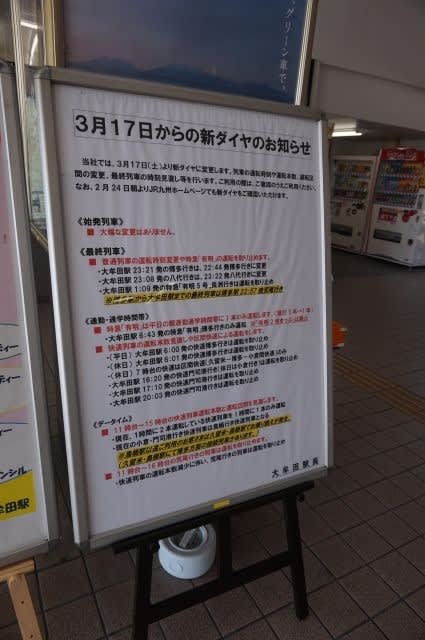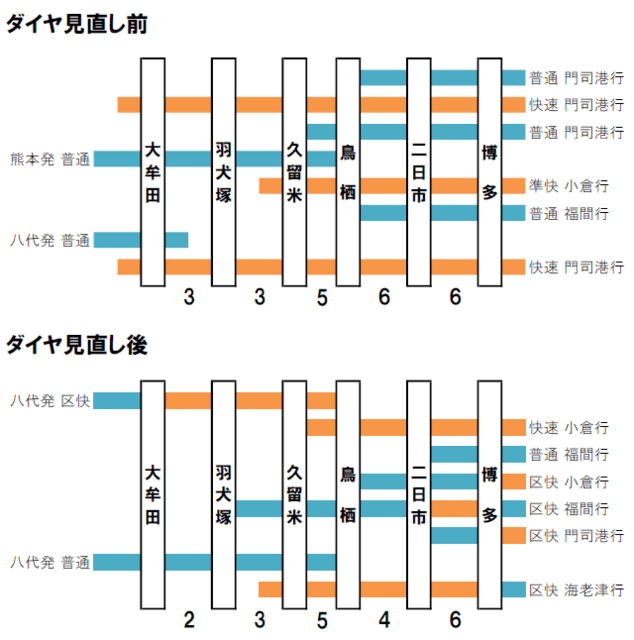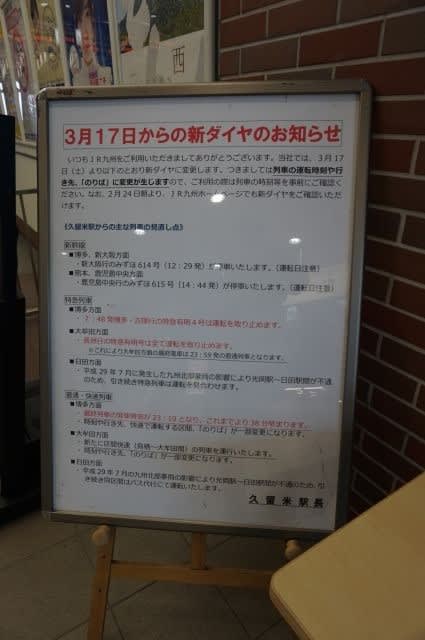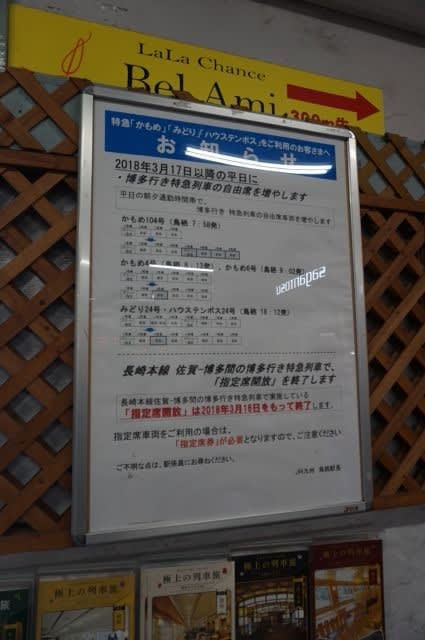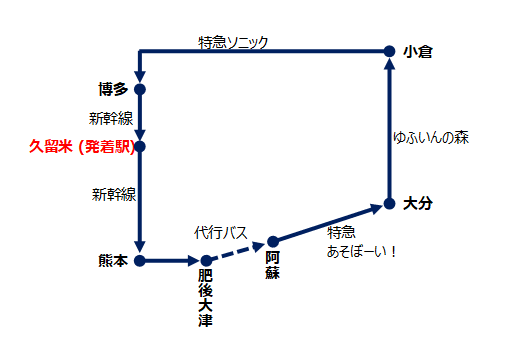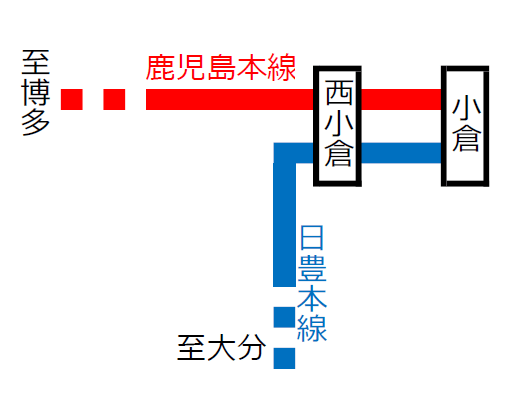8月26日の西鉄ダイヤ改定では、バス路線の大きな改変も行われました。一方、西鉄電車では今後も、さまざまな動きが予定されています。
ダイヤ改定の翌日と翌々日、変わったところ、変わるところも訪ね歩いてみました。
連接バス郊外延伸、通勤の強い味方に?
昨年から市内中心部で運行されている、“都心循環BRT”こと連接バス。今回のダイヤ改定で、郊外の車庫から都心循環に送り込むまでの回送運行が「特快」となり、乗客が乗れるようになりました!
朝の郊外から都心方向、夕刻の都心から郊外方向が中心だけに、通勤客の強い味方になりそうです。

早朝の特急電車を大橋で降り、一般バスで那珂川営業所へ。福岡市内を運行するバスの多くが在籍する一大ターミナル、ずらりと並ぶバスは壮観の一言です。

黄色い流線形の車体が目を引く連接バスも、「回送」ではなく「W特快」の表示を出して待機中。
「W系統」は本来、大橋~天神間のバス路線の系統名。那珂川まで入る便には振られない系統のはずだけど、まあいいか。1日に上り4本、下り3本の特別運行です。

車庫から長い車体をくねらせ、8:00発の連接バスが乗り場に姿を現しました。営業開始2日目だけに、
「あ、長いやつだ」
と、お連れさんに話す人もいますが、他の乗客は当たり前のように乗っていきます。いつも見てた車両に乗れるようになった、という感覚なのかな。

バス停には目立つ黄色で「W特快停車バス停」の表示がされています。

大柄な車体だけに、車内はゆったり。座席も多く、通勤には強い味方になるんじゃないでしょうか。朝4本、20分毎のバスを狙う人が増えそうな気がします。
途中バス停からは、初乗り目当ての母子連れも乗車。連接バスの注目度は、なかなか高いものがあります。

大橋駅のロータリーに、長い車体が入っていきます。回送区間の営業運転化というと簡単そうだけど、バス停のチェックや警察との協議など、苦労は多かったんじゃないかと思います。
連接バスの購入には、都心循環用バスとして福岡市からの補助も入っているはずで、「目的外使用」に対する整理も大変だったんじゃないかな。

2両目のドアは那珂川、大橋駅のみで乗降可能。しかし渡辺通りから“BRT”の区間に入ると、突如ドア扱いが始まります。降車時はICカード専用で、慣れない人は戸惑うはず。
しかし天神ソラリアステージ前には案内員が出ていて、降車客にガイドしていました。ダイヤ改定のフォローは抜かりなしです。

渡辺通りから先は、すっかり連節バスが日常となった区間に。一旦は混んだ車内も、再び空きました。
おおむね20分間隔の運行なので、連接バス同士がすれちがうシーンも多くあります。

博多港国際ターミナルに到着。独特の「まっ黄色のお尻」を振りながら(笑)、転回場へと帰っていきました。

ターミナルをぶらぶら見物して、今度は博多駅方面の“BRT”に乗車。

蔵本バス停で下車しました。
ワシントニアパームを背景にした連接バス、どこか異国な雰囲気すら感じます。
西鉄香椎駅前バスロータリ完成、立派なターミナルに変貌

蔵本からは、都市高経由のバスで香椎へと向かいます。
以前なら地下鉄箱崎線と西鉄貝塚線を乗り継いだんだろうけど、「ホリデーアクトパス」を手にして以来、バス利用が増えました。

JR香椎駅前で下車。区画整理事業もいよいよ佳境、駅前広場の外形が見えてきました。

そして、もう一つの香椎駅こと西鉄香椎駅にも、立派な駅前広場とバス乗り場が完成。昨日から、路線バスの乗り入れが始まりました。

駅前広場の屋根は、どこか南欧風。

駅と広場の間にある木、確か地上時代の西鉄香椎駅にもあったように記憶しています。
立派なバス乗り場ながら、乗り入れるのは西鉄香椎折り返しの便のみで、経由便は従来通りの路上バス停へと分かれてしまったのは惜しいところ。経由便を広場に乗り入れると余計な時間がかかってしまうという事情は分かるのですが…
西鉄とJRの駅を相対させて、間に駅前広場とバス乗り場を配置するような計画にはできなかったものかと、いまさら言っても遅い戯言も出てしまいます。

2006年の高架化から9年、高架下の店舗もだいぶ充実してきました。乗降客数は3,500人と、久留米の西鉄花畑駅の半分以下ながらずっと店が多いのも、香椎という街そのものの大きさゆえでしょう。


せっかく香椎まで来たので、10年ぶりくらいにアイランドシティにも足を伸ばしてみました。

天を衝くような、2つのタワーマンション。

広大な人工の自然に映る、新しい住居たち。街びらきの頃に生まれた子どもも、もう小学校の中学年です。
香椎、千早、六本松、九大学研都市…同時進行で開発が進行する福岡は、どこまで大きくなってしまうのでしょうか。

そしてこの巨大な新都市の公共交通を、西鉄バスが一手に担うというのも、福岡らしい一面です。
地下鉄乗り入れの案は立ち消えになり、都市高速の延伸は決定。西鉄バスが、より速達性を増して都心とを結ぶことになるんでしょう。
福岡空港国際線ターミナルへの新ルートを試す

大橋駅に戻ってきました。西鉄大橋駅への特急停車は、福岡市南部での拠点性を高める施策の一環。そのもう一つの取り組みである、大橋駅~福岡空港国際線のバスに試し乗りしてみました。
特急停車を前に、今年の3月25日から走り始めた新路線です。

国際線ターミナル行きは、系統番号なしの無番。那珂川営業所から大橋駅を経由するものと、大橋駅始発の便があります。
出発時刻は分かりやすく、毎時00分、30分に統一。18分、48分に到着する上り特急から、ゆとりを持って乗り継げるダイヤです。

空港までは直行ではなく、主要バス停に止まる快速運行。日赤通りでは各バス停に停車し、大橋駅周辺の細かな需要を拾います。
きよみ通りに入れば、停車するバス停は山王一丁目のみ。昼間は渋滞も少なく、比較的スムーズなルートです。ラッシュ時はどうなのかな。

福岡空港国際線ターミナルでは、2階の出発ロビーまで乗り入れてくれるのはラクですね。

出発ロビー目の前に停車する西鉄バス。ちょっとミスマッチな感も(笑)。

日曜日の午後、出国者で賑わう時間帯です。

せっかく空港まで来たので、空港内シャトルバス(無料)で国内線にもお邪魔してみました。

大改良工事が進む国内線。営業しながらの改築に苦労が伴うのは、鉄道駅と同じです。新しいビルを少しずつ建て、古いビルを少しずつ壊す、の繰り返し。

1月にオープンした国内線の目玉施設、「the foodtimes」へ初訪問!福岡の名店が揃ったフードコートです。

福岡勤務時代は天神でたまに食べていた、風月のビーフバター焼きとひさびさに再会です。ガッツリ系なサラリーマンの味方は、旅行者にもきっとウケるはず。

いっぱいのお腹を抱え、シャトルバスで国際線へバック。国際線ターミナル1階から出発するバスも、ずいぶん多彩になってきました。特に別府行き、太宰府行きは、インバウンドの皆さまで大混雑です。
別府、黒川など名だたる観光地に並んで、「大橋」の行き先も加わりました。

大橋駅行きに乗り込んだのは、僕の他に2名。インバウンドとは無縁です。

今のところ、あまり乗客は多くないと聞く路線ですが、特急停車後のこれからが本領発揮する路線のはず。
天神地下街や地下鉄の混雑に巻き込まれないのはラクで、天神大牟田線沿線からの、メインルートに育ってほしいものと思います。
雑餉隈~下大利で進む高架化、昭和の駅の香りもあとわずか
2020年度の完成に向けて工事が進む、天神大牟田線の高架化事業。高架柱が立ち上がり、高架化後の姿が少しずつ描けるようになってきました。
一方、旧来からの駅舎が残っていた雑餉隈・春日原の仮駅舎化も、迫りつつあります。

まずは雑餉隈駅で途中下車。昨年夏まで住んでいた街なので、馴染みの駅です。それだけに次第に変わりゆく風景は、期待でもあり、寂しくもあります。

質実剛健、飾り気のない橋上駅舎も、残りわずか。


来年1月からの仮駅舎化が、すでに予告されています。

すでに駅の両側は、すっかり工事現場と化しています。高架化後の駅舎の形が見えてくるのは、もうしばらく先になりそうです。

あいかわらず庶民的な下町情緒漂う銀天町。高架化され踏切の音が聞こえてこなくなると、少し寂しくなりそう…個人の所感ですが。



一方、春日原駅はすでに高架駅の工事が始まっています。


2面2線だけに、大きな規模の駅になりそう。花畑のように、様変わりしそうです。

現在の駅の仮駅化はアナウンスされていないものの、そう遠くはないように思います。
8000形電車、間もなくラストラン…「旅人」車両交代へ
僕ら世代には寂しいニュースも入っています。現在は二日市~太宰府の観光電車「旅人」で残るのみの、1989年デビューの特急電車・8000形の引退が9月16日に決まりました。
たぶん最後になるであろう、短い8000形の旅を楽しみます。


ラッピングだけでも、車両の印象はずいぶん変わるもの。幼い頃から乗って来た8000形とは、別物の電車という感じがします。
昼間に二日市~太宰府の普通電車として往復する姿も、全盛期の特急運用とはまったく異なるものです。




しかし赤いクロスシートが並ぶ車内は大きく手が加えられておらず、全盛期の面影を探せます。久留米~福岡間で座れる機会は少なかったけど、座れればゆっくりくつろげて、天国の電車でした。

平成元年製。もう29歳になるんですね。
しかし同い年の京阪8000系がリニューアルされ、今年は特別車両のプレミアムカーまで新設されたのを見ると、こっちももっと活躍できたはずの車両だったとも思います。

最新鋭の設備だったはずのLEDインフォメーションも、フルカラーモニタ全盛の今では、古めかしくも映ります。

観光PRコーナーになっている一角には、公衆電話が付いていたんだよなあ。JRでも新幹線や最新鋭の特急にしか付いていない設備で、格の違う電車だと感じられました。
通勤電車でもローカル線でも、めいめいが電話を手にしている時代になってからも、ずいぶん時間が流れました。



そして鉄道少年としては、最前部の展望席が何よりの魅力でした。側窓も大きく、当時は日本最大と言われたものです。西鉄福岡で行列してもたいてい座れず、大牟田から乗る時こそチャンスでした。
普通運賃だけで乗れる特等席は、貧乏な小中学生時代、手の届く範囲でできる特別な経験でした。

6両・2ドアの表示が見られるのも、あとわずか。ラストランまで、無事故で走ってほしいものです。


太宰府は観光客でいっぱい。博多方面のもう一つの「旅人」にも、大行列ができていました。