 | 失敗の本質―日本軍の組織論的研究 (中公文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 中央公論社 |
専門家が「事故の起こる確率は、ヤンキースタジアムに隕石が落ちる確率のようなもので、ほとんどゼロに近い。絶対安全だ」と言い募ってきて、結局、原発事故は起こりましたが、それでも政府-電力会社-多数の企業人-大多数の専門家-かなりの数の市民が、止めようとしないどころか再稼動に踏み切ってしまいました。
それはなぜだろう、それはリーダーの多くが日本のこれからあるべき姿について合理的で中長期的な展望――グランド・デザイン、理念とビジョン――を持っていない・持てないため、短期・一時の失敗があっても隠したり誤魔化したりせず明らかにしてその失敗から学んで方向転換をするという姿勢が取れないという体質を持っているためだ、と考えている中で、名著という定評があるので買っておいたままだった『失敗の本質――日本軍の組織論的研究』(1989年、ダイヤモンド社、1991年、中公文庫版)を取り出して読んでみて、なるほどやはりそうか、とうなづきました。
本書では、ノモンハン、ミッドウェー、ガダルカナル、インパール、レイテ、沖縄、各戦の敗北・失敗という六つのケースを取り上げていますが、詳細は本文を見ていただくことにして、いくつかポイントだと思った文章を紹介して共有したいと思います。
「そもそも軍隊とは、近代的組織、すなわち合理的・階層的官僚制組織の最も代表的なものである。戦前の日本においても、その軍事組織は、合理性と効率性を追求した官僚制組織の典型とみられた。しかし、この典型的官僚制組織であるはずの日本軍は、大東亜戦争というその組織的使命を果たすべき状況において、しばしば合理性と効率性とに相反することを示した。つまり、日本軍には本来の合理的組織と馴染まない特性があり、それが組織的欠陥となって、大東亜戦争での失敗を導いたと見ることができる。日本軍が戦前日本において最も積極的に官僚制組織の原理(合理性と効率性)を導入した組織であり、しかも合理的組織とは矛盾する特性、組織的欠陥を発現させたとすれば、同じような特性や欠陥は他の日本の組織一般にも、程度の差こそあれ、共有されていたと考えられよう。……日本軍の組織的特性は、その欠陥も含めて、戦後の日本の組織一般のなかにおおむね無批判のまま継承された、ということができるかもしれない。
なるほど日本軍の組織原理や特性は、すべてがいかなる場合にも誤りではなかったであろう。日本軍の組織的欠陥の多くは、大東亜戦争突入まであまり致命的な失敗を導かなかった……平時において、不確実性が相対的に低く安定した状況のもとでは、日本軍の組織がほぼ有効に機能していた、とみなされよい。しかし、問題は危機においてどうだったか、ということである。危機、すなわち不確実性が高く不安定かつ流動的な状況--それは軍隊が本来の任務を果たすべき状況だった--で日本軍は、大東亜戦争のいくつかの作戦失敗にみられるように、有効に機能しえずさまざまな組織的欠陥を露呈した。
戦後、日本の組織一般の置かれた状況は、それほど重大な危機を伴うものではなかった。したがって、従来の組織原理に基づいて状況を乗り切ることは比較的容易であり、効果的でもあった。しかし、将来、危機的状況に迫られた場合、日本軍に集中的に表現された組織原理によって生き残ることができるかどうかは、大いに疑問となるところだろう。」(23-25頁)
「いかなる軍事上の作戦においても、そこには明確な戦略ないし作戦目的が存在しなければならない。目的のあいまいな作戦は、必ず失敗する。それは軍隊という大規模組織を明確な方向性を欠いたまま指揮し、行動させることになるからである。本来、明確な統一的目的なくして作戦はないはずである。ところが、日本軍では、こうした。ありうべからざることがしばしば起こった。」(268頁)
「作戦目的の多義性、不明確性を生む最大の要因は、個々の作戦を有機的に結合し、戦争全体をできるだけ有利なうちに終結させるグランド・デザインが欠如していたことにあることはいうまでもないだろう。その結果、日本軍の戦略的目的は相対的に見てあいまいになった。この点で、日本軍の失敗の過程は、主観と独善から希望的観測に依存する戦略目的が戦争の現実と合理的論理によって漸次破壊されてきたプロセスだったということができる。(274頁)
「日本軍の戦略思考は短期的性格が強かった。日米戦自体、緒戦において勝利し、南方の資源地帯を確保して長期戦に持ち込めば、米国は戦意を喪失し、その結果として講和が獲得できるというような路線を漠然と考えていたのである。連合艦隊の訓練でもその最終目標は、太平洋を渡洋してくる敵の艦隊に対して、決戦を挑み一挙に勝敗を決するというのが唯一のシナリオだった。しかし、決戦に勝利したとしてそれで戦争が終結するのか、また万一にも負けた場合にはどうするのかは真面目に検討されたわけではなかった。/日本は日米開戦後の確たる長期的展望がないままに、戦争に突入したのである。」(277頁)
「短期決戦志向の戦略は……一面で攻撃重視、決戦重視の考え方とむすびついているが、他方で防禦、情報、諜報に対する関心の低さ、兵力補充、補給・兵站の軽視となって表われるのである。」(280頁)
「日本軍の戦略策定は一定の原理や論理に基づくというよりは、多分に情緒や空気が支配する傾向がなきにしもあらずだった。これはおそらく科学的思考が、組織の思考のクセとして共有されるまでには至っていなかったことと関係があるだろう。たとえ科学的思考らしきものがあっても、それは「科学的」という名の『神話的思考』から脱しえていない(山本七平『一九九〇年の日本』)のである。」(283頁)
「日本軍は、初めにグランド・デザインや原理があったというよりは、現実から出発し状況ごとにときには場当たり的に対応し、それらの結果を積み上げていく思考方法が得意だった。このような思考方法は、客観的事実の尊重とその行為の結果のフィードバックと一般化が頻繁に行なわれるかぎりにおいて、とりわけ不確実な状況下において、きわめて有効なはずだった。しかしながら、すでに指摘したような参謀本部作戦部における情報軽視や兵站軽視の傾向を見るにつけても、日本軍の平均的スタッフは科学的方法とは無縁の、独特の主観的なインクリメンタリズム(積み上げ方式)に基づく戦略策定をやってきたといわざるをえない。」(285頁)
「他方、日本軍のエリートには、概念の創造とその操作化ができたものはほとんどいなかった。個々の戦闘における『戦機まさに熟せり』、『決死任務を遂行し、聖旨に添うべし』、」『天佑神助』、『神明の加護』、『能否を超越し国運を賭して断行すべし』などの抽象的かつ空文虚字の作文には、それらの言葉を具体的方法にまで詰めるという方法論がまったく見られない。」(287-288頁)
「日本軍の戦略策定が状況変化に適応できなかったのは、組織の中に論理的な議論ができる制度と風土がなかったことに大きな原因がある。日本軍の最大の特徴は「言葉を奪ったことである」(山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』)という指摘があるように、戦略策定を誤った場合でも、その修正行動は作戦中止・撤退が決定的局面を迎えるまではできなかった。ノモンハン、ガダルカナル、インパールの作戦はその典型的な例だった。」(289頁)
「以上あげたような日本軍の組織構造上の特性は、『集団主義』と呼ぶことができるであろう。ここでいう『集団主義』とは、個人の存在を認めず、集団への奉仕と没入とを最高の価値基準とするという意味ではない。個人と組織とを二者択一のものとして選ぶ視点ではなく、組織のメンバーとの共生を志向するために、人間と人間との間の関係(対人関係)それ自体が最も価値あるものとされるという『日本的集団主義』に立脚していると考えられるのである。そこで重視されるのは、組織目標と目標達成手段の合理的、体系的な形成・選択よりも、組織メンバー間の『間柄』に対する配慮である。ノモンハンにおける中央の統帥部と関東軍首脳との関係、ガダルカナル島撤退決定遅らせる結果になった陸軍と海軍の関係、インパールにおける河辺ビルマ方面軍司令官と牟田口第一五軍司令官との関係、これらはいずれも『間柄』を中心として組織の意思決定が行なわれていく過程を示している。日本軍の集団主義的原理は、このようにときとして、作戦展開・終結の意思決定を決定的に遅らせることによって重大な失敗をもたらすことがあった。」(315頁)
「およそ日本軍には、失敗の蓄積・伝搬を組織的に行なうリーダーシップもシステムも欠如していたというべきである。ノモンハンでソ連軍に敗北を喫したときは、近代陸戦の性格について学習すべきチャンスだった。ここでは戦車や重砲が決定的な威力を発揮したが、陸軍は装備の近代化を進める代わりに、兵力量の増加に重点を置く方向で対処した。装備の不足を補うのに兵員を増加させ、その精神力の優位性を強調したのである。こうした精神主義は二つの点で日本軍の組織的な学習を妨げる結果になった。一つは、敵戦力の過小評価である。とくに相手の装備が優勢であることを認めても、精神力において相手は劣勢であるとの評価が下されるのがつねであった。敵にも同じような精神力があることを忘れていたといってもよい。精神主義のも一つの問題点は、自己の戦力を過大評価することである。『百発百中の砲一門、よく百発一中の砲百門を制す』(日本海開戦直後の東郷司令長官の訓示)といったたぐいの精神論は海軍でも例外ではなかった。……
ガダルカナル島での正面からの一斉突撃という日露戦争以来の戦闘は、功を奏さなかったにもかかわらず、何度も繰り返し行なわれた。そればかりか、その後の戦場でも、この教条的戦法は墨守された。失敗した戦法、戦術、戦略を分析し、その改善策を探求し、それを組織の他の部門へ伝播していくということは驚くほど実行されなかった。これは物事を科学的、客観的に見るという基本姿勢が決定的に欠けていたことを意味する。
……大東亜戦争中一貫して日本軍は学習を怠った組織であった。」(325-327頁)
「戦略・戦術が意図したものと、実際の結果との間にパフォーマンス・ギャップがなければ、その結果は既存の知識・技能や行動様式としての組織文化をますます強化していく。しかしながらパフォーマンス・ギャップがある場合には、それは戦略とその実行が環境変化への対応を誤ったかあるいは遅れたかを意味するので、新しい知識や行動様式が探索され、既存の知識や行動様式の変更ないし革新がもたらされるのである。既存の知識や行動様式を捨てることを、学習(learning)に対して、学習棄却(unlearning)という。このようなプロセスが組織学習なのである。軍事組織は、このようなサイクルを繰り返しながら、環境に適応していく。……
このように考えてくると、組織の環境適応は、仮に組織の戦略・資源・組織の一部あるいは全部が環境適応であっても、それらを環境適応的に変革できる力があるかどうかがポイントであるということになる。つまり、一つの組織が、環境に継続的に適応していくためには、組織は環境の変化に合わせて自らの戦略や組織を主体的に変革することができなければならない。こうした能力を持つ組織を、『自己革新組織』という。日本軍という一つの巨大組織が失敗したのは、このような自己革新に失敗したからなのである。」(347-348頁)
きわめて困ったことに、全文の「日本軍」のところを「日本政府」、「日本の省庁」、「日本の(多くの)企業」などなどに置き換えても、そのまま当てはまりそうです。
特に現状の日本で致命的に危険なのは言うまでもなく、原発に関して、「集団主義的原理は、このようにときとして、作戦展開・終結の意思決定を決定的に遅らせることによって重大な失敗をもたらす」、「戦略策定を誤った場合でも、その修正行動は作戦中止・撤退が決定的局面を迎えるまではできな」いという事態になりつつあることです。
幸いにして戦前と異なり、戦後の日本は代議制民主主義の国家なので、リーダーがダメな場合、国民の多数の意思があればリーダーを取り替えることができるのですから、国民が意思表示をすべきなのですが、肝心の善意の国民の多くも「……は功を奏さなかったにもかかわらず、何度も繰り返し行なわれた。そればかりか、その後の戦場でも、この教条的戦法は墨守された。失敗した戦法、戦術、戦略を分析し、その改善策を探求し、それを……伝播していくということは驚くほど実行されなかった」という状態にあるのではないかと思われます。
心(心情と理性の両方)ある市民・国民のみなさん、原水爆禁止運動以来ずっと敗北・失敗しつづけてきた「戦法、戦術、戦略を分析し、その改善策を探求し」ていこうではありませんか。










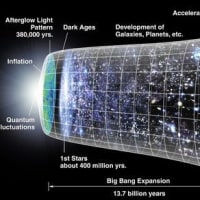



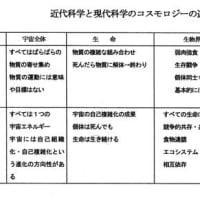
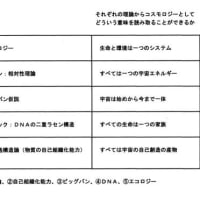







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます