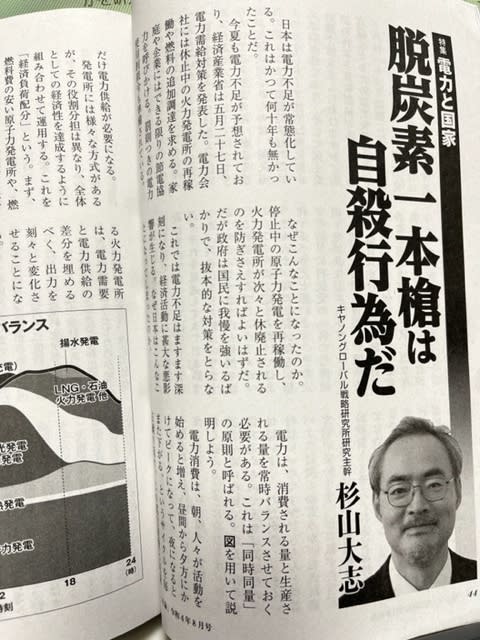以下は前章の続きである。
中国依存高まる洋上風力
太陽光発電だけではなく、風力発電もいまや中国が世界市場を席捲している。かつては安定した強い風の吹く北海・バルト海の地理的有利性を活用して、欧州諸国が世界の風力発電の先頭に立ってきた。
だがこの状況はすっかり変わった。
昨年世界で導入された洋上風力設備容量2,100万キロワットのうち中国が8割、1,800キロワットを占めた。
設備製造量のシェアでも2021年には中国が世界の4分の3を占めた。
陸上風力発電設備についても、その半分以上は中国メーカーにより供給されている。
中国メーカーは、欧州市場にも進出を始めている。
日本はいまから洋上風力を導入し、2030年までに1,000万キロワット、2040年までに4,500万キロワットという計画になっているが、中国製品を大量に輸入することになるのではないか。
仮に日本のメーカーが建てるとしても、部品は中国から供給されるのではないか。
発電機には磁石が必要だが、この磁石に用いるレアアースであるネオジムの採掘・精錬は中国が世界の9割を占めている。
これを原料として生産するネオジム磁石も中国が世界の9割を占めており、日本は1割しかない。
脱ロシア・脱炭素を理由に風力発電を推進すると、欧州も日本も、こんどは新たな中国依存を作り出す。
そもそも日本は風況が悪く、風力発電に向かない。
日本で洋上風力発電の建設が多く予定されているのは北海道や東北地方の日本海側であるが、風力発電設備の稼働率は安定した偏西風が吹く欧州に比べて低くなり、それだけでコストは5割増しになる。
洋上風力建設にあたっては国防上の問題も指摘されている。
海洋の地形・気象データが中国企業に漏洩すること、また、防衛用のレーダーの機能に支障が出て、ミサイルが発見できなくなるなどだ。
この状況で洋上風力を推進するとなると、高いコストは国民負担となって跳ね返り、中国企業ばかりが儲かり、防衛上の問題が生じるのみならず、中国依存がますます高まる。
これでは、太陽光発電の失敗の二の舞ではないか。
中国依存高まる洋上風力
太陽光発電だけではなく、風力発電もいまや中国が世界市場を席捲している。かつては安定した強い風の吹く北海・バルト海の地理的有利性を活用して、欧州諸国が世界の風力発電の先頭に立ってきた。
だがこの状況はすっかり変わった。
昨年世界で導入された洋上風力設備容量2,100万キロワットのうち中国が8割、1,800キロワットを占めた。
設備製造量のシェアでも2021年には中国が世界の4分の3を占めた。
陸上風力発電設備についても、その半分以上は中国メーカーにより供給されている。
中国メーカーは、欧州市場にも進出を始めている。
日本はいまから洋上風力を導入し、2030年までに1,000万キロワット、2040年までに4,500万キロワットという計画になっているが、中国製品を大量に輸入することになるのではないか。
仮に日本のメーカーが建てるとしても、部品は中国から供給されるのではないか。
発電機には磁石が必要だが、この磁石に用いるレアアースであるネオジムの採掘・精錬は中国が世界の9割を占めている。
これを原料として生産するネオジム磁石も中国が世界の9割を占めており、日本は1割しかない。
脱ロシア・脱炭素を理由に風力発電を推進すると、欧州も日本も、こんどは新たな中国依存を作り出す。
そもそも日本は風況が悪く、風力発電に向かない。
日本で洋上風力発電の建設が多く予定されているのは北海道や東北地方の日本海側であるが、風力発電設備の稼働率は安定した偏西風が吹く欧州に比べて低くなり、それだけでコストは5割増しになる。
洋上風力建設にあたっては国防上の問題も指摘されている。
海洋の地形・気象データが中国企業に漏洩すること、また、防衛用のレーダーの機能に支障が出て、ミサイルが発見できなくなるなどだ。
この状況で洋上風力を推進するとなると、高いコストは国民負担となって跳ね返り、中国企業ばかりが儲かり、防衛上の問題が生じるのみならず、中国依存がますます高まる。
これでは、太陽光発電の失敗の二の舞ではないか。
この稿続く。