何はともあれ”とり完”し(た事にし)ました
数年前にSMERのキットを作った時から
少しは技量が上がったのか、はたまた下がったのか!?
何となくどころでない不安に駆られている今日この頃ですが
まぁ...見てやってくださいませ<(_ _)>









どうもスライドキャノピーの頂部が盛り上がり過ぎのように思えますが...
胴体下のIFF MkⅢと思われるアンテナは
流石にプラパーツでは厳しいと思い、0.3mmの洋白線に替えています
スライドキャノピー後部のホイップアンテナも
恐らくそうではないかと思われるパーツが、ランナーに有ったのですが
組説には見当たらず、こちらも同上で0.25mmの真鍮線に替えました
ここまで工作してから、ウオークラインを塗装し忘れているのに気付きまして
急遽マスキングしてエアブラシ塗装しています(汗)

よく見て頂くとわかると思いますが、マスキングの位置を間違えて塗装してしまい
再度マスキング、でまた塗装というアホな事をしてしまいました(恥)
塗り直し後です(^^;

前にも書きましたが、空冷エンジンのセントーラスに替えたMkⅡの他に
スーパーチャージャーの空気取り入れ口や、オイルクーラーを翼前縁に移したMkⅥへの
バリエーション展開を考えたパーツ割になっています
これ自体はメーカーの考えですし、レアアイテムのMkⅡやⅥを出してもらえるのは蛇の目ファンとしてはありがたいことなのですが
如何せん、メーカーの技術力が追い付いていないのが残念な所なんですよねぇ~
って、もうMkⅡ予約しちゃってるんですけどね(笑)
このW2◎X SN:EJ705は
オスプレイ社『ホーカー・タイフーンとテンペストのエース』のP70に写真と簡単な記事が載っています
それによると、特定の誰かの専用機という訳ではなく
No80Sqnのオーストラリア人パイロット4人が交代で使用していたそうです
それでカンガルーが、オーストラリア国旗を持っている図柄のマークを描いていたとの事

アップにすると本当にドットが粗いのがよく分かります(-_-;)
で、この機体がその後どうなったかと云うと
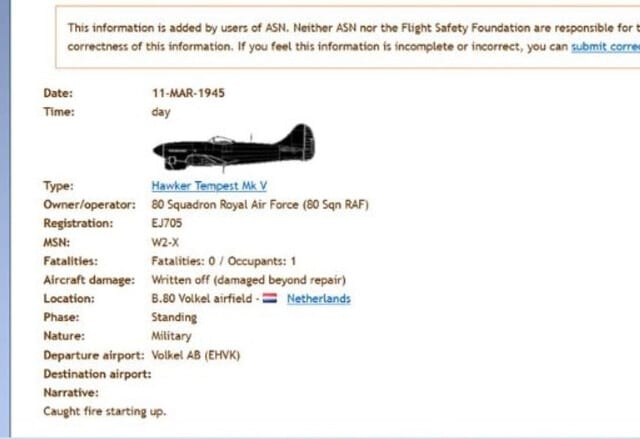
幸いパイロットの F/O F.A. Langさんは助かったみたいですが、修理不能でスクラップになったみたいですね
こちらからです
これでテンペストはSMERとKPモデルの2メーカーのものを作った事になります
今のところ作りやすさではSMERに軍配かなぁ
こうなったらAIRFIXのキットも作って、ぜひ3社比較をやってみたいものです
【終了】
数年前にSMERのキットを作った時から
少しは技量が上がったのか、はたまた下がったのか!?
何となくどころでない不安に駆られている今日この頃ですが
まぁ...見てやってくださいませ<(_ _)>









どうもスライドキャノピーの頂部が盛り上がり過ぎのように思えますが...
胴体下のIFF MkⅢと思われるアンテナは
流石にプラパーツでは厳しいと思い、0.3mmの洋白線に替えています
スライドキャノピー後部のホイップアンテナも
恐らくそうではないかと思われるパーツが、ランナーに有ったのですが
組説には見当たらず、こちらも同上で0.25mmの真鍮線に替えました
ここまで工作してから、ウオークラインを塗装し忘れているのに気付きまして
急遽マスキングしてエアブラシ塗装しています(汗)

よく見て頂くとわかると思いますが、マスキングの位置を間違えて塗装してしまい
再度マスキング、でまた塗装というアホな事をしてしまいました(恥)
塗り直し後です(^^;

前にも書きましたが、空冷エンジンのセントーラスに替えたMkⅡの他に
スーパーチャージャーの空気取り入れ口や、オイルクーラーを翼前縁に移したMkⅥへの
バリエーション展開を考えたパーツ割になっています
これ自体はメーカーの考えですし、レアアイテムのMkⅡやⅥを出してもらえるのは蛇の目ファンとしてはありがたいことなのですが
如何せん、メーカーの技術力が追い付いていないのが残念な所なんですよねぇ~
って、もうMkⅡ予約しちゃってるんですけどね(笑)
このW2◎X SN:EJ705は
オスプレイ社『ホーカー・タイフーンとテンペストのエース』のP70に写真と簡単な記事が載っています
それによると、特定の誰かの専用機という訳ではなく
No80Sqnのオーストラリア人パイロット4人が交代で使用していたそうです
それでカンガルーが、オーストラリア国旗を持っている図柄のマークを描いていたとの事

アップにすると本当にドットが粗いのがよく分かります(-_-;)
で、この機体がその後どうなったかと云うと
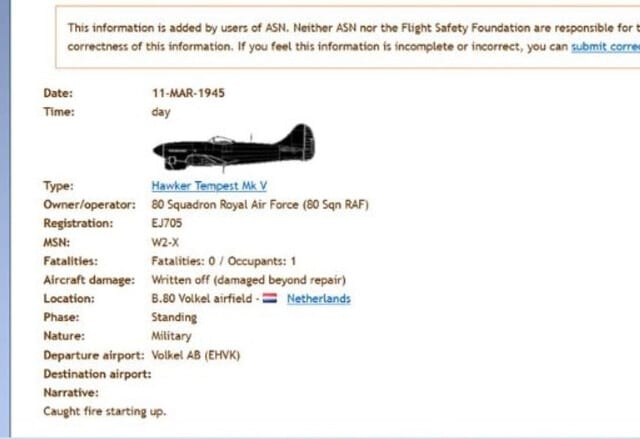
幸いパイロットの F/O F.A. Langさんは助かったみたいですが、修理不能でスクラップになったみたいですね
こちらからです
これでテンペストはSMERとKPモデルの2メーカーのものを作った事になります
今のところ作りやすさではSMERに軍配かなぁ
こうなったらAIRFIXのキットも作って、ぜひ3社比較をやってみたいものです
【終了】




























