
フジバカマが咲きだした。
「フジバカマ」と称する植物が、観賞用として園芸店で入手でき庭にも好んで植えられる。しかし、ほとんどの場合は本種でなく、同属他種または本種との雑種である。
等とある。


いつもの田んぼに行ってみると面白いものが目に入った。
なるほど風か吹くと音が鳴る仕掛けらしい。
8世紀以前からあったという。
鳴子(なるこ)は音を出す道具のひとつ。もともとは引板(ひきいた、ひいた、ひた)と呼んだ。「鳥威し」(とりおどし)の一種。
木の板に数本の竹筒や木片を糸で吊るしたものを、田畑の中に設置する。木の板には長い縄をつけて、家や樹木の陰などまで引いてくる。
この縄を田畑と離れたところにいる人間が引くと揺れ、竹筒や木片が木の板に当たって音が鳴る。この音で鳥獣を脅かし追い払う。
「宿ちかき 山田の引板(ひた)に 手もかけで 吹く秋風に まかせてぞ見る」(後拾遺和歌集)、
「いほりさす そともの小田に 風すぎて 引かぬ鳴子(なるこ)の おとづれぞする(嘉元百首)、
「人ぞなき 月ばかりすむ 小山田の なるこは風の 吹くにまかせて」(文保百首)、
「夜もすがら たえず鳴子の 音(おと)すなり 山田のいほを 風や守(も)るらむ」(新千載和歌集)、
これを踊りに取り入れた高知県高知市のよさこい祭りが知られている。
「よさこい鳴子」
等とある。
161006
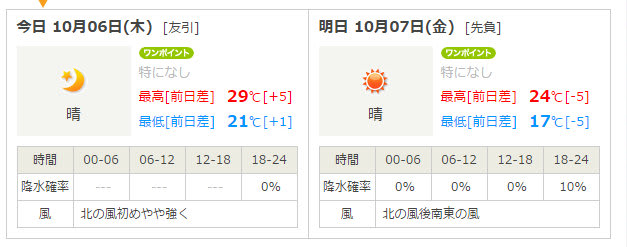
昨日 閲覧数1,170 訪問者数241




















