みなさんこんばんは。
11月4日に谷田部アリーナで開催された、ヨコモGT全日本選手権2018に参戦してきました。
ワタシは今回、GTストッククラスとGTオープンクラスのWエントリーを選択しました。
先ずは、GTストッククラスからレースの様子を記したいと思います。

朝7時開門のレース当日、朝食はホテルの無料サービスを利用して簡単に済ませて、7時ちょっと過ぎに谷田部アリーナ会場入りしました。
とはいっても、前日練習者はピットをそのまま置いていけるサービス(盗難等のリスクは自己責任ですけどね)を活用したため、ピットに到着するやすぐにバッテリー計測を始めます。
充電するバッテリーはもちろん、レース用バッテリーです。
朝一に充電しても、レース開始は9時半ですし、しかも最初はポンダーチェックという名の4分間練習走行なので、なぜレース用バッテリーを充電するのか?
理由は二つ、一つ目は充放電してバッテリーを活性化すること、もう一つは充電したレース用バッテリーで事前に車検場で車検に使うタイヤ回転計と電圧計で計測するためです。
東広島ラジコン研究所は今回、事前に赤外線式の回転計を自前で準備していて、前日練習でもタイヤ回転数を確認しながら練習していました。
しかし、実際の車検場のタイヤ回転計との誤差等を補正する必要があるため、朝一のレース用バッテリー充電が必要なワケなんですねえ。
また、レース前には上の画像にある通り、リアのアクスルベアリングにAXON製のX9 BALL BEARING (3/8x1/4フランジ付き)を奢ってみました。
ちょっとお高めではありますが、非常にベアリング自体の精度が高く、また特殊オイルに漬けた状態で販売されているため、何の処理も施す必要なくただ組み替えるだけで低フリクションが得られるお勧めの商品ですね。

上記の画像はヨコモさんのEVENT REPORTから拝借しました。
ところが、車検場に行って驚いたことに、タイヤ回転計がこれまで使用されていた赤外線式から直接ホイールナットに連結して回転を測定する直結式に変更されていたことです。
理由は、赤外線式だと周囲の光の加減等で測定に時間がかかるため、車検時間が想定以上に伸びてしまうという懸案を解決するためとのことでした。
この直結式タイヤ回転計をヨコモの方からお借りして、自分で計測したところ、回転計の押し付け方に応じて測定される回転数が変わることに気づきました。
となると、今すぐにできる対策はひとつ。ヨコモの車検ご担当者にお願いして、タイヤ回転数を測って貰うことにしました。
実際に測って戴いたところ、赤外線式に対してストッククラスの30.5Tで30~50rpm、オープンクラスの21.5Tで70~100rpmくらい低めに測定されるようです。
そこで、自分のピットと車検場を何度も往復して、ピットにある自前の赤外線式タイヤ回転計である程度狙ってアンプの設定を変更しました。
この際、ポイントはモーターの進角はいじらないことです。モーターの進角をいじると、パワーソースのセッティングがまるで狂ってしまい、事前の走りができなくなるリスク大のためです。
結果として、ワタシが使っているSP3のアドバンスを5から9に上げることでかなり良い回転レベルに合わせこむことができました。
回転数の微修正はバッテリーの充電終了電圧を変更することで対処しました。
ワタシが愛用しているkimihiko-yano取り扱いのブラックホークV2は充電終了電圧をかなり広範囲に変更可能なため、通常は1セル当たり4.20Vに設定するところ、ワタシはちょっと低めにした次第です。
具体的には、1セル当たり0.01V電圧を下げることで、タイヤ回転数は10rpmくらい下がります。そこでワタシは今回のレースでは1セル当たり4.17Vになるよう充電器を設定した次第です。
これをストックとオープンの2台で実施したのでかなり時間がかかってしまい、9時過ぎから始まるドライバーズミーティング(通称ドラミ)に危うく遅れるほどでした。

上記の画像はヨコモさんのEVENT REPORTから拝借しました。
延べ108名もの参加者を集客したヨコモGT全日本選手権、なんだか昨年よりも盛況じゃないですかねえ。GTクラスと2WDツーリングカーとの併催ということもあり、集客に貢献した模様ですねえ。
さて、みんなで集合写真撮影、コンデレマシン3台選定の後は、横堀社長からのご挨拶、正美さんからのレース概要説明を済ませてすぐ、予選組み合わせそのままの流れでポンダーチェックという練習走行が始まります。
ワタシは今回、手持ちバッテリーから4本を選定してレース用としました。更に4本のうちから上位2本をストッククラス用、残りをオープンクラス用としました。
理由は簡単、ストッククラスのほうが目標のAメインに届く可能性が高いと考えたからです。
バッテリー選定にはハイペリオン製のEOS i720を使って、放電電流5Aで放電容量と内部抵抗値を測定することで判定しました。
この方法は簡単かつ、実走行とそれなりに相関性があるようなので、日頃より愛用しております。ただ、この充電器はかなり古いためか、充電終了電圧設定の幅が狭く、レース用充電にはもう使ってません。

ちょっと画像が横になっていて申し訳ないですが、ワタシが使ったモーターはノートの真ん中に記載のものになります。KV 1467のデータですね。進角もご覧の通り、AVEで39°です。
ノート下のモーターデータは広島から参加のワタシのお友達のデータとなります。ワタシのより回ってますよね。
ワタシは基本、モーターの進角はフルには付けずアンプ(SP3)のアドバンスで調整しています。だいたい、目盛り読みで5~6コマ目くらいの進角設定が良い場合が多いように思います。
このモーター仕様でストックの練習走行にはオープンクラス用レースバッテリーを使用することにしました。
というのも、ストックレース用バッテリーは2本しかないので、予選2回をそれぞれ1回ずつ使い、決勝は良いほうのバッテリーをストック決勝に2回目使用で使う予定なんです。
となると、ストックレース用バッテリーをストッククラスの練習走行に使うわけにはいかないんですよねえ。まあ、オープンクラスのほうは多少結果に目を瞑る感じです。
果たして練習走行前に、車検でタイヤ回転数を測って貰います。練習走行では車検は任意なのですが、ワタシはレースシミュレーションとしてちゃんと測定してもらいました。
するとタイヤ回転数は基準の3200rpmに対して3170rpmとまずまずです。これで練習走行に臨みます。
タイヤは前がMSスリック、後ろがSスリックに対し、グリップ剤はファニーグリップを後ろ1分、前30秒で拭き取り実施しました。
そんなに厳密ではないのですが、まずリアにグリップ剤を塗布し、次にフロントにグリップ剤を塗布、すぐにフロントのグリップ剤を拭き取ってから、すぐリアを拭き取るという流れです。
塗布幅は前後ともに全塗りですが、フロントはわずかに外側を1~2㎜くらい気持ち残して塗る感じです。やはり、超ハイグリップな谷田部アリーナのCRC新型ブラックカーペットでハイサイドは怖いですからね。

尚、フロントタイヤにはエッジ部にのみ瞬間接着剤を塗布しました。この瞬間接着剤は最近スクエアさんから発売された、ハイサイド抑制GLUEです。
これは超お勧めの逸品です。GT500に限らず、ツーリングカー、1/12ストック&モディいずれもハイグリップカーペットコース走行するのにもはや必携のアイテムといえます。
ワタシは前日の練習時にまず、これを塗布せずにハイサイドするようにセットアップしたのち、このハイサイド抑制GLUEを少しずつ塗布してハイサイドしなくなるまでしっかり塗り上げる方策をとってます。
これで、ワタシのハイサイド対策は完璧となりました。しかもハイサイド抑制効果はかなり長期間にわたり、GT500ストッククラスなら20~30パックくらいは対策効果が確認できています。










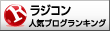
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます