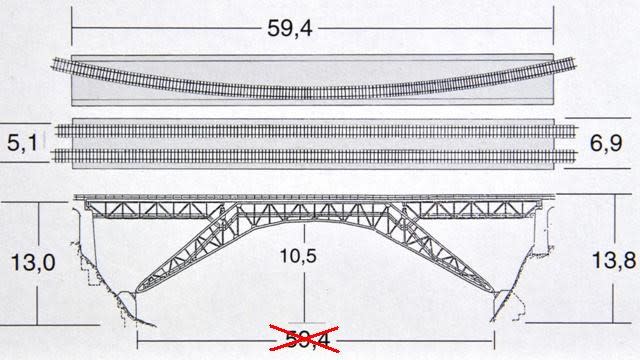群馬県 南牧村の
鹿岳 ( かなだけ ) の登山記録です。 撮影日 2016.5.22。 一年遅れの掲載になります。

鹿岳の駐車スペースは、上段・下段で10台以上駐車できます。

村道沿いの河原。 水面に新緑が映えます。

駐車場から50mくらい先に登山口があります。 山頂までの標高差は500mほど。 休憩を含めて 一時間半の行程です。
西上州 の どこの登山道も同じですが、しばらくは沢沿いの路を進んでいきます。

道の途中に洞窟のようなものを発見。 今まで何度も歩いていたのに、今回始めて気付きました。
近づいてみると、ただの凹凸 ( おうとつ ) でした。 光と影のでき方で、天然のトリックアートになっていました。

登山路の大半は、スギやヒノキの植林地になっています。 登るにつれて傾斜がキツくなります。
足元が悪いので、雨天や積雪期は 樹の幹や枝につかまって歩きます。

水場を過ぎ、ここから先は水分の補給は出来なくなります。 間伐材が放置された様になっていました。

薄暗い林の先に、藤の花がきれいに咲いていました。 しばらく訪れていない内に植生が変わったのか、鹿岳のあちこちに藤が咲いています。
木々の間から村道が垣間見えました。 望遠レンズで写しているので遠近感が圧縮されて、何だかたいして登ってないみたいな写真になっちゃってます。

短いクサリ場が見えるとホッとします。 ようやく、杉林の急登から解放されました。
このクサリを登った所が、
南峰 と
本峰 に挟まれた 鞍部 ( あんぶ ) になります。

今回登ってきたのが
高原 ( たかはら ) の集落です。 丸太のハシゴを登ると
南峰 (
一ノ岳 )。 左に行くと、鞍部のヤセ尾根を抜けて
本峰 (
二ノ岳 ) に続きます。

南峰への路は、山ツツジの咲く ガレた岩場を進みます。 明るい路です。

山頂は 「
摩利支天 」 が祀られています。
さらに通り過ぎ、一段下がった所にも石の祠があります。 南に開けた断崖絶壁に位置し、眺めが良いです。

南峰から本峰の眺め。
鹿岳は 二こぶラクダの 双耳峰 です。 その特徴的な山容は、どこから見てもすぐに鹿岳と分かってしまう、
西上州のランドマーク です。

先に登っていた方が、山頂直下の岩場を歩いていました。 この辺りからの眺めも良いです。

白い岩肌と見分けの付きにくい場所もありますが、藤の花が多く咲いていました。 疲れが癒える思いです。

南東側を望みます。 緑色の山は
四ッ又山 です。 小沢岳や秩父の山々を見渡せます。
芽吹いたばかりの低木が、紅葉のように鮮やかです。

再び、鞍部の尾根に戻りました。 東へ、四ッ又山 ・ 大久保地区 への分岐があります。 「 これ、道なの? 」 と心配になります。 数年前に歩きました。 そこそこ楽しめます。
四ッ又山の駐車スペースは少ないので、鹿岳と周回するのが良いです。 標高差で400mくらい下って、350mくらい登ります。

北側を望みます。 ノコギリの歯のような
妙義山 が印象的です。

山ツツジの花の盛りは過ぎていました。 新緑に朱い花は良く似合います。
 鹿岳 本峰
鹿岳 本峰 より、北西側を望みます。 右奥には
浅間山 が見えます。

コントラストを強くして、浅間山方面を望遠レンズで眺めます。 少しモヤっているので目立ちませんが、写真の中央に 日本一の100万ボルトの超高圧線と鉄塔が写っています。
新潟県の
刈羽原発 から山梨県の変電施設までを結んでいます。 震災以来、送電はされていません。
一般的な高圧線鉄塔の建設費は、一基あたり100億円と言われています。 この超高圧線鉄塔を 国境の山岳部を縦貫していたら、その域ではありません。
西上州の風景を二分する存在であり、風景写真を撮る者にとっては 邪魔すぎます。
地上から100m以上高い位置に高圧線がありますが、その下で三脚を立てて写真を撮ろうとすると、三脚がずっと微振動を起こしていたのを覚えています。

山頂から 高原地区の集落を望みます。 標高差は500m以上あるはずですが、写真に撮ると それほどの高低差は感じられません。
ハシゴで二階の屋根に上るのは 足がすくんで無理ですが、急な岩場を歩くのは楽しいです。 目のピントが合わないからでしょうか?
 本峰
本峰 より
南峰 ( 写真 右 ) と
四ッ又山 を望みます。 つい20分前まで、あの山頂と、すぐ右下の垂直の岩場に立っていたわけです。

初めて鹿岳に登ったのは30年ほど前になります。
山歩き初心者の私は、下界の道路から見上げて 「
まさか あんな険しい岩山には 人は登れないだろう 」 と、一気に胸の鼓動が高鳴りました。 が、ガイドブックを信じて、覚悟を決めたのを覚えています。
その頃はまだ、本峰直下のハシゴなどの整備はされておらず、南峰だけ登って帰る方も多かったです。 北斜面なので雨に濡れると乾きにくく、岩と樹の根や枝にしがみついて登っていました。
それから十数回、季節を変え、天気を変えて訪れる事になりました。 私は、西上州と 鹿岳の魅力に ぐいぐい引き寄せられていったのでした。。。
関連記事
 フォトエッセイ - 第二話 -
フォトエッセイ - 第二話 - 2007.1.31
 フォトエッセイ ・ 秋色コレクション
フォトエッセイ ・ 秋色コレクション 2007.10.24