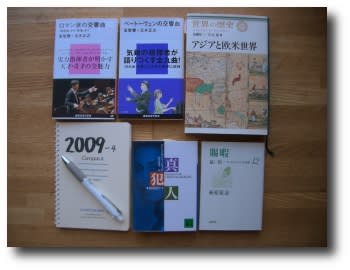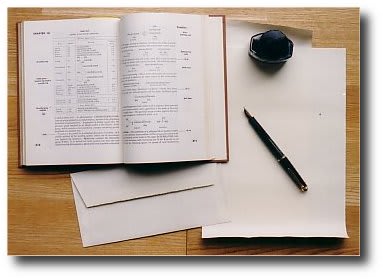吉村昭著『白い航跡』(講談社文庫)下巻は、英国留学を終えた高木兼寛が帰国するところから始まります。
第7章、明治13年11月、5年ぶりに帰国した兼寛は、家族が身を寄せている妻の実家に戻ります。義父に続いて、故郷の母と、東京では娘を亡くし、不幸が続いた年月でしたが、英国での留学生活は、学位とフェローシップ免状を授与され、優れた業績をあげた充実した日々でもありました。彼は、海軍省医務局に帰国報告を済ませ、日本での仕事に着手します。海軍病院付属の軍医学校とは別に、イギリス流の医学を教える民間の機関、成医会講習所を作り、不遇のウィリスの講演会を開催するなどに取り組みながら、英国ではなぜ脚気病患者がいなかったのだろうと考えるのでした。
そこで兼寛が採用した手法が興味深いものです。まず、実態としての発生状況を統計から調査し、明治11年には海軍兵員の約3分の1が脚気患者であること、発病と季節との関係や配属部署との関連もないこと、などを知ります。そして、注目したのは、軍艦の行動記録と発病状況でした。とくに、航海中は続々と発症する脚気患者が、外国の港に寄港中は発生が止むことに注目し、停泊時には、上陸した際の洋食が発病を抑えたのではないか。ひるがえって脚気病は、和食に原因があるのではないか。この時点では、まだ和洋食の比較のレベルであって、やはり因果関係が米に焦点化されてはおりません。脚気専門の漢方医・遠田澄庵の「脚気ハ其原(因)、米ニ在リ」という説は、やはり卓見です。
京城事変により、海軍は脚気病によりほとんど戦闘行動不能状態にあることが明らかとなり、対策が急がれますが、本質に目を向けず、周辺事象にのみ原因を求めようとするのは、今も昔も変わらないというべきでしょうか。
第8章、海軍の脚気病の蔓延は著しく、戦闘行動など不可能な状況にあることを憂え、海軍省医務局長に昇格した高木兼寛は諸方に自説を訴えますが、海軍兵食制度の根幹にかかわるために、例によって「予算が。」
財政当局は首を縦に振りません。しかし、明治天皇に奏上する機会を得て、ついに遠洋航海に出航する予定の軍艦「筑波」において、脚気病予防試験が実施されることになります。筑波の試験航海の間、極度の緊張のため、ほとんどノイローゼ状態になっていたときに届いた「筑波」からの一通の電報に、彼は救われます。
「ビョウシャ 一ニンモナシ アンシンアレ」
そしてそれは、海軍内から脚気病が一掃される端緒となったのでした。
また、この頃の兼寛は、看護婦教育所の設立に熱意を持って奔走しており、わが国初の看護教育のスタートと言えそうです。
第9章、米麦を混食するという改善により、海軍の脚気病患者は急減し、ついに死者はゼロになります。海軍全体が喜びにわき、兼寛は看護婦教習所の発足とともに満足感に浸りますが、東京大学医学部と陸軍軍医本部は、高木説は学理に基づかぬ妄説で、たまたま脚気病患者数の周期的変動で死者が減少したに過ぎないと攻撃します。ただし、同じ陸軍でも現場では違っていました。いくつかの部隊では、刑務所に脚気病の発生を見ないことをヒントに麦飯を支給し予防効果を上げていたのでしたが、陸軍中枢は麦飯推進者に対し報復人事を行います。この中心にあったのが、陸軍軍医本部次長の石黒忠悳(ただのり)であり、これに学問的な装いで支えていたのが、ドイツ留学中の森林太郎(鴎外)でした。高木兼寛が英文で発表した論文が外国で高い評価を受けていても、ドイツ医学至上主義に凝り固まる国内ではいっこうに評価されない。兼寛は孤立感を抱きます。
第10章、兼寛の最大の論敵、森林太郎がドイツから帰国します。そして、その文章の力を持って、弱点を徹底的に攻撃されます。たしかに、まだビタミンが発見される以前ですから、麦飯が良いと実証的に明らかにしたものの、その因果関係が論理的に明らかにはなっていません。森林太郎はそこを突いてくるわけです。昭和になって水俣病の水銀説を攻撃した御用学者と同じ論理です。兼寛は海軍を辞任しますが、時代は日清戦争に突入、結果は犠牲者の数により、明らかとなりました。
■海軍では、脚気病による死者がわずかに1名であったのに対し、
■陸軍では、戦死者977名に対し病死者20,159名、脚気による死亡者3,944名
という状況でした。現場から上がる麦飯採用の稟議を無視して米食至上主義を貫いた陸軍兵站軍医部長は、そのころ鴎外というペンネームで文名が上がっていた、森林太郎でした。
第11章、海軍を退いた兼寛が、東京慈恵病院でおだやかな生活を送る頃、日露戦争が始まり、戦病者数はさらに悲惨な状況を呈します。日露戦争で出動した陸軍では、
■戦死者数約47,000名に対し、傷病者数は352,700名、うち脚気病患者は211,600名に達し、脚気による死者は27,800名
に及んだといいます。このとき、石黒軍医部長はすでに引退しており、後任の軍医部長には森林太郎が昇任しておりました。世論は、海軍の脚気病撲滅成功と比較して陸軍の惨状を問題視し、その責任を問います。高木兼寛に対し、誤れる説により世を惑わす学者と攻撃した森林太郎の責任は、脚気病死した陸軍兵士の家族から見れば、まさに万死に値するものでありましょう。
第12章、残念ながら、高木兼寛の晩年は、みそぎに凝るなどいささか神がかりで、だんだんおかしくなってきます。このあたりは、残念というよりはむしろお気の毒。晩節を汚さず生涯を全うするのは、なかなか難しいようです。
陛下の忠良なる軍隊に粗悪なる麦飯を食わせるとは何事か、と主張する陸軍中枢の論理に対して、明治天皇自身が脚気に悩み、愛娘を脚気病で失っており、麦飯を採用していたという皮肉。文豪・森鴎外の現実の姿は、なんともひどいものです。ドイツに女性を置き去りにした道義的責任などよりも、大量の戦病死者を続出させた張本人として、現代ならば厳しく法的責任を問われるところでしょう。高木兼寛の業績は、鈴木梅太郎のオリザニンの発見、そして世界中で各種ビタミンの発見へと導きます。