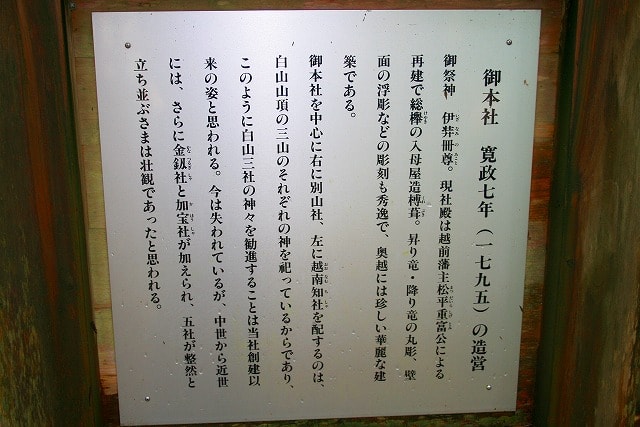オークションでは、売る経験もしましたが、
買うほうが安心。
ここのところ、絵画のジャンルに関係なく、
ハッッそして、ほしい~ぃです。
そんなに高価な原画は買えませんが、20色刷りくらいのリトグラフが、
私のねらい目です。

今回のものは「山口蓬春」画伯の「菊」。
この絵、明治神宮によく似たものが有るのを見たことがあります。

「山口蓬春」画伯は、日本画壇では、巨星と言われた人、文化勲章受賞者、
1971年77歳で死去。神奈川県三浦町葉山に記念館が公開されています。
皇居新宮殿の杉戸絵《楓》も制作した人。
買うほうが安心。
ここのところ、絵画のジャンルに関係なく、
ハッッそして、ほしい~ぃです。
そんなに高価な原画は買えませんが、20色刷りくらいのリトグラフが、
私のねらい目です。

今回のものは「山口蓬春」画伯の「菊」。
この絵、明治神宮によく似たものが有るのを見たことがあります。

「山口蓬春」画伯は、日本画壇では、巨星と言われた人、文化勲章受賞者、
1971年77歳で死去。神奈川県三浦町葉山に記念館が公開されています。
皇居新宮殿の杉戸絵《楓》も制作した人。