(棒渦巻銀河NGC 1097中心部)

※ 綺麗な画像です。まるで"万華鏡"を覗いているようです。
① ""棒渦巻銀河NGC 1097中心部""
天体写真・2017年11月 7日
② アルマ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡で観測した、棒渦巻銀河NGC 1097の中心部です。この画像では、アルマ望遠鏡が捉えたHCN(シアン化水素)分子の運動のようすを、赤から紫の色の変化で表現しています。
アルマ望遠鏡による観測からは、星とは異なり、ガスが銀河の中心とそれを取り巻くリング状に分布していること、そしてその速度分布までもがはっきりと描き出されています。豊富な情報を持つデータから何が読み解けるか、研究者の腕の見せ所です。
文:平松正顕(チリ観測所)
③ 見えないブラックホールの見える証拠
ほとんどの銀河中心に存在し、その重力で銀河の星々を引き付けているとされる超巨大ブラックホール。直接観測されていない天体だからこそ、その最も基本的な物理量である質量を測定することはたいへん重要です。
研究チームはアルマ望遠鏡を使って銀河の中心部分でのガスの回転運動を観測し、その力学から銀河中心にあるはずのブラックホールの質量を割り出しました。アルマ望遠鏡の高い性能によって、このように新しい科学的事実が次々と解き明かされていきます。これからもアルマ望遠鏡から目が離せません。
文:大西響子(愛媛大学宇宙進化研究センター)
※ 本当に理解するには、物理学、化学、そして数学が必要なようです。
④ ブラックホール(wikipedia)
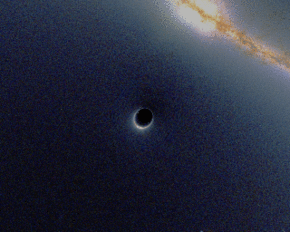
ブラックホール(black hole)とは、極めて高密度かつ大質量で、強い重力のために物質だけでなく光さえ脱出することができない天体である。
⑤ 名称
「black hole」という呼び名が定着するまでは、崩壊した星を意味する「collapsar(コラプサー)」などと呼ばれていた[1]。光すら脱け出せない縮退星に対して「black hole」という言葉が用いられた最も古い印刷物は、ジャーナリストのアン・ユーイング(英語版)が1964年1月18日の『サイエンス・ニュースレター(英語版)』で記した「'Black holes' in space」と題するアメリカ科学振興協会の会合を紹介する記事である[2][3][4]。一般には、アメリカの物理学者ジョン・ホイーラーが1967年に初めて用いたとされるが[5]、実際にはその年にニューヨークで行われた会議中で聴衆の一人が洩らした言葉をホイーラーが採用して広めたものであり[3]、またホイーラー自身は言葉の考案者であると主張したことはない[3]。
⑥ 特徴
ブラックホールはその特性上、直接的な観測を行うことは困難である。しかし他の天体との相互作用を介して間接的な観測が行われている。X線源の精密な観測と質量推定によって、いくつかの天体はブラックホールであると考えられている
⑦ 事象の地平面
周囲は非常に強い重力によって時空が著しくゆがめられ、ある半径より内側では脱出速度が光速を超えてしまう。この半径をシュヴァルツシルト半径、この半径を持つ球面を事象の地平面(シュヴァルツシルト面)と呼ぶ。この中からは光であっても外に出てくることはできない。ブラックホールは単に元の星の構成物質がシュヴァルツシルト半径よりも小さく圧縮されてしまった状態の天体であり、事象の地平面の位置に何かがある訳ではなく、ブラックホールに向かって落下する物体は事象の地平面を超えて中へ落ちて行く。
ブラックホールから離れた位置の観測者から見ると、物体が事象の地平面に近づくにつれて、相対論的効果によって物体の時間の進み方が遅れるように見えるため、観測者からはブラックホールに落ちていく物体は最終的に事象の地平面の位置で永久に停止するように見える[7]。同時に、物体から出た光は重力による赤方偏移を受けるため、物体は落ちていくにつれて次第に赤くなり[8]やがて可視光領域を外れ見えなくなる。
※ ブラックホールにも大小のサイズがあるというが、それはどうやって計算する
のだろうか?















