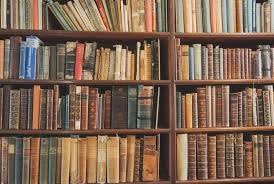(日本列島周辺で発生する地震のタイプ)

※ 「南海トラフ地震に関する情報(定例)」が、本日(7日)更新されました。
一か月に一回、月初。
① ""南海トラフ地震に関連する情報(定例)""
平成30年08月07日
気象庁地震火山部
本日(8月7日)開催した第10回南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会、第388回地震防災対策強化地域判定会で評価した、南海トラフ周辺の地殻活動の調査結果は以下のとおりです。
現在のところ、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。
1.地震の観測状況
プレート境界付近を震源とする主な深部低周波地震(微動)を以下の領域で観測しました。
(1) 愛媛県中予から愛媛県南予:7月10日から28日
(2) 豊後水道:7月18日から20日
2.地殻変動の観測状況
上記(1)、(2)の深部低周波地震(微動)とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計でわずかな地殻変動を観測しました。
一方、GNSS観測 ※1
等によると、御前崎、潮岬及び室戸岬のそれぞれの周辺では長期的な沈降傾向が継続しています。
なお、2018年5月まで実施したGNSS・音響測距観測によると、紀伊水道沖で通常とは異なる変化を2017年末頃から観測しています。
3.地殻活動の評価
上記(1)、(2)の深部低周波地震(微動)及びひずみ観測点で観測した地殻変動は、想定震源域のプレート境界深部において発生した「短期的ゆっくりすべり」に起因すると推定しています。
GNSS・音響測距観測で観測されている紀伊水道沖の通常とは異なる変化は、紀伊水道沖における非定常地殻変動によるものである可能性があります。
上記観測結果を総合的に判断すると、南海トラフ地震の想定震源域ではプレート境界の固着状況に特段の変化を示すようなデータは今のところ得られておらず、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていないと考えられます。
② ※1 ""GNSS観測""
(1) GNSS連続観測システムとは
GNSS連続観測システム(GEONET: GNSS Earth Observation Network System)とは、全国約1,300ヶ所に設置された電子基準点とGEONET中央局(茨城県つくば市)からなる、高密度かつ高精度な測量網の構築と広域の地殻変動の監視を目的とした国土地理院によるGNSS連続観測システムです。
(2) 地殻変動の監視
全国の電子基準点で取得された観測データをもとに、地震や火山の活動に起因する地殻変動を把握することで、そのメカニズムを明らかにしています。また、日本周辺のプレート運動が日々実測され、例えばゆっくり地震などといった他の観測手段では捉えられない現象を捉えることができます。GEONETは地殻変動観測に欠かせない基本的な観測網としての役割を果たしています。
(3) 電子基準点を利用した測量
GNSSによる測量では、既知点と新点にGNSS機器を設置し相対測位(干渉測位)を行い、既知点からの位置関係を測定して測定点の座標を割り出します。
電子基準点を既知点として用いることで、利用者が自分で既知点にGNSS機器の設置を行う必要がなくなります。 国土地理院が提供する電子基準点データを利用し、新点でGNSS観測を行うだけで新点の座標を得ることができるため、作業の効率化が図られます。 このように電子基準点は、GNSSを用いた測量のインフラとして活用されています。
(4) 測量成果におけるGEONETの役割
電子基準点や三角点などの測量成果は、基本的に座標値が固定されています。 しかし、日本のような地殻変動の大きい地域では、固定された座標値と実際の座標値との間に時間とともにずれが生じてきます。このずれが大きくなって測量に不都合が生じた(許容範囲を超えた)場合には、測量成果の改定を行う必要があります。
GEONETによる地殻変動観測は、測量成果改訂の判断材料として、適切な測地基準点体系の維持管理に役立っています。