三井寺も2回目の参拝になるが、最初に訪れた時の写真が操作ミスかなにかで、私のパソコンから消えてしまっていた。
新たな気持ちで境内を廻ったため写真の枚数が増えてしまい、数回に分けての報告になる。
大門<仁王門>(重要文化財)
室町時代(宝徳四年 1452)。三間一戸楼門 入母屋造 桧皮葺

三井寺中院の表門で、東面して建ち、両脇の仁王像が山内を守護している

天台宗の古刹常楽寺(湖南市)の門で、 後に秀吉によって伏見に移され、慶長六年(1601)に家康によって現在地に 建てられた
*常楽寺(湖南市)平成25年12月7日付けで公開

仁王像を撮ろうとしたが、格子と細かな鉄網が試練を与えてくれる
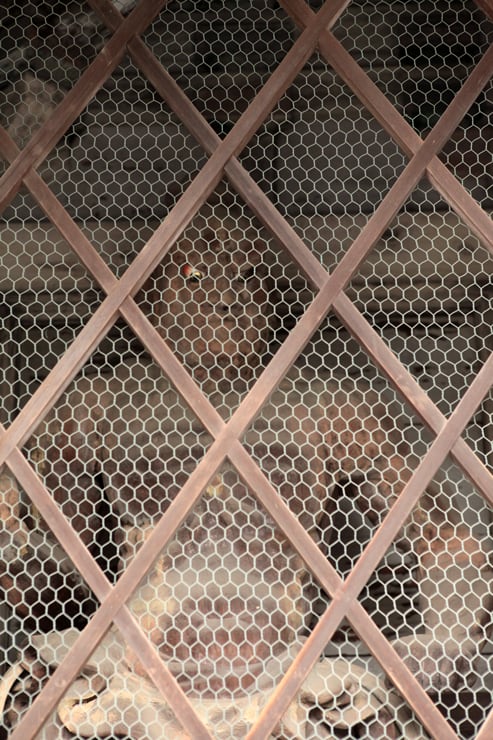
悪戦苦闘したが私の技術ではここまでが限界
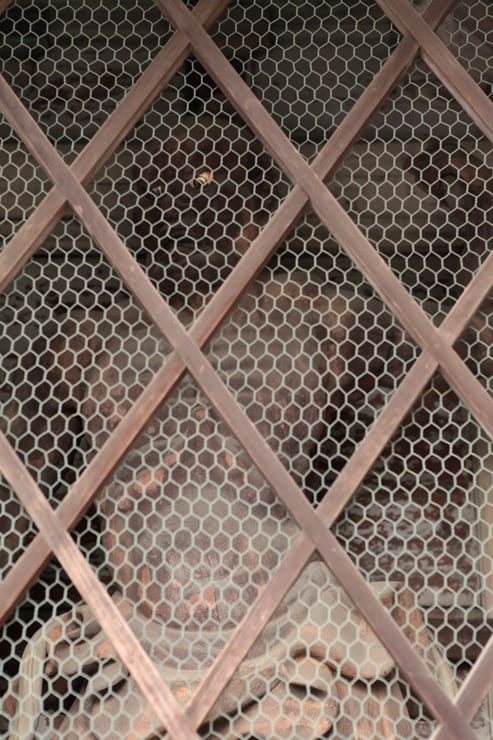
釈迦堂から見える仁王門

釈迦堂<食堂>(重要文化財)
大門を入って金堂に至る道の右側にある。天正年間(16世紀末)造営の御所清涼殿を下賜され移築したもの

「園城寺境内古図」には、大門を入ってすぐ右手に食堂が描かれている。
この堂も食堂として移築されたものと思われるが、 現在は清涼寺式釈迦如来像を本尊とする釈迦堂として信仰されている

仏像が好きな人は堂中に入ると近くから拝観することができる。
清涼寺式の仏像についてだが、最初は奇異に感じていたが、見慣れてくると病みつきになる不思議な魅力を持っている
歩を進めていくと石段の上に金堂が見えてくる

金堂<本堂>(国宝)
三井寺再興を許可した豊臣秀吉の遺志により、高台院が慶長4年(1599年)に再建した。入母屋造、檜皮葺きの和様仏堂である。なお、移築された旧金堂が延暦寺に現存する。

672年、天智天皇の永眠後、大友皇子(天智天皇の子)と大海人皇子(天智天皇の弟)が 皇位継承をめぐって争い、壬申の乱が勃発。
壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王は父の霊を弔うために 「田園城邑(じょうゆう)」を寄進して寺を創建し、天武天皇から「園城」という勅額を賜わったことが園城寺の始まりとされている

三井寺の金堂には、本尊として弥勒菩薩が祀られている。
「寺門伝記補録」によると、身丈三寸二分の弥勒菩薩(絶対秘仏)

三井寺と呼ばれるようになったのは、天智・天武・持統天皇の三帝の誕生の際に 御産湯に用いられたという霊泉があり「御井の寺」と呼ばれていたものを後に 智証大師円珍が当時の厳義・三部潅頂の法儀に用いたことに由来。
現在、金堂西側にある「閼伽井屋」から湧き出ている清水が御井そのものとされている

貞観年間(859~877)になって、智証大師円珍が、 園城寺を天台別院として中興してからは、東大寺・興福寺・延暦寺と共に「本朝四箇大寺(しかたいじ)」の一つに数えられ、南都北嶺の一翼を担ってきた

円珍の死後、円珍門流と慈覚大師円仁門流の対立が激化し、正暦四年(993)、円珍門下は比叡山を下り一斉に三井寺に入る。
この時から延暦寺を山門、三井寺を寺門と称し天台宗は二分された。
その後、両派の対立や源平の争乱、南北朝の争乱等による焼き討ちなど幾多の法難に遭遇した

以前訪れた時、後陣の売店を担当していた男性が、仏像に光を当て表情まで丁寧に説明してくれたことを思い出す。
その親切に応えるため、その時に購入した数珠をいまでも愛用している。
次回に続く
撮影 平成25年11月12日
新たな気持ちで境内を廻ったため写真の枚数が増えてしまい、数回に分けての報告になる。
大門<仁王門>(重要文化財)
室町時代(宝徳四年 1452)。三間一戸楼門 入母屋造 桧皮葺

三井寺中院の表門で、東面して建ち、両脇の仁王像が山内を守護している

天台宗の古刹常楽寺(湖南市)の門で、 後に秀吉によって伏見に移され、慶長六年(1601)に家康によって現在地に 建てられた
*常楽寺(湖南市)平成25年12月7日付けで公開

仁王像を撮ろうとしたが、格子と細かな鉄網が試練を与えてくれる
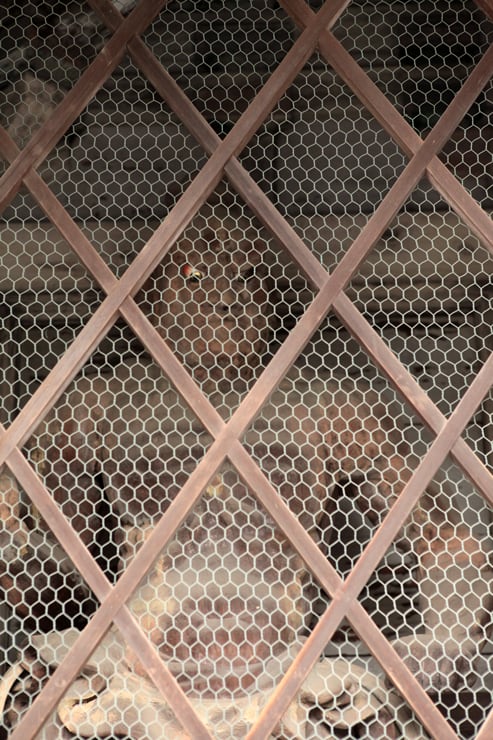
悪戦苦闘したが私の技術ではここまでが限界
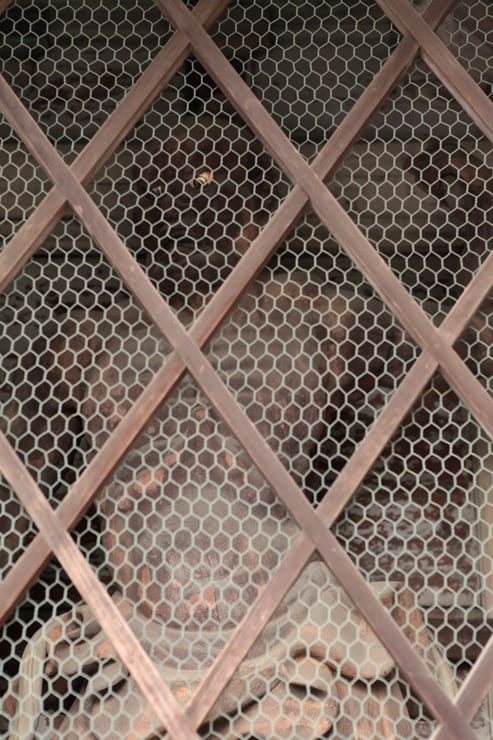
釈迦堂から見える仁王門

釈迦堂<食堂>(重要文化財)
大門を入って金堂に至る道の右側にある。天正年間(16世紀末)造営の御所清涼殿を下賜され移築したもの

「園城寺境内古図」には、大門を入ってすぐ右手に食堂が描かれている。
この堂も食堂として移築されたものと思われるが、 現在は清涼寺式釈迦如来像を本尊とする釈迦堂として信仰されている

仏像が好きな人は堂中に入ると近くから拝観することができる。
清涼寺式の仏像についてだが、最初は奇異に感じていたが、見慣れてくると病みつきになる不思議な魅力を持っている
歩を進めていくと石段の上に金堂が見えてくる

金堂<本堂>(国宝)
三井寺再興を許可した豊臣秀吉の遺志により、高台院が慶長4年(1599年)に再建した。入母屋造、檜皮葺きの和様仏堂である。なお、移築された旧金堂が延暦寺に現存する。

672年、天智天皇の永眠後、大友皇子(天智天皇の子)と大海人皇子(天智天皇の弟)が 皇位継承をめぐって争い、壬申の乱が勃発。
壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王は父の霊を弔うために 「田園城邑(じょうゆう)」を寄進して寺を創建し、天武天皇から「園城」という勅額を賜わったことが園城寺の始まりとされている

三井寺の金堂には、本尊として弥勒菩薩が祀られている。
「寺門伝記補録」によると、身丈三寸二分の弥勒菩薩(絶対秘仏)

三井寺と呼ばれるようになったのは、天智・天武・持統天皇の三帝の誕生の際に 御産湯に用いられたという霊泉があり「御井の寺」と呼ばれていたものを後に 智証大師円珍が当時の厳義・三部潅頂の法儀に用いたことに由来。
現在、金堂西側にある「閼伽井屋」から湧き出ている清水が御井そのものとされている

貞観年間(859~877)になって、智証大師円珍が、 園城寺を天台別院として中興してからは、東大寺・興福寺・延暦寺と共に「本朝四箇大寺(しかたいじ)」の一つに数えられ、南都北嶺の一翼を担ってきた

円珍の死後、円珍門流と慈覚大師円仁門流の対立が激化し、正暦四年(993)、円珍門下は比叡山を下り一斉に三井寺に入る。
この時から延暦寺を山門、三井寺を寺門と称し天台宗は二分された。
その後、両派の対立や源平の争乱、南北朝の争乱等による焼き討ちなど幾多の法難に遭遇した

以前訪れた時、後陣の売店を担当していた男性が、仏像に光を当て表情まで丁寧に説明してくれたことを思い出す。
その親切に応えるため、その時に購入した数珠をいまでも愛用している。
次回に続く
撮影 平成25年11月12日
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます