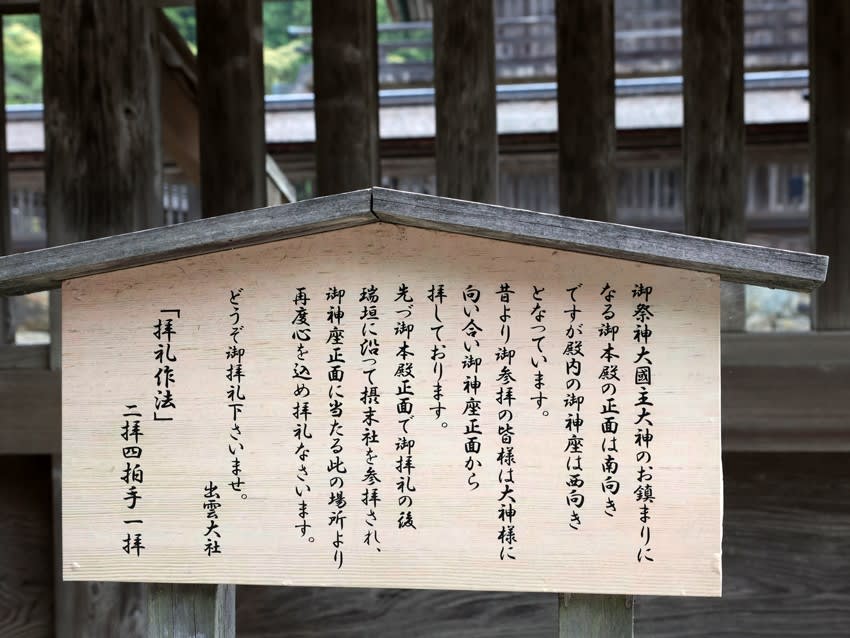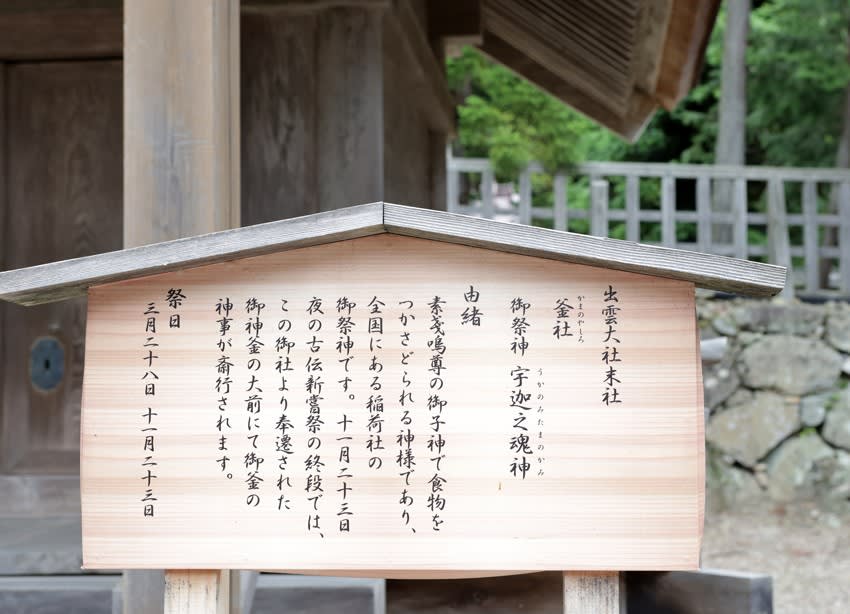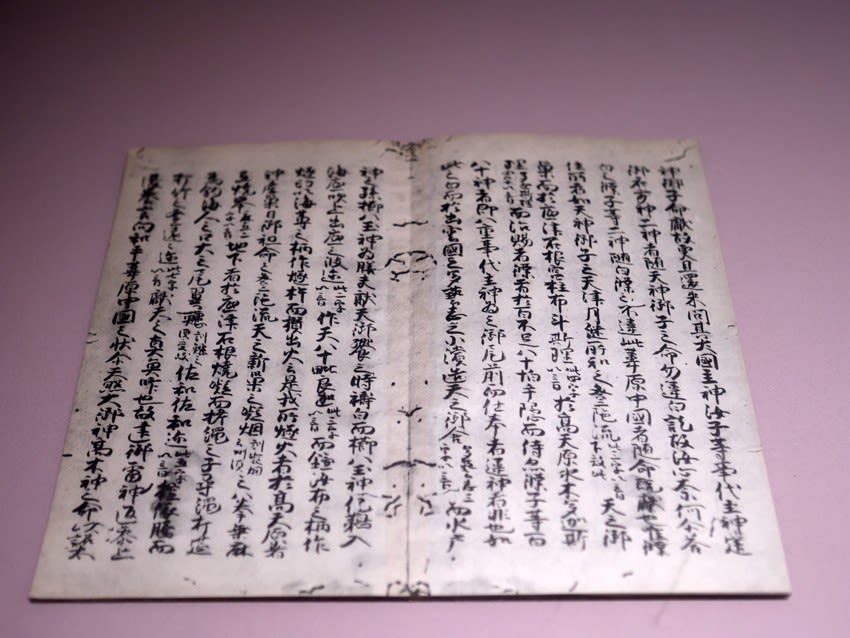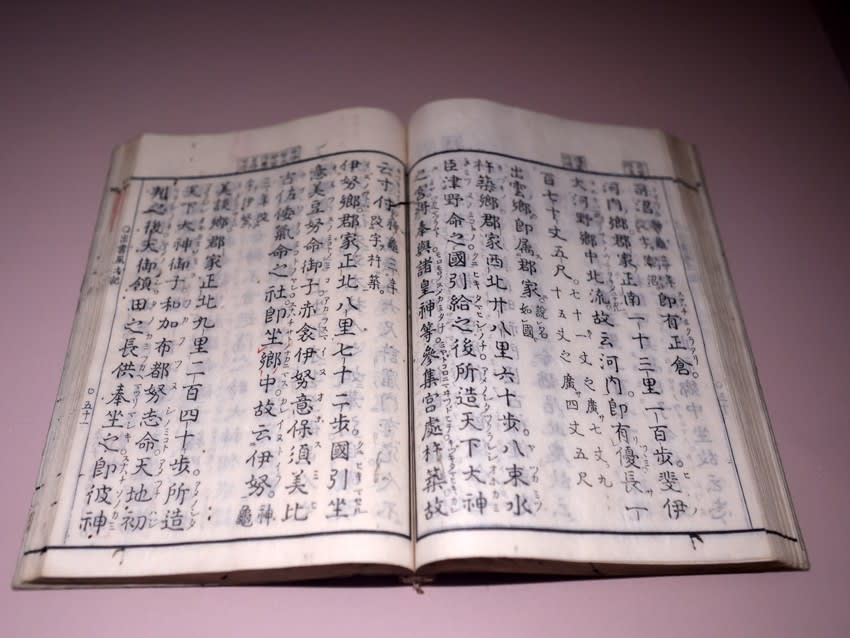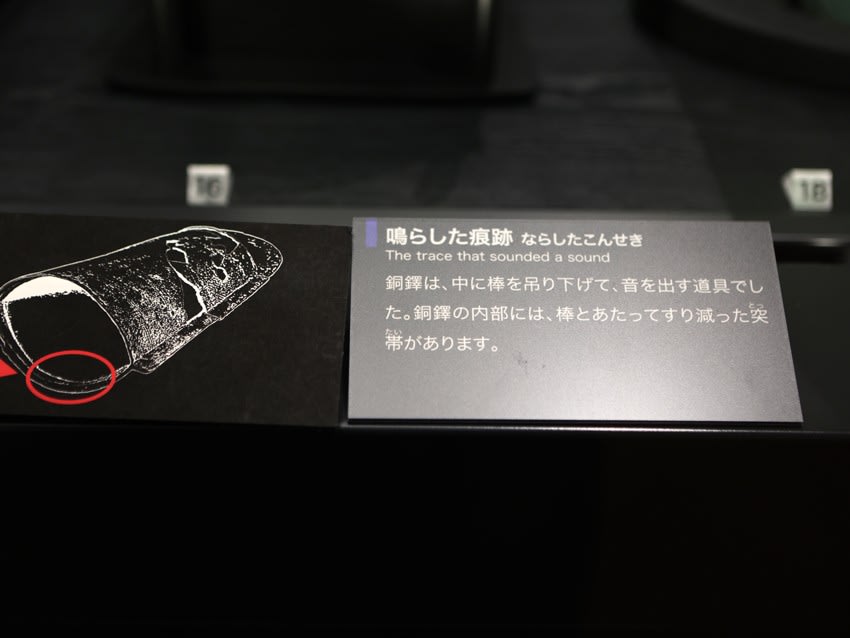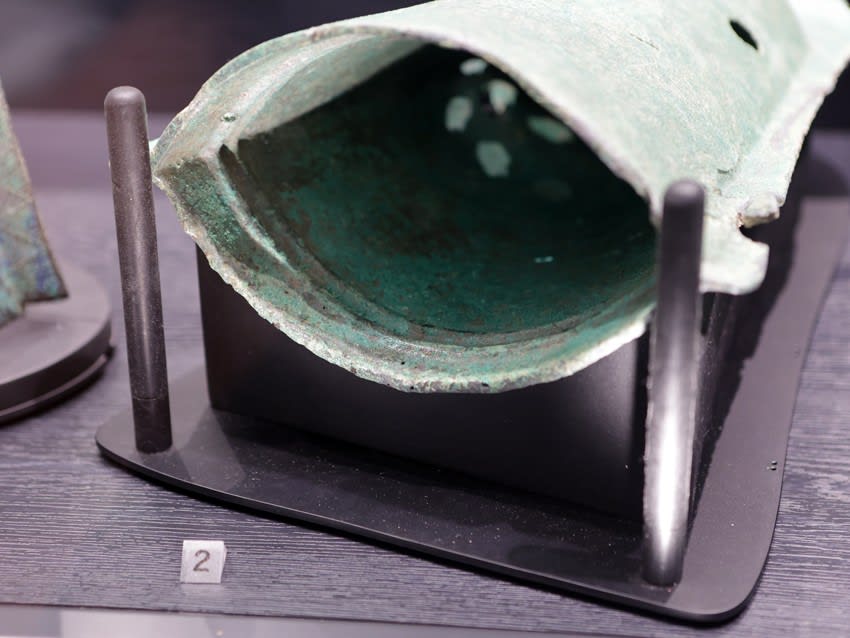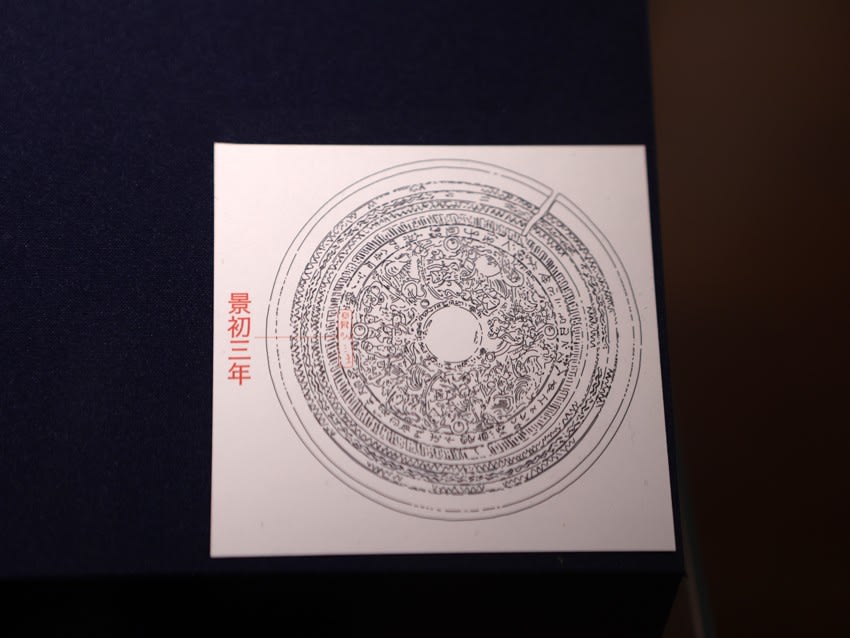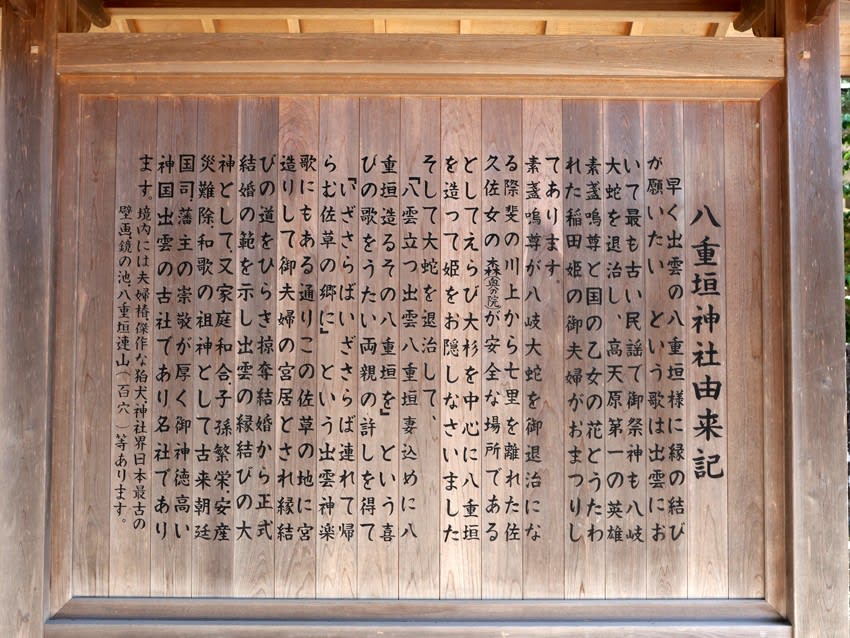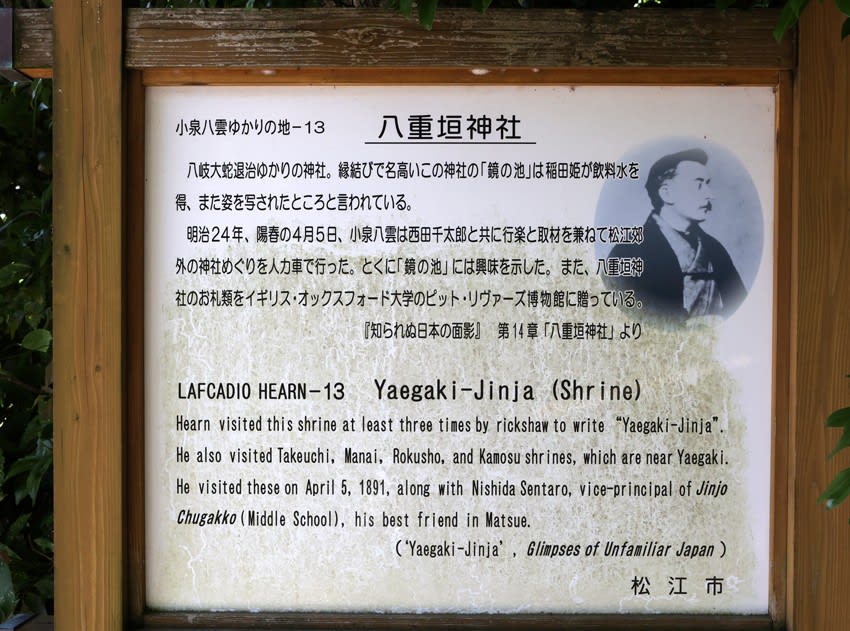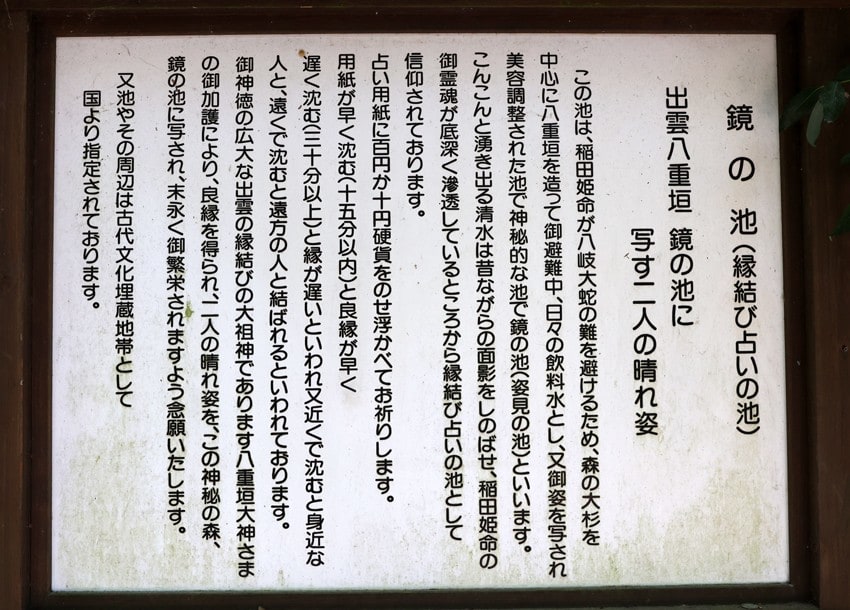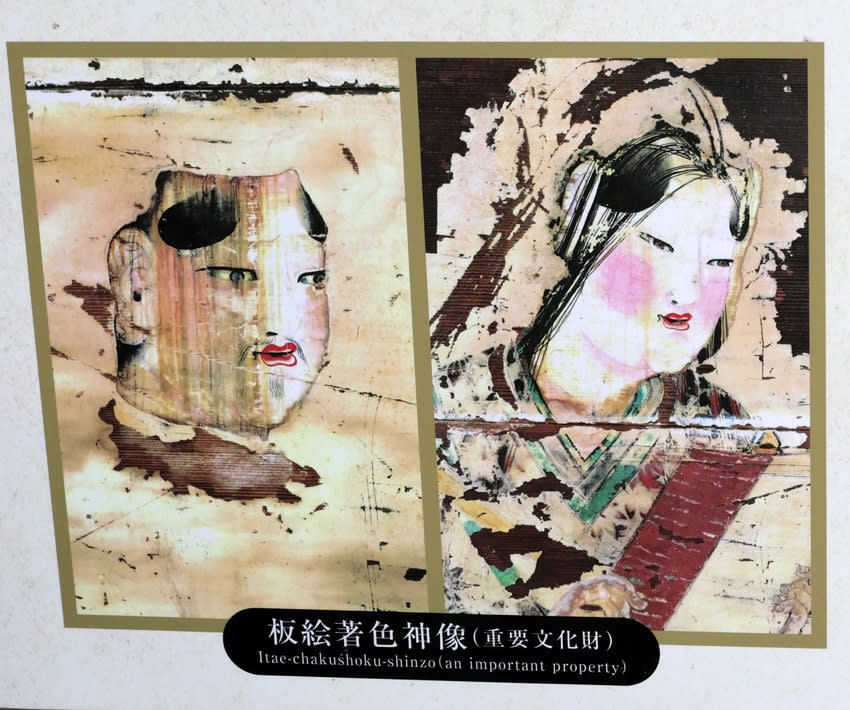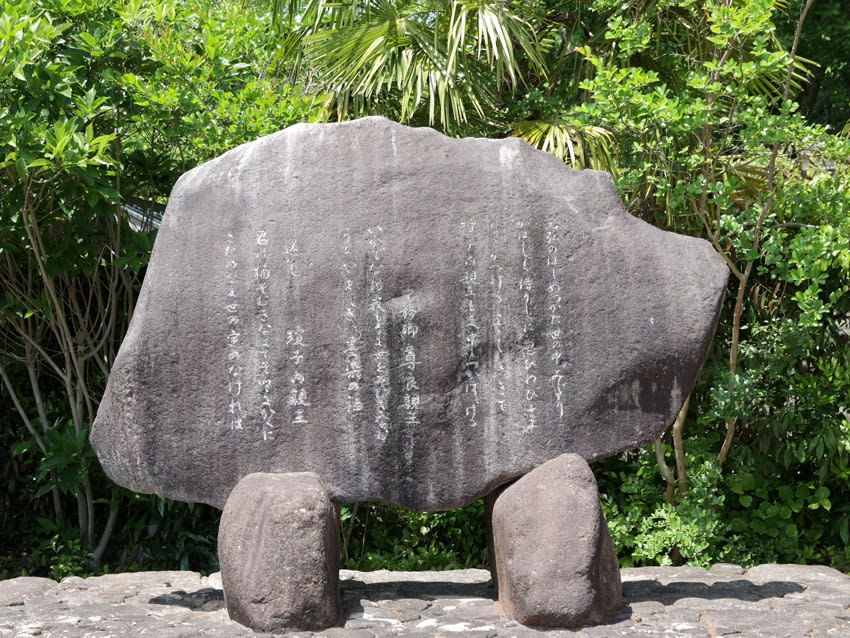訪問日 令和5年5月19日
岩谷山 心覚院 来迎寺
この日は昨夜からの雨が降り止まず観光は無理かなと思いながら道の駅で待機していた
9時過ぎに雨が止み、「最寄りの有名寺社」で検索し選択した寺である

重要文化財の「木造阿弥陀如来立像」の拝観が主な目的である

創建は大同3年(808年)当初は来迎寺と称した天台宗の寺院で亀山にあった
元和5年(1619年)亀山に浜田城が築かれる事になりこの地に移された
寛文3年(1663年)当時の浜田藩主松平康映が生母(心覚院)の菩提所に定めた事で心覚院と寺号を改め遍挙を招いて浄土宗に改宗開山した

松原湾を見下ろす閑寂なたたずまいの中に本堂や観音堂などが建っている

仏像拝観をお願いすると寺の歴史と仏像の説明なども丁寧にしていただいた

仏像を観るのが好きだが多くの寺院では撮影禁止なのが残念だと話すと
「自由に撮ってください」と言われた

木造阿弥陀如来立像(重要文化財)
漁師が沖に浮かぶ光を放つ箱を引き上げたところ、中からこの仏像が現れたと云い伝えられている
建長7年(1255年)6月18日の造営銘文があり「安阿弥(快慶)」風の立像である

ヒノキの一木造りで仏像彫刻としては岩見地方唯一の重要文化財として貴重な仏像である


台座は漆箔で彩色された八角形框座の踏割蓮華座で2つに分かれた蓮華上に片足ずつ踏み分けて立っている

脇侍仏
両脇侍(観音・勢至)菩薩像 文政年間(1820年頃)造立


住職から横から観る姿が美しいと





本堂仏像撮影後住職からお茶をご馳走になりしばらく歓談する
その時に観音堂の仏像を観ませんかと云われた

観音堂堂内の仏像
写真の仏像が「秘仏 聖観音菩薩」(33年に一度開帳)









あまりにも興奮しすぎてピンボケ写真が多く掲載できなかった
この春の旅を通して記憶に残る寺院であった
撮影 令和5年5月19日
岩谷山 心覚院 来迎寺
この日は昨夜からの雨が降り止まず観光は無理かなと思いながら道の駅で待機していた
9時過ぎに雨が止み、「最寄りの有名寺社」で検索し選択した寺である

重要文化財の「木造阿弥陀如来立像」の拝観が主な目的である

創建は大同3年(808年)当初は来迎寺と称した天台宗の寺院で亀山にあった
元和5年(1619年)亀山に浜田城が築かれる事になりこの地に移された
寛文3年(1663年)当時の浜田藩主松平康映が生母(心覚院)の菩提所に定めた事で心覚院と寺号を改め遍挙を招いて浄土宗に改宗開山した

松原湾を見下ろす閑寂なたたずまいの中に本堂や観音堂などが建っている

仏像拝観をお願いすると寺の歴史と仏像の説明なども丁寧にしていただいた

仏像を観るのが好きだが多くの寺院では撮影禁止なのが残念だと話すと
「自由に撮ってください」と言われた

木造阿弥陀如来立像(重要文化財)
漁師が沖に浮かぶ光を放つ箱を引き上げたところ、中からこの仏像が現れたと云い伝えられている
建長7年(1255年)6月18日の造営銘文があり「安阿弥(快慶)」風の立像である

ヒノキの一木造りで仏像彫刻としては岩見地方唯一の重要文化財として貴重な仏像である


台座は漆箔で彩色された八角形框座の踏割蓮華座で2つに分かれた蓮華上に片足ずつ踏み分けて立っている

脇侍仏
両脇侍(観音・勢至)菩薩像 文政年間(1820年頃)造立


住職から横から観る姿が美しいと





本堂仏像撮影後住職からお茶をご馳走になりしばらく歓談する
その時に観音堂の仏像を観ませんかと云われた

観音堂堂内の仏像
写真の仏像が「秘仏 聖観音菩薩」(33年に一度開帳)









あまりにも興奮しすぎてピンボケ写真が多く掲載できなかった
この春の旅を通して記憶に残る寺院であった
撮影 令和5年5月19日