
画像は講演中の熊谷氏です。
月刊『つり人』での連載、そして、最近では当Blogでも紹介した『タナゴ類ポケット図鑑」なども発刊されていますので、彼についてはあまりにも有名なのでここで説明する必要はないでしょう。僕が知る彼は人間的にもとても優しい人で、過去に心が折れそうになった時に個人的に助けて頂いた経験があります。あの時の御恩は一生忘れられません。
以前にタナゴサミットっていうのに参加させていただいたのですが、その基調はタナゴの保護・増殖でしたから釣り師はある意味敵でした。しかし今回は、その表題が『今こそ、釣り人みんなで考える~残そう地域固有のタナゴたち~』となっていますので、要は対象が『釣り人』です。安心して行って来ました。
基調がタナゴ族の遺伝的固有性を保存することでしたので、なんとなく納得だったのですが、個人的にはその必要をあまり感じていませんでした。といいますのも、タナゴはその昔はどこにでも居た魚です。そして、その昔は河川も自然に流れていましたから、時には洪水なども起こしてあっちの遺伝子がこっちに来たり、こっちの遺伝子があっちに行ったりなんてことは普通にあったことだと思います。ところが、タナゴ族が減少したため、その生息域が限局的になり、河川も整えられて洪水なども無くなり、それによってタナゴたちは近親交配を余儀なくされ、その結果、遺伝的固有性が生まれたのだと考えています。勿論、突然変異の固定などもあるでしょうが、確率的には新たな形の遺伝子が誕生するのは、かなり低いと思っています。事実、他との交流のない小笠原などでは生物のほとんどが亜種となっているほどですから。要は、タナゴ族の遺伝的固有性は人が作った物だと思えたのです。そして、それを保護することは、より近親交配の率を高めて、結局絶滅に導いてしまうのではないか?と危惧していました。
基調講演は三重大学大学院の三宅氏でしたので、懇親会でその辺の事を個人的に聞いてみました。彼は僕の話をよく聞いてくれて、僕の考えも正しい事を教えてくれて、しかも僕が思っていた危惧について案外とあっさりと僕を納得させてくれました。案外正反対だと思っていたことは、実は紙一重の違いだったのです。ここで、それを書こうとすると論文一個分くらいなってしまうので、詳細は記載しませんが、要は僕の考えも正しく、彼の考えも正しく、ただ程度の違いだけの問題だったようです。やはり、しっかりした基盤の上に成り立っている科学って凄いですね!
この問題は僕の中で正しい事が解からずにいた大きな問題でした。これが一つ解決しただけでも物凄い宝物となりました。三宅さん、ありがとうございました。
その他、様々な演者様から沢山の知見を得ました。そのほとんどが間違いはないでしょうが、自分で出来る事はこれから時間を掛けて一つづつ検証して知見を得て行きたいと思っています。
やはり、総合的に考えて素人が安易に放流することは良くない事です。これはタナゴ族に限った事ではなく、渓流から海まで総ての魚類をはじめ、総ての生物に言える事だと思います。
ただ、放流をしなくてはならない究極な場合もあります。その時は三宅さんのような人に報告して、しかるべき人がしかるべき方法を持って行われるべきなのが放流です
本当に素晴らしいシンポジウムでした。こういう素晴らしいシンポジウムには沢山の釣り師に参加して頂きたいと思いました。我々釣り人だからこそ出来る自然保護っていうのもありますから、各自がこういうシンポジウムで正しい理論を知り、それに基づいて考え、そして実行てもらいたいと思いました。
素晴らしいシンポジウムにお誘いしてくれた熊谷氏には心より感謝致します。ありがとうございました。
月刊『つり人』での連載、そして、最近では当Blogでも紹介した『タナゴ類ポケット図鑑」なども発刊されていますので、彼についてはあまりにも有名なのでここで説明する必要はないでしょう。僕が知る彼は人間的にもとても優しい人で、過去に心が折れそうになった時に個人的に助けて頂いた経験があります。あの時の御恩は一生忘れられません。
以前にタナゴサミットっていうのに参加させていただいたのですが、その基調はタナゴの保護・増殖でしたから釣り師はある意味敵でした。しかし今回は、その表題が『今こそ、釣り人みんなで考える~残そう地域固有のタナゴたち~』となっていますので、要は対象が『釣り人』です。安心して行って来ました。
基調がタナゴ族の遺伝的固有性を保存することでしたので、なんとなく納得だったのですが、個人的にはその必要をあまり感じていませんでした。といいますのも、タナゴはその昔はどこにでも居た魚です。そして、その昔は河川も自然に流れていましたから、時には洪水なども起こしてあっちの遺伝子がこっちに来たり、こっちの遺伝子があっちに行ったりなんてことは普通にあったことだと思います。ところが、タナゴ族が減少したため、その生息域が限局的になり、河川も整えられて洪水なども無くなり、それによってタナゴたちは近親交配を余儀なくされ、その結果、遺伝的固有性が生まれたのだと考えています。勿論、突然変異の固定などもあるでしょうが、確率的には新たな形の遺伝子が誕生するのは、かなり低いと思っています。事実、他との交流のない小笠原などでは生物のほとんどが亜種となっているほどですから。要は、タナゴ族の遺伝的固有性は人が作った物だと思えたのです。そして、それを保護することは、より近親交配の率を高めて、結局絶滅に導いてしまうのではないか?と危惧していました。
基調講演は三重大学大学院の三宅氏でしたので、懇親会でその辺の事を個人的に聞いてみました。彼は僕の話をよく聞いてくれて、僕の考えも正しい事を教えてくれて、しかも僕が思っていた危惧について案外とあっさりと僕を納得させてくれました。案外正反対だと思っていたことは、実は紙一重の違いだったのです。ここで、それを書こうとすると論文一個分くらいなってしまうので、詳細は記載しませんが、要は僕の考えも正しく、彼の考えも正しく、ただ程度の違いだけの問題だったようです。やはり、しっかりした基盤の上に成り立っている科学って凄いですね!
この問題は僕の中で正しい事が解からずにいた大きな問題でした。これが一つ解決しただけでも物凄い宝物となりました。三宅さん、ありがとうございました。
その他、様々な演者様から沢山の知見を得ました。そのほとんどが間違いはないでしょうが、自分で出来る事はこれから時間を掛けて一つづつ検証して知見を得て行きたいと思っています。
やはり、総合的に考えて素人が安易に放流することは良くない事です。これはタナゴ族に限った事ではなく、渓流から海まで総ての魚類をはじめ、総ての生物に言える事だと思います。
ただ、放流をしなくてはならない究極な場合もあります。その時は三宅さんのような人に報告して、しかるべき人がしかるべき方法を持って行われるべきなのが放流です
本当に素晴らしいシンポジウムでした。こういう素晴らしいシンポジウムには沢山の釣り師に参加して頂きたいと思いました。我々釣り人だからこそ出来る自然保護っていうのもありますから、各自がこういうシンポジウムで正しい理論を知り、それに基づいて考え、そして実行てもらいたいと思いました。
素晴らしいシンポジウムにお誘いしてくれた熊谷氏には心より感謝致します。ありがとうございました。















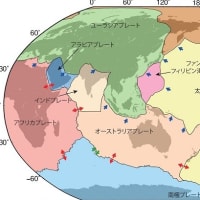




本当にシンポジウムは考えさせられる内容でした。
固有の話しを聞きながら閉鎖的な環境ではやがて血がこくなり滅びてしまうのではと感じました。また環境が悪化する一方の場所へ閉じ込めたところで昔のように水路の魚たちは自ら良い環境を求めて移動することさえ制限されやすい状況下ではますます減少するしかありません。専門家に鑑定された種を人工授精で増殖し、本来の生息エリアを考慮した様々な状況のところ放流していく意外に方向性が見えてこない気がしました。何しろすでにデータが少なすぎです。ミヤコタナゴなどの例とすれば保護だけでは失敗は目にみえてます。また、公的な機関だけではなく認定でどんどんマニアにまかせたほうが未来はあると思えます。日本では固有など霞ヶ浦に限らずイワナやヤマメそしてアユなど公式にばらまかれていままできています。まずは現実を受け入れてから取り組みかたを考えるべきと思いました。関西の方だからか分かりませんが放射能のタナゴへの影響もネタとして準備してほしかったです。
本当にタナゴ釣りの現代を考えさせられる内容でしたね。
『専門家に鑑定された種を人工授精で増殖し、本来の生息エリアを考慮した様々な状況のところ放流していく意外に方向性が見えてこない気がしました。』
そうでしょうか。僕はまた違った考えを持っています。
多分、今回このシンポジウムに参加された方は今までこういう事を考えていなかった人も含めて、それぞれに様々な新たな知識を得られ、いろいろな事を考え始めたのではないでしょうか?そして、どこかで良い案が生まれてくる可能性もあります。案外、学者は固定観念が強いですから、素人が名案を出す事もあると思います。ですから、先日の講演を思い出しながら色々と考えて頂きたいと思います。そして、その考えに従って行動をすることも大切だと思います。
コメントをありがとうございました。
P.S
遊漁料を徴収するためには放流していないといけないという法律(?)があるらしいです。これが問題です。彼らは釣り券を徴収するためには何でもしますから。
未使用の養魚場借りて養殖するような定年後のライフワークにするかたとかいないでしょうかね?種を守って放流し、入漁料をとる。または北浦のような閉鎖ドックに入場券を発行するとか。
タイバラの認識も年代で逆転してるから難しいですね。
あのかたたちにとってのタナゴとはタイバラですからね。他は鮒みたいなものでしょうか?
ところで最近はそちらのヤリは健在でしょうか?初めてうかがったときにみたバカながを履いた集団にその後も荒らされていないでしょうか?
管理人は釣ったその場でのリリースは別として、放流はいかなる理由をもってしても許されるものではないと考えております。例えその地方特有の遺伝子を持った魚でも、その場所で生きていけるMAXが現在の数であって、そこに放流したらMAXを超えます。そうするとどこかでその分は★になります。要は、放流した分の魚がどこかで減る訳で、放流は全く意味を持ちません。そう考えております。ただし、これが正しいかどうかは確証を持っておりません。
タイリクバラタナゴやカネヒラなどの国内・外移入種は困りますね。釣りとして面白いのは解かるのですが、自然を守る観点から申せば駆除対象です。出来ましたら(関東の場合)ああいう魚は自然からは排除し、釣り堀でやってもらいたいものです。
こちらのヤリタナゴは健在ですが、やはりこの時期は釣り辛いです。
コメントをありがとうございました。