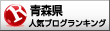こちらは自生地に何かを刺して測定しています。
測定しているのは土壌内の酸素濃度。
地下40cmまでの酸素が何%あるのかがわかります。
普通は地下深くなるほど酸素濃度は減少します。
さらに塩害を受けると土壌は隙間がなくなり通気性が悪くなることから
土壌内の酸素濃度は浅いところでも低下し、生物に悪影響を与えます。
昨年、種差海岸の土壌酸素濃度を測定したところ
やはり表層は酸素濃度が20%以下で塩害の痕跡がありました。
ところが地下30cmでは逆に濃度が高いのです。
チームはおそらく毎年枯れた草が積み重なってできた腐葉土層のため
内部は隙間がたっぷりあり、そのため酸素濃度が高かったのだと考えています。
このふかふかの土壌がサクラソウなどの植物を守ったのです。
この豊かな自然で形成された環境が種差海岸の秘密であり宝なのです。
チームはこの数値を見てあらためて自然の力の強さを実感しました!
今年の調査では地表から地下部まで酸素濃度はすべて20%以上。
もう塩害の影響はありません。
測定しているのは土壌内の酸素濃度。
地下40cmまでの酸素が何%あるのかがわかります。
普通は地下深くなるほど酸素濃度は減少します。
さらに塩害を受けると土壌は隙間がなくなり通気性が悪くなることから
土壌内の酸素濃度は浅いところでも低下し、生物に悪影響を与えます。
昨年、種差海岸の土壌酸素濃度を測定したところ
やはり表層は酸素濃度が20%以下で塩害の痕跡がありました。
ところが地下30cmでは逆に濃度が高いのです。
チームはおそらく毎年枯れた草が積み重なってできた腐葉土層のため
内部は隙間がたっぷりあり、そのため酸素濃度が高かったのだと考えています。
このふかふかの土壌がサクラソウなどの植物を守ったのです。
この豊かな自然で形成された環境が種差海岸の秘密であり宝なのです。
チームはこの数値を見てあらためて自然の力の強さを実感しました!
今年の調査では地表から地下部まで酸素濃度はすべて20%以上。
もう塩害の影響はありません。