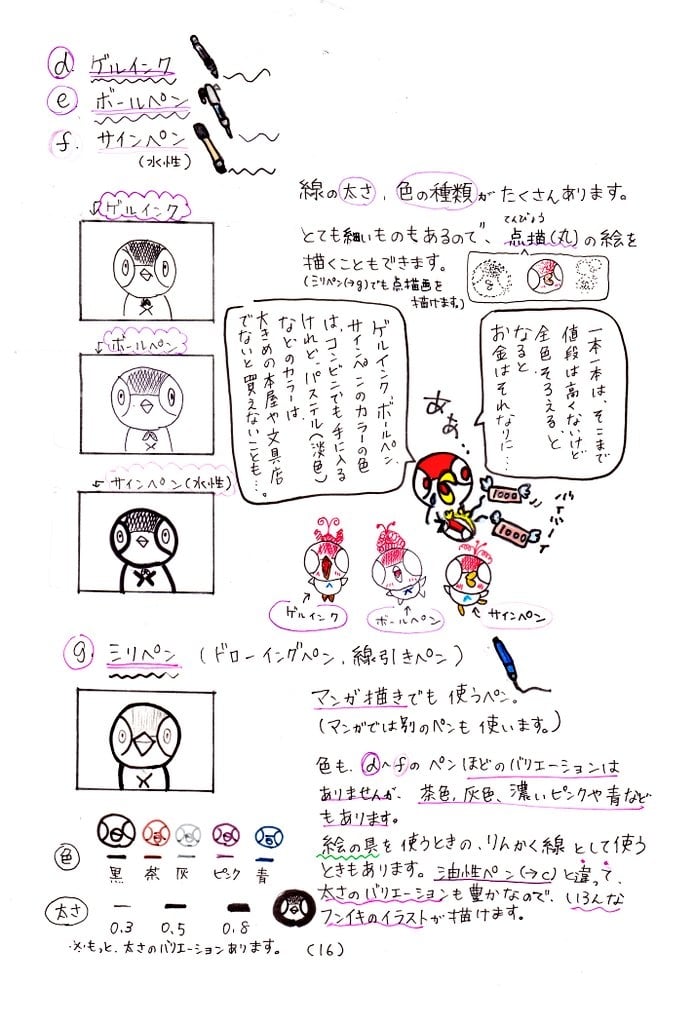みなさま、本日もありがとうございます。

今回は「ASDの子が癇癪をおこす理由」と
前回までにアップしていたシリーズ
「ASDの子が癇癪おこさず、楽しく絵が描ける方法が
なぜ、声掛けなどのハウツー本でなく、
絵についての知識の説明のみなのか?」
についての話をしたいと思います。

ただ、その前置きのお話を先に話したいと
思います。
1 データ分析とその後の対策
最近は子供に
全教科教える日々が続いています。
ひさびさに数学をやると、
ヒストグラム、相対度数などの分野は
新しく入った分野なんだな(昔から書かれていたけれど、最近、重要視されてきた)、と思いました。
自分が生徒だったときに二進法の分野は
習ったけれど、自分が塾講師になったときは
削られてて、など、数学の内容も時期によって変わってるな、としみじみ?思うことはあります。社会科ほどの大きな変化ではありませんが。
今回、ヒストグラムなどを教えてて
思ったのですが、
入試やテスト対策を指導する講師や先生には
「データ読み取り」
そしてそれに伴う
「データ分析」が、できる力と、
その分析から、
具体的にどう対策していけば
良いのか?を考えて実行できる力
が必要だと改めて思いました。

私自身が中学生だったとき
学校のテスト結果や模試の結果が出た時
母が、「このデータはこう読み解くんだよ」と毎回教えてくれたので、
平均点、偏差値、合格判定、などは
毎回、データ分析だけに留め、
そこで次回にすべきことのみを考え、
それを実行にうつし、その実行から得られる
対価交換の結果を手に入れられたか?
だけに専念していました。







その経験から
「受験対策って面白い!」と
思ったことから
結果的に塾講師になりました。
2 私が癇癪をおこしていた理由
私は昔から精神的に不安定で
よく癇癪をおこしていました。
小学生のころまでは
あらゆることがわけがわからなく
ふとしたきっかけで、癇癪を
おこし、自分でも癇癪をとめたくても
止められなくて、とても苦しかったです。
とくに幼稚園や、小5でいじめられて以降。
今だと、ASDゆえんの癇癪であるのは
わかるので、対処方法がわかり、
よほどのことでないと癇癪はおきません。
でも、当時は、ASDという概念もなく
心療内科という世界も浸透してない時代。
どうしようもなかったといえば
どうしようもありませんでした。
私の場合の癇癪は
不安感ベースのパニックが
我慢の限界の頂点に達するとおきます。
パニックがおこりやすい要因は
例えば、
「ダブルバインドの命令を出される状態」
「指示があいまいすぎて、どうしていいか
わからなくて困っているが、怒られる&馬鹿にされる&何かを禁止される(とりあげられる)未来が予測される状態」
だったりします。
(ダブルバインドの命令とは、
2つの、同時に実現不可能な
矛盾した命令のこと。
たとえば、Aさんに「全部、おまえが自分で考えてやれ!」と指示を出されたので、
自分で考えてやったら
何か失敗した時、
同じAさんから
「なぜ、私に聞かなかった?
毎回、きちんと私に聞け!」と命令すること、など。)
因果関係がはっきりして怒られるのなら
それはパニックになりません。
例えば、「やってはいけない」
と言われたことで、
それを自分でも「やってはいけない」
とわかっていてしてしまった、
ときなどは
猛烈に反省することのみ。
おのれの不甲斐なさに怒りをおぼえ
反省して泣くことはありますが、
ただ涙を流すのみ。
癇癪おこして、自分を殴りながら
地響きするのよな泣き叫びを
することはありません。
つまり、私の癇癪がおこる条件は
「他人からの指示」が
「矛盾していて、かつ、不明瞭」
ということがいえます。
3 癇癪をおさえる方法
「他人からの指示」そのものは
なくせるものではないし
時には必要なものです。
しかし、「他人の不明瞭な指示」を
自分で対処することができます。
自分が相手に指示を出す時は
なるべく「不明瞭」にしない、
態度や言動は一貫性をもたせるように
しています。
例えば、「静かにしなさい」ではなく
「口を閉じなさい」
「何も声を出さず、前を見なさい」など、
相手がすべきこと(してほしいこと)
を明確化するなど。
テスト対策でも
「いい点とりなさい」とか
「結果を出しなさい」などの
数値があいまいな目標ではなく
「平均点より+10点以上を目指そう」とか
「偏差値55オーバーを目指そう」
「◯◯高校合格目指すなら、全教科、
各偏差値60オーバーを!」とか
そういう風に、相手がテスト返却&成績されたときに、すぐにわかる目標を話しています。(相手の学力次第で数値は変わる)
先述したように、
自分が指示を受ける側の時は
相手の指示が明確な場合なら
素直に従えるんですが
相手の指示が不明瞭の場合
従いたいけれど、どう従えば良いか
わからないです。
そのため、小さい頃はよく
パニック→癇癪をひきおこしていました。
しかし、中学生のときに
平均点と偏差値の違い、
平均点や偏差値は母体によって変動する、
私立の学校の一般受験の合格基準は
五教科合計点数が高い順から(高校によって合格判定基準は異なる)、
などを知り、
学校の先生が言う
あいまいな学習アドバイスで
精神的にパニックにならないようきし、
テストの結果や塾の模試の結果の数値を
自分で分析するようになってから
かなり癇癪は減りました。
学校の先生には
まじめに授業をうけて、
クラス内で上位の順位をとって
内申点相応の高校を受験すると
提示しておけば
それ以上は先生は何も言わない
ということは中3の時点でわかったので
中3からは、
他人への恐怖が減り
癇癪が格段に減りました。
知識を得て、
自分でデータを分析、
そして、
自分で自分に具体的で明確な指示を出す、
そういう生き方をするようにしたら
かなり生き方が楽になりました。



他人の顔色を伺い、ビクビクし、
それでいて、突然、相手からしたら
発狂したように泣き叫ぶ(癇癪)、
相手がドン引きしているのがわかる、
相手に迷惑をかけているのがわかるのに
止められない、すぐに止めるには自分で自分を殴ったりして止めるしかなくて
でもそれが痛くて辛くて、
そんな毎日から抜け出ることができた
最初のきっかけは
私には受験勉強でした。
知識吸収し、それで、
より正確なデータ分析ができること、
それが受験勉強でできるのが
とても楽しくて安心感を得られたのです。
4 強迫性障害になったきっかけ
癇癪は定期的にはおきましたが、
中学3年生から塾講師をしている間は
比較的精神が安定した私でした。
しかし、何度も流産し、
しかも、定期テスト対策授業時に
流産して、何日か休まなきゃいけなくなった、というのを繰り返すうちに、
塾講師をしているかぎり、子供を産めない、と思い、塾講師をやめました。
しかし、その後、子供がうまれ、
その後、復帰しようと思ったけれど
あらゆる諸事情で
復帰できないまま、今に至ります。
何回もの流産経験と子育てでの違和感から
子供が2歳のとき、私は強迫性障害を
発症しました。
そこからは強迫性障害との
長いつきあいです。
今では、軽症にはなってきましたが
まったくなくなったわけではありません。
ただ、強迫性障害が激減するきっかけと
なったのは、
マンガ作成と子供へのテスト対策勉強でした。
マンガ作成に関しては
小5のときにいじめられ
小6のときに絵の盗作冤罪を先生に
かけられて、自分だけ絵を描くのを先生に
禁止されたことがトラウマで
マンガをずっと描きたくても描けなかった
うっぷんをはらすために始めました。
今でもマンガ作成は大切な趣味です。
テスト対策は、抜群に、強迫性障害の軽減につながりました。
やはり、データ分析と対策、そしてその対策の等価交換的な結果、を出すのが楽しい。
テスト対策の時期が過ぎると、
強迫性障害の強迫観念がポッと出る
ことがあるのが最近わかったきました。
そこで、ローリスクで
代替的なこと(同じような楽しみを与えてくれる行為)はないか?と探していたら
あったんですね。
それが、RPGゲームをすること。
RPGって、自分でデータ分析して、
それでコツコツとキャラクターたちを
育てて、戦いに勝利する楽しさが
受験勉強、受験対策、に似てるんです。
常に、頭の中で、データ分析してないと
強迫観念が出る、というのがわかってきた
ので、空いている時間は
テスト勉強対策するか
余暇はゲームするか、
を常にするようにしました。
そうしたら、強迫性障害の強迫観念が出ることが少なくなりました。
私にとっての
ASDの癇癪、二次障害で生じた強迫性障害、
の大きな要因は、
「あいまいな指示」への「恐怖」が
ひきおこしていた、と私は思います。
5 「ASDの癇癪をおこさず〜」シリーズアップの理由
ひとえにASDといっても
どのような理由で癇癪おこすのか?
も人によって違いますし、
癇癪をおこす人もいればおこさない人も
います。
あくまで、私の場合は、の話ですが
私と同じような理由(あいまいな指示で不安感が積み重なって、最終的に、他人からしたら、ささいなことで感情が爆発する)で癇癪をおこしてつらい思いをする人の助けになれば、という気持ちから、
先週は、かつてつくった「ASDの子が癇癪おこなさい方法」シリーズをアップしました。
ASDの癇癪は
「泣けば、やりたくないことから
逃れられる」
「泣けば、自分のワガママを聞いてもらえる」
と思って、泣いているわけではありません。
でも、他人からはそう見える。
何度、
「ワガママ」
「プライドが高い」
「完璧主義!」と怒られたことか!
でも、ただのパニックで、
本当は自分の言う事を
聞いてもらいたい
わけでない。
相手があいまいな指示をするのを
変えてもらうことは不可能です。
それは相手の人格や、それまで育った世界を
否定することにつながりますし、
仮に相手に変わってもらいレベルのものでも
「指示を出す」立場の方が、
「指示を出される」立場の人より
権力が強かったりします。
学校だと、高校入試までは
内申点という影響力、
高校では卒業単位をという影響力が
「指示を出す立場」=「学校の先生」
側にあるので、
生徒としてはどうしようもありません。
だから、
「自分で自分に明確な指示が出せる」
ようにすれば、
あいまいな指示が苦手なASDの子にとって、少しは楽になれる。
図書館や書店に行けば
専門的な良質の本に出会えます。
そこで知識を吸収して
「自分で自分に指示を出せるスキル」を
作り出して欲しい、と思うのですが、
その専門的な本に出会えても、
まったく知らないと、その本を
読みこなせません。
なので、その橋渡しができるような
冊子になれればいいな、と
思って、「ASDの子が癇癪おこさず」シリーズを作成&アップしました。
また、定期的に、
「れくす先生の歴史授業」と
並列して
過去につくった「ASDの〜」シリーズも
アップしていきたいと思いますので
これからもよろしくお願いいたします。