新☆歴史模擬授業 第三回 ゲルマン民族の大移動・十字軍です。
詳細は,この前の記事①をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーー
キンコーンカンコーン
 「さて,今日は古代ローマ帝国(西ローマ帝国)が滅亡したところから,13世紀ころのまでの
「さて,今日は古代ローマ帝国(西ローマ帝国)が滅亡したところから,13世紀ころのまでの
ヨーロッパの歴史をザッと見ていきますね。」
 「はい!」
「はい!」
 「では,まず前回の復習をば。
「では,まず前回の復習をば。
古代ギリシャ・ローマで,(今の数学・理科などの基礎となる)発達した学問と
民主主義が誕生・発展し,
西ローマ帝国の滅亡により,
その文明が一時的に西ヨーロッパから失われた。
しかし,そのギリシャ・ローマ文明は,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)と
イスラーム教徒による国家により保存されていた,ということは前回話したよね。」
 「はい。」
「はい。」
 「じゃあ,まず何によって西ローマ帝国が滅んだのか,から見ていこう。」
「じゃあ,まず何によって西ローマ帝国が滅んだのか,から見ていこう。」
 「そういえば,なぜ滅んだかを聞いてなかった・・。」
「そういえば,なぜ滅んだかを聞いてなかった・・。」
 「ヨーロッパっていうと,みんな,どちらかというと都会!というイメージがあるよね。」
「ヨーロッパっていうと,みんな,どちらかというと都会!というイメージがあるよね。」
 「うん。フランスとかでショッピング旅行する子もいるってよく聞くしね。」
「うん。フランスとかでショッピング旅行する子もいるってよく聞くしね。」
 「でも,(イタリアなどの地中海を除いて)ヨーロッパが都会になったのは,ずっと後のことで,
「でも,(イタリアなどの地中海を除いて)ヨーロッパが都会になったのは,ずっと後のことで,
この時期のヨーロッパは,乾燥して寒冷な地域,森林が広がっている地域などが多いの。
だから,厳しい自然条件によって,人々はよく移動をした。
さらに,人口増加がおこると,農地が不足するから,食料不足がおきる。
だから,生きるために新たな土地を探して,そこに住んでいる民族単位で大きな移動がおこったり。」
 「寒すぎる場所とか乾燥しすぎる場所,森林が多いと,
「寒すぎる場所とか乾燥しすぎる場所,森林が多いと,
なかなか人間が食べられる植物が育たなかったりするものね・・。」
 「西ヨーロッパでは,古代ギリシャやローマができる時代のずーっと前から,
「西ヨーロッパでは,古代ギリシャやローマができる時代のずーっと前から,
民族の大移動はあったんだけど,
4世紀後半に,ヨーロッパの歴史変えるほどの大きな大移動がおこったの。
それをゲルマン民族の大移動と言います。」
 「ゲルマン民族っていう民族が移動したんだ。」
「ゲルマン民族っていう民族が移動したんだ。」
 「ゲルマン民族というのは,フランス人やドイツ人・イギリス人など,
「ゲルマン民族というのは,フランス人やドイツ人・イギリス人など,
現在のヨーロッパでみんながよく知っている国に住んでいる人々だと思っていいわよ。
(イタリア・スペインなどはラテン民族,アイルランドはケルト民族なので違いますが・・。)」
 「はい。」
「はい。」
 「ゲルマン民族が大移動して,ヨーロッパの各地に住み,自分たちの王国を建て始めます。
「ゲルマン民族が大移動して,ヨーロッパの各地に住み,自分たちの王国を建て始めます。
そして,ついに476年にゲルマン人の一派が西ロ―マ帝国を滅ぼし,自分の国を建てます。」
 「西ローマ帝国が滅んだのは,ゲルマン民族の大移動によるものだった。」
「西ローマ帝国が滅んだのは,ゲルマン民族の大移動によるものだった。」
 「そういうことです。
「そういうことです。
そして,イタリアを含む,イギリス・フランス・ドイツを中心とした西ヨーロッパ世界は,
新しい時代に入っていきます。」
 「ほえー,ここで,いったん頭の区切りをつけるのね。」
「ほえー,ここで,いったん頭の区切りをつけるのね。」
 「そういうこと。話の区切りをつけて歴史を見ていくことはすっごく重要なの。」
「そういうこと。話の区切りをつけて歴史を見ていくことはすっごく重要なの。」
 「えへへ。」
「えへへ。」
 「西ローマ帝国滅亡までを古代とし,その後1000年ほどの時代を中世と言います。
「西ローマ帝国滅亡までを古代とし,その後1000年ほどの時代を中世と言います。
日本でも,古代・中世という区分はあるけど,日本の時代とは年代的に誤差があるので注意してね。
日本は古代は12世紀の平安時代まで,中世は鎌倉~室町時代のことだから。」
 「はい。」
「はい。」
 「で,中世の西ヨーロッパは,(細かい部分は省き,結果的に)
「で,中世の西ヨーロッパは,(細かい部分は省き,結果的に)
精神的にはキリスト教を中心としたローマ教皇を中心に,
実質的には,地方の有力者,つまり封建領主(諸侯)を中心に生活していきます。
それぞれの国に王様はいたんだけど,実質的な力はあまりなくて,
ほぼ封建領主(諸侯)をまとめる代表役,って感じ。
また,原則物々交換をし,多くの人々が自給自足の生活をしていました。」
 「自給自足ってことは,自分の食べ物は自分で作って食べる。
「自給自足ってことは,自分の食べ物は自分で作って食べる。
スーパーとかで買って,とかじゃない,ということだね。」
 「うん。スーパーとはここ最近のものだから当然この時代にはないけど,
「うん。スーパーとはここ最近のものだから当然この時代にはないけど,
お金を交換してモノを売る市場(という形態)というものが古代ローマにはあったけど,
中世の西ヨーロッパにはなくなっていたの。」
 「ほえー。」
「ほえー。」
 「かんたんに言えば,中世ヨーロッパでは,
「かんたんに言えば,中世ヨーロッパでは,
キリスト教という大きい精神的なつながりで人々は結ばれていて,
日々の生活は自分の住む周りで小さくほそぼそと生きていた,と思って。」
 「はい。」
「はい。」
 「そういう風に西ヨーロッパの人々が生活をしていった時代に,
「そういう風に西ヨーロッパの人々が生活をしていった時代に,
東ヨーロッパ世界や西アジアの地域はどうだったか,を見ましょう。
東ヨーロッパでは,西ローマ帝国のかたわれ,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)が君臨していました。
東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は古代ローマ帝国の形式も文化も多く引き継いでいたし,
西ヨーロッパとは違って,皇帝の力で人々はまとめられていたし,
グローバル(国際的に)色々な地域と交流し,貿易がさかんだった。」
 「古代ローマ帝国のような感じがそのまま残ったんだね。」
「古代ローマ帝国のような感じがそのまま残ったんだね。」
 「そういうこと。
「そういうこと。
で,そんな東ローマ帝国(ビザンツ帝国)を脅かす存在が登場した。
それが,イスラーム勢力です。
7世紀に誕生したイスラーム教を信じる人々が,
7世紀から,現在の,シリアやイラク,イランやトルコやエジプトなどに
次々と強い王朝をたてていきます。」
 「そうだったんだ。」
「そうだったんだ。」
 「それが東ヨーロッパと西アジアの地域の話。
「それが東ヨーロッパと西アジアの地域の話。
また西ヨーロッパに話しを戻します。
この間,西ヨーロッパはほそぼそと自給自足の生活を営み,力をつけていきます。
その時期は,農業技術が進歩して,比較的気候が温和だったせいもあり,
どんどんと生活が豊かになり,人口が飛躍的に増加してきていました。
それで,だんだんと,それまでウチにこもっていた西ヨーロッパ世界の人々が外に目を向け始めたのよね。」
 「ウチにこもって,どんどんと力をつけていったんだ・・。」
「ウチにこもって,どんどんと力をつけていったんだ・・。」
 「うん。
「うん。
このように,外に目が行き始めた西ヨーロッパ世界,
古代ローマ帝国を引き継いだ東ヨーロッパ世界,
勢いのあるイスラーム世界が,
ついに直接出会う大きな事件がおきます。
それが11世紀末から始まった,十字軍というものです。」
 「ほえー。ついに3つが出会うときが!」
「ほえー。ついに3つが出会うときが!」
 「きっかけは,聖地イェルサレム(エルサレム)を支配においた,
「きっかけは,聖地イェルサレム(エルサレム)を支配においた,
あるイスラーム王朝(セルジューク朝),
ついで東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の領地までおびやかしそうになりました。
それで,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の皇帝が,西ヨーロッパのローマ教皇に助けてくれ!と頼んできました。
そして,ローマ教皇は,「聖地イェルサレムを回復しよう!(聖地をヨーロッパの手に戻そう!)」と唱え,
それに,各地域の諸侯たちが参戦し,軍をつくりました。
その軍を十字軍と言います。」
 「ほえ?聖地回復?東ローマ帝国(ビザンツ帝国)を助けよう?ではなくて?」
「ほえ?聖地回復?東ローマ帝国(ビザンツ帝国)を助けよう?ではなくて?」
 「・・というか,聖地ってなに?」
「・・というか,聖地ってなに?」
 「2人とも良い質問だね。
「2人とも良い質問だね。
聖地というのは,神や聖人などに関係ある神聖な土地のこと。
イェルサレムは,キリスト教にとってはキリスト教の始祖イエス=キリストの誕生の地であり,
イスラム教にとっては,イスラーム教の始祖ムハンマドの最期の場所なので,
イェルサレムは,キリスト教にもイスラーム教にとっても大切な場所なの。
(※イェルサレムはユダヤ教の聖地でもあるので,これが現在の中東問題・パレスチナ問題に関係してきます。)
だから,イスラーム教からしたら,聖地を自分の配下におくのは当然だし,
逆にキリスト教からしても,聖地を奪い返したい!という気持ちは当然といえば当然なのね。」
 「お互いの考えがあるのね。」
「お互いの考えがあるのね。」
 「そういうことね。
「そういうことね。
たいがい,戦争や争いというのは,それぞれの正義によって1つのものを取り合おうとするから
おこるものだからね・・。」
 「うーん。」
「うーん。」
 「十字軍は,11世紀の末から約200年,7回も行いました。」
「十字軍は,11世紀の末から約200年,7回も行いました。」
 「え!200年も?」
「え!200年も?」
 「じゃあ,最初に十字軍に参加した人は,もう7回目ではこの世にいないじゃん!」
「じゃあ,最初に十字軍に参加した人は,もう7回目ではこの世にいないじゃん!」
 「そうなの。
「そうなの。
しかも,毎回,その十字軍を構成する中心メンバーが違うものだから,脇道にそれたりすることも。
1回目はまじめーに聖地奪回!という感じだったのが,
第四回のときは聖地回復の目的を捨てて,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の首都を占領して
新しい国を経てちゃったりね。」
 「え,仲間同士なのに・・。」
「え,仲間同士なのに・・。」
 「東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の首都は商業がさかんな国際貿易都市でね。
「東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の首都は商業がさかんな国際貿易都市でね。
そこで,この時期に力をつけてきた,イタリアの商人たちが自分たちの利益を拡大しようとして
十字軍に要求してね。」
 「ほえー。だんだんと,本来の目的がおかしくなっていったのね。」
「ほえー。だんだんと,本来の目的がおかしくなっていったのね。」
 「十字軍は,名目上は聖地回復だったけど,参加者それぞれの意図が複雑にからみ合ったもので。
「十字軍は,名目上は聖地回復だったけど,参加者それぞれの意図が複雑にからみ合ったもので。
ローマ教皇からしたら,古代ローマ帝国の分裂で分かれていた西と東のヨーロッパを教会を統一しよう!
諸侯は,自分の領地拡大や戦利品を目当てに,
さきほど話したイタリアの商人たちは商業的利益を拡大しようと,という意図があってね。」
 「ほえー。」
「ほえー。」
 「その後,フランス国王が単独で十字軍を結成したりしましたが,ついに失敗に終わりました。
「その後,フランス国王が単独で十字軍を結成したりしましたが,ついに失敗に終わりました。
それが13世紀。」
 「そうだったんだ。」
「そうだったんだ。」
 「十字軍は失敗でした。
「十字軍は失敗でした。
でも,この十字軍によって,西ヨーロッパ世界は大きく180度変わったといっても過言ではないんです。」
 「え・・。」
「え・・。」
 「3つの点で大きな変化があったの。
「3つの点で大きな変化があったの。
政治・経済・文化の3つの点で。
まずは,政治の分野。
十字軍により権力を持つ人が代わります。
それまでは,権力者はローマ教皇・諸侯たちでしたが,十字軍で遠征を指揮した国王が
しだいに力をつけることになっていきます。それが16世紀の,王様が一番つよい政治(絶対王政)に
つながっていきます。」
 「十字軍そのものは失敗だったから,その中心人物だった教皇たちは弱くなってしまったのね・・。(予想)」
「十字軍そのものは失敗だったから,その中心人物だった教皇たちは弱くなってしまったのね・・。(予想)」
 「2つ目は経済の点。十字軍で道が開かれたから,
「2つ目は経済の点。十字軍で道が開かれたから,
地中海を中心にした貿易がさかんになって,
西ヨーロッパと,東ヨーロッパ・イスラーム世界の人々と
交流がさかんになるの。
そうすると,西ヨーロッパは東からの文化なども伝わってくるわけよ。
それが3つの目の変化の点。文化にも変化が。」
 「人が行き来すれば,文化も一緒に入ってくるもんね。」
「人が行き来すれば,文化も一緒に入ってくるもんね。」
 「前回のお話で,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は古代ローマの文化を受け継いでいた,と話したよね。
「前回のお話で,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は古代ローマの文化を受け継いでいた,と話したよね。
また,イスラームの王朝も,古代ギリシャの文化を勉強していました。
西ヨーロッパは,西ローマ帝国滅亡後,キリスト教中心の文化になっていたよね。」
 「うん。つまり,西ヨーロッパは古代ギリシャ・ローマの文化からキリスト教中心の文化になっていたんだよね。」
「うん。つまり,西ヨーロッパは古代ギリシャ・ローマの文化からキリスト教中心の文化になっていたんだよね。」
 「そういうこと。そうすると,西ヨーロッパが,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)やイスラームと
「そういうこと。そうすると,西ヨーロッパが,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)やイスラームと
十字軍を通して接して,またその後の交易を通して,交流をしたら・・。」
 「あ,西ヨーロッパに,ふたたび,古代ギリシャ・ローマの文化が入ってくる!」
「あ,西ヨーロッパに,ふたたび,古代ギリシャ・ローマの文化が入ってくる!」
 「正解!古代ギリシャ・ローマの文化というのは,
「正解!古代ギリシャ・ローマの文化というのは,
民主主義を基本とした人間らしく合理的な文化だった。
それが西ヨーロッパに伝わり,その文化が華やぐのが14世紀のルネサンス。」
 「ほえー。十字軍によって,いろんなことが変わったのね。」
「ほえー。十字軍によって,いろんなことが変わったのね。」
 「そういうことね。十字軍によって,古代のものがまた新しい形で復活することになった,ということです。
「そういうことね。十字軍によって,古代のものがまた新しい形で復活することになった,ということです。
それは次回行います。
では最後に。
今回習った分野も,古代同様,あまり高校入試では出題はされないんだけど,
ゲルマン民族の大移動,東ローマ帝国(ビザンツ帝国),十字軍,という言葉は
私立高校入試で出題されることもあるので覚えておきましょう。」
 「はい!」
「はい!」
 「では,これで終わります!起立!礼!」
「では,これで終わります!起立!礼!」


 「ありがとうございました!」
「ありがとうございました!」
キンコーンカンコーン
※「ゲルマン民族」は「ゲルマン人」と,「イスラーム」は「イスラム」と表記される場合あります。
※わかりやすく解説していので、「こういう説もある!」という専門的なことを
引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。
不快な気持ちになった方には申し訳ありません。
ーーーーーーーーー
ランキングに参加しております。
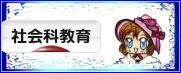
にほんブログ村





















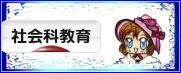










 十字軍までは,現在参考にさせて頂いている教科書には
十字軍までは,現在参考にさせて頂いている教科書には

 「はい!」
「はい!」 「そういえば,なぜ滅んだかを聞いてなかった・・。」
「そういえば,なぜ滅んだかを聞いてなかった・・。」 「うん。フランスとかでショッピング旅行する子もいるってよく聞くしね。」
「うん。フランスとかでショッピング旅行する子もいるってよく聞くしね。」 「寒すぎる場所とか乾燥しすぎる場所,森林が多いと,
「寒すぎる場所とか乾燥しすぎる場所,森林が多いと, 「うーん。」
「うーん。」 「ほえー。だんだんと,本来の目的がおかしくなっていったのね。」
「ほえー。だんだんと,本来の目的がおかしくなっていったのね。」 「十字軍そのものは失敗だったから,その中心人物だった教皇たちは弱くなってしまったのね・・。(予想)」
「十字軍そのものは失敗だったから,その中心人物だった教皇たちは弱くなってしまったのね・・。(予想)」 「あ,西ヨーロッパに,ふたたび,古代ギリシャ・ローマの文化が入ってくる!」
「あ,西ヨーロッパに,ふたたび,古代ギリシャ・ローマの文化が入ってくる!」

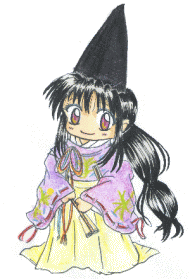 私はある別ブログで,
私はある別ブログで,


 が降ってきてしまったので,目標の半分の歩数で終わってしまいましたが,
が降ってきてしまったので,目標の半分の歩数で終わってしまいましたが,
