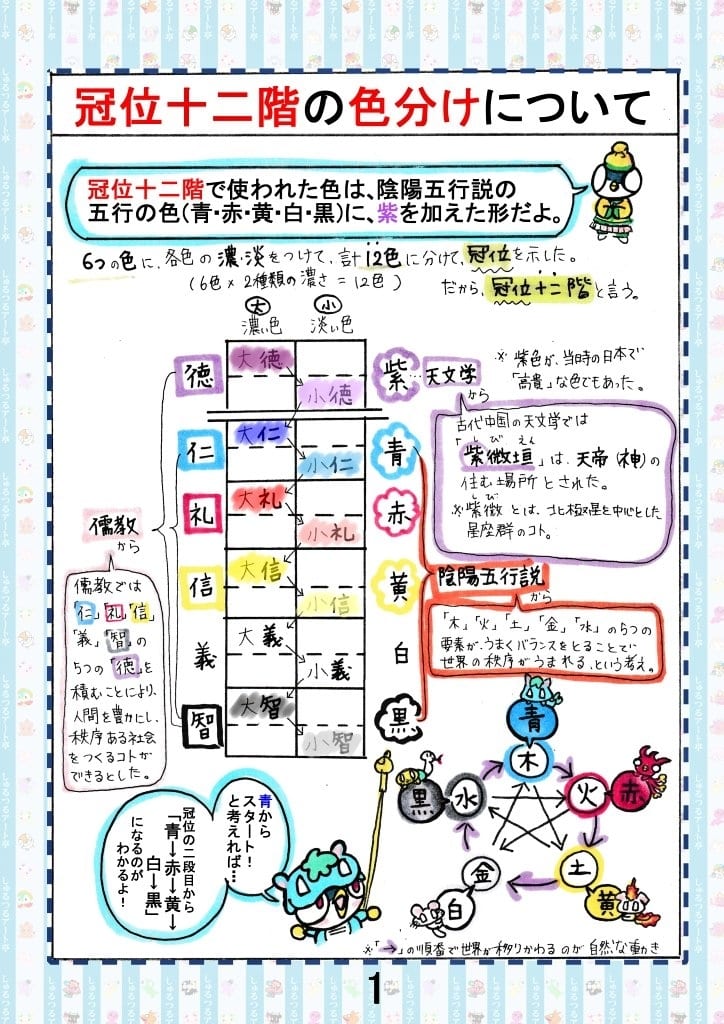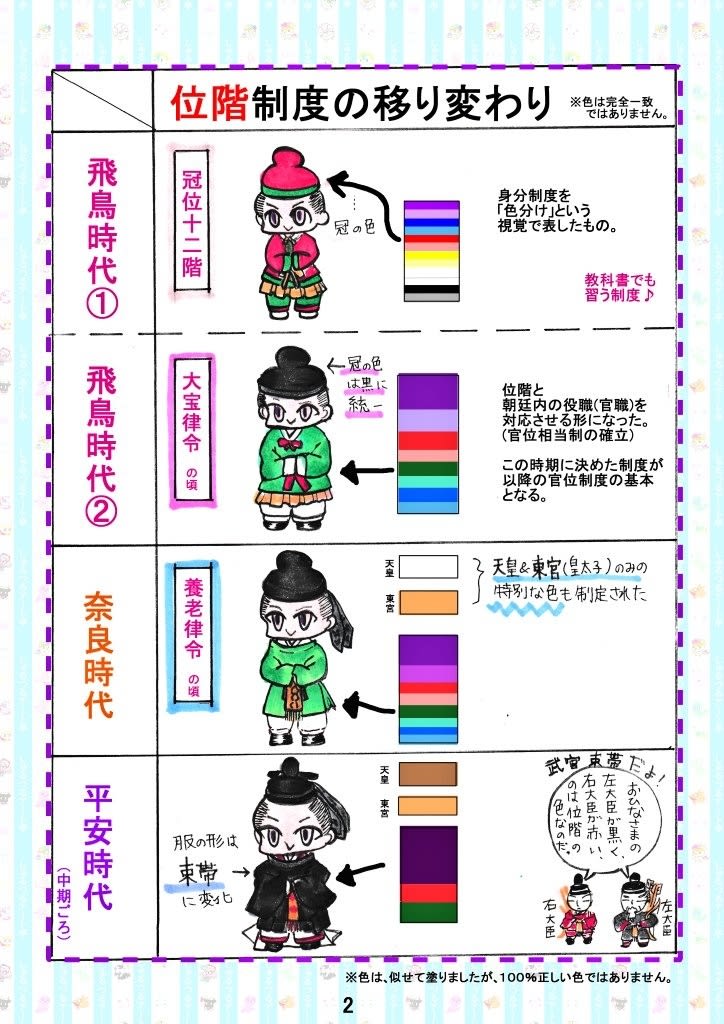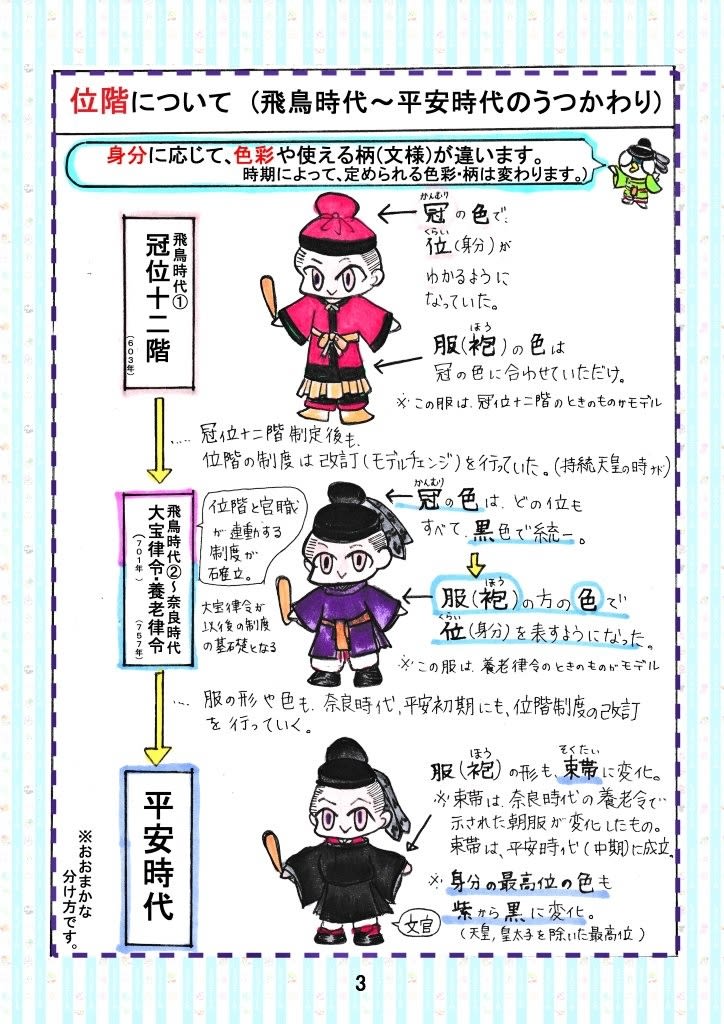みなさま、本日もありがとうございます。
更新がノロノロすぎて申し訳ないのですが、「れくす先生の歴史授業」の続きが書けましたのでアップさせていただきます。
可能な限り、定期的に更新できるようにしたいです。
現在、子育ての方向性で悩んでいて、なかなか記事を書けない状態が続きまして・・・。
れくす先生の歴史模擬授業シリーズです。
今回は、第5回 古代の文明①(導入編) の話です。

※この授業のコンセプトは第1回の内容をご覧ください。
「古代文明」の分野は、中国文明以外は私立中学入試ではあまり出ない分野です。
中学生になってから初めて習う内容のことが多いです。
(私立中学入試で絶対に出ない、とは言えないので、受験予定の学校の過去問の確認をオススメします。)
テスト勉強のために用語を覚える、という意味では
最初から用語をしっかりバシバシ入れた方がわかりやすいと思います。
ただ、今回のシリーズは、
「はやく覚えないと誰かに人格否定される、という不安感でパニックになることを
防いで、落ち着いて、学校とは関係なく、受験勉強し続ける」というのが目的の1つなので
「用語を受け入れる前に下地を作る→その後でテストで用語をバシバシ出す」
・・・という形にしています。
今回から、何回かに分けて、
世界史の部分、文明の誕生と代表的な文明を見ていきます。

今回は、導入のみを扱い、
次回から、各文明を見ていきます。
歴史の内容を習うとき、
「どこに視点をおいて、その歴史を見ていくか」
「あらゆる情報をどう整理していくか?」
というのを先に先生に提示してもらえると、
具体的な内容に入ったときに、頭に入りやすかった経験がありました。

そのため、
初めての分野をお話するときは
「ここは、ここに立って、歴史を見ると良いよ」と話したいと思います。
ではでは始めます。
1 文明の誕生
(1)文明とは
文明は、ある日、突然、作られたわけではありません。
約1万年前に間氷期に入り、新しい環境になり、
その新しい環境に慣れるために定住生活をするようになったことから、徐々に、文明が形作られました。
では、「文明」とは、いったいどういうものなのでしょう?
文明とは、「豊かな生活(当時)を送れるようになった、実質的な状態」のことです。
その状態を具体化したもの、例えば、大きな建物や文字などを
私たちは「文明」とイメージしています。
「文明=豊かな生活」の象徴が
・大きな建物などの集団で力を合わせて作ったものが存在している(存在していた)。
・決まった身分または役職、に従って、社会全体が動いている。
・1つの法則(暦や文字など)で、住民がコミュニティをとり、それに基づいた生活をしている。
・1つの価値観(宗教・法など)で、一定数の人間が考え方を共有している。
・金属器(青銅器など)という高度な技術と集団作業を必要とするものを作成している。
・・・などになります。
各文明には、形が違っても、似たようなものが存在しています。
(2)文明ができるメカニズム
農耕・牧畜を行うことがメインの生活になった人々が多くなり、
様々な地域で、同じ場所に住む生活(定住生活)が始まりました。
同じ人間達で暮らすので、小さな集団コミュニティができてきます。
その生活コミュニティを「ムラ」と言います。
そして、そこで、食料を計画的に生産して蓄えるようになってきました。
場所や、能力の差、運、などによって、蓄えに差が出てきます。
「蓄え」を別の言い方で言うと「富(とみ)」になります。
蓄え(富)の差が、そのまま、貧富の差になっていきます。
そして
この「蓄え=富」を巡る戦いがおき、そこで勝利した者や
農作業や(豊穣の祈りなどの)祭りを指揮していた者、などの中から
強い権力を持つ支配者が出てきました。
そうして、1つの集団コミュニティ内で、支配者・被支配者が生まれ、
だんだんとそれが、次世代に引き継がれるなどして固定化していきます。
(もしくは、支配者が次々と変わっていく形)
その結果、1人のリーダー(または1つの組織や1つの固定集団)が支配者になり、被支配者を動かすことになります。
こういうと、嫌がる被支配者を支配者が強制的に動かそうとしている、というイメージを持つ人もいるかもしれません。
中にはそういう人々もいたでしょう。
でも、今のように「先祖が残した建物や知識」があるわけでなく、
「0」から、その「建物」「知識」を作っていった時代なのですので、
「優れたリーダーに従った人々が、力を合わせて、建物やルールを作っていった」
と思った方が、私はしっくりきます。
暦がないと、農作業はできません。
暦に従って農作業することで、計画的に種をまき、育て、収穫することで、
食べられる農作物を多く、手に入れることができます。
集団をまとめるには、その場にいる人だけでなく、空間や時間を超えて、情報を伝える必要があります。
それを実現するツールが文字になります。
文字そのものは、「文明」に必須アイテムというわけではありませんが、
文字がない場合は、別の意思伝達共通手段があったと思われます。
世界各地には様々な文明があります。その中で、「◎◎文明」という名称がついた状態で中学生レベルで
習う4つの文明は4つになります。
4つの文明は、
メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明。
(昔は、この4つの文明をまとめて、四大文明と言っていましたが
現在ではその括りの用語は使いません。)
また、他にも「文明」という括りでは「用語」として中学では聞かれることはありませんが、
メソポタミア文明・エジプト文明と時代的、文化的にリンクしている、
古代ギリシャ、古代ローマも扱っていきます。
(ギリシャは、エーゲ文明や、クレタ文明、ミケーネ文明などの用語はありますが、
中学では「◎◎文明」としては扱わず、ミケーネ文明後のポリス社会の古代ギリシャのみを扱います。)
話を、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明の話に戻します。
文明の内容を覚える(理解していく、情報整理していく)ときに・・・
a:文明名とその場所
・・・その文明が存在したところが、現在のどの地域(国名)にあったものか?までチェック。
文明関係だけでなく、歴史を学ぶとき、場所も一緒に覚えることは大切。
b:文明があった川(大河)の名前
・・・大河(大きな川)が近くを流れているからこそ、農耕もでき、大きな荷物も運ぶことができます。
そのようなことから、文明の発祥には、大河の存在は、ほぼ必須とも言えます。
(地域によっては、大河がない文明もありますが、中学で習う文明では大河は必須です。)
c:文字
・・・必ずしも、どの文明にも「文字」が存在しているわけではないですが、
中学レベルで習う文明は、すべて文字が存在している文明になります。
そして、この文字があったからこそ、現代の我々は、その時代の歴史を多く知ることができます。
d:建物、遺跡
・・・現存している建物もあれば、かつて建物があったとされる痕跡のある場所(遺跡)もあります。
建物や遺跡から、当時の人々がどういう暮らしをしていたのか?政治形態はどのようであったのか?を推測することができます。
e:王朝・国家名
・・・各文明内で、ずっと同じ一族や地域がトップに立っているわけではないので、王朝の移り変わりはあります。
しかし、中学では、中国の王朝以外は、王朝名は、ほとんど扱いません。
※王朝とは?:歴史の分類方法の1つ。君主が歴代同じ血筋の人になる、または、同じ君主のタイプで国を支配するごとに、
1つのまとまりで考える。
f:その他
・・・その文明で使われた、暦やきまり、宗教、学問(数学など)など。
・・・・の6つの項目に分けて見ていくと良いです。
その文明の時期(◎◎年頃、××年前など)はチャックして、
頭を整理していく必要がありますし、時期を覚えるにこしたことはありません。
ただし、細かい暗記(語呂合わせ年号など)に固執する必要はありません。
ただし、その文明が一番古いか?同時期の文明の動き、文明同士の交流はあったのか?などは考える必要はあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回は以上です。
次回から具体的な内容に移りたいと思います。
ご覧いただき、ありがとうございました。