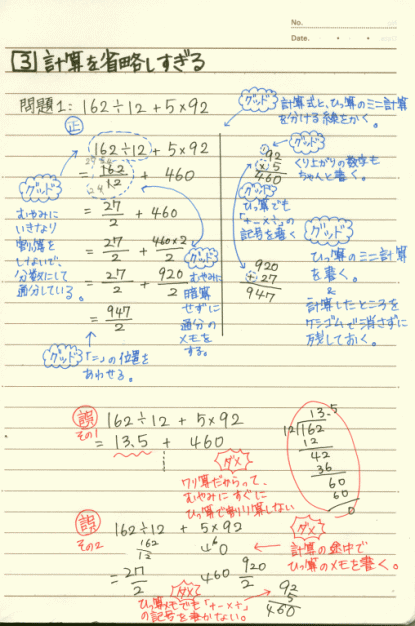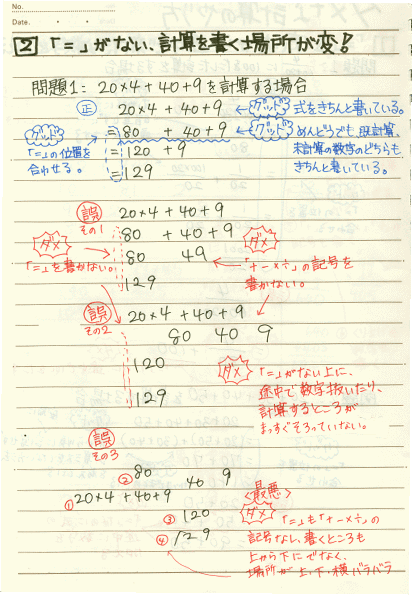今回は,勉強方法として
頭で論理的に考えるのが良いのか?
それとも
心で直観的に感じとるのが良いのか?
というお話です。
A 「頭での理解を優先し、理論を考えることで大成する」方法
B 「細かいところを見るより、全体を見て、頭より心で感じ取って、
反復練習を行い大成する」方法、
どちらが良いでしょうか?
これは、こっちが良い!というよりは、
場合によって使い分けることで良い結果が残せると思います。
主要五教科(国語、数学、社会、理科、英語)は、Aの理論的に考える方が良いです。
Bのような感覚的なアプローチでやって成功するのは小学校までで、
そのやり方をそのまま中学で続けていくと、中2あたりから、うまくいかなくなってしまいます。
高校では授業についていけなくなるかもしれません。
では、Bの感覚的なやり方は何に適するか、ですが、
これは技能4教科、とくに、体育や芸術分野(音楽・美術)です。
この分野は、もちろん理論も大切なんですが、
とにかく、その技法をやり続けることで、なんとなくその世界観がわかってくるのです。
そして、無意識に条件反射のように出来るようになってくればオッケーです。
(教える立場にたったら、理論も教える必要はありますが。)
では、ここで問題です。
英会話はAの理論的アプローチとBの感覚的アプローチ、どちらのタイプになるでしょうか?
答えは、Bの感覚的、反復練習が大切な方になります。
さて、では学校で習う、受験英語は?というと、Aの論理的思考を必要とする方です。
ですから、いくら、受験英語を勉強しても、英会話ができるわけありません。
そして,英会話ができるからって,学校の英語のテストで点数がとれるわけではありません。
ここで大切になのは、その事実について、みなさんは、どういう結論を導き出すか、ということです。
おそらく、多くの方は、
「英語がしゃべれなきゃ、国際社会に通じないじゃん!じゃあ、学校で英語は習った意味ない!」とか、極論では「受験英語の勉強は悪」と思うかもしれません。
でも、私はその結論には大反対!なんです。
「受験英語にも意味が大いにあります!」と。
言語を論理的に考えることは、その言語を話す民族の伝統的価値観や生き方が理解できます。
人類に必要なものの1つには、
「相手を理解する力」で、
とくに異質の性格、価値観を持つ相手を理解するには、そうとうな努力と能力を必要とします。
もし「異質な価値観の相手を理解」できれば、
戦争という人類がどれだけ長い年月をかけても根絶できなかったものを、消し去ることができると思います。
戦争の多くは、宗教対立、政治体制の対立でおこるのだから。
だから、受験英語は受験英語として、英会話は英会話という授業を設けて学ばせれば良いと、私は思います。
今は、中途半端に、英会話を受験英語に入れ込み、どちらも適当になってしまってるのが現状だと。
これは、かなり時間と労力を必要とする改革が必要だから簡単にはいかないし、
さまざまな意見があるから、実現は難しいですが、
私は、そのようなスタンスでやり続けたいと思います。
※私の意見は1つの意見で、それが絶対的に正しいものではありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※現在,過去の記事を削除・編集しております。その中の記事の中でいくつかピックアップして
ブログに再度アップしています。この記事はその1つです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ランキングに参加しております。ぽちっと押して頂けると嬉しいです♪


























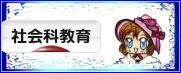



 が、かまって!と言わんばかりの顔で机で待ちかまえていたので、思わず、勉強を始めちゃいました。
が、かまって!と言わんばかりの顔で机で待ちかまえていたので、思わず、勉強を始めちゃいました。

 )
)
 今回は塾に通っておられるみなさん&保護者の方々へのお話です
今回は塾に通っておられるみなさん&保護者の方々へのお話です また、今の塾に不満を持っている方は、
また、今の塾に不満を持っている方は、
 また、小5の生徒さん(と親御さんたち)は
また、小5の生徒さん(と親御さんたち)は



 たとえば、辞書。
たとえば、辞書。