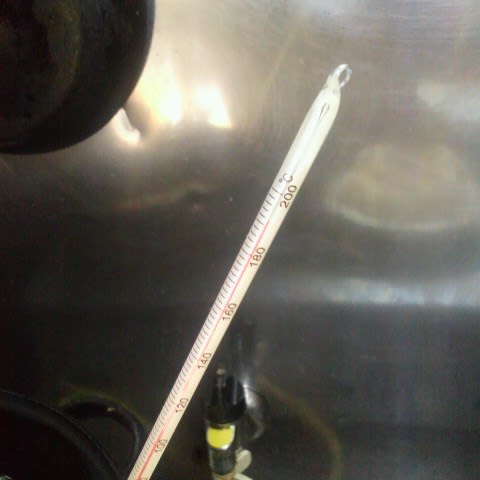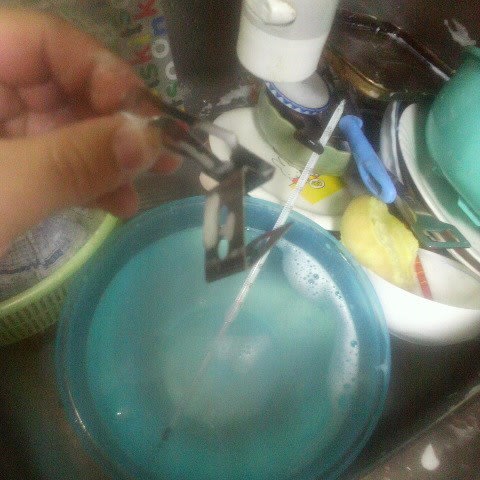出汁を取った後の昆布って、瞬間、処理に迷いませんか?

普通は佃煮にしたり、ふりかけにするようだが、
自分はどうも塩辛い・甘辛いのが苦手で、佃煮は魚卵が入っているのなら、贅沢だけれど、少しは食べるんだけれど。
で、捨てるのは勿体無いからいろいろ調べてみると・・・
そういう時は、昆布の水分を拭いて

塩とか味塩をふって(昆布自体も海のモノだしやや塩気がある素材だから塩の量に注意)

キッチンペーパーではさんで

様子を見ながらレンチンをする

(自分は500wで30秒温め、

1度庫内の蒸気を逃してからひっくり返して更に30秒ぐらいでいいのでは?と)

すると、昆布がボコボコのパリパリの昆布煎餅みたいになる。

これは身体に良さそう。
因みに、上下の紙をきちんとしないと、レンジ内部に昆布の破片が飛んで

結構、拭き掃除が大変。
その乾燥した昆布をフードプロセッサーへ。

細かくなりきらないので、すりこぎ的に麺棒で壊すと、

昆布パウダー(パウダーって程、細かくはならないかもしれないけれど、納豆や汁物に入れても面白いかも)に。
又、出汁を取った昆布を乾燥させず、更に水に漬けておいて、豆腐も漬けて、

湯豆腐に。薬味と醤油、飽きたら酢と醤油で。

魯産人風とまでは言わないが、これで酒か焼酎を一杯やるとたまらない。
↓
余ったら、翌日温め、味噌を溶いて

豆腐の味噌汁に。

ダシがこれでもか!!と効いているので、味噌は薄味でも、十分、味がある、スゴイモノが出来る。

普通は佃煮にしたり、ふりかけにするようだが、
自分はどうも塩辛い・甘辛いのが苦手で、佃煮は魚卵が入っているのなら、贅沢だけれど、少しは食べるんだけれど。
で、捨てるのは勿体無いからいろいろ調べてみると・・・
そういう時は、昆布の水分を拭いて

塩とか味塩をふって(昆布自体も海のモノだしやや塩気がある素材だから塩の量に注意)

キッチンペーパーではさんで

様子を見ながらレンチンをする

(自分は500wで30秒温め、

1度庫内の蒸気を逃してからひっくり返して更に30秒ぐらいでいいのでは?と)

すると、昆布がボコボコのパリパリの昆布煎餅みたいになる。

これは身体に良さそう。
因みに、上下の紙をきちんとしないと、レンジ内部に昆布の破片が飛んで

結構、拭き掃除が大変。
その乾燥した昆布をフードプロセッサーへ。

細かくなりきらないので、すりこぎ的に麺棒で壊すと、

昆布パウダー(パウダーって程、細かくはならないかもしれないけれど、納豆や汁物に入れても面白いかも)に。
又、出汁を取った昆布を乾燥させず、更に水に漬けておいて、豆腐も漬けて、

湯豆腐に。薬味と醤油、飽きたら酢と醤油で。

魯産人風とまでは言わないが、これで酒か焼酎を一杯やるとたまらない。
↓
余ったら、翌日温め、味噌を溶いて

豆腐の味噌汁に。

ダシがこれでもか!!と効いているので、味噌は薄味でも、十分、味がある、スゴイモノが出来る。