「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」というフレーズは、これまでお会いした中で霊長類学者の河合雅雄氏から、そして動物行動学者の日高敏隆氏からご教示いただいた言葉である。それぞれの研究の立場からのアプローチは異にするものの、この先、人類はどこに向かっていくのか、進化か退化といった遠大な命題が仕込まれたフレーズなのである。
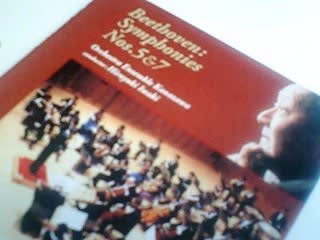 ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。
ヒトは都市化する動物であるとすれば地域の過疎化は当然至極、流れに棹をさす地域再生に向けた研究自体は無駄である。しかし、商品経済にほだされて、都会へと流れ生きる現代人の姿がヒトの一時的な迷いであるとすれば、自然と共生しながら生きようとするヒトを地域に招待し応援することは有意義である。私なりにこの命題を自問自答していたとき、これまで聴こうとしなかった7番の第1楽章と第2楽章に耳を傾けたみた。第2楽章の短調の哀愁的な響きにヒトの営みの深淵を感じ、目頭が熱くなるほどの感動を得た。そして、ベートーベンの曲想の壮大なスケールに気づき、7番の主題は「ヒトはどこから来て、どこへ行くのか」のテーマそのものではないのか、と考えるようになった。ここから「つまみ食い」の愚かさを知り、第1楽章から第4楽章までをトータルで聴くようになった。1月上旬のことだった。
2月下旬、研究費の申請を終えて、自宅に帰り、ある意味で孤独な戦いを精神的に支えてくれたベト7に、そして指揮した岩城さんとオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)に感謝した。
私は音楽的な教養や才能を持ち合わせてはいない。ネットで調べると、ベートーベンは5番運命を1808年に完成させ、スランプに入り、4年後に7番を完成させた。42歳のとき。初演は1813年12月。ナポレオンに抗したドイツ解放戦争で負傷した兵士のための義援金調達のチャリティーコンサート(ウィーン大学講堂)で自ら指揮を執った、という。戦時中なので聴衆の士気を高めるテンポのよさ、未来へと突き進む確信とっいったものが当然込められていた。そして、静かに心を振るわせる前段の葬送風の響きはこの戦争で亡くなった者たちへの弔い、あるいは戦争の理不尽さを嘆き悲しむメッセージかもしれないとも想像する。
先日、学生の携帯電話の着メロで7番が鳴っているのを聴いた。テレビドラマの「のだめカンタービレ」で人気だとか。7番はいろいろなCDが出ている。私だったら、岩城指揮のOEKのベト7を推薦する。1番から9番までを2度も連続演奏するほどにベートーベンを愛した指揮者の演奏には「違い」というものあるからだ。
⇒11日(日)午後・金沢の天気 雪










 聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。
聴いているベト7は2002年9月にオーケストラ・アンサンブル金沢が石川県立音楽堂コンサートホールで録音したものだ。指揮者は岩城宏之さん(故人)。はまり込んだきっかけは、岩城さんがベートーベンのすべての交響曲を一晩で演奏したコンサート(2004年12月31日-05年1月1日・東京文化会館)での言葉を思い出したからだ。演奏会を仕掛けた三枝成彰さんとのトークの中で岩城さんはこんな風に話した。「ベートーベンの1番から9番はすべてホームラン。3番、5番、7番、9番は場外ホームランだね」「5番は運命、9番は合唱付だけど、7番には題名がない。でも、7番にはリズム感と同時に深さを感じる。一番好きなのは7番」と。 から量刑を軽く」と弁護士は公判の中でまくしたて、あえて争点にする。
から量刑を軽く」と弁護士は公判の中でまくしたて、あえて争点にする。
 ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より)
ミツバチの集団失踪が相次いでいる。アメリカでのこと。全米養蜂協会によると、元気だったハチが翌朝に巣箱に戻らないまま数匹を残して消える現象は、昨年の10月あたりから報告され始め、フロリダ州など24州で確認された。しかし、ハチの失踪数に見合うだけの死骸は行動圏で確認されないケースが多く、失踪したのか死んだのかも完全には特定できないという。そんな中、原因の一つとされているのが、養蜂業者の減少で、みつの採集などの作業で過度のノルマを課せられたことによる“過労死説”だ。国家養蜂局(NHB)が緊急調査に乗り出した。ハチを介した受粉に依存するアーモンドやブルーベリーといった140億ドル(約1兆6000億円)規模の農作物への深刻な影響が懸念され始めた。(3月1日・産経新聞インターネット版より) 




