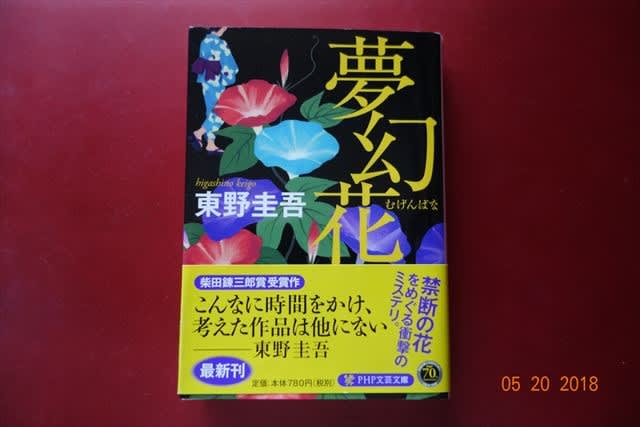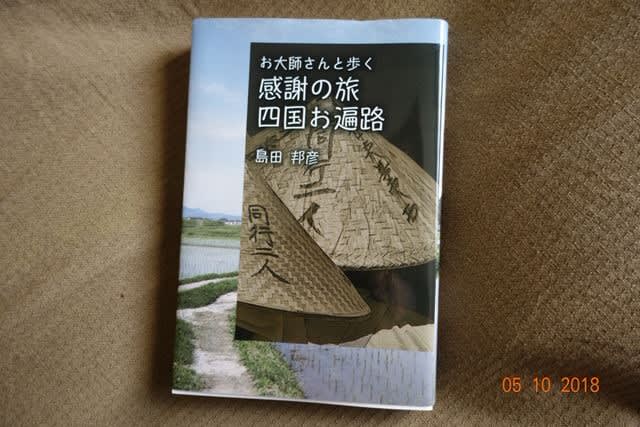井上智洋「人工知能と経済の未来」文春新書
最近AIとか、IoTとかいわれ、コンピューターが一段階上がったような気がする。わかりやすいのは、自動運転の車の出現、あるいは応答をするスピーカー、スマートスピーカーなどであろう。囲碁や将棋の世界でも、コンピューターがプロ棋士を凌駕してきている。
この動きが進んでゆくとどこまでゆくのだろうかと言うのが本書のテーマである。2045年ころにはコンピューターが人類の能力を超えると予測される。蒸気機関、電気モーター、コンピュータ+インターネット、そして人工知能と次々と革新的なことが起きてきたが、そのなかでも人工知能は人間の代わりをするという点では恐るべき影響力を持つ。
生産が全て自動化され、生産設備も自動生産する世の中が来たとき、労働者は一部を除いて必要がなくなる。それはユートピアなのかそれともディストピアなのか。生産力は余るほどあるが、消費する人の購買力がなくなる社会はどう維持されるのだろうか。
著者はベーシックインカムがその一つの解決策だと提唱するが、もうその時期は目前にきている。コンピューターの発達が社会を根底から変える時代を生み出す。政治家の覚悟と先見性が必要となってきた。
本書はあらゆる意味で社会を考えさせる啓蒙書である。