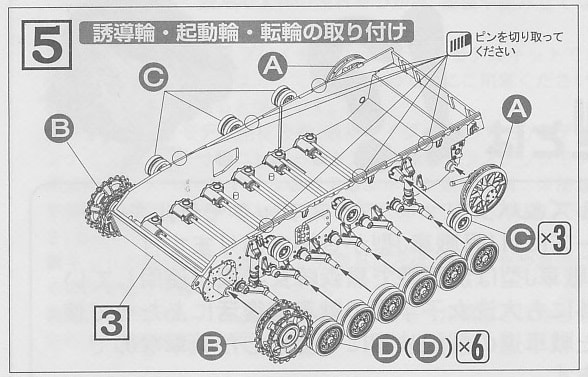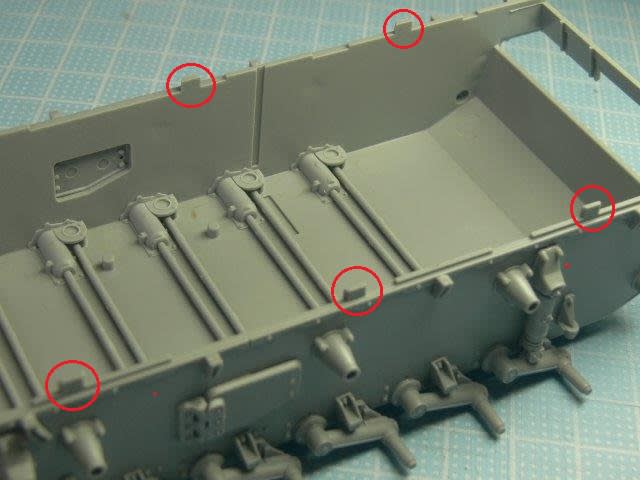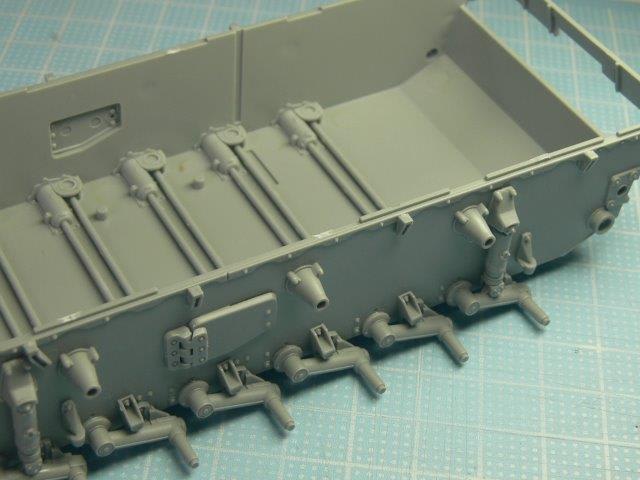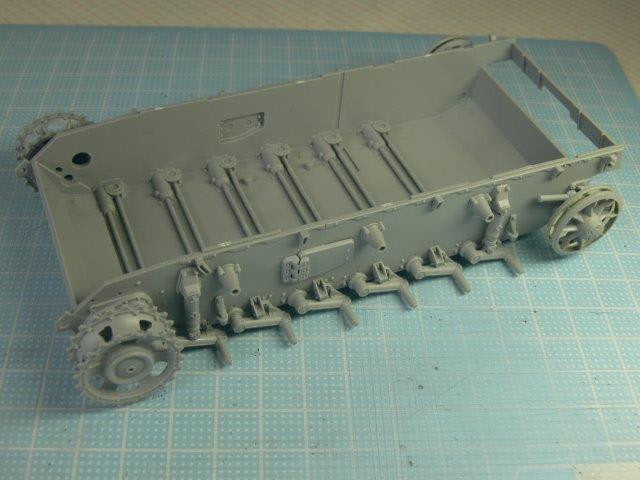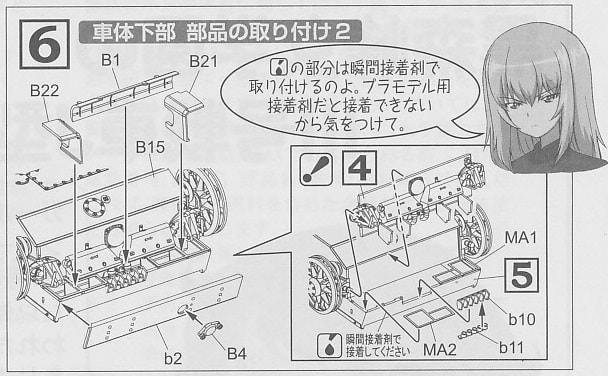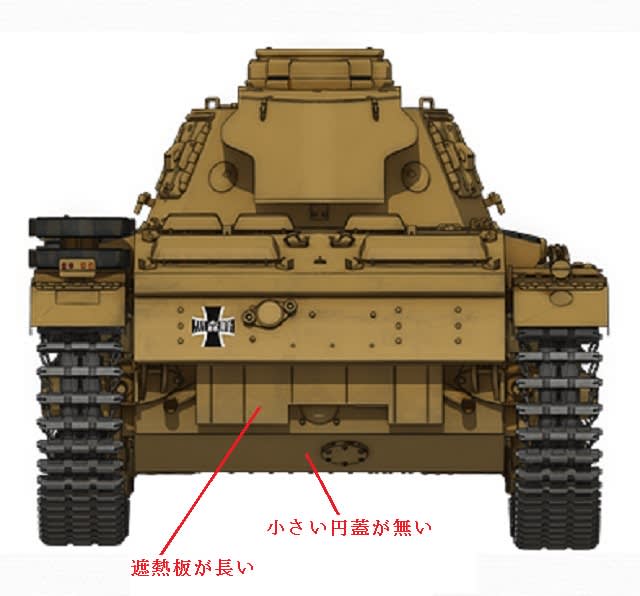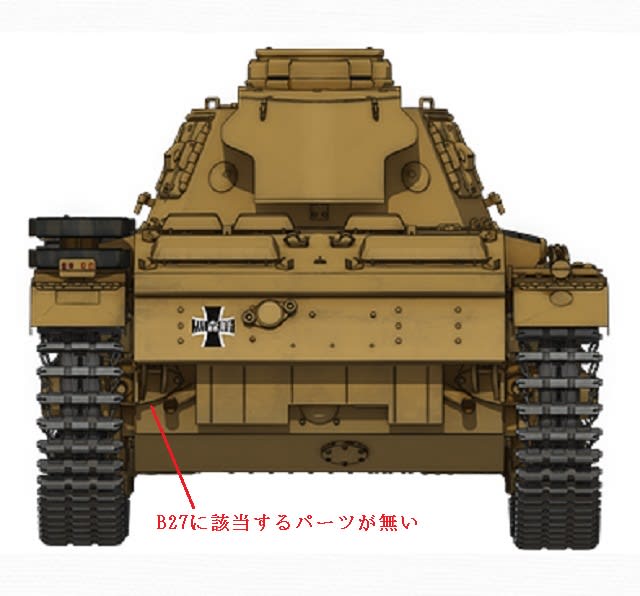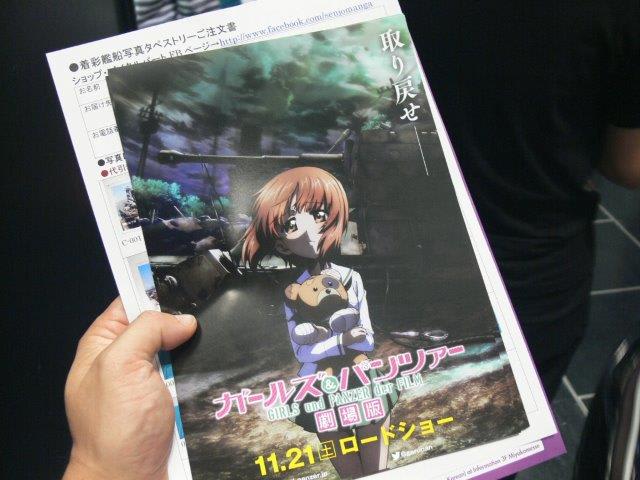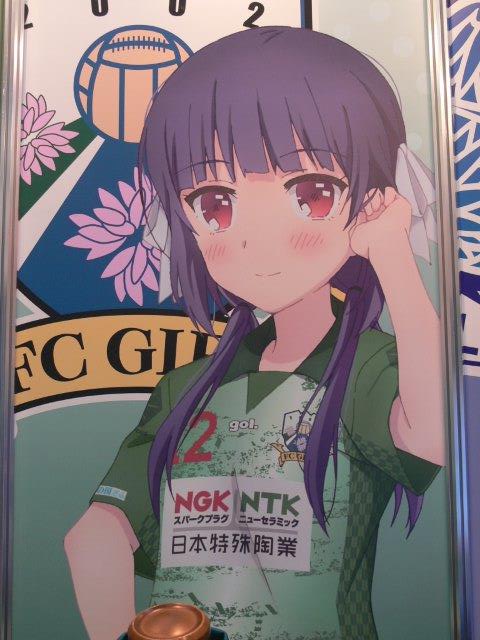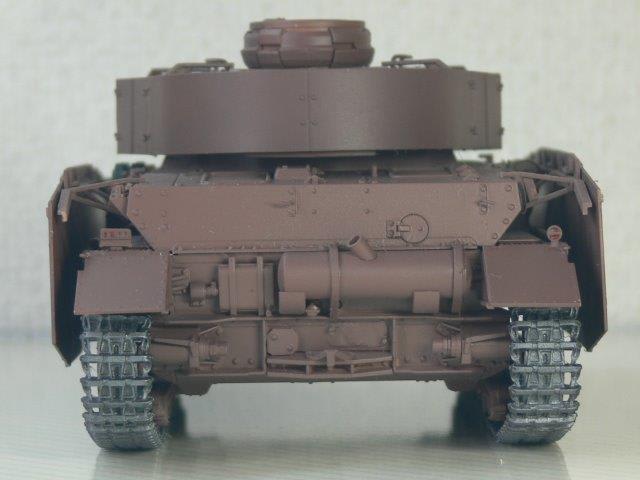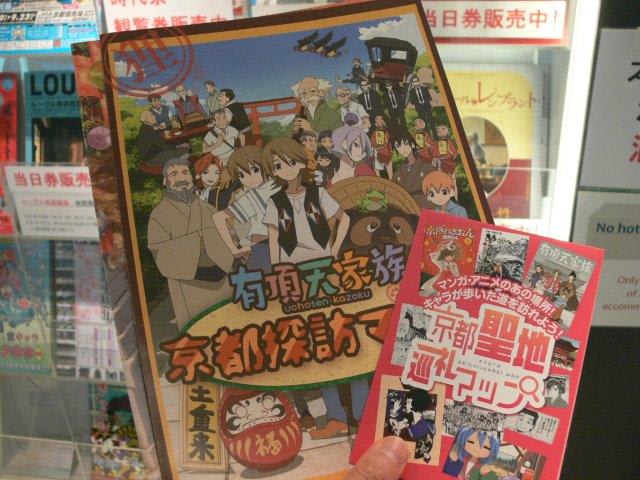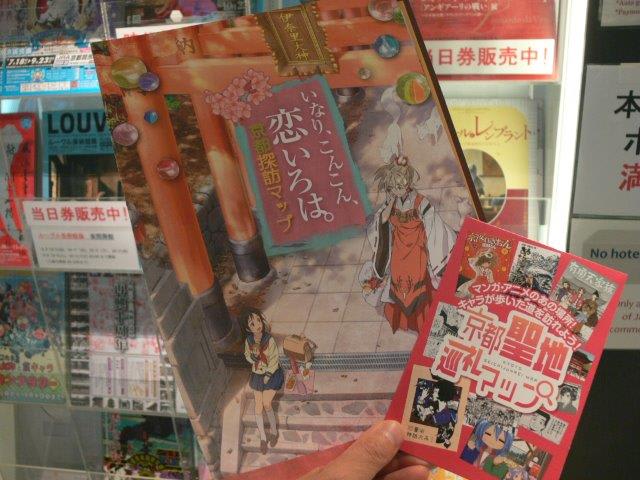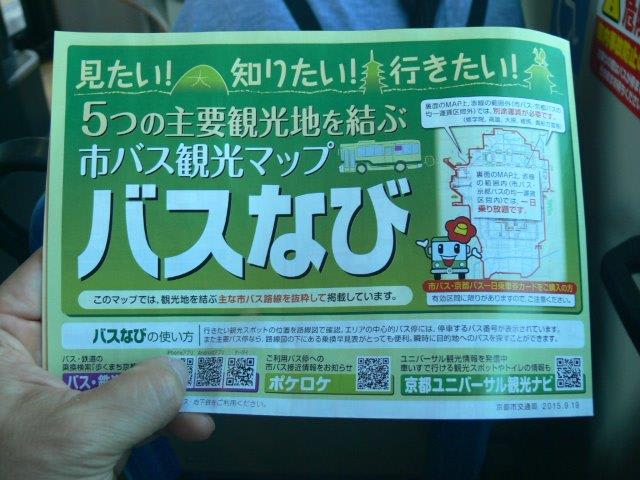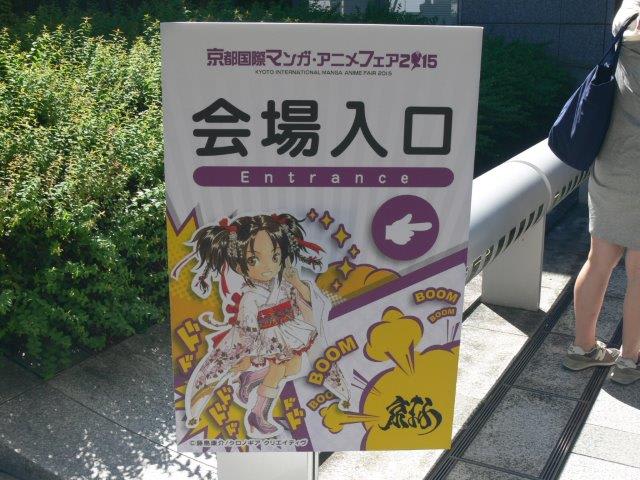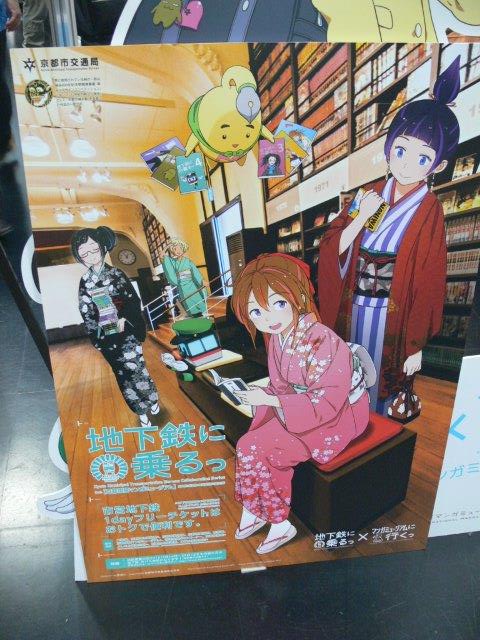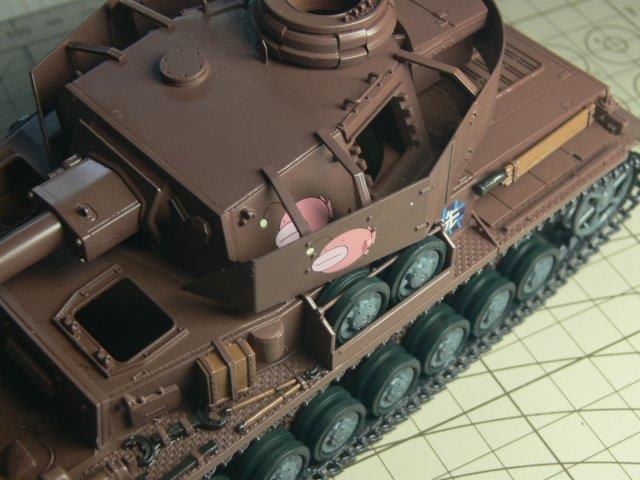大洗のガルパン公式缶バッジに関する中間報告です。今回で十二回目となりました。
今回は、2015年8月および9、10月の大洗行きにて新たに知り得た、ガルパン公式缶バッジに関する諸々の情報を追加すると同時に、2015年10月の時点において知られるガルパン公式缶バッジの動向をまとめました。
また、これまで大洗以外の地域にて入手出来るものに関しては対象外としておりました。しかし、最近に問い合わせを何度かいただいたこともあり、今回の機会に大洗町(水戸、ひたちなかを含む)以外で出されているガルパン公式缶バッジについて知り得る限りの情報をまとめました。
上画像は、2015年8月19日から21日までの大洗滞在中に、色々な形でいただいたガルパンバッジの数々です。宿泊特典品や夏季限定品などが新たに登場していました。
上画像は、2015年9月28日から10月1日までの大洗滞在中に、色々な形でいただいたガルパンバッジの数々です。夏あたりから登場した品が大部分を占めますが、過去の限定品や品切れ分などの一部もまだ在庫があったようです。
今回、新たに追加または更新した分については、
赤字で表しています。
1 大洗女子学園 あんこうチーム
西住みほ(坂本文具店、シーサイドホテル) 誕生日イベント、バーベキューイベント、献血イベント、水戸ホーリック試合観戦特典品などの限定品を含めて数種類があり、クリスマスバージョンもあるが、普通に入手出来るのは宿泊特典ぐらい。宿泊特典には、ガルパン応援宿泊プラン実施施設共通のタイプ、シーサイドホテルの宿泊特典オリジナル品が
新旧三種類ある。また、2014年6月に鹿島臨海鉄道より大洗駅インフォメーションの入場者数10万人達成を記念して限定で配布されたオリジナル品がある。2015年には
D1レース観戦特典が登場。店舗オリジナル品としては、坂本文具店の品、
カノウヤの品、好梅亭の品がある。また
2015八朔祭デザインに角谷杏とともに登場。
武部沙織(カワマタ) 吉田屋のオリジナル品が二種類あったが完売し、2014年4月からの梅カフェの戦車ケーキの予約特典品が500点限定にて登場。さらに2015年3月から購入特典として梅カフェ一周年の新オリジナル品が出た。吉田屋の他には、カワマタのオリジナル品がある。また宿泊特典の品、商工会発の品、献血イベントの品、誕生日イベント時の限定品などがある。2015年には
D1レース観戦特典が登場。
五十鈴華(たかはし) 宿泊特典の品がある。誕生日イベントや水戸夜梅祭の限定品があるが、いずれも入手は不可能に近い。夏の海水浴期間に合わせた「2014SUMMER大洗」バージョンでは西住みほ、秋山優花里と三人で登場。まいわい市場あんこう焼コーナーの購入特典品がある。また水戸ホーリック試合観戦特典の品が二種類ある。2015年には
D1レース観戦特典が登場したほか、
ホテルレイクビュー水戸の宿泊特典オリジナル品がある。
秋山優花里(年宝菓子店) 宿泊特典の品のほか、誕生日イベントの限定品がある。「冬の進軍ボコ作戦」の参加賞品にエルヴィンとのペア後姿がデザインされている。また年宝菓子店のオリジナル品が新旧二種類ある。さらに田口理髪店のオリジナル品があるほか、大洗ガイド大作戦の特典品がある。2015年には
D1レース観戦特典が登場したほか、
シーサイドホテルの宿泊特典夏季限定オリジナル品がある。
冷泉麻子(大洗ホテル) 宿泊特典の品のほかに、エンカイウォーイベントや誕生日イベントの限定品がある。いずれも入手は不可能に近い。2015年には
D1レース観戦特典が登場。
五人のセット 「がんばっぺ大洗」デザインの新旧二種類のほか、好梅亭のオリジナル品がある。他に鹿島臨海鉄道が販売している缶バッジセットの新旧二種類があるが、旧バージョンの6種セットは入手不可能に近い。日本赤十字社茨城県血液センターのガルパン献血イベント品や水戸ホーリック試合観戦特典品などのイベント限定品が幾つかあるが、いずれも入手不可能に近い。2014年3月の海楽フェスタにて出された抱きボコ熊バージョン、夏の海水浴期間に合わせた夏バージョンが2014、2015年の二種ある。また、大貫商店街から出されているEDバージョンがある。2015年1月には戦隊バージョンが出ている。また
D1レース観戦特典がある。
Ⅳ号戦車D型 ブーム初期の百円商店街くじ景品、タヤマ石油のオリジナル品、今村金網工業のオリジナル品があるほか、大貫商店会レンタサイクルの利用特典品がある。
あんこうチームマーク 商工会より、背景色が白と青、水色、クリーム色の三種類が出ているほか、梅原屋のオリジナル品、まいわい市場あんこう焼コーナーの通販限定購入特典品、
あんこうタクシー2号のオリジナル品がある。
2 大洗女子学園 カメさんチーム
角谷杏(丸五水産) 商工会が数種類を制作。「がんばっぺ大洗」デザイン二種類、「あんこう踊り」や「迎春」、「いばらきイメージアップ大賞受賞」、「
2015八朔祭」などのタイプがあるが、「迎春」タイプは季節限定。オリジナル品としては、丸五水産のオリジナル品および2015年1月の誕生日記念品があるほか、ブロンズの澤梓とのコンビ品、
マルトBBQのオリジナル品がある。
小山柚子(茨城県信用組合) 「あんこう踊り」のみ。
河嶋桃(石福) 「あんこう踊り」の他、石福のオリジナル品がある。
三人のセット 「あんこう踊り」と「エンカイウォー」の二種類のほか、大貫商店街から出されているEDバージョン、
クックファンのオリジナル品がある。
38t戦車 ブーム初期の百円商店街くじ景品、大貫商店会レンタサイクルの利用特典品がある。
3 大洗女子学園 カバさんチーム
カエサル(加藤豆腐店) 加藤豆腐店のオリジナル品が新旧二種類ある。
エルヴィン(和泉屋米穀店) 和泉屋米穀店のオリジナル品が新旧二種類ある。イベント「冬の進軍ボコ作戦」の参加賞品に秋山優花里とのペア後姿がデザインされているが、イベント終了後はほぼ入手不可能。
左衛門佐(江口又進堂) なし
おりょう(玉屋菓子店) なし
四人のセット 大貫商店街から出されているEDバージョンがある。
Ⅲ号突撃砲F型 ブーム初期の百円商店街くじ景品、ガルパンスタンプラリー第2弾の完了特典品、さくらい食堂のオリジナル品があるほか、大貫商店会レンタサイクルの利用特典品がある。
4 大洗女子学園 アヒルさんチーム
磯辺典子(鳥孝) 鳥孝のオリジナル品が二種類ある。八九の日イベントの限定品に佐々木あけびと二人で登場。
近藤妙子(魚忠) なし
河西忍(森屋菓子店) 森屋菓子店のオリジナル品がある。ひたちなかの「世界一楽しい片道きっぷ」記念オリジナル品にも登場。
那珂湊ほのぼの作戦2の特典に佐々木あけびとコンビで登場。
佐々木あけび(タグチ) タグチのオリジナル品がある。ひたちなかの「世界一楽しい片道きっぷ」記念オリジナル品にも登場。
那珂湊ほのぼの作戦2の特典に河西忍とコンビで登場。
四人のセット 大貫商店街から出されているEDバージョン、鳥孝のオリジナル品のほか、夢タウン大洗のスポーツテスト記念品、
森屋菓子のオリジナル品がある。
八九式中戦車甲型 ブーム初期の百円商店街くじ景品、ガルパンスタンプラリー第2弾の完了特典品、大貫商店会レンタサイクルの利用特典品がある。
5 大洗女子学園 ウサギさんチーム
澤梓(いそや) いそやの宿泊特典オリジナル品が二種類あるほか、ブロンズの角谷杏とのコンビ品がある。ひたちなかの「世界一楽しい片道きっぷ」記念オリジナル品にも登場するほか、2015年3月8日のいそや感謝祭の記念限定オリジナル品がある。また
那珂湊ほのぼの作戦2の特典に宇津木優季とコンビで登場。
山郷あゆみ(新屋酒店) 新屋酒店のオリジナル品がある。またバーベキューイベントの限定品に西住みほとコンビで登場。
丸山紗希(大勘荘) 大勘荘の宿泊特典オリジナル品が
新旧二種類ある。
阪口桂利奈(大久保酒店) 大久保酒店のオリジナル品がある。
宇津木優季(黒沢米穀店) 黒沢米穀店のオリジナル品が
新旧二種類ある。ひたちなかの「世界一楽しい片道きっぷ」記念オリジナル品にも登場。
那珂湊ほのぼの作戦2の特典に澤梓とコンビで登場。
大野あや(お好み焼き道) お好み焼き道のオリジナル品が新旧三種類ある。
六人のセット 「エンカイウォー」と、大貫商店街から出されているEDバージョン、日本赤十字社茨城県血液センターのガルパン献血イベント限定品があるほか、2015年3月3日の「M3の日」の記念限定オリジナル品がある。
M3中戦車リー ブーム初期の百円商店街くじ景品、今村金網工業のオリジナル品が二種類ある。
ウサギさんチームマーク お好み焼き道のオリジナル品があるほか、2014年3月3日の「M3の日」の記念限定オリジナル品がある。
6 大洗女子学園 カモさんチーム
園みどり子(大進) 大進のオリジナル品があるほか、大貫商店会こそこそ作戦6の購入特典品がある。
後藤モヨ子(スルガヤ薬局) なし
金春希美(みむら時計) みむら時計のオリジナル品がある。
三人のセット みむら時計の購入特典品および大貫商店街イベント時に配布された「早寝早起きバージョン」のほか、大貫商店街から出されているEDバージョンがある。
ルノーB1bis みむら時計のオリジナル品が二色ある。
7 大洗女子学園 アリクイさんチーム
ねこにゃー(川崎燃料店) なし
ももがー(ウスヤ精肉店) ウスヤ精肉店のオリジナル品が新旧二種類ある。
ぴよたん(藤乃屋) なし
三人のセット 大貫商店街から出されているEDバージョンがある。
三式中戦車チヌ なし
8 大洗女子学園 レオポンさんチーム
ナカジマ(ブリアン) ブリアンのオリジナル品がある。
ホシノ(カジマ) カジマのオリジナル品が
新旧二種類ある。
スズキ(小沼酒店)
小沼酒店のオリジナル品がある。
ツチヤ(豊年屋機工部) 豊年屋機工部のオリジナル品が新旧二種類ある。
四人のセット 大貫商店街から出されているEDバージョンがある。カジマのオリジナル品がある。
ポルシェティーガー ココストアのオリジナル品がある。
レオポンさんチームマーク ココストアのオリジナル品があるほか、カジマの2015年の海楽フェスタ限定購入特典品がある。
以上の大洗女子学園の8チーム全員のデザイン品が2015年3月の海楽フェスタにて登場。また大洗女子学園の校章のデザインは、黒沢米穀店のオリジナル品、茨城交通の限定オリジナル品、シーサイドホテルの修学旅行記念限定品などがある。
9 大洗女子学園 その他のキャラクター
新三郎(常陸屋) 商工会および各商店街で配布している品がある。
蝶野亜美(月の井) 商工会および各商店街で配布している品がある。
五十鈴百合(福本楼) 福本楼の宿泊特典オリジナル品がある。
西住しほ(さまた接骨院) なし
冷泉久子(酒井屋) なし
10 聖グロリアーナ女学院
ダージリン(肴屋本店) 肴屋本店の宿泊特典オリジナル品がある。
アッサム(国井屋) 国井屋のオリジナル品および誕生日記念品がある。
オレンジペコ(ヴィンテージクラブむらい) ヴィンテージクラブむらいのオリジナル品がある。
チャーチルⅡおよびマチルダ歩兵戦車 いずれも肴屋本店の宿泊特典オリジナル品がある。
11 サンダース大付属高校
ケイ(飯岡屋水産) 飯岡屋水産の2015年3月14日のホワイトデー記念限定品がある。
ナオミ(あんばいや) あんばいやの宿泊特典オリジナル品がある。
アリサ(小林楼) 小林楼の宿泊特典オリジナル品が新旧二種類ある。
M4シャーマン他 味ごよみ宮田のオリジナル品がシャーマンファイアフライのデザインで登場。
12 アンツィオ高校
アンチョビ(山戸呉服店) JR東日本びゅうチケットの景品バッジ三種の一つ。2014年2月28日に終了。2014年4月から5月まで実施の「イラストラリー」の景品がある。山戸呉服店のオリジナル品、誕生日イベント時の限定品がある。
カルパッチョ(ぎらばり) ぎらばりのオリジナル品がある。
ペパロニ(ブロンズ) ブロンズのオリジナル品が
新旧二種類、誕生日イベント時の限定品がある。
モブキャラ二人 しゅんさい(旬菜)のオリジナル品がある。
P40他 なし
13 プラウダ高校
カチューシャ(さかげん) さかげんのオリジナル品がある。
ノンナ(森寅ひもの館→さかげん) なし
T34/76 寿々翔のオリジナル品がある。
IS-2 日野屋商店のオリジナル品がある。
14 黒森峰女学園
西住まほ(さかなや隠居) さかなや隠居の宿泊特典オリジナル品がある。
逸見エリカ(かまや) かま家のオリジナル品が新旧二種類ある。
二人のセット 厳密には大洗の缶バッジではないが、寿司店栗崎屋の系列店「海鮮どんどん」と「すし一番」のオリジナル品がある。
ティーガーⅠ 栗崎屋および系列店「海鮮どんどん」と「すし一番」のオリジナル品にデザインされている。
15 知波単学園
西絹代 2015茨城空港スタンプラリー完了記念特典品がある。
16 その他のキャラクターなど
稲富ひびき(ヨシモト) 大洗ポイントカード会の品(審判三人が一緒のデザイン)がある。
篠川香音(浜野屋商店) 大洗ポイントカード会の品(審判三人が一緒のデザイン)がある。
高島レミ(大黒屋) 大洗ポイントカード会の品(審判三人が一緒のデザイン)がある。
17 その他のデザインなど
優勝旗 商工会発のオリジナル品とそのエラー品とがある。
ボコ熊 商工会発のオリジナル品のほか、
あんこうタクシー1号のオリジナル品がある。
戦車道チームを有する全国各地の高校の校章 リゾートアウトレット内のガルパンギャラリー併設の物産品販売コーナーの抽選品として登場。
2015年10月時点で9種類がある。メイプル高校、知波単学園、ヴァイキング水産高校、ヨーグルト学園、伯爵高校、マジノ女学院、継続高校、ポンプル高校、ビゲン高校。
戦車カツ クックファンのオリジナル品がある。
続いて、入手方法別に追加更新してみました。●がついているものは公式オリジナル品です。在庫が無くなり次第終了、という所もありますので、事前に在庫を問い合わせておくのが良いでしょう。参考までに、( )内に設置パネル名を示しました。新たに追加または更新した分については、赤字で表しています。
1 グッズやお土産やおやつなどの買い物をすると貰える
●和泉屋米穀店(エルヴィン) あんみつやプラッシーなど購入
あいりす(Ⅳ号戦車D型改H型仕様) 「男の身だしなみセット」購入
●ココストア大貫店(ポルシェティーガー全国大会時) ガルパン関連のDVD、書籍、酒類など購入
●今村金網工業(M3中戦車リー全国大会時) ガルパン網戸購入
●みむら時計(金春希美) ガルパンメガネ拭きなど1000円以上を購入
榎澤輪業商会(ヤークトティーガー) レンタサイクルを利用
島屋米穀店(八九式中戦車甲型発見時) あんみつなど購入
小野瀬海藻店(38t戦車親善試合時) お土産など購入
●お好み焼き道(大野あや) 駄菓子セット500円購入
●鳥孝(磯辺典子) 商品合計500円以上を購入
●国井屋(アッサム) 「茶ーちる歩兵煎茶」やティーセットなど購入
坂本文具店(西住みほ) ガルパン名札や文房具セットなどを購入
●黒沢米穀店(宇津木優季) 聖地大洗茶碗と箸セットまたは大洗女子学園学生食堂茶碗と箸セットを購入
●大久保酒店(阪口桂利奈) 日本酒「桂利奈」購入
●森屋菓子店(河西忍) 商品やおやつなど購入
●吉田屋 「常陸乃梅」など購入
●新屋酒店(山郷あゆみ) 商品購入
●丸五水産(角谷杏) 「丸五式戦兵」購入
●ウスヤ精肉店(ももがー) 串カツ購入
●カジマ(ホシノ) 「ホタテの履帯揚げ」など500円以上を購入
●タグチ(佐々木あけび) 商品合計1000円以上を購入
金丸釣具店 「砲弾型ウキ」など購入
●好梅亭 「キューポラ煎餅」など購入
まいわい市場 ガルパングッズの購入
●まいわい市場あんこう焼きコーナー あんこう焼きドリンクセットの購入
●まいわい市場あんこう焼きコーナー 通販にてあんこう焼き9個セットを購入
●ガルパンギャラリー物産品販売コーナー 500円以上の購入で1点を抽選
キラキラクレープ ガルパンクレープ各種の購入
●カワマタ(武部沙織) 商品合計500円以上を購入
●石福(河嶋桃) 商品合計250円以上を購入
●加藤豆腐店(カエサル) 商品合計350円以上を購入
セイコーマート島忠 商品など購入
●梅原屋 ガルパンシャツなど購入
●タヤマ 商品を購入
●田口理髪店 650円以上のカッティングシートなど購入
●豊年屋機工部 ガルパン軍手を購入
●さかげん(カチューシャ) プラウダウォッカを購入
2 食事をすると貰える
●栗崎屋(ティーガーⅠ) ガルパン寿司コースなど。まいわい市場で販売している「海鮮丼」にも缶バッジがついています。また水戸市に展開する支店の「海鮮どんどん」と「すし一番」にて800円以上の食事をして栗崎屋の缶バッジを示すと、それぞれの支店の缶バッジが貰えます。
渡来人(ヘッツアー) ラーメンなど
●さくらい(Ⅲ号突撃砲F型親善試合時) 「あのカツ丼」など
●大進(園みどり子) 蕎麦など
常陸屋(新三郎) 蕎麦
●お好み焼き道(大野あや) たらしなど
●ブロンズ(ペパロニ) ガルパンメニュー
●寿々翔(T34-76) 海鮮ちらし丼など
●かま家(逸見エリカ) 海鮮丼など
●ヴィンテージクラブむらい(オレンジペコ) コーヒーや酒類などを注文
●しゅんさい 昼の「アンツィオランチ」または夜限定の「アンツィオセット」を注文
●ぎらばり(カルパッチョ) 夜にランチなどを注文
●味ごよみ宮田(シャーマンファイアフライ) 海鮮料理など
3 宿泊すると貰える
大洗の各ホテルや旅館や民宿のなかには、「ガルパン宿泊応援プラン」を実施しているところがあります。共通の宿泊特典缶バッジとしてあんこうチームの五人のいずれか一つが大洗女子学園タオルと共に貰えますが、なかには設置パネルのキャラをデザイン化して独自の特典缶バッジを渡している施設もあります。独自の特典缶バッジを出している所は●をつけています。宿によっては在庫がなくなっている所もありますので、事前に確認しておくのが良いでしょう。
旅館くるみ屋 缶バッジの他にポストカードなどのオリジナルグッズも貰えます
入船 缶バッジの他にオリジナルトートバッグも貰えます
東光苑
勝村荘
雲仙
●いそや(澤梓) 缶バッジの他にポストカードなどのオリジナルグッズも貰えます
忠愛丸
たくみ
●小林楼(アリサ) 缶バッジの他にオリジナルグッズも貰えます
●あんばいや(ナオミ) 缶バッジの他にオリジナルマグカップも貰えます
●肴屋本店(ダージリン) 缶バッジの他にオリジナルグッズも貰えます
大和旅館(Ⅳ号戦車D型プラウダ戦時)
南荘(Ⅲ号突撃砲F型プラウダ戦時)
浜の湯(マチルダⅡ)
●大勘荘(丸山紗希) 缶バッジの他にポストカードなどのオリジナルグッズも貰えます
浜野屋(パンターG型)
●セイラーズ(ルノーB1bis全国大会時)
●シーサイドホテル(西住みほ)
●さかなや隠居(西住まほ) 缶バッジの他にナップサックも貰えます
●福本楼(五十鈴百合)
4 販売している
公式缶バッジを制作している大洗町商工会館にて一部を販売しているほか、大洗の各商店街の店舗によっては1個100円で販売しているところがあります。販売品である以上、完売や売り切れも多いので、在庫が常にあるとは限りません。各店舗での仕入れ補充の動きなどを確かめておいた方が良いでしょう。
ここでは、私がこれまでに缶バッジを1個100円で買った所を挙げておきます。その多くは、私が訪問した時に数種類を販売していたお店なので、一種類だけを販売しているお店ですと、他にも沢山あり、主に大貫地区のほうに分布しているようです。
大洗町商工会館
さかげん(カチューシャ)
新屋酒店(山郷あゆみ)
ウスヤ精肉店(ももがー)
カワマタ(武部沙織)
みとや
黒澤米穀店(宇津木優季)
鳥孝(磯辺典子)
和泉屋米穀店(エルヴィン)
小野瀬海藻店(38t戦車親善試合時)
セイラーズ(ルノーB1bis全国大会時)
住谷商店
梅原屋(38t戦車全国大会時)
島屋米穀店(八九式中戦車甲型親善試合時)
坂本文具店(西住みほ)
カネハチ海藻店(三式中戦車チヌ発見時)
金丸釣具
大洗観光協会
5 店舗オリジナル品
最近、大洗町の各店舗では、公式缶バッジの他に、ガルパンとは関係ない各店のオリジナル品を出すところが増えています。お店の御主人の顔写真、ペットの犬や猫、ファンのイラストなど様々なものがあります。かなりの数が出ているようですが、全部を把握していません。
商工会館 あんこうマーク新旧六種、がんばっぺ大洗の茨城県デザインなど
大洗町観光協会 アライッペの青と赤の二種、アライッペの鳥居日の出
大野屋 お店のオリジナルマーク
今村金網工業(M3中戦車リー全国大会時) M3中戦車リーのシルエット
丸五水産(角谷杏) 鮮魚道始めます、丸五式軽鮮車二種、丸五の日など
森屋菓子店(河西忍) シベリアセットの色違い四種
和泉屋米穀店(エルヴィン) 猫、戦車シルエット、泉マークなど多数
梅原屋(38t戦車全国大会時) 犬二種
オレンジペコ(ヴィンテージクラブむらい) 店主さんの誕生日記念イラスト二種
坂本文具店(西住みほ) 店主さんの写真
ウスヤ精肉店(ももがー) 店主さんの写真、串カツを食べるブタの色違い五種
肴屋本店(ダージリン) 店主さんの写真
カワマタ(武部沙織) 武部沙織誕生日祝い
金丸釣具 お店のロゴマーク
ブロンズ(ペパロニ) お店のロゴマーク
松のぶ うなぎ
親潮 あんこう
お好み焼き道(大野あや) 道のマーク、日の出屋のマーク、戦車デザイン、M3リーデザイン四色、大洗道
日野屋商店(IS-2) おからアート
国井屋(アッサム) 煎茶道マーク六種類、亀チャーチル、亀戦車
石福(河嶋桃) 八百屋マーク、店主さんの短歌、戦車と桃助、店主さんの写真
寿々翔(T34-76) 店主さんの写真二種、賀正玉子握り、かっぱ巻き
黒澤米穀店(宇津木優季) 「聖地巡礼大洗」、「いつも心は大洗」
田口理容店 「倒福」、「照準器」、「歴女チーム関連のマーク」九種ほか多数
大貫商店会 八朔祭のⅢ号突撃砲色違い六種、歴史ギャラリー三種、
2015盆踊り記念品
カジマ(ホシノ) ななぷりん
吉田屋 梅カフェの店名ロゴ
多満留屋(M3リー練習試合時) 犬
曲松商店会 曲がり松デザイン
6 商工会発および共通品
大洗町商工会発の品、および共通配布品です。
がんばっぺ大洗 最初の大洗缶バッジ
大洗校章 初期のポイントカード会のものも含めて二種類、プリントエラーが二種類
優勝旗 プリントエラーも含めて二種類
大洗へGO
2014八朔祭
2014SUMMER大洗
夏だ海だ大洗!
ゆっくり巡ろうおおあらい
皆様いつも応援ありがとうございます
マリンタワー広場での大洗チーム全員
2015SUMMER大洗
2015八朔祭
6 公式缶バッジがまだ出ていないキャラクター
現時点で、まだ公式缶バッジが出ていないキャラクターは、以下の通りです。
左衛門佐(江口又進堂) 「出しませんよ」と公言。
おりょう(玉屋菓子店) 出すかどうか決めかねている、との事。
近藤妙子(魚忠) 出ない可能性が高いと噂されている。
後藤モヨ子(スルガヤ薬局) 「出す予定はありません」との事。
ねこにゃー(川崎燃料店) 情報なし
ぴよたん(藤乃屋) 情報なし
ノンナ(さかげん) 情報なし
西住しほ(さまた接骨院) 情報なし
冷泉久子(酒井屋) 情報なし
番外 大洗町(水戸、ひたちなかを含む)以外で配布された公式缶バッジ
現時点で把握しているものを、古い順に並べてみました。
アニメイト ガチャ第1弾全12種および第2弾6種
ムービック アニくじ商品の対戦校セット3種
コンテンツシード デカンバッチあんこうチーム5種
アンツィオ戦OVAのDVD特典 あんこうチーム5種
茨城空港 スタンプラリー特典のウサギさんチーム6種の第1弾、第2弾
大阪ぼちぼち作戦 あんこうチーム5種、対戦校隊長5種
Ⅳ号戦車日本上陸作戦 あんこうチームなど8種
ガールズ&パンツァー オーケストラ・コンサート2015 あんこうチーム5種