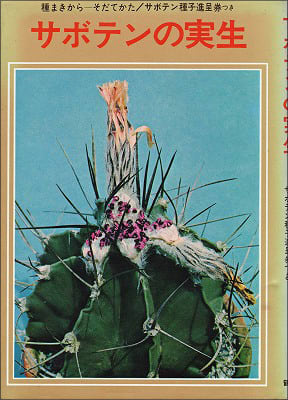学校支援ボランティアの“活用”,人材の“活用”といういい方をする人があります。それがふつうのようです。でも,その“ふつう”を気にしておきたいと思います。わたしは使う気にはなれません。その理由はいずれ書くことにします。
ことばはともかくとして,地域の人の助けなり応援なりを得て(いただいて),学校づくりをしなくてはならない時代に入っています。というより,助けが不可欠なのです。ただ,学校本位の目で“活用”するといった次元で助けを求めるのは禁物。それはまことに軽率な話です。
軽率さに気づいて学校が地域と一体となり,地域本位・子ども本位の発想に軸を移さない限り,学校の未来には期待が持てない,というのがわたしの変わらぬ見方でした。今もそうです。なぜなら,学校本位の発想では一定の心理的垣根が相変わらず存在し続けるでしょうから。結果,真の信頼関係が築けないと思われるからです。
今のままでは,わたしの描く像に遠く及ばないでしょう。社会の常識が学校の常識に変わる本流がほしいのに,学校内部からそれをつくり出す萌芽が見えてきません。悲しいですね。地域で暮らしていると,関係者には申し訳ありませんが,自覚とスペード感が欠けているようにしか思えません。
現職校長時代,わたしが地域の方に期待した手助けは,子どもの学校生活,教育活動,学校運営へのきめ細かな援助でした。やがて自分なりの段取りがうまくいったようで,ある程度,そして徐々に実を結んでいきました。
一つめの勤務校では当時めずらしかった教室学習支援,校外学習支援,図書室運営,クラブ活動指導などボランティア活動の面で改革が進みました。立ち上げ時こそ苦労しましたが,すこしずつ地域の理解が広まりました。それが教職員の意識を変えるきっかけになり,学校の垣根を低くする流れにつながったのでした。

二つめの学校でボランティアとしてお世話になった方がYさんです。山間部に位置する学校でした。わたしがボランティアを探して谷あいを歩いているとき,声を掛け知り合った方です。その後の手助けでは子どもの登下校の見守り,学校施設の手入れ,学習活動への参加などで,献身的に汗を流してくださいました。子どもたちに溶け込んで,笑顔で声掛けをしていらっしゃる姿が脳裏に焼き付いています。

ありたがいことに,その後,当時描いたデザインが元になって学校と地域との連携が深まっていると聞いています。Yさんの姿が目に浮かぶようです。
ところが年末に,そのYさんのご家族から喪中葉書を頂戴したのです。なんともショックでした。転勤後,ご自宅を数回お訪ねしましたが,そのときはお元気そうだったのに。突然の訃報に目を疑ってしまいました。さっそくお訪ねして,奥様とご長男から,死の直前のご様子,またわたしとの出会いの話などについて,お伺いできました。一つひとつが刺激的な内容でした。会話を通して,わたしが求めていた学校づくりが全うであったことを改めて確認できた思いがしました。
Yさんはわたしの目指す学校づくりのよき理解者で,学校を“地域化”するのに汗を流されました。その汗で,職員の意識が徐々に変わってきたのですから,真の貢献者であり“人財”であったのです。職員が持つ,一種頑固な“おらが学校”意識に風穴を開けていただいたことに感謝しています。
わたしの中のYさんは,未来の学校をつくる礎の役を演じ続けてくださいました。見事な助っ人であり,支援者でもありました。ご冥福をお祈り申し上げます。合掌。