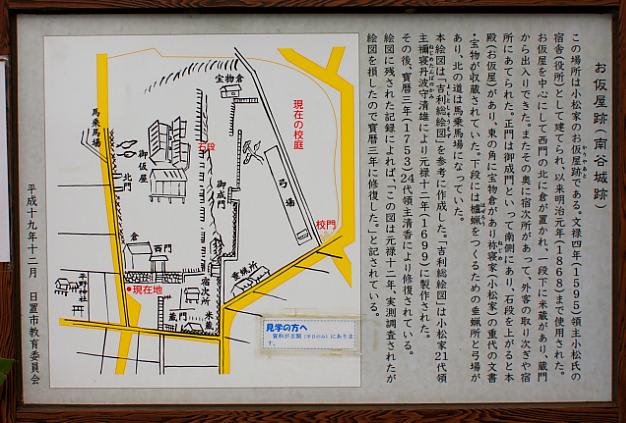吉利麓に続き、永吉麓を訪れる。日置市吹上町永吉。4年ぶりです。
永吉小学校近くの武家門。4年前と変わらぬ姿だがこの先どうなるのだろう。


かつて「村長の家」と呼ばれたところ。
武家門はそのまま。グループホームに使われていた大きな古民家は取り壊されていた。実に残念。

永吉麓でもっとも好きな風景。畑の向こうに石垣と生垣、武家門。ずっと残って欲しい風景。


永吉麓に残る西洋建築物。左手に古い石垣も見える。

4年前と比較すると武家門が改築されたようにみえる。風景によくなじんでいると思う。
右の石垣と竹垣は古いまま。

参考:旧吹上町・永吉麓の風景(2007年11月訪問)・・・4年前に永吉麓を初めて訪れたときの記録です。