京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。
京都観光では最も詳しいです!
Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)
KYOTO MAIKOYA 祇園清水店(旧伊藤喜商店)2 無量子庵内部

-
写真は、露地庭の腰掛待合(右)と茶室 松庵(左)。
KYOTO MAIKOYA 祇園清水店は元伊藤喜商店(いとうきしょうてん)の無量子庵(むりょうしあん)で、表にある貴匠桜が店舗と主屋だったようです。
共に大正15年の建築の登録有形文化財です。
貴匠桜に向かって右手にある路地に入ります。
細い石畳を進むと、路地は左に折れ貴匠桜の裏手を進みます。
両側の塀は木の皮や竹で作られており、非常に風情があります。
突き当り右手に門があり、それをくぐると無量子庵の玄関前庭です。
無量子庵は当時桧より高級と言われた栂(ツガ)普請。
また外壁が聚楽壁なので、やや赤みがかっています。
正面が主屋の通り庭になり勝手口、その手前の右手に式台の玄関があり、当日は勝手口から入ります。
式台も勝手口も入ると3畳間があり、左右に並んでいます。
式台の正面は廊下を挟んで、露地庭があります。
露地庭の正面に腰掛待合が見え、右手に茶室 松庵があります。
左手斜め前方が大広間で、左手奥に進むと6畳間があり、これが1階の大体の間取りです。
勝手口を入った正面に左向きに2階への階段があります。
左手奥の6畳間で待ちますが、こちらにも隠れてはいますが2階への階段が右向きに付いています。
なので2階に上がるとちょうど2つの階段が向かい合っており、珍しい構造です。
1階の大広間に入ります。
左手が10畳の本間、右手が8畳の次の間です。
10畳間には付書院、床の間に床脇があり、欄間は下半分が1枚板で端が卍のような意匠になっていました。
10畳間の左手は廊下を挟んで、奥庭。
飛び石は残っていますが、苔などはなくなっています。
庭の奥には川の流れのように石が配されていました。
また奥庭の右手奥には蔵があり、こちらも登録有形文化財です。
お庭に降りて右奥に進むと前述の露地庭につながります。
立派な腰掛待合があり、その奥に小間の茶室 松庵があります。
庭に面した2面に貴人口と躙口が並んでおり、内部は4畳半。
床の間が貴人口の隣に並んで造られているのが変わっています。
さらに露地庭の通路を挟んで左手には新しいお庭があり、そちらはきれいで赤い鳥居、毛氈に傘があり、撮影用なのでしょう。
主屋に戻り2階へ。
2階にも1階の大広間の真上に同じように10畳間と8畳間がありますが、こちらの10畳間には床の間と床脇がありますが、両方の床が1枚板です。
また欄間は大きな1枚板を基調にした風車型でした。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
KYOTO MAIKOYA 祇園清水店(旧伊藤喜商店)1 茶道体験

-
写真は、2階の大広間。
KYOTO MAIKOYA 祇園清水店は主に海外の方向けに茶道体験をしておられ、
建物は元伊藤喜商店(いとうきしょうてん)の無量子庵(むりょうしあん)で、大正15年の建築の登録有形文化財です。
アクセス
京阪電車の清水五条駅で下車し、改札を出て4番出口から地上に出ます。
そのまままっすぐに五条通を直進し、約400m先の6個目の交差点(目の前に歩道橋がある)を側道へ左折します。
再び約320m直進し、左手の六波羅蜜寺を越えた次の交差点(八坂通)を右折します。
右折してすぐ右手にフレンチの貴匠桜があり、向かって右手の路地の奥にKYOTO MAIKOYA 祇園清水店があります。
伊藤喜商店は龍野の醤油や塩、酒、味噌などを料亭へ卸していた商家で、表の貴匠桜は伊藤喜商店旧店舗兼主屋、裏にある無量子庵は邸宅だったと思われます。
貴匠桜
玄関を入ると通り庭の部分がアプローチになっており、「醤油」の看板が残っています。
右手の旧店の間はキッチンです。
奥に進むとおくどさんが残され、会計カウンターに転用されています。
靴を脱いで右手に上がると、右手に応接間があり、左手の階段に案内されます。
階段は右に登りますが、その正面奥には1階の奥座敷が個室になっており、その向かいに小さなお庭もあります。
主な客席は2階で、2階は仕切りが取り払われ、広くイス席として使っておられます。
茶道体験
茶道体験はネットで申し込みで出来ますが、着物に着替えさせてもらって行うプランで7,000円です。
海外の方向けなので説明はすべて英語です(ただし日本の方が話されるので、ある程度分かると思います)。
時間は全員の着替えに約30分、お茶席が40分+撮影タイム20分の計90分です。
最初に路地の入口に行くと、着替えの棟が別にありさらに北側の町屋に行くよう指示が書いてあります。
まずはそちらで着物を選んで着替えさせてくれます。
無量子庵に入ると左手奥の待合の椅子に座って待ちます。
参加者が揃ってくると、1階の大広間に通されそちらでお茶席を体験します。
2階にも同じような大広間があり、体験は正味60分なので上下で30分ずらしで開催しているようです。
1席10名弱でした。
茶道とは何か、一期一会や和敬清寂の説明。
お菓子を戴いた後、抹茶の入った茶碗と茶筅があるので、自分でお抹茶を点てて戴きます。
最後は室内やお庭に出て、着物での撮影タイムでした(僕はお茶席体験で失礼しました)。
僕の場合は9:30着替え、10:00からの1席目。
しかも早めに行ったので、前に誰もおらず。
また建物が非常に好きなのを察して下さり、優しい女将さんが全部屋とお庭から小間の茶室 松庵の中も躙口から見せて下さいました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2025 1/19の拝観報告1(建仁寺 西来院 京の冬の旅 呈茶席)

-
写真は、方丈奥の呈茶席。
日曜日です。
この日も9:00頃に自宅を出て、地下鉄で三条京阪駅へ。
そこから徒歩で建仁寺に向かいました。
実は4月に某アーティストのライブに誘われて行くことになりまして。
一生に1度は行ってみたかったアーティストさんだったので、メッチャ楽しみ。
なので最近はそのライブの先に終わった公演の情報からセットリストをspotifyで作って通勤時や徒歩時に聞いているので、歩きがちですw
また行った際は報告します。
10:00にやって来たのが建仁寺の西来院です。
こちらは昨年から独自公開しておられ、その際にも来ています。
ではなぜ来たかというと、別途1,000円での呈茶席が面白いとアマ会のあきさらさんから伺ったからです。
庫裏から入って拝観料は800円。
方丈の左手奥の8畳間2つが呈茶席です。
1番に入ったので、もちろん1人。
床の間には織田信長の建仁寺の所領を安堵する書状が軸装して掛けられていました。
お菓子は虎屋の最中。
やっぱり虎屋、美味しいですねw
そして主茶碗が楽雅臣氏(当代楽吉左衛門さんの実弟)の溶岩をくり抜いた楽茶碗。
これがなかなかのズッシリ感で、吸い口もちょっとザラザラで野性味がありました。
茶入れも壺仙(こせん)という銘の安土桃山時代のもので、お軸と時代を合わせておられます。
呈茶と言ってもちゃんとお点前はして下さいますし、半東さんが説明もして下さるので1,000円なら十分でした。
お茶席後は一応拝観もして、10:40頃にこちらを出ました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 12/21の拝観報告6 最終(グランマーブル祇園本店 「京都祇園 茶室と坪庭を貸切 アートに囲まれ五感で味わうデザートプラン」 EX旅)

--
写真は、店舗奥の茶室。
満足稲荷神社を出て、シェアサイクルで東大路通を南下します。
八坂神社の手前のポートに返却して、花見小路へ。
14:50頃にやって来たのが、グランマーブル祇園本店です。
EX京都で「秋の大セール!京都祇園 茶室と坪庭を貸切 アートに囲まれ五感で味わうデザートプラン」があったので、アマ会の皆さんで申し込みました。
一力亭のさらに南側に町屋を改装したグランマーブル祇園本店があります。
1階が店舗で2階がカフェですが、1階の1番奥に6畳の茶室があります。
坪庭は店舗からも見えますが、茶室はちょうど見えない角度になっています。
ここを貸し切って甘味を戴きます。
今回はあきさらささん、シヲさん、frippertronicusさんと僕の4名。
1人5,000円でした。
2人利用だと1人6,000円、3人利用だと1人5,500円。
人数が多いと個人負担は減りますが、合計料金は増すという絶妙の設定ですw
時間は75分制ですが、前に使用がない場合は早く着くと入れて下さいました。

--
写真は、この日のデザート。
まずゆずの香りの白湯が出てきます。
次にノンアルコールのウェルカムスパークリングワイン。
希望があればアルコールにしてくれます。
そしてデザート。
左上:日本一大きいと言われる秋田県の「善兵衛栗」を使った栗の巾着
右上:祇園辻利の抹茶を使った自家製抹茶ジュレ
左下:マーブルデニッシュの卵サンド
右下:マーブルデニッシュのフルーツサンド
でした。
最後に 抹茶、コーヒー、紅茶のいずれかのドリンク。
卵サンドはまだ暖かくて、卵がフワフワでした。
栗の巾着は栗が濃厚でした。
お話しながらデザートを戴き、食後は室内の撮影。
坪庭にも出れたので、そちらも撮影しました。
75分だと16:15まででしたが、早めに入ったこともあり16:10頃にグランマーブル祇園本店を出て、この日は帰宅しました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 11/23の拝観報告5 最終(にいさん茶会 いづ重2階 菊渓茶屋)

-
写真は、残月亭写しの茶室。
正行院のあと、京阪電車で出町柳駅から祇園四条駅へ。
南座の地下の発券機で、予約した今後の公演のチケットを発券。
そして知恩院の和順会館のロビーへ。
16:00まで1時間ほどあったので、こちらで休憩しつつ14日目の十両の取り組みをスマホで観ていましたw
そして16:00前にやって来たのが、八坂神社の西総門の前にあるいづ重です。
最近大改修を終えられて営業を開始されましたが、こちらの2階にお茶室があるそう。
そちらのお茶室で毎月23日に開催されているにいさん茶会が、席披き、炉開きとして事前予約制で開催されました。
参加費は5,000円、1席10名でした。
昔、この辺りに菊渓川が東山から流れていたことにちなみ、菊渓茶屋と命名されたそうです。
食事をする店舗の入口手前左手に2階への階段があります。
その上に玄関から待合、そして写真のように残月亭写しのお茶席がありました。
しかも材も結構いいのを使っておられると思います。
そしてこの日は床の間に・・・国宝 源頼朝公像の写し。
こちらなんでも、いづ重の御主人が美大卒で在学中に自ら写されたものだそう。
この大きさ、実物大ですよね。
また香合は蝶であり、平家の紋。
それと義経ゆかりのものもあり、源平尽くしでした。
席主はいつもの中路さんなので、自由も自由w
そういうところに集まる皆さんも楽しい方ばかり。
まさに一期一会を楽しめました。
16:45頃にこちらを出て、この日は帰宅しました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 11/3の拝観報告2(あじき路地 京都モダン建築祭)

-
写真は、路地。
9:50に六波羅蜜寺を出て、清水五条駅に向かう途中の10:00にやって来たのがあじき路地です。
京都モダン建築祭のパスポート公開です。
100年前の長屋が並ぶ路地に、最近は若い方のギャラリー、ショップやカフェがオープンしています。
採光の問題で北側の家は2階建てですが、南側のは1階建てです。
10:00に到着したらお客さんは7人ぐらいで、以倉さんが来ておられましたねw
本来は北4の家がオープンされる予定でしたが、結局開かなかったようですね。
しかしcafe&place 075のお店の中を拝見出来てよかったです。
10:10頃にこちらを出ました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 11/3の拝観報告1(六波羅蜜寺 十一面観音像御開帳)

-
写真は、お札と本堂。
前日はお雨の中での京都モダン建築さんとお茶会開催のアマデウス会総会でしたが、そんなのカンケーなく翌日も朝から出かけますw
7:15頃に自宅を出て、地下鉄と京阪で清水五条駅へ。
8:05にやって来たのが六波羅蜜寺です。
もちろん12年ぶりの十一面観音像御開帳(11/3~12/5)です。
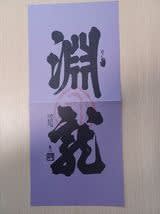
その際のお札もきれいに残っています。
5回で満願とか。
1回目 38歳 12年前
2回目 50歳 今回
3回目 62歳 まあ来れるか
4回目 74歳 行きたいところ
5回目 86歳 ワンチャンあるかw
僕の場合は初回が38歳というアドバンテージ?があるので、ワンチャン満願あるかもですw
さて今回お札の授与は11/3~11/5で「先着500枚」という触れ込み。
前回は枚数制限なかったと思ったのですが。
そうなると必然、皆さん早朝から来られます。
僕は8:05頃着でしたが、列は南側の門から北に延び、八坂通でターンしたところぐらいでした。
ちょうど連絡をくださったDrの先輩と一緒になったので2人で並びました。
8:30開門で9:00から授与でしたが、もう9:00前には列が3ターンしたので少し早めに授与を始められました。
それでも本堂がいっぱいになるので、進みは遅く結局お札を戴いて本堂にお参りして出て来たのが9:50頃でした。
しかも御朱印希望の方は、これからまた行列に並んでおられました。
長時間の待ちでしたが、久しぶりにお会いした先輩と近況報告が出来てよかったですw
まだまだ伸びる列を見ながら(500枚限定ってホンマかいなw)、次へと向かいました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 11/2の拝観報告1(八坂圓堂 京都モダン建築祭 ガイドツアー)

-
写真は、廊下と2階への階段。
3連休の初日です。
この日は昼過ぎ大雨だった日です。
朝のうちはまだ小雨でした。
9:20頃に自宅を出て、京阪の清水五条駅で下車。
ちょうと10:00頃にあじき路地の前を通過したので、京都モダン建築祭のチケット交換だけしておきました。
そこから徒歩で向ったのが、八坂圓堂の北邸です。
この日は京都モダン建築祭で当選した八坂圓堂のガイドツアーでした。
参加費は食事込みで18,000円。
参加者は18名、アマ会のYDさんもおられました。
10:30からスタート。
北邸は昭和初期のお茶屋さんを改装した店舗。
数寄屋の要素がたくさん残っていました。
詳細は今後の本編で掲載しますが、最初に入った2階は広間と茶室の様な小部屋の2つ。
1階はよく写真で見る、両面庭園の個室と大きなカウンター席、6人部屋で部屋の中央にカウンターがある堀こたつ席。
そして小間の茶室の個室がありました。
個人的にはこの廊下。
柱の材も違うし、葦の船底天井とか珍しいですよね。
なかなか食事で行っても、全部屋見るのなんてムリなんで非常によかったです。
30分強の見学会の後はお食事です。

-
写真は、この日のてんぷらのコース。
写真3~7までガッツリ天ぷらのコース。
昔はこれでも物足りないぐらいでしたが、今はこれで十分ですねw
ご存知のように天ぷら屋さんの天ぷらは全然違うので、非常に美味しかったです。
最後はミニ天丼も。
圓堂さんは八坂通りに他にも店舗が複数あり、特に南邸も古いようなので気になりますねw
12:20頃に終了し、こちらを出ました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 9/15の拝観報告3 最終(祇園の老舗「菊梅」の見学とあんこライターさんセレクトの和菓子を楽しむ会 Niwaco)

-
写真は、2階の座敷。
貴匠桜を出て、frippertronicusさんと北に歩きます。
建仁寺の境内のを抜けて花見小路へ。
12:40頃にやって来たのが、菊梅です。
この日は13:00~15:00まで、烏賀陽先生のNiwacoでの「祇園の老舗 菊梅の見学とあんこライターさんセレクトの和菓子を楽しむ会」でした。
参加費は13,000円、参加者は16名。
参加者には同行のfrippertronicusさんと、最近よくご一緒するUさんもおられました。
菊梅は花見小路にある旧料亭で、今は紹介制で旅館をされています。
また1階の表屋部分では和小物の販売もしておられるので、そこまでは通常でも拝見可能です。
そして今回はさらにその奥の奥座敷と2階部分を拝見し、あんこライターかがたにさんのおすすめ和菓子を戴く企画です。
最初から2階の奥座敷に上がります。
上の写真の様な感じ。
詳細は今後の本編で掲載します。
宿泊では手前がリビング、奥が第2寝室なります。
そして手前に戻って座敷の向かい側に洋間があります。
ベッドルームで、床の寄木の意匠が細かいです。
こちらは写真撮影禁止で、ネットにも写真が上がってないですね。
中2階の応接間。
そして1階に戻って奥座敷。
こちらは不定期開催の喫茶の会場です。
なかなかいい数寄屋でしたね。
前半は建物の見学でした。

-
写真は、和菓子 千本玉壽軒 着せ綿(上)、聚洸 白菊(下左)、かぎ甚 糸桜(下右)。
そして後半は2階の座敷に戻って、お菓子を戴きます。
菊梅での開催で9月ですので、菊がテーマ。
千本玉壽軒の着せ綿はくずで覆われているのがポイント。
聚洸の羽二重は卵白が入っているので、ふわふわです。
かぎ甚の糸桜はきんとんにつくね餅が入っているのでまったりしており、さらになかが餡子ではなくて道明寺。
歯ごたえの良さと甘みが抑えられており、個人的にはこれが1番美味しかったです。
お気づきでしょうか。
この日僕は朝からベイクドチーズケーキ、ランチでコースのデザートを既に戴いております。
そこに和菓子3つ。
最初はムリかもと思いましたが、結果楽勝でしたw
14:50頃にこちらを出て、この日はこれで帰宅しました。
コメント ( 1 ) | Trackback ( )
2024 9/15のランチ報告2(仏亜心料理 貴匠桜)

-
写真は、1階 奥座敷の個室。
HARIO CAFE 京都店を出て、八坂通から松原通をウロウロしますw
11:20頃にやって来たのが、仏亜心料理 貴匠桜です。
この日のランチは11:30からfrippertronicusさんとこちらでした。
こちらは登録有形文化財の伊藤喜商店の店舗棟。
裏にあるのが同じく登録有形文化財の伊藤喜商店の無量子庵で、9/1に茶道体験に来ました。
貴匠桜は随分前に行ったきりでしたのでまた見たくなったのと、この日の11:00頃までfrippertronicusさんが裏で茶道体験をしておられたので、一緒に参りました。
改めてみてもやはり内部はかなりリノベ―ションされており、裏の駐車場部分は本来もっと奥にも建物があったのではないかと推察されます。

-
写真は、松原コース 4,500円。
コースは1番リーズナブルなシングルメインのコース。
実は2人とも13:00から花見小路で予約のイベントがあったので、その旨を最初にお伝えしました。
すると非常にテンポよく給仕して下さいました。
食事自体は12:15頃には完了しましたし。
4,500円のコースでこのお味とボリュームなら、十分合格点だと思います。
フレンチで写真5の出汁茶漬けは珍しいというか個性的ですねw
12:30頃にこちらを出て、次へと向かいました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 9/1の拝観報告1(KYOTO MAIKOYA 祇園清水店 茶道体験)

-
写真は、奥庭。
結局台風が熱帯低気圧に変わった日曜日です。
この日は午後からアマ会の皆さんとランチ会でした。
その前に1つ予約を入れました。
今回はKYOTO MAIKOYA 祇園清水店で外国人向けの茶道体験です。
こういうの以前も行っていますね。
京都阪口庵です。
ということは、主眼は「建物」ってことですw
1度こういうのにネットで申し込むと、またおすすめで出てくるじゃないですか。
そしたらこちらは登録有形文化財の町家でって書いてありました。
もちろんすぐに調べますw
京都、登録有形文化財で検索すると、便利な時代なんで全部出てきます。
大正12年建築の伊藤喜商店の無量子庵という建物なんですね。
路地裏にあるので表は何かとみたら、フレンチの貴匠桜。
2017年に来ており、こちらが伊藤喜商店の店舗棟だったんですね。
着物に着替えての体験プランが7,000円。
着替えに30分、お茶体験40分、写真撮影タイムが20分の計90分です。
9:30集合に早めに行ったので、1番に着替えて無量子庵に到着。
「まだ時間があるので、よかったらお庭とかお部屋を観ていてください」と。
まさに望むところですwww
お庭や建物を熱心に見ていたら、女将さんが「日本の方お1人でのご参加は非常に珍しいんですよ。御熱心に見ておられるので、建築がお好きなんですか?」と聞いてくださったので、正直にそうお話しました。
すると「今は1回目の前で誰もいないので、お部屋全部観てください」と案内して下さいました。
メッチャラッキー!
1階、2階の大広間や小間の茶室 松庵もあり、お庭に降りて躙口から内部を拝見出来ました。
建物については今後の本編で掲載します。
10:00から集まて来られた海外の方(インドネシアの3人家族、インドの5人家族と僕1人)と体験開始。
最初は茶道とは何か、設えや亭主のおもてなしなどを説明されます。
もちろん全部英語です。
今回も「全部英語の説明ですが、大丈夫ですか?」と念押しのメールが来ました。
お話されるのが日本の方なので、十分聞き取れます。
それに話の流れから「次はこういうことを言うのだろう」と予測も付くので、ほぼ話は分かりました。
お菓子を戴き、自分でお薄を点てて戴きます。
最後は室内やお庭に出て、着物での撮影タイムです。
しかし僕はもう先に十分建物もお庭も拝見しましたし今更自分の写真は不要なので(笑)、10:45ぐらいに着替えて11:00頃にはこちらを失礼しました。
コメント ( 3 ) | Trackback ( )
弓煎閣

-
写真は、外観。
弓煎閣(きゅうせんかく)は昭和初期に町会所として建てられた町家です。
通常は閉まっていますが、祇園祭先祭の7/15、7/16、7/17は武具飾りの展示のため開けられます。
アクセス
京阪の清水五条駅で下車し、5番出口から地上に出ます。
出て左手に進みます。
約300mで松原通と交差するので、ここを右折します。
さらに約300m進んだ右手に「Panasonic」の大きな看板がある左手の砂利道を進みます。
砂利道の突き当り右手に弓煎閣があります。
祇園祭での公開時なら、ちゃんと案内が出ています。
この地は弓矢町といい平安時代から弓箭の作成を生業にしていた人々が住んでおり、祇園社の庇護のもと一定の警察権を持っていました。
その関係で祇園祭での神輿渡御の際には神輿が進む道を清める役割を担っており、昭和49年まで甲冑姿で行列に参加していました。
現在は行列へ参加する代わりに、虫干しを兼ねて武具飾りを行っています。
入場は無料ですが、寄付金のボックスは置いてあります。
当日は納戸もすべて開放され、左手の玄関から入ります。
玄関間の奥に6畳間があり、まずそちらに3領の鎧兜が飾られています。
部屋の奥には中庭も見えています。
玄関間の右手に2階への階段があります。
2階は15畳間で、武具甲冑の他に古文書,古写真などの昔の記録が多数展示されていました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 6/8の拝観報告3(祇園花街芸術資料館)

-
写真は、歌舞練場の舞台上。
熟成豚かわむらを出て、地下鉄東西線で山科駅から三条京阪駅。
京阪電車に乗り替えて三条駅から祇園四条駅へ。
徒歩で12:15頃にやって来たのが、祇園花街芸術資料館です。
いわば祇園甲部歌舞練場ですね。
今年の5/15から春の都をどりと秋の温習会の期間以外の歌舞練場を使わない時は、祇園花街芸術資料館として開館されることになりました。
1,600円です。
最近改修もされましたし、建物もお庭もいいのでいい取り組みだと思います。
都をどりに3回ほど来ており、内部の様子はある程度知っていたのでサクッと見れました。
ただ先に見たことがあるのでサクッと見れましたが、初めての方は見応えがあると思います。
それに何より都をどりの時と違うのは、「舞台に上がれる」ことですね。
ここからの景色は初めて観ました。
12:45頃まで拝見して、次へと向かいました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 5/12の拝観報告4 最終(建仁寺 大統院 京都産業大学 春茶会)

-
写真は、本席のあった書院。
京都御苑の中立売駐車場を出て、烏丸通→松原通→大和大路通を進み、祇園のコインパーキングに駐車します。
この日はこちらで京都産業大学の春茶会がありました。
大統院には2011年と2012年の特別公開で来ています。
その際は方丈での展示と方丈前庭の拝観。
今回のお茶会の要綱を見ると、薄茶2席とあります。
1席は方丈の1室とすると、もう1席は・・・。
どこかあるなと思い、13:30からの3席目に予約しました。
方丈に入った縁で受付。
2席なのに1,000円。
申し訳ないw
方丈に向かって左手の礼の間が待合。
やはり室中などは水屋ですね。
礼の間の奥の部屋がOB/OGの待合でした。
待っているとアマ会のKiさんが来られました。
時間になると呼ばれ、1席目は方丈裏の書院へ。
やはりそうですよねw
こちらは初めて入りました。
6畳間が2つですが、3席目は5人でした。
OBの方がお正客をして下さいました。
そして2席目は方丈を時計回りに回って、礼の間の対角にある衣鉢の間。
こちらは干菓子と壺に入った金平糖が出てきました。
最終的に方丈を1周して受付に戻ってきました。
1席5名だったこともあり、2席で1時間。
14:30頃に終了し、この日は帰宅しました。
そうなんですよ、この日は五月場所の初日でしたw
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2024 5/9の拝観報告4 最終(建仁寺 両足院 Spring Tea Meditation)

-
写真は、臨池亭の内部。
いもぼう 平野家本店を出て、再びシェアサイクルを借ります。
この日は京都グラフィーの開催と共に、事前予約制でSpring Tea Meditationがお茶室の臨池亭でありました。
13:00までは書院で京都グラフィーの写真を拝見。
ワインのブドウ園での風景を写真に撮っていました。
13:00から庭園の臨池亭へ。
1席6名で、参加費は2,000円でした。
海外の方やリピートの方もおられ、自由な感じ。
お菓子は建仁寺のチョコレート。
お薄は6人分、すべてお点前して下さいました。
お茶碗も非常に薄く、お点前さんの手が透けて見えるほど華奢なものや、ガラスのお茶碗など変わった趣向。
お棗が鉛製なので拝見に回ってきて持ったらメッチャ重いしw
一見そう見えない外観なのも卑怯ですwww
天気も気候も良くて非常に気持ちよく、あっという間の1時間でした。
そして14:00に建仁寺の両足院を出ますが、ここから学会に京都駅へ戻る必要がありました。
いろんな交通機関を考えた結果、1番京都駅に早く戻る手段は・・・
自転車でしたw
なのでシェアサイクルを借りたままで待機にして、信号は出来る限り青優先で京都駅に向かった結果、無事14:21発の新幹線に乗れましたw
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 前ページ |
 -泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札
——
-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札
——
 -火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—
---------------
-このブログの見方
22:00に自動更新。
-
22:00は拝観報告。
--タイトルに訪問日時が入っているもの。--
内容は最近の拝観の--主観的な感想です。
----------------------
拝観報告がない時は、本編。
----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-
内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。
-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—
---------------
-このブログの見方
22:00に自動更新。
-
22:00は拝観報告。
--タイトルに訪問日時が入っているもの。--
内容は最近の拝観の--主観的な感想です。
----------------------
拝観報告がない時は、本編。
----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-
内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。